この記事でわかること
- プロジェクトマネジメントDAYの概要・目的・対象者
- 2025年の開催情報・注目ポイント
- 2024年の成果と人気の理由
- 参加によって得られる実務的メリット
- 関連用語と次のアクション
プロジェクトマネジメントDAYは、2016年から毎年開催されている注目の大型イベントです。プロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトリーダー(PL)をはじめ、情報システム部門の担当者、さらには経営層の方々まで、幅広い立場の人たちが一堂に会します。このイベントは「プロジェクトマネジメントの祭典」とも呼ばれ、年々参加者が増えている人気のカンファレンスです。
このイベントの主な目的は、急速に変化するビジネス環境や複雑化するプロジェクト運営の課題にどう立ち向かうかを学び、実践に活かすことです。会場では、著名な専門家による講演や、実際の企業・現場での事例紹介、さらに最新のツールやソリューションの情報が提供されます。たとえば、昨年の実績ではプロジェクトの進め方に悩む現場リーダーや、新しい管理手法を模索する経営者など、多様な参加者が前向きな議論を交わしていました。
また、プロジェクトマネジメントDAYは、経験値や業種を問わず学びと刺激を得られる貴重な機会となっています。その証拠に、2024年は2,100件を超える申込みがあり、翌2025年も開催発表と同時に1,400人以上が早期エントリーしています。多くの方が関心を寄せている理由は、今まさに求められる“現場実践に役立つヒント”が得られるからです。
次の章では、プロジェクトマネジメントDAY 2025の開催情報についてご紹介します。
目次
プロジェクトマネジメントDAY 2025の開催情報

プロジェクトマネジメントDAY 2025は、2025年6月6日(金)の朝9時45分から夕方18時15分まで行われます。開催形式は、オンラインと東京・TODA HALL & CONFERENCE TOKYOのホールAを会場にしたハイブリッド型です。現地で直接参加できるだけでなく、ご自宅や職場などからインターネットを通じて誰でも気軽に参加できるのが特徴です。
このイベントを主催するのは、株式会社システムインテグレータです。参加費は一切かからず無料で、多くの方が参加しやすくなっています。
プロジェクトマネジメントDAYは、プロジェクトマネージャー(PM)だけでなく、プロジェクトリーダー(PL)やIT担当者、さらには経営層まで、幅広い職種・立場の方々を対象としています。内容は、プロジェクト管理に役立つ実践的な知識や、課題解決のための失敗事例とその学び、最新トレンドに関するセッションなどで構成されています。実際の現場で役立つテーマが毎年多く取り上げられている点が、大きな魅力です。
さらに2025年は、特別講演として安野貴博氏の登壇が予定されています。安野氏による現場で活かせる貴重な講演に、多くの参加者が注目しています。
次の章に記載するタイトル:昨年(2024年)から読み解く注目ポイント
昨年(2024年)から読み解く注目ポイント

2024年のプロジェクトマネジメントDAYは、6月6日に開催されました。申込み者数は2,100名を超え、これは過去最高の記録です。また、好評を受けて同年12月には「アンコール」回も実施され、多くの人々が関心を寄せていたことが伺えます。
注目すべきポイントとして、主催者はプロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトリーダー(PL)だけでなく、さまざまな役職や業種の方々が参加している点を挙げています。実際、経営層から現場担当者まで幅広く集い、共通の課題について自由に意見を交わせる風通しの良い雰囲気が特徴でした。それぞれの立場で抱える悩みや課題、工夫している点が多く共有され、参加者同士の刺激となっています。
さらに2024年は、「最新のPM課題」と「それに対する具体的な解決策」の議論が盛んに行われ、実務に直結するヒントが得られる場として一層評価を高めました。例えば、「リモートワーク時代の進捗管理」や「複数部門との連携強化」など、現場でつまずきやすいテーマに対して、具体的な事例やノウハウの披露が目立ちました。このような進化が、プロジェクトマネジメントDAYの成長と人気の背景にあると言えるでしょう。
次の章に記載するタイトル:参加を検討する人への実務的メリット
参加を検討する人への実務的メリット

プロジェクトマネジメントDAYの参加を検討している方にとって、実務的なメリットは多岐にわたります。まず、プロジェクトマネージャー(PM)としてのスキル強化が図れる点が挙げられます。実際の現場では、要件定義から納品、その後の運用まで、プロジェクトは複雑な課題に直面します。本イベントでは、それぞれのプロセスに対する最新の解決例や経験談を横断的に知ることができるため、「どう進めればよいか」「どこでつまずきやすいのか」といったヒントを得やすいです。
また、プロセス全体の整流化や標準化への気づきも期待できます。たとえば、業務フローの改善や、共通の課題を乗り越えるためのノウハウ共有の場があります。他社の事例や参加者同士のディスカッションを通じ、自社の手順を見直しやすくなる効果もあるでしょう。
さらに、プロジェクトマネジメントDAYは職種や役職の壁を越えてコミュニティが広がります。PM、プロジェクトリーダー(PL)、IT担当者、さらには経営層まで多様な立場の参加者が交流します。組織ごとに抱える課題を共有することで、自分だけが悩んでいるのではないと気づくことができたり、他社での実践例を自分の業務に応用できたりといった学びがあります。
加えて、このイベントは参加費無料で、オンラインと現地参加のハイブリッド開催です。忙しくて移動が難しい方や、遠隔地の担当者も気軽に参加しやすく、実利的な知見を得やすいのが特徴です。
次の章に記載するタイトル:関連キーワード1:Day 0 / Day 1 / Day 2は何を意味するか
関連キーワード1:Day 0 / Day 1 / Day 2は何を意味するか

プロジェクトマネジメントDAYに関連してよく耳にする用語が「Day 0」「Day 1」「Day 2」です。これは、Adobeのデジタルサイネージ導入ガイドの中で紹介されている考え方に基づいており、プロジェクト管理の流れを分かりやすく3段階に整理しています。
Day 0:立ち上げ前の準備段階
Day 0とは、プロジェクトが本格的に始動する前の段階を指します。このフェーズでは、プリセールス活動(販売前の相談・提案)、顧客や関係者との要件整理、プロジェクト範囲の確定などを進めます。たとえば、どんな機材が必要か、いつまでに導入を終えるか、どの部署がどこまで担当するかを細かく定めていきます。
また、Day 0はさらに8つの主要な作業に分かれます。
- スコープ(範囲)定義
- スケジュール策定
- 社内外のリソース調整
- 機器調達計画
- 必要な許認可取得
- サイト(現場)へのアクセス調整
- 電源やネットワーク回線の準備
- 技術図面など資料の最終レビュー
これらはチェックリストのように活用でき、見落としを防ぐ助けになります。
Day 1:現場への導入・展開
Day 1は、いよいよ実際の設置やサービス開始、システム展開などを担う段階です。たとえば、現場でディスプレイの取り付け工事を行なったり、ソフトウェアの稼働開始を見届けたりするタイミングがDay 1にあたります。準備段階(Day 0)がしっかりしていれば、このDay 1での混乱やトラブルも少なく済みます。
Day 2:運用とサポート
Day 2は、設置や導入が無事終わってからの継続的な運用・改善フェーズです。日常的な運用管理、問合せ対応、障害対応や定期的な機能改善などがここに入ります。たとえば、導入したデジタルサイネージを定期的に点検したり、ソフトのアップデートやトラブル対応を担当したりする業務です。
この「Day 0/Day 1/Day 2」という分け方は、どんな業種のプロジェクト運営にも応用できる枠組みです。次の章では、1Day診断(短期診断サービス)の位置づけについて解説します。
関連キーワード2:1Day診断(短期診断サービス)の位置づけ

1Day診断サービスとは何か
RAISE Consulting Groupが展開する「プロジェクトマネジメント 1Day診断サービス」は、短期間でプロジェクトの状態や課題を明らかにする支援サービスです。特徴的なのは1日という限られた時間で実施できる点です。多忙な現場スタッフやマネージャーでも無理なく利用でき、手軽さと迅速さが大きな魅力です。
サービスの流れ:一次診断と二次診断
このサービスは「二段階構成」になっています。まず、一次診断としてアンケートをベースにしたクイック診断を行います。これにより、現状のどこに課題がありそうかを分かりやすく"見える化"します。
その後の二次診断では、一次診断で見つかった課題の関係性や優先順位、そして今後どのような方向性で対応すべきかを整理し、具体的な改善案につなげます。プロジェクト運営で悩みやすい"何から手をつければよいか分からない"状態を解消できるサービスです。
なぜ今必要とされているのか
現代はDX(デジタルトランスフォーメーション)や業務改革、基幹システムの刷新といった大きな変化を企業が求められる時代です。しかし、専門の人材や時間が不足する中で、プロジェクトマネジメントの重要性が増してきています。少ない人手で効率よくプロジェクトを確認し、短期間で現状のボトルネックを把握して、改善計画を立てる手助けとなるため、このサービスが注目されています。
具体的な活用のイメージ
プロジェクトの停滞やトラブルに気づいたタイミングで導入すれば、現状確認から課題抽出、その後の具体的な中期改善計画の作成までをスムーズに進めるきっかけになります。また、イベントでは先着10社限定で無料トライアルの案内も発表されたため、まずは試してみる価値が高いと言えるでしょう。
次の章に記載するタイトル:関連トピック:現場PMに役立つ視点と学習の勘所
関連トピック:現場PMに役立つ視点と学習の勘所

現場PMが押さえたい4つの成立条件
プロジェクトマネージャー(PM)として現場で求められる基本は、プロジェクトの「目標」「未知性」「締切」「コスト/日程の上限」という4つの条件をしっかり理解し、管理することです。たとえば、新しいウェブサービス立ち上げでは「目標(いつまでに、どんなサービスを出すか)」を明確に設定するところから始まります。しかし実際には想定外の課題(未知性)が必ず発生しますので、柔軟な対応力も重要です。さらに納期(締切)や予算(コスト)には抑えが効いており、これらを守ることは避けて通れません。
「段取り」の重視と失敗要因の見える化
プロジェクト成功のカギは「作業分解=段取り力」です。現場経験が豊富なPMは、全体を細かい作業単位に分解して無理や抜け漏れがないか注意深く確認します。たとえば、新商品を発売する場合、広報・製造・物流など、それぞれの動きがいつ、どの順番で必要かを事前に洗い出します。このプロセスは「計画抜け」「タスク忘れ」といった失敗の芽を摘むことにも繋がります。
計画抜け・再発防止の実務アプローチ
もし計画の段階で抜け漏れがあれば、後々トラブルの原因になります。現場PMは「なぜ抜けたのか」「次はどう防ぐか」を振り返り、小さな抜けも放置しません。たとえば、イベント用資料の作成を計画に入れ忘れた場合、チェックリストの改善や情報共有体制の見直しを早期に行うことが実務のポイントです。
スタートアップ文脈の合意形成とX Day
スタートアップなど勢いのある現場では、「X Day」(公開日・イベント開始日など)に向け、社内外の関係者全員が同じゴールイメージを持ち、合意することが特に重要です。どんな成果物を、どの基準で完成とみなすか最初に話し合うことで、後の混乱を防げます。
このプロセスは前章で触れたDay 0/1/2の枠組みと重なります。計画や合意(Day 0)、進行(Day 1)、振り返りと改善(Day 2)の各段階において、合意形成=ゲート(判断基準)を明確にし、現場をリードする視点が役立ちます。
次の章に記載するタイトル:プロジェクトマネジメントDAYの活用法(参加前・当日・後日)
プロジェクトマネジメントDAYの活用法(参加前・当日・後日)

参加前の準備:事前の課題整理で学びを最大化
プロジェクトマネジメントDAYを有効活用するためには、まず自社プロジェクトの課題を事前に書き出しておくことが大切です。たとえば「納期が遅れやすい」「要件が途中で変わる」「担当者が足りない」「リスク対策に不安がある」といった点をメモにして可視化します。そのうえで、Day 0(企画の準備)、Day 1(立上げ・デプロイメント)、Day 2(運用・改善)のどこにその課題が目立つのか仕分けしてみてください。事前準備が、会場での情報収集や質問の精度を高めます。
当日の動き方:テーマと事例を重視して参加
当日は、自社の課題や興味に合ったセッションを優先的に選びましょう。特に、システムの本番稼働(Day 1)や実際の運用フェーズ(Day 2)まで扱う事例発表は、実践的で応用しやすい内容が多いです。分からない点や気になった話題は、質疑応答の時間に自社の事情と結び付けて質問してみてください。オンライン参加や会場でのハイブリッド形式でも、チャットや専用フォームを使った質問が可能な場合が多く、自分だけでなく他の参加者の視点も得られます。
後日の活用法:職場への展開と第三者評価
イベント終了後は、学んだことやヒントを自社の決めごとや手順(チェックリスト、タスク管理表、リスク台帳、変更管理ルールなど)へ反映するのが有効です。さらに必要に応じて、イベント内で紹介された1Day診断(短期のプロジェクト診断サービス)などを利用して、プロジェクトを第三者の視点から評価してもらうことも検討しましょう。イベント参加をきっかけに、現場の仕組みや体制をブラッシュアップできます。
次の章に記載するタイトル:よくある疑問への回答
よくある疑問への回答

「プロジェクトマネジメントDAY」は誰が対象ですか?
プロジェクトマネジメントDAYはプロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトリーダー(PL)を主な参加対象としています。ただし、プロジェクトに関わるすべての方に向けたイベントです。たとえば、IT担当者や経営層、またプロジェクト推進に携わる事務局スタッフなど、役割に関わらずプロジェクトをより良くしたいと考える方へ幅広く価値があります。プロジェクトマネジメント初心者や、これから関わる予定の方も、気兼ねなく参加いただけます。
オンラインでのみ参加できますか?
2025年開催では、オンラインでの参加が可能です。また、会場でのオフライン参加も選べます。ご自身の都合や好みに応じて、参加方法を自由に選択できます。例えば、遠方からの参加や移動が難しい場合はオンラインが便利です。逆に、現場で交流や体験を重視したい方は会場参加もおすすめです。
参加費はいくらですか?
プロジェクトマネジメントDAYの参加費は無料です。事前申込のみで、追加の費用はかかりません。毎年多くの方が気軽に参加しやすい理由のひとつです。
どのくらいの規模で開催されていますか?
ここ数年は1,000~2,000名規模の申込みがあります。2024年は2,100件を超える申込みがありました。2025年は発表時点ですでに1,400名以上がエントリーしています。今後も多くの参加が見込まれています。
次の章に記載するタイトル:出典に基づく重要データの要点
出典に基づく重要データの要点
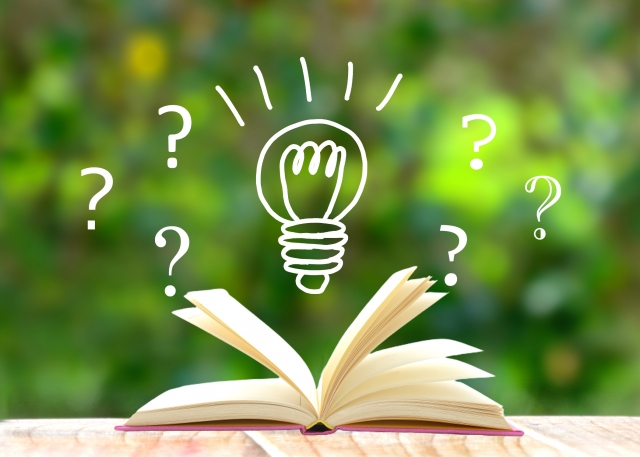
公式発表に基づく数値・ファクト
プロジェクトマネジメントDAY 2025の開催については、主催者がPR TIMESで一次情報として発表しています。特に、特別講演者として安野貴博氏が登壇することや、既にエントリーが1,400名を超えている点が公式リリースで言及されています。開催日時、会場、参加費無料という点は、イベント業界紙・Weekly BCNの公式サイトでも明確に確認できます。これらの数字や基礎情報は、信頼できる一次情報に基づいています。
前回実績・反響の根拠
2024年のプロジェクトマネジメントDAYは、申込件数が2,100件を超え、さらに大きな反響によりアンコール開催も行われたとのことです。これもPR TIMESの主催側発表で確認できる事実です。これらのデータは、イベントへの注目度や実際に多くの人に利用されていることを裏付けるポイントです。
専門ガイドや技術記事の引用
イベントでよく扱われる「Day 0」「Day 1」「Day 2」という専門用語や、「Day 0の8ステップ」については、Adobe社の公式技術ガイドを参考に説明されています。また、1Day診断(短期診断サービス)の枠組みも、RISEの公式告知記事に基づき整理されています。
ナレッジの裏付けとなる外部記事
現場のプロジェクトマネージャーに役立つ考え方や学習ポイントについては、Qiitaなどの技術系記事、ならびにスタートアップ向けのノート記事から要点を抽出し、根拠としています。これにより、実務や学習現場で活かせる知識として信頼性を担保しています。
次の章に記載するタイトル:次のアクション提案
次のアクション提案

プロジェクトマネジメントDAY 2025への参加を最大限に活用するために、具体的な次のステップをご提案します。
参加準備:告知ページから正確な情報を
まずは公式の主催告知ページを必ずチェックし、参加登録を済ませましょう。日程や場所、オンライン・現地の参加方法もここで確認できます。案内は逐次更新されるため、イベント直前まで定期的にページを確認することをおすすめします。
事前準備:自社やご自身の課題整理
Day 0/Day 1/Day 2の視点(プロジェクト開始前・初動・運用中)で、自社プロジェクトの現状や課題を整理しておきましょう。例えば、「自分たちのチームは進め方のどこでつまずきやすいか」「判断や情報共有で困っている点は何か」など、メモやチェックリストにまとめておくと、当日得られるヒントの活用度が上がります。
参加後の活用:チェックリスト化と1Day診断
イベント参加後は、気づきやヒントを整理し、組織内で簡単なチェックリストとして展開しましょう。さらに、1Day診断サービスなどを使い、第三者視点で課題を洗い出すと、改善の優先度がクリアになります。小さな改善からでも実行に移すことで、プロジェクト運営の質を高めやすくなります。
情報収集のポイント
イベントの個別セッション内容やタイムテーブルは変更の可能性があります。最新の詳細は主催ページで随時ご確認のうえ、ご自身の目的に合ったセッション選択を行ってください。
本記事の情報は公開されている内容に基づいていますので、公式情報のアップデートにもご注意ください。