この記事でわかること(主要5点)
- プロジェクトマネジメントDAYの全体像
主催(システムインテグレータ)、目的、歴史、参加者層を理解できます。 - 2025年の開催情報と注目ポイント
開催日・場所・特別講演者(安野貴博氏)など、最新の概要が分かります。 - 過去の実績とイベントの継続性
2024年の2,100名超申込みなど、成長の背景と信頼性を把握できます。 - 関連トピック(Day0/1/2・1Day診断・X Day)
現場で使える考え方やサービスの意味を理解できます。 - 実務での活用法と学習のヒント
スケジュール管理の基本、PM育成の視点、イベントを起点にした活用アイデアを学べます。
目次
プロジェクトマネジメントDAYとは(主催・目的・歴史)

株式会社システムインテグレータが主催する「プロジェクトマネジメントDAY」は、プロジェクト管理に携わる多くの方々が一堂に会する年に一度の大規模イベントです。2016年に第1回が開催されて以来、プロジェクトマネージャー(PM)やリーダー(PL)、情報システムの担当者、さらには経営層まで幅広い参加者層が特徴となっています。
このイベントの目的は、近年ますます複雑化・高度化しているプロジェクトマネジメントの課題や最新事例、知見を共有し合うことです。実際の現場で使えるノウハウや、先進的なマネジメント手法など、すぐに役立つ内容が多数取り上げられる点が多くの参加者から支持されています。
歴史としては、開始以来毎年継続開催されており、着実に規模を拡大してきました。直近の開催では2,100名超が申し込むなど、毎年1,000名以上が集う大型イベントへと成長しています。これにより「プロジェクトマネジメントの祭典」として、業界内でも注目される存在となっています。
次の章では、2025年の開催情報(日程・注目ポイント)についてご紹介します。
2025年の開催情報(日程・注目ポイント)
2025年のプロジェクトマネジメントDAYは、6月6日(金)に開催されます。すでに発表されている注目ポイントとして、特別講演に安野 貴博 氏の登壇が決定していることが挙げられます。安野氏は多方面で活躍されている方であり、その知見や実体験を聞くことができる絶好の機会です。毎年違った顔ぶれの講演者が招待されることで、多様な視点が得られるのもこのイベントの魅力の一つです。
参加対象者としては、プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダー、IT担当者だけでなく、経営層の方々も対象となっています。現場でのプロジェクト進行に従事している方から、全体を俯瞰するマネジメント層まで、幅広く参加できるのが特徴です。すでに1,400名を超えるエントリーがあるとのことで、注目度の高さがうかがえます。
また、プロジェクトマネジメントに関心のある人であれば、職種や役職に関係なく学びや刺激を受けられるイベントです。これまでとは違う視点や新しい知識を得ることで、日々の業務や将来のキャリアにも役立つはずです。
次章では、昨年までの実績と継続性についてご紹介します。
昨年までの実績と継続性(ベンチマーク)

プロジェクトマネジメントDAYは、年々参加者の数を増やしながら継続されているイベントです。2024年には実に2,100名を超える申込みがあり、イベントの注目度や信頼性の高さがうかがえる結果となりました。参加者数の多さは、プログラムの内容が幅広いニーズに応えている証と言えるでしょう。この大規模なイベントは例年恒例となっており、多くの人々にとって年度の重要な行事となっています。
また、過去の実績から「毎年1,000名以上が集まるイベント」として定着し、広報においてもその規模が強調されています。こうしたベンチマークは、はじめて参加を検討する方にとって安心材料となるはずです。地方や遠方からの参加者も多く見られ、全国規模でのネットワーク形成や情報交換の場として活用されています。
特に2025年の開催においては、開催決定直後から申し込みが多数寄せられ、前年を超える盛り上がりが期待されています。このことからも、プロジェクトマネジメントDAYが情報収集や新たな出会い、知見の共有において有効であるとみなされている様子が伝わってきます。
次の章では、「Day」という用語のプロジェクト運用における使われ方について詳しく解説します。
「Day」という用語の別文脈:プロジェクト運用のPhase表現(Day 0/1/2)
プロジェクトマネジメントの現場では「Day」という言葉が、イベントのタイトルだけでなく、実際の業務プロセスの中でも活用されています。特に、デジタルサイネージ導入などのプロジェクト管理ガイドでは、プロジェクトの進行を「Day 0」「Day 1」「Day 2」と3つの段階に分けて整理する手法があります。
この区分けは、プロジェクトの各フェーズを順序立てて把握しやすくするためのものです。
Day 0(ゼロデイ):この段階は、実際の作業開始前に必要な準備を行うフェーズです。例えば、プロジェクトの目的や範囲(スコープ)を明確にする、全体スケジュールを設定する、外部ベンダーや自社の体制を決める、必要な機器の調達計画を進める、といったタスクがあります。また、サイトのアクセスや設備の許可を取得する計画、電源やネットワーク接続の検討、技術図面のレビューなども含まれます。これらはすべて円滑なプロジェクトスタートのために欠かせません。
Day 1(ワンデイ):この段階が、いよいよシステムや機器を現場に導入するフェーズです。たとえばデジタルサイネージであれば、モニターやシステムを現場に設置し、動作確認を行い、基本的な設定などを実施します。ここが実質的なプロジェクトの“スタート”と捉えられることが多いです。
Day 2(ツーデイ):導入後の運用や保守、場合によっては改善提案などを行っていく継続フェーズです。例えば、運用マニュアルに従った日々のチェックや、トラブルが発生した場合の対応、定期的なアップデートや改善の提案といったタスクが施行されます。実際、この段階がプロジェクトの「持続力」を試される重要なフェーズとなります。
このように、「Day」という用語を使った段階表現は、プロジェクトを計画通り進行するうえで役立つ目安となります。イベント名の“DAY”とは若干用途が異なりますが、実務の現場で非常に便利な考え方です。
次の章では、「1Day」診断サービスという関連トレンドについてご紹介します。
「1Day」診断サービスという関連トレンド
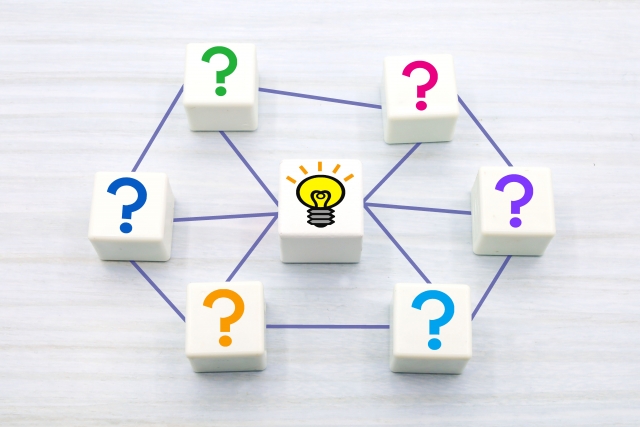
近年、企業ではプロジェクトマネジメントにおける課題を短期間で明らかにし、早期に改善点を見つけることへのニーズが高まっています。こうした流れの中で注目されているのが、「1Day診断サービス」です。これは、名前の通り1日という限られた時間で現場のプロジェクト運営状況を診断し、課題の可視化や改善の方向性を示すサービスです。
具体的には、まず簡単なアンケートに社員が回答し、その結果から一次診断として現状の課題やリスクを短時間で洗い出します。その後、必要に応じて二次診断に進み、より詳細な分析や優先度付け、改善の方向性についてアドバイスが行われます。たとえば「作業の属人化が進んでいませんか」「進捗報告が形式的になっていませんか」など、実際の業務でよく直面する悩みにフォーカスして診断します。
このようなサービスが求められる背景には、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)や基幹システム刷新のプロジェクトが急増していることがあります。また、限られた人員で多くの業務をこなさなければならない現場では、じっくりと問題点を分析する時間がとれないことも多いのが現状です。そこで、“1Day”というブランドで短時間に本質的な課題を抽出できる仕組みが広がっているのです。
こうした時短型の診断サービスは、スピーディーな意思決定や改善活動を求められる現代のビジネス環境にフィットしています。また、プロジェクトマネジメントDAYのテーマとも親和性が高く、今後も関連サービスや事例が増えていくことが予想されます。
次の章:スケジュール管理の基本とテンプレ活用(実務補足)
スケジュール管理の基本とテンプレ活用(実務補足)
スケジュール管理は、プロジェクトを成功に導くための重要な基本作業です。始まりから終わりまで、すべての作業が計画通り進んでいるかを確認しながら、必要に応じて調整します。核となるのは「いつ何をするか」の明確化です。たとえば新商品発売プロジェクトでは、企画・試作・製造・販売準備・発売日まで、それぞれのタスクの開始日や終了日、必要な人材、作業の順番や関係性が決まります。この情報を整理しておくことで、チーム全員が迷わず動けるようになります。
また、適切なスケジュール管理は「納期が遅れる」「コストが必要以上にかかる」といったリスクを避ける助けになります。進捗状況をチーム内で共有することで、仕事の重複や、意思疎通のズレを未然に防ぐことも可能です。
実務の現場では、スケジュール管理のためのテンプレート(ひな型)が数多く使われています。例えば、WBS(作業分解構成図)は大きな作業を細かいタスクに分けて見える化し、クリティカルパス法では「どこかが遅れると全体が遅れる」重要な作業の繋がりを明らかにします。ガントチャートは、全体スケジュールを横棒グラフで示し、一目で進行状況が分かります。
これらテンプレートを使うことで、初めてのプロジェクトでも抜けやミスが少なくなり、「この手順で進めれば大丈夫」という安心感が得られます。さらに、過去のプロジェクトで使った管理表を流用すれば、作業の精度と再現性がグッと高まります。
次の章では、スタートアップにおける“X Day”の合意形成について解説します。
スタートアップにおける“X Day”の合意形成

スタートアップでは、新しいサービスや製品のリリース、またクラウドファンディングの開始日など、特定の日を“X Day”として設定することがよくあります。“X Day”は、単なるイベント当日だけでなく、全ての関係者が共通の目標やアウトプットを意識しやすくするマイルストーンの役割も果たします。
例えば、アプリの公開日を“X Day”と定めた場合、開発チーム、マーケティングチーム、経営陣、外部の協力者がその日に向けて何を達成しなければならないかを明確にします。これにより、「どの時点で、誰が、どんな成果物を提供するべきか?」という合意形成が行いやすくなります。
さらに、社内プロジェクトであっても、“X Day”を決めて、決裁のタイミングや全社員への説明会の日を逆算し、どの段階で必要な資料やプロトタイプを用意するか調整します。これによりタスクの優先順位や依存関係が整理され、作業の手戻りを最小限に抑えることができます。
実践例としては、クラウドファンディングの場合は「公開日=X Day」とし、PR動画や紹介記事、必要書類の準備スケジュールを逆算して設定します。また新機能のリリースなら、リリース日から逆に、テストやローンチ準備、内部周知のタイミングを計画します。
“X Day”を明確にし、周囲と合意することはスタートアップのスピード感と柔軟性を活かすためにも大切です。
次は、「PM不足時代の学習・育成の視点」について解説します。
PM不足時代の学習・育成の視点
近年、プロジェクトマネージャー(PM)の人材不足が多くの業界で課題となっています。PMの育成においては、単に座学で知識を得るだけでなく、実際のプロジェクトを小規模に模した「ミニプロジェクト」に取り組む方法が有効と言われています。
ミニプロジェクトでは、限られた期間やリソースという上限制約を設定します。また、プロジェクトを細かい作業に分解(段取り)し、何がどの順番で必要かを明確にすることがポイントです。この経験を通じて、計画の段階で生じやすい「抜け漏れ」を自分で発見できるようになり、実際の業務でのミスが減少します。
さらに、プロジェクトの振り返りを行い、どこに失敗の原因があったのかを考える「内省」も大切です。たとえば、「予定より作業が遅れたのは、初期の情報集めに時間をかけすぎたからだった」と気づくことで、次回はより現実的なスケジュールが立てられるようになります。
このように、形式知(マニュアルやテンプレート)と、実際の行動(経験)を往復するサイクルが、現場で再現性の高い道筋を身につけるために役立ちます。また、イベント参加をきっかけに、「自分でもミニプロジェクトをやってみよう」と取り組み、習慣化することも大いに意味があります。
次の章では、実務での活用アイデア(イベントを起点に)についてご紹介します。
実務での活用アイデア(イベントを起点に)

プロジェクトマネジメントDAYなどのイベントは、日常の業務を見直すよい機会となります。ここでは、イベントを起点として実践できる活用アイデアについて説明します。
イベント前の準備:自組織の課題整理
イベントに参加する前に、自分たちの組織が抱える課題を棚卸ししておきましょう。たとえば、「Day 0(立ち上げ)」「Day 1(デプロイ)」「Day 2(運用)」といったプロジェクトの各フェーズごとに:
- どこがスムーズに進んでいるか
- どこでボトルネック(停滞や問題)が生まれているか
このように区分しながら仮説を立てて整理してみると、イベントで得たい答えが明確になります。また、現在のスケジュール管理プロセスや利用しているテンプレートを再確認しておくことで、課題解決のヒントを見つけやすくなります。
イベント中のインプット活用
イベント当日は、登壇者のテーマと自社課題との関連性に注目しましょう。気になったポイントはメモしておくと、帰社後の実践に活かせます。また、懇親会やネットワーキングの機会には、他社の担当者と「1Day診断」などの外部の視点を取り入れられる仕組みについて意見交換するのもおすすめです。外部からのアドバイスは自社内だけでは見えない観点に気づけることがあります。
イベント後の実践と仕組み改善
イベントで得た情報や気づきをもとに、「X Day」のような重要な節目となる日を自社プロジェクトの計画に再定義しましょう。関係者間で合意を形成し、そこから逆算して何を・いつまでに行うか具体的に更新します。さらに、WBS(作業分解構成図)や依存関係、クリティカルパス(最重要な工程)を見直し、段取りを再設計することで、より実効性あるプロジェクト運営が期待できます。
イベントでの学びや刺激を、日常業務の具体的なアクションに落とし込むことで、プロジェクトマネジメントの質を高めやすくなります。