この記事でわかること
- ベンダーの「プロジェクトマネジメント義務」の定義と法的背景
- 裁判例から読み解く義務の具体的範囲と実務上の注意点
- ユーザーの「協力義務」との関係・役割分担
- 契約書でPM義務を明確にするための条項設計のポイント
- 実務で使えるチェックリストとよくある落とし穴の回避策
目次
ベンダーの「プロジェクトマネジメント義務」とは何か(定義と法的位置付け)

システム開発プロジェクトにおいて、ベンダー(開発会社)には「プロジェクトマネジメント義務」と呼ばれる役割があります。これは、単にプログラムを作成するだけでなく、プロジェクト全体を見渡して進捗状況を確認したり、問題が起きそうな部分を早めに見つけて対応を検討したりする役割を指します。また、社内・社外の関係者としっかり調整を行い、円滑にプロジェクトを進めるように努めなければなりません。
この「プロジェクトマネジメント義務」は、法律(例えば民法など)に明確に書かれているものではありません。しかし、過去のシステム開発プロジェクトで起きた裁判の中で、ベンダーにはこうしたマネジメントの義務があると認められ、徐々に実務でも定着してきました。つまり、法律そのものというより、裁判例を通じて「守らなければならない」と考えられるようになった義務なのです。
さらに、この義務は契約を結んだ後だけでなく、契約前の段階、たとえば提案書を作ったり、お客様の要望(要件)をまとめたりする段階でも発生する場合があります。提案時に「できる」と説明した内容について責任を持ったり、不明点があれば積極的に確認したりする姿勢も、プロジェクトマネジメント義務の一部と考えられています。
次の章では、実際の裁判例でどのような点が「プロジェクトマネジメント義務」の範囲として認められてきたのか、具体的にご紹介します。
裁判例で示された具体的内容(どこまでが「義務」か)

裁判例から読み解くプロジェクトマネジメント義務
この章では、実際の裁判例から、ベンダーがどこまでプロジェクトマネジメントの義務を負うのか、具体的な内容に焦点を当てて説明します。
1. 実際の裁判で問われた義務の中身
たとえば、東京地方裁判所の平成16年3月10日判決では、以下のような点がベンダーの「プロジェクトマネジメント義務」として示されました。
- 提案書や契約で約束した手順・方法・工程を守って作業を進めること
- 作業の進捗状況を常に管理し、問題が起こればすぐに気づく体制を作ること
- 進行を妨げる要因を早めに見つけ、迅速かつ適切に対応すること
このように、単に仕事を進めるだけでなく、周囲の状況にも気を配りながらプロジェクト全体を健全に保つことが求められました。
2. ユーザーとの関係で求められる対応
さらに裁判では、ユーザーの多くがITの専門知識を持たないことを前提に、ベンダーがユーザーの関与度合いを調整し、開発の妨げとならないよう工夫することが必要だとされました。たとえば、不明点や決定事項についてユーザーに適切な説明や提案を行い、必要な関与を引き出すことも「義務」とみなされます。
3. 仕様追加や要求変更への義務
SOFTICの判例整理によれば、開発中にユーザーからの仕様追加や変更要求が頻繁に生じるのはよくあることです。ベンダーには、こうした要求がもたらす影響(たとえば追加の費用や納期延長など)を明確にユーザーに伝えること、そして即座に協議して解決策を図ること(撤回や延期の相談など)が義務として求められます。これにより、「言われるまま何でも引き受ける」のではなく、影響を説明し合意形成を図る姿勢が重要となります。
4. 仕事完成義務や変更管理との関係
裁判例では「仕事の完成義務」や「変更管理」の論点と密接に関連して議論されています。そのため、個々の義務を単独で評価するのではなく、プロジェクト全体を通した総合的な観点でベンダーの対応が妥当かどうかを判断する流れが主流となっています。
次の章では、こうしたベンダーのプロジェクトマネジメント義務とセットで語られることの多い、ユーザーの「協力義務」についてご紹介します。
ユーザーの「協力義務」とのセットで捉える

ベンダーのプロジェクトマネジメント義務についてお話ししてきましたが、この義務はユーザー側の「協力義務」とセットで初めて現実のプロジェクト運営が成り立ちます。ユーザーの協力がなければ、どれほどベンダーが誠実に計画や管理をしても成果は期待できません。ユーザーの「協力義務」にも複数のポイントがあります。
情報提供や意思決定が不可欠
プロジェクトでは、ベンダーからの質問や確認事項に対し、ユーザーが必要な情報を迅速に提供することが求められます。例えば「業務に関する仕様を教えてください」といったベンダーからの依頼には、わかりやすく内容を伝えることが大切です。また、設計やテストのタイミングでは、レビューや承認といった意思決定にも積極的に参加しなければなりません。
追加・変更時には影響評価への合意
実際のプロジェクトでは、「やはりあの機能も入れたい」といった追加事項や「ここの仕様を変えたい」という希望がユーザーから生じることがあります。この段階で、ベンダーは費用や納期への影響を評価し、その説明をユーザーに行います。ユーザーにはこれらの影響を受け入れたうえで、必要に応じて費用追加やスケジュール再調整にも合意する義務があります。
変更管理はベンダーの責任で主導
ユーザーからの要望によってプロジェクト内容が変わるときは、ベンダーが主導して変更管理プロセスを進めます。ですが、その過程でユーザーが適切に判断・協力しないと、トラブルが発生する原因になります。両者が「自分だけに責任がある」と思い込まず、お互いの役割と義務を意識して協力することがポイントです。
次の章では、こうした義務を実際の契約書にどのように反映し、明確にしていくべきかを解説します。
契約書にどう落とし込むか(条項設計の要点)

プロジェクトマネジメント(PM)に関する義務は、法律に明文化された基準がほとんどありません。そのため、現実のITシステム開発や導入の場面では、個々の案件ごとに詳細な義務内容を契約書上で定めておくことが大切です。ここでは、契約書にPM義務をどのように盛り込めばよいか、条項設計の要点と具体的な例を挙げながら説明します。
1. PM義務の代表的な項目を明記する
案件ごとに重要なポイントを契約書に明示しましょう。例えば、以下のような項目がよく規定されます。
- 進捗管理…定例会議の開催やスケジュール遵守状況の報告
- 品質管理…成果物の品質確保の基準やレビュー方針
- リスク・課題管理…問題発生時の対応フローや是正提案のルール
- 変更管理…仕様変更時の見積もり・影響評価・合意制手続き
- コミュニケーション…議事録・決定事項の文書化や連絡手段の明確化
2. ユーザーの協力義務も盛り込む
ベンダー側だけでなく、ユーザー側にも協力義務が求められます。たとえば、「レビューや決裁は何日以内とする」「ユーザーは必要な前提情報や資料を所定の期限で提供する」など、双方の役割を具体的に明記することで、トラブル防止につながります。また、受入テストの参加やフィードバック提出期限なども盛り込むべき点です。
3. 変更・記録管理、早期警告の義務化
契約書には、作業の拡大ややり直しが起きた際の責任を明確にするよう、「合意なき作業拡大防止」や「議事録・承認記録の義務化」なども忘れず入れましょう。問題やリスクを感知したら、遅滞なく連絡し是正案を提示する義務(「早期警告義務」)も重要なポイントです。
4. 契約形態ごとの書き分け
請負契約の場合はベンダーの責任範囲が広くなり、委任・準委任契約ではやや限定的になる場合があります。「どこまでがベンダーの義務か」や「どこからはユーザーの領域か」を具体的に規定し、責任の所在が曖昧にならないよう注意しましょう。
次の章では、PM/PL体制と責任分担(達成責任と実行責任)について詳しく解説します。
PM/PL体制と責任分担(達成責任と実行責任)

PM(プロジェクトマネージャー)の役割と「達成責任」
PM(プロジェクトマネージャー)は、プロジェクト全体の責任者です。PMは、システム開発や導入プロジェクトの成功を目指し、計画立案や進捗管理、課題解決をはじめとした「全体最適」を担います。ここでの「達成責任」とは、最終的にプロジェクトの成果(例:システムの稼働や納期の遵守)を実現することに責任を持つ、という意味です。例えば、プロジェクトの途中で予期しないトラブルが発生した際も、その解決に向けた最善の策を講じることがPMには求められます。関係者全員とのコミュニケーションや調整が不可欠なため、組織内外を問わず、様々な人と信頼関係を築く役割も果たします。
PL(プロジェクトリーダー)の役割と「実行責任」
PL(プロジェクトリーダー)は、各作業チームや工程のリーダーとして、現場を指揮します。「実行責任」とは、与えられた計画や方針に基づき、タスクを具体的に勧めていく責任のことです。たとえば、要件定義、設計、プログラミング、テストなど、個別の作業やその進め方を管理し、計画どおりに作業を完了させることがPLの役割です。PLは日々の進捗や課題を管理し、メンバーへの指示やサポートを行います。問題が発生した場合は、速やかに上司であるPMへ報告し、連携しながら対応策を練ります。
最終成果の責任と体制の意味
プロジェクトが成功するためには、PMとPLが互いの役割を明確にし、協力する体制が不可欠です。PLが現場で個々のタスクを確実に実行し、その結果をPMが集約しつつ全体像を把握・調整します。最終的な成果物の品質や納期に対する最終的な責任はPMが負いますが、PLの現場でのコントロールが適切でなければ、PMも責任を果たせません。多くのプロジェクトで、この「達成責任」と「実行責任」の分担が明文化され、メンバー全員が自分の役割を正しく理解していることが重要です。
実務上の課題と「見える化」のポイント
現場では、プロジェクトの進捗や課題が関係者全員に分かりづらくなることが多いです。それにより、問題の早期発見や対応が遅れ、PMのプロジェクトマネジメント義務の履行が難しくなることがあります。このような状況を防ぐために、進行状況や課題をリアルタイムで可視化できるツールや仕組みが有効です。例えば、ガントチャートやタスク管理ツール、定期的な進捗会議などによって「今、何がどこまで進んでいて、どこにリスクがあるのか」を見える化することが、PM/PL体制の円滑な運用には不可欠です。
次の章に記載するタイトル:公共領域における示し方(参考)
公共領域における示し方(参考)

公共案件ならではの特徴
公共領域、つまり政府や自治体が発注主体となる情報システム開発などのプロジェクトにおいては、民間と比べて「プロジェクトマネジメント体制の整備」がより重視されます。例えば、PjMO(プロジェクトマネジメントオフィス)体制の構築や、プロジェクト要員の計画(どんな役割を何人アサインするかなど)が挙げられます。これらは、プロジェクトを混乱なく進行させるために不可欠だと認識されています。
明文化の度合いと期待
公共案件では、契約段階や提案依頼書(RFP)などの段階で、体制・工程・ガバナンスについて詳細に記載することが一般的です。たとえば、「週次での進捗報告」「リスク管理会議の開催」「課題管理台帳の運用」といった具体的な管理方法が求められる場合もあります。こうした項目は、“ルールを明確にし、全ての立場の人が同じ理解を持てるようにする”という考え方からきています。
法的義務との違い
一方で、「こうした体制を整備しなければならない」と直接法律で定めているわけではありません。ガイドラインや要件定義書、各種指針などで推奨される形となっているのが一般的です。つまり、明文化はされているものの、法的な罰則を伴うルールではなく、信頼性や品質確保のための慣行として位置づけられている点が民間と比べた場合の特色といえます。
各種ドキュメントでの取り扱い例
具体的には、RFP(提案依頼書)や契約書の別紙で、プロジェクト体制図や主要担当者の指名基準、定例会議の設置、緊急時対応フロー、品質管理の手順などを明記します。これにより、発注者と受注者が相互に「どう進めるべきか」の共通認識を得やすくしています。
次の章では、PMの責任・プレッシャーと「責任の比重」の実務感覚について解説します。
PMの責任・プレッシャーと「責任の比重」の実務感覚(補足)

プロジェクトマネージャー(PM)は、進捗やリソース、コスト、リスクなど、さまざまな側面でプロジェクトを管理しなければなりません。このため、PMにはプロジェクトの成功や失敗が直接的に結びつき、時には非常に重い責任と強いプレッシャーが求められる場面もあります。
「PMの責任」とは、単に問題が発生した際に謝ることや対処することだけではありません。実際には、「依頼された内容を決められた条件のもと達成すること」が責任の本質です。たとえば、新しいシステムの導入プロジェクトで、約束された納期・予算内で、求められる品質を確保することこそが、PMに求められる達成責任です。
一方で、組織の中ではこの責任の比重が本来よりも偏ってしまうことがあります。具体的には、本来チームや関係者全体で分担すべき責務が、PMひとりに集中してしまったり、別部署や他のメンバーが取るべき責任をPMに転嫁するリスクがあります。こうした状況が生じると、プロジェクト全体のバランスが崩れ、結果的に失敗につながることもあり得ます。
実務の現場では、こうした「責任の偏在や転嫁」を防ぐ工夫が大切です。具体例としては、PMの権限や責任範囲、決裁基準を最初から明確に決めて記録しておくことが挙げられます。また、重要な判断やトラブル発生時には関係者に情報共有し、必要に応じて上位者に報告・相談する「エスカレーションルール」を整備しておくことで、責任の所在が曖昧にならず健全な運営がしやすくなります。
次の章では、実際の現場で役立つチェックリスト(受注側・発注側)についてご紹介します。
実務で使えるチェックリスト(受注側・発注側)

受注側(ベンダー)のためのチェックリスト
ベンダーがプロジェクトを進めるにあたり、特に意識したい実務ポイントをまとめました。社内でプロジェクトマネージャーやリーダーが確認できる一覧として活用できます。
- 提案段階からプロジェクトマネジメント義務を念頭に置き、対応方針や体制を明確にしていますか?
- 前提条件・制約事項・各種リスクを初期段階で列挙し、文書に明記して伝えていますか?
- チームの体制やPM/PLの役割分担を明示していますか?関係者への説明・可視化が十分ですか?
- 工程ごとに合意事項や変更点を記録し、影響範囲を都度整理していますか?
- 要件や工程の変更が発生した際、その影響を適切に評価・説明し、ユーザーと合意を取っていますか?
- ユーザーのレビューや検討が必要なポイントを明らかにし、参加状況を管理していますか?
- ユーザーから協力を得るべき事項や阻害要因を早期に検知し、適切に通知・記録していますか?
- 変更管理のプロセスを主導し、ユーザーとも合意形成をしていますか?
発注側(ユーザー)のためのチェックリスト
ユーザー(発注者)側にも協力義務が生じます。負担・責任が明確な内容になっているか、次の点でも確認してみましょう。
- プロジェクトの情報提供・仕様レビュー・決裁が滞りなく進むよう、社内調整をしていますか?
- ベンダーからの影響評価や質問への応答を遅滞なく実施できますか?
- 要求・要件の変更や追加は個人判断になっていませんか?必ずプロジェクト全体で合意し、記録(チケット管理など)していますか?
- 意思決定権限者を明確にし、必要なタイミングで稼働・出席できる体制ですか?
- 議事録や仕様変更の履歴(バージョン管理)を残し、証跡として整理していますか?
次の章に記載するタイトル:よくある落とし穴と回避策
よくある落とし穴と回避策

プロジェクトマネジメントでは、一見小さな油断や手順の甘さが後々大きなトラブルにつながることがあります。ここでは、現場でよく見かける落とし穴と、その防ぎ方についてポイントごとにご紹介します。
1. 口頭のみの合意に頼る
口頭で「この修正だけなら追加費用なしで」と安易に合意し、後から仕様変更が膨らんでトラブルになる例が目立ちます。必ず、すべての変更は書面かメールで記録し、申請・影響評価・承認という流れを社内外で徹底することが重要です。
2. 変更範囲・納期・予算が曖昧なまま進行
「前回同様の機能で」など、曖昧な指示で開発を進めると後々認識ずれが生じがちです。見積もり・納期・作業範囲の各項目を具体的に文書化するだけで、不必要なトラブルをかなり減らせます。
3. ユーザー側の意思決定・レビューの遅延
ユーザー側で承認やレビューが遅れるケースも多いです。契約書や運用ルールにレビュー期限を明記し、期限を超えたら自動的に承認したとみなす(自動承認規定)などの工夫が有効です。
4. 前提条件の食い違い
システム開発開始後に「想定していた環境と違う」「作業できない日があった」などの認識違いが判明することも少なくありません。提案段階で前提条件や作業可能日、参照システムなどをリスト化し、双方で確認・合意しておきましょう。
5. 責任範囲があいまい
プロジェクトで問題が発生したとき、「誰がどこまで責任を持つか」が明確でないと、解決が困難になります。責任者や担当範囲(PM/PL/QAなど)は、契約の付属文書やRACIチャートなどで事前に定義しておくと安心です。
次の章に記載するタイトル: 用語の簡潔整理
用語の簡潔整理
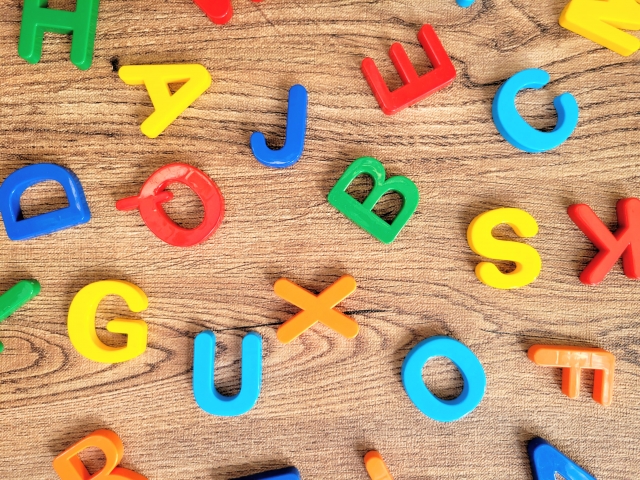
プロジェクトマネジメント義務
「プロジェクトマネジメント義務」とは、システム開発などの契約において、ベンダー(システム会社など)がユーザー(発注者)に対して、プロジェクト全体を計画・調整・監督し、無事に完了に導くよう努める義務のことです。この義務は日本の法律に明文では書かれていませんが、さまざまな裁判例から実践的な基準として認められています。
協力義務
「協力義務」とは、ユーザー側がベンダーのプロジェクト管理を妨げるのではなく、むしろ必要な情報を提供したり、意思決定に協力するなど、プロジェクトの円滑な推進のために積極的にサポートする責務を意味します。たとえば、要件の中身を早期に確定したり、疑問点を速やかに回答することなどがこれにあたります。
達成責任と実行責任
「達成責任」とは、プロジェクト全体を期日どおりに成功させる目標について責任を持つことです。これは主にプロジェクトマネージャー(PM)の担当となります。一方、「実行責任」とは、現場で具体的な作業や管理を進めることに対する責任で、多くの場合プロジェクトリーダー(PL)が主体になります。PMとPLが役割を分担することで、プロジェクト進行の安定性を確保できます。
その他の基本用語
- ベンダー:開発や運用を請け負う会社や担当者
- ユーザー:システムなどを発注・利用する側の担当者や組織
- プロジェクトマネージャー(PM):プロジェクト全体の指揮・管理を担当する人
- プロジェクトリーダー(PL):実務の現場管理や実行を担当する人
次の章に記載するタイトル:「注記・限界」
注記・限界

本章では、これまでご紹介してきたベンダーの「プロジェクトマネジメント義務」について注意いただきたい事項や限界について整理いたします。
ケースごとの違いについて
プロジェクトマネジメント義務の内容は、多くの場合、特定の契約や具体的な業務内容、またはそのときの運用実態によって大きく左右されます。実際の裁判例を見ても、同じようなシステム開発でも案件ごとに義務の範囲や評価が異なることが多いです。
契約や記録の重要性
プロジェクト開始時にどこまで義務を明記したか、提案書や議事録をどれだけきちんと残したかによって、万が一のトラブル時に「義務を果たしたかどうか」の判断材料となります。現場の実情や交渉の経緯を記録に残しておくことが非常に大切です。
本記事の意図
本記事は、公開されている判例や一般的な情報をできるだけ分かりやすくまとめたものですが、あくまで参考情報の範囲です。個別のお悩みや具体的な契約書作成、トラブル対応など、実際の対応には法的な専門知識が必要となる場合があります。
ご相談のすすめ
少しでも心配や疑問がある場合には、早めに弁護士や専門家に相談することを強くおすすめします。早めのアクションが将来的なリスク回避につながります。