この記事でわかること
- PMBOKの基本概念と10の知識エリアの全体像
- 各知識エリアの定義・目的・実務での活用ポイント
- 試験や現場で特に重視される5つの重要領域
- 5つのプロセス群と知識エリアの関係性(第6版基準)
- 第7版への変化と現場で使える実務チェックリスト
目次
PMBOKの10知識エリアを完全ガイド:定義・実務ポイント・第7版との関係まで

PMBOKとは?
PMBOK(ピンボック)は、プロジェクトを成功に導くためのノウハウや手順をまとめたガイドブックです。書籍やマニュアルのようなイメージで、主にプロジェクトマネージャーが活用します。簡単にいえば「どうやったらプロジェクトをしっかり進められるのか」を整理した道しるべです。
10の知識エリアとは
PMBOK第6版では、プロジェクト管理に必要な内容を10の『知識エリア』に分類しています。これはプロジェクト管理の世界標準として多くの現場で使われています。この分類は、以下の10個です。
- 統合マネジメント:プロジェクト全体の流れをまとめます。
- スコープマネジメント:やるべき範囲をはっきりさせます。
- スケジュールマネジメント:納期に向けて計画や進行を管理します。
- コストマネジメント:予算や経費をしっかり管理します。
- 品質マネジメント:決めた品質を守るように進めます。
- 資源マネジメント:人や物、設備など必要なものを集めて活用します。
- コミュニケーションマネジメント:情報の伝達や共有をスムーズにします。
- リスクマネジメント:トラブルや不安要素に備えて対策します。
- 調達マネジメント:必要なものを外部から調達します。
- ステークホルダーマネジメント:関係者との良い関係を築きます。
この構成はQCD(品質・コスト・納期)の考え方を基盤とし、「何を、いつまでに、どんな質で、どうやって実現するか」を現場ごとに具体化するのに役立ちます。
実務でどう活用するのか
実際のプロジェクトでは、計画段階でこれらの知識エリアすべてを意識し、実行や進捗確認でも適宜参照します。例えば「スケジュールが遅れている」と気づいた際、スケジュールだけでなく関連するコストやリスクも見直す必要があります。知識エリアごとに分けて考えることで、各分野の見落としを減らし、全体最適につながります。
第7版との関係について
PMBOK第7版では知識エリアの並びよりも「原理や価値観」に重きが置かれるようになりました。ですが第6版の10の知識エリアの区分は、今も多くの現場で使われ続けており、基礎的な理解として非常に役立ちます。第7版を学ぶ際も「元になっている考え方」として第6版の10知識エリアを押さえておくと失敗が減ります。
次の章に記載するタイトル:PMBOKと知識エリアの前提:なぜ必要か
PMBOKと知識エリアの前提:なぜ必要か

プロジェクトマネジメントでは、目的やゴールを達成するために、チーム全体で協力して作業を進めていきます。例えば、新しいアプリの開発やイベントの開催など、さまざまな人が関わる大きな仕事には計画的な管理が欠かせません。
こうしたプロジェクトは「どんな目的をどのような手順で、どれくらいの期間とコストをかけて進めるか」を明確にしておかないと、途中で迷走したり、予算オーバーや納期遅延などのトラブルが発生しやすくなります。
そこで、PMBOK(ピンボック:プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)では、プロジェクトを成功させるために何を押さえればよいかを、複数の視点(知識エリア)にまとめています。たとえば「進捗をどう管理するか」「費用はどこまで許容できるか」「成果物の品質をどう保証するか」など、現場でよく直面するテーマごとに整理されているのが特徴です。
このように、知識エリアはプロジェクト運営の基本的な土台や着眼点を体系化する役割を担っています。一通り全体像をおさえることで、抜けや漏れを減らし、関係者と情報を共有しながらプロジェクトをスムーズに進めやすくなります。
次の章では、10の知識エリアの全体像についてご紹介します。
10の知識エリアの全体像(第6版)

10の知識エリアとは
PMBOK第6版では、プロジェクトを成功に導くために押さえておきたい「10の知識エリア」が定められています。具体的には、次の10分野を指します:
- 統合マネジメント
- スコープマネジメント
- スケジュールマネジメント
- コストマネジメント
- 品質マネジメント
- 資源マネジメント
- コミュニケーションマネジメント
- リスクマネジメント
- 調達マネジメント
- ステークホルダーマネジメント
各知識エリアのイメージ
それぞれの知識エリアは、プロジェクト進行に必要な分野をカバーしています。たとえば、スケジュールマネジメントは「いつ何をするか」、コストマネジメントは「どのくらいお金をかけるか」という点に焦点を当てます。品質管理であれば「作るモノやサービスの出来をどうやって良く保つか」を考えます。このように、各エリアはプロジェクトの重要ポイントを担当していると考えてみてください。
中核となる統合マネジメント
10分野の中でも、「統合マネジメント」は特に要となるものです。これはプロジェクト全体を見渡し、個々の知識エリアがうまく連携するよう調整する役割を持ちます。言い換えれば、各領域のバランスを保ちながらプロジェクト成功につなげる舵取り役です。
5つのプロセス群との関係
これら10の知識エリアは、プロジェクトの流れを示す「5つのプロセス群」(立ち上げ・計画・実行・監視コントロール・終結)の各フェーズで必要に応じて関与します。例えば、計画段階では「スケジュール」や「コスト」を考え、実行段階では「品質」や「コミュニケーション」が重要になります。
次の章に記載するタイトル:統合マネジメント(中核領域)
統合マネジメント(中核領域)

統合マネジメントとは何か
統合マネジメントは、プロジェクト全体の運営を一貫性もってコントロールする役割を担います。例えば、計画や実行に関わるさまざまな知識エリア(予算、スケジュール、品質など)をバラバラに扱うのではなく、「全体として一つのプロジェクト」としてまとめ、整合を取るイメージです。
主なプロセス
実際の統合マネジメントは、以下のようなプロセスから成り立っています。
- プロジェクト憲章の作成:プロジェクト立ち上げ時に、目的やゴールを明確にする文書を作成します。プロジェクトのスタート地点として、関係者の合意形成にも役立ちます。
- PM計画書策定:全体計画を整理した文書を用意します。ここでは、ほかの知識エリアと連動しながら管理方針や手順を定めます。
- 作業の指揮・管理:日常のタスク進捗や課題を取りまとめて、プロジェクトを着実に前へ進めます。
- 監視・コントロール:計画と現状のズレを定期的に確認し、必要な調整(修正や優先順位の変更)を行います。
- 統合変更管理:計画外の変更が持ち込まれた場合、その妥当性と影響を評価し、許可すべきか判断します。決められた窓口で「変更申請」を集約するルールが重要です。
- プロジェクトの終結:ゴール達成や中止になった場合に、必要な最終処理や振り返りを実施します。
実務のポイントと具体例
統合マネジメントでは、何より「バランスを取ること」が大切です。たとえば、納期の短縮を求められた場合、「範囲を減らすか、コストを増やすか、品質基準を見直すか」など、関係するすべての要素を考慮して調整を行います。
また、仕様変更や追加要望が頻発する現場では、変更管理を一元化しないと混乱しがちです。申請を一カ所に集めて、影響と優先度を判断する仕組みが役立ちます。
統合マネジメントは、日々の調整や意思決定が多く「まとめ役」「調整役」として大きな責任を担いますが、その分プロジェクトの成否に直結する重要な役割です。
次の章ではスコープマネジメントについて解説します。
スコープマネジメント

スコープマネジメントとは
スコープマネジメントは、プロジェクトで「何を作るか」と「どこまでやるか」をはっきりさせるための考え方と実践です。プロジェクトが進む中で、必要な成果物や作業の範囲があいまいになると、無駄な作業やトラブルが発生しやすくなります。スコープマネジメントでは、それらを防ぐために、はじめにしっかりと範囲を決めて管理します。
主な活動
スコープマネジメントの中で重要な活動は4つあります。
- 要求事項の収集:顧客や関係者の「これをして欲しい」という要望をきちんと聞き出し、整理します。たとえば、家を建てる場合なら「2階建てで南向きの窓が欲しい」といった具体的な希望です。
- WBS(作業分解構成図)の作成:成果物を細かい単位まで分解し、作業の全体像を見える化します。大きな仕事を小さな作業に分けることで、もれや重複を防げます。
- スコープベースラインの設定:決定した作業範囲を「これが基準」として正式に記録します。ここから外れる追加作業には必ず承認手続きが必要になるため、安易な変更を防げます。
- スコープ検証とコントロール:途中や終了時に「本当に決めた範囲内でできているか」をチェックします。不足や過剰な作業があれば軌道修正します。
実務ポイント
スコープマネジメントでは、次の3つのポイントがとても大切です。
- スコープクリープの防止:最初に決めた範囲がいつの間にか広がる現象を「スコープクリープ」と言います。これを防ぐには、追加・変更のたびに正式な承認をもらう運用を徹底しましょう。
- 受入基準の明確化:成果物が「できた」とみなす条件を具体的に決めておくことで、関係者同士の認識違いをなくせます。
- WBSによる成果物中心の分解:作業の抜けやダブりを防ぐだけでなく、「この仕事は何のため?」といった疑問にも答えやすくなります。
次の章ではスケジュールマネジメントについて解説します。
スケジュールマネジメント

スケジュールマネジメントの基本とは
スケジュールマネジメントは、プロジェクトで「いつ・どの作業を・どのくらいの期間」で進めるかを計画し、管理する重要な領域です。たとえば家を建てる場合、「基礎工事→骨組み→内装→引き渡し」といった作業の順序や各工程の所要時間を明確に定めます。これによって無駄な待機や遅延を防ぎ、計画通りにプロジェクトを進めることができます。
主なステップと管理手法
スケジュールマネジメントにおける主なステップは、①作業の洗い出し(アクティビティ定義)、②順序決定、③所要期間の見積もり、④スケジュールの作成・調整の4つです。
管理手法として、以下のような具体的なツールや考え方があります。
- ネットワーク図(作業フロー図):作業の前後関係や流れを図解し、全体像を視覚化します。
- クリティカルパス法(CPM):一番長い作業の流れを特定し、全体の最短完了日を把握します。
- ガントチャート:作業ごとの開始日・終了日を横棒グラフで示し、進捗管理を容易にします。
- ベースライン設定:進捗を正確に比較・評価するため、「当初計画」の基準を設定します。
実務で意識すべきポイント
実務では、計画を立てても状況は変化します。リード(前倒し)やラグ(遅延)といった調整を柔軟に使い、現場の都合やトラブルに対応できるようにしましょう。また、リソース(人や機材)の制約下では、必ずしも理想通りの順序で進められません。「一部を同時進行させる」「余裕期間を設けてリスクに備える」といった現実的な工夫が必要です。
次の章に記載するタイトル:コストマネジメント
コストマネジメント

コストマネジメントは、プロジェクトを成功させるうえで「予算内でやりきること」を主な目標としています。つまり、プロジェクト実行にかかる費用を適切に計画し、進捗をしっかりと管理することがポイントです。ここでは、代表的な実務の流れと重要項目、現場での工夫について解説します。
コストの計画とベースライン設定
まず、プロジェクトを始める際は全体にどれくらい費用がかかるか「見積もり」を行います。このとき、複数の担当や外部要員、資材費なども漏れなく考慮することが大切です。その後、プロジェクト全体を貫く「コストベースライン」を設定します。これは「この範囲までは予算内」と線を引く役割を持ち、プロジェクト終了までの指標になります。
進捗とコストのバランス監視
進行中は、実際に使った金額(実コスト)と、進捗(実際に何割進んだか)を比較します。この時役立つのが「アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)」という手法です。例えば『この時点で半分まで進んでいるはずなのに、実際の支出が半分以上だったら要注意』という具合に、危険信号を早期にキャッチできます。
指標で問題点を発見
EVMでは「CPI(コスト効率指数)」や「SPI(スケジュール効率指数)」という数値を活用します。たとえばCPIが1より低いと「予算より多く使っている」ことを表します。
また、今後プロジェクトを続けた場合に総額でどれくらいになるかを予測する「EAC」も大事です。これにより、必要に応じて対策を練ることができます。
実務の工夫とトラブル時の対応
実際の現場では、スコープ(やるべき範囲)や品質とのバランスが重要になります。範囲が広がるとコストも増えるため、変更管理をしっかり行う工夫が求められます。また「予備費」をあらかじめ確保しておいて予期しない出費に備える実践もよく行われています。
次の章に記載するタイトル:品質マネジメント
資源マネジメント

資源マネジメントとは
資源マネジメントは、プロジェクトを円滑に進めるために必要な「人」「モノ」「設備」など、あらゆるリソースを計画し、手配・活用・管理する知識エリアです。高品質な成果物を作るには、品質マネジメントだけでなく、必要な資源を適切に確保し、その性能や働きが十分に発揮されることが欠かせません。例えば「専門スキルを持ったエンジニアをプロジェクトごとに適切に配置する」「レンタル機材の使用スケジュールを調整する」といった作業が資源マネジメントに該当します。
資源マネジメントの主な活動
- 資源の計画:最初に、プロジェクトにどれくらい・どんな資源が必要か見積もります。人員だけでなく、パソコンや会議室、特殊なツールなども含みます。
- 資源の確保:必要なものを実際に用意します。たとえば、外部パートナーから技術者を派遣してもらうことや、リース機材の手配などがこれにあたります。
- 資源の配分と管理:適切なタイミング・場所で資源が最大限効果を発揮するようにアサイン(割り当て)します。途中で過不足が生じた場合は追加手配や再配置が必要になります。
- チーム育成とモチベーション維持:特に「人」に関しては、スキルアップやコミュニケーション強化、働きやすい環境作りなど、やる気や成長を支える取り組みもこの領域に含まれます。
実務で意識したいポイント
資源マネジメントはただ人やモノを用意するだけでなく、「最適に使い切る」ことが大事です。例えば、全員が役割を理解して動ける体制づくりや、繁忙期は外部リソースを活用して負荷を分散するといった工夫が役立ちます。また、人員のメンタルヘルスやコミュニケーションの工夫も、現場では重要な資源の一部です。
次の章に記載するタイトル:コミュニケーションマネジメント
コミュニケーションマネジメント

コミュニケーションマネジメントは、プロジェクト関係者同士が円滑に情報をやり取りし、誤解やトラブルを最小限に抑えるための領域です。前章で述べたように、計画的かつ効率的に情報を届けること、また問題発生時には速やかに調整が行われることが非常に重要です。この章では、実際の現場で役立つコミュニケーションマネジメントの具体的な取り組みについてわかりやすく説明します。
コミュニケーション計画の立て方
プロジェクト開始時には、関係者が必要とする情報やその提供方法をあらかじめ整理します。例えば、プロジェクトリーダーには週1回の進捗報告、現場メンバーには日次のタスク更新、顧客には月1回の正式レポートといった形です。情報の媒体も、メールだけでなくチャットや会議ツールなど、目的や内容、相手に合わせて選びます。
情報配布の実務
計画で決めた通りに、タイミング良く、必要な情報を届けることが肝心です。例えば、重要な仕様変更があれば、できるだけ早く関係者全員にメールなどで知らせ、混乱を防ぎます。また、情報がきちんと届いたかどうかを確認するのも忘れてはいけません。会議では議事録を共有し、誰にどんな発言や決定があったかを明確にすることも大切です。
問題発生時の対応
コミュニケーションの停滞や誤解から生じる問題にも柔軟に対応します。もし誤った情報が共有された場合には、速やかに正しい内容でフォローを行い、影響を最小限に抑えます。意見の対立があれば、中立的な立場で調整役を設けて話し合い、全員が納得できるよう働きかけることも求められます。
実務でのポイント
実際には、一人ひとり情報を求めるタイミングや度合いが違います。プロジェクトごとに、相手に合った伝え方や配慮が大切です。例えば、ITプロジェクトでは専門用語を避けて説明したり、現場作業なら短い文や図解にしたりと、工夫を重ねることで情報伝達が効果的になります。
次の章に記載するタイトル:リスクマネジメント
リスクマネジメント
リスクマネジメントの基本
リスクマネジメントは、プロジェクトに潜む「予期しない出来事」に備えるための領域です。ここでいうリスクとは「プロジェクトに悪影響を及ぼす可能性のあること」だけでなく、「良い結果につながる可能性」も含みます。たとえば、機材の納品が遅れるリスクだけでなく、予想より早く納品されるというポジティブなリスクも管理します。
主要なプロセスとポイント
リスクの識別:関係者が集まって、どのようなリスクが起こりうるかを洗い出します。現場では「ブレインストーミング」や「過去プロジェクトの振り返り」など、ざっくばらんな話し合いを行います。
リスク分析
- 定性的リスク分析:リスクを重要度や起こりやすさで大まかに分けます。たとえば「発生頻度が高く影響が大きいものは要注意」と分類します。
定量的リスク分析:より深く、数値や確率を使ってリスクがプロジェクト全体に及ぼす影響を計算します。大規模案件で活用されることが多いです。
対応計画の策定:洗い出したリスクに対して、どんな対応を取るか考えます。主な対策には以下のような種類があります。
- 回避:リスクの原因そのものをなくす工夫(例:外注先への依存をやめる)。
- 軽減:リスクが与える影響を少なくする策(例:複数仕入先を確保する)。
- 転嫁:保険や契約でリスクを移すこと(例:損害保険に加入)。
- 受容:やむを得ず、リスクが発生する可能性を受け入れる。
活用:良いリスク(機会)を積極的に追求する。
リスク監視と再評価:プロジェクトが進む中で、リスクの状況や対応策がうまくいっているかを確認し、必要に応じて計画を更新します。
実務でおさえるポイント
- リスクの早期識別:プロジェクト開始時にできるだけ多くのリスクを洗い出します。
- リスクトリガーの設定:リスクが表面化しそうな兆し(例:発注の遅れ)をあらかじめ決めておき、早めに対応できるようにします。
- 残余リスクの管理:どれだけ準備しても消えないリスク(例:天災など)には、発生した場合の具体的な対応案を持つことが大切です。
具体例
例えば、ITシステム開発プロジェクトの場合、「主要メンバーの退職」は重大なリスクです。これに対し、「作業の手順書を整えチームで共有」「メンバー追加を事前検討」などで軽減策を講じます。また、台風による工事の中断など自然災害リスクには、スケジュール調整の余裕やバックアッププランを用意します。
次の章に記載するタイトル:調達マネジメント
調達マネジメント

調達マネジメントとは
調達マネジメントは、プロジェクトで必要なモノやサービスを外部から調達するプロセスのことです。プロジェクトが順調に進むためには、信頼できるパートナーやベンダーを選び、計画通りにものやサービスが届く体制を整えることが求められます。
契約タイプの選定
最初に重要となるのが、どんな契約形態にするかの選択です。たとえば「固定価格契約」なら、費用を確定させたいときに向いています。一方で状況が流動的な場合は「工数払い契約」など柔軟な契約も考慮します。実際には、リスクとコスト、納期がどこまで確定できるかが判断の材料になります。
入札・評価・ベンダ選定
調達の中心は、複数の供給者から見積もり(入札)を取り、その内容と実績などを評価して選ぶプロセスです。その際、単純な価格比較だけでなく、納入実績やアフターフォロー体制なども重要な評価ポイントになります。
スコープ明確化と契約管理
調達範囲を明らかにするため、作業範囲記述書(SOW)や成果物条件(SoR)を準備します。これが曖昧だと期待外れの納品や追加費用が発生しやすくなります。また、納入遅延や成果物の不備を防ぐために、契約変更時のルールやサービスレベルアグリーメント(SLA)の設定も大切です。
ベンダパフォーマンスの管理
調達後は、定期的にベンダーと連絡を取り納品状況やサービスについて確認します。納品物の受入や検収は、要件通りかどうかを丁寧にチェックすることが必要です。問題発生時には速やかに是正措置を講じることが欠かせません。また、複数ベンダーが関係する場合、連携や調整も重要です。
次の章に記載するタイトル:ステークホルダーマネジメント
ステークホルダーマネジメント
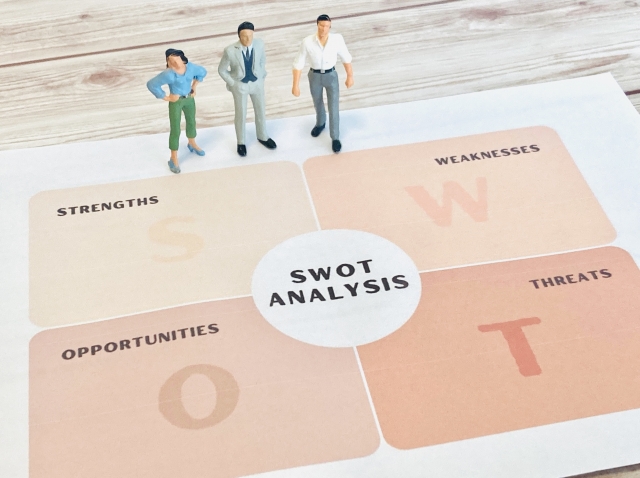
ステークホルダーマネジメントとは
プロジェクトの成功には、関係するすべての人や組織(ステークホルダー)の理解と協力が不可欠です。ステークホルダーマネジメントは、プロジェクトに影響する人々を見極め、その関与を計画し、適切に対応し続ける活動を指します。
ステークホルダーの特定
最初のステップは、プロジェクトに関係するすべての人や団体を明らかにすることです。例えば、プロジェクトの依頼主だけでなく、利用者や現場担当者、他部署の関係者なども含まれます。
関係性や影響度の分析
次に、それぞれのステークホルダーがプロジェクトにどのような期待や不安を持っているか、どの程度影響力があるかを分析します。たとえば、「この人は最終的な決裁権を持つ」「現場から実際の意見を伝える役割」など、役割を可視化することが重要です。マトリクス(表)にまとめると、全体像を把握しやすくなります。
エンゲージメント(関与)戦略の策定
利害関係者の期待や懸念をふまえて、どのように関与を高めていくか計画します。たとえば、影響の大きい人とは定期的に意見交換の場を設けたり、懸念を持つ部署には説明を丁寧に行ったりします。スポンサー(後援者)にはプロジェクトの進捗をこまめに報告して協力を得ることも欠かせません。
情報伝達の優先順位付け
全員に一律の情報を送るのではなく、重要なメッセージや進捗は影響力の強い人や関心の高い人に優先して伝えます。例えば「会議はメールで済ませる」「重要ポイントは個別に説明する」など、効果的な情報伝達方法を選びます。
実務での工夫と注意点
・スポンサーや重要人物とのアラインメント(足並みをそろえる努力)が大切です。
・反対意見や懸念が見える場合には早くから働きかけ、誤解を減らす工夫が重要です。
・ステークホルダーの関係性や状況は時間とともに変化するので、定期的な見直しや対応が求められます。
次の章に記載するタイトル:試験・実務で重視される知識エリア(優先5領域)
試験・実務で重視される知識エリア(優先5領域)

プロジェクトマネジメントの中でも、試験や実際の仕事現場で特に重要とされる知識エリアは、「統合」「スコープ」「スケジュール」「コスト」「リスク」の5つです。これらの領域をしっかり理解し、実践できることが、成果を出せるプロジェクトリーダーの条件とも言えます。
統合マネジメント
プロジェクトの計画作りから実行、完了まで全体をまとめる役割が統合知識エリアです。実務では情報や方針が複雑に絡む場面も多く、計画をまとめたり変更を調整したりする力が求められます。たとえば、目的と手段が食い違っていないかを定期的に確認し、適切な変更を加えることがプロジェクト成功に直結します。
スコープマネジメント
スコープ=「やること」と「やらないこと」を明確にする作業です。業務範囲や納品物の条件が曖昧だと、追加作業や無駄な手戻りが増えてしまいます。そのため、スコープは最初に必ず具体化し、途中でも合意形成を確認する癖が大事です。
スケジュールマネジメント
スケジュールは「時間管理」のことですが、ただ予定を組むだけでなく、遅れやすいポイントを見極め、事前に解消策を考えておくことが重要です。たとえば、複数のタスクが重なる時期や外部依存の多い工程を洗い出し、早めに関係者と調整しておきます。
コストマネジメント
プロジェクト予算を守るため、費用の見積もり・予実管理・調整を行う領域です。予想外の費用発生には、早く気づき、必要に応じて優先事項を見直す冷静な対応が実務で問われます。
リスクマネジメント
リスクは「起こり得る問題や障害」を意味します。リスクを事前に洗い出し、予防策や対応策を用意しておくことが、結果的には納期遅延やコスト増を防ぎます。具体的には、「この作業が遅れた場合はどんな影響があるか」「代替案はあるか」を事前に考えておくのが基本です。
次の章に記載するタイトル:5つのプロセス群と知識エリアの関係(第6版)
5つのプロセス群と知識エリアの関係(第6版)

PMBOK第6版では、プロジェクトマネジメントの流れを5つのプロセス群で整理します。
- 立ち上げ
- 計画
- 実行
- 監視・コントロール
- 終結
この各プロセス群ごとに、これまで説明してきた10の知識エリアが関わります。
プロセス群ごとの役割
まず、立ち上げはプロジェクトの開始にあたり、統合マネジメントやステークホルダーマネジメントが大きな役割を果たします。立ち上げの段階では、プロジェクトの概要や目的を明確にし、関係する人たちの期待を把握します。
次に、計画フェーズでは10の知識エリア全てがバランスよく関与します。例えば、スコープやスケジュール、コストなど各項目の計画がこのタイミングで作成されます。コミュニケーションの進め方やリスク対策もここで明文化します。
実行フェーズでは、主に資源・コミュニケーション・品質などの知識エリアの内容が具体的な活動として発揮されます。他にも計画通り進んでいるかどうかを都度確認しながら進めます。
監視・コントロールフェーズにおいては、統合、コスト、スケジュール、品質、リスクなどの知識エリアが状況の把握と是正に活用されます。進捗の確認や必要に応じての修正がここで行われます。
終結フェーズでは、統合マネジメントや調達マネジメントの観点から、成果物の引き渡しや学びの整理を行います。
5つのプロセス群と知識エリアの関係性まとめ
このように、それぞれの知識エリアはプロセス群のどこかで必ず活用しますが、特に計画フェーズと監視・コントロールフェーズでの比重が高いです。一方、統合マネジメントは、プロジェクト全体を通じて全てのプロセス群に関与し、他の知識エリアの調整役として中心的な役割を果たします。
次の章に記載するタイトル:第7版との関係に一言で触れる
すぐ使える実務チェックリスト(知識エリア別)

各知識エリアを現場ですぐに活かすための項目を、具体的にリストアップします。このチェックリストは、日々の業務で「どこを見落としていないか」「必要な対策がとれているか」を確認するためにお使いください。また、第7版の原則的な視点も念頭に、価値提供の意識を持って活用することが重要です。
1. 統合マネジメント
- 進捗・課題・決定事項をチーム全体で共有できていますか?
- プロジェクトの目標や優先順位は明確になっていますか?
2. スコープマネジメント
- やるべきこと・やらないことがはっきりしていますか?
- 途中で依頼内容が変わった場合、履歴をきちんと残していますか?
3. スケジュールマネジメント
- 工程ごとの締切や担当は明文化していますか?
- 遅延時のリカバリ案を用意していますか?
4. コストマネジメント
- 必要な予算(人件費や資材費など)を把握できていますか?
- 想定外の支出にも備えていますか?
5. 品質マネジメント
- 事前に基準やチェックポイントを決めていますか?
- 不具合発生時の対応手順が整っていますか?
6. 資源マネジメント
- 誰が何を担当し、どんな役割か整理できていますか?
- 欠員が出た場合のフォロー策も考えていますか?
7. コミュニケーションマネジメント
- 連絡ルートが全員にはっきり伝わっていますか?
- 情報共有に「抜け」「伝達ミス」がないか確認していますか?
8. リスクマネジメント
- 起こりそうなトラブルやリスクを事前に洗い出していますか?
- 万一の時の対応方法を決めていますか?
9. 調達マネジメント
- 必要な資材や外部サービスの調達先を決めていますか?
- 契約内容や納期を相手側としっかり確認できていますか?
10. ステークホルダーマネジメント
- 影響を受ける関係者が誰か把握していますか?
- 関係者の期待や要望を定期的にヒアリングしていますか?
次の章に記載するタイトル:すぐ使える実務チェックリスト(知識エリア別)
すぐ使える実務チェックリスト(知識エリア別)

プロジェクトを成功に導くには、日々の業務で知識エリアごとのポイントをおさえることが大切です。ここでは、各知識エリアごとにすぐ使えるチェックリストをまとめました。
統合マネジメント
- プロジェクト憲章が明文化されているか
- プロジェクトマネジメント計画書のベースラインが最新の内容と一致しているか
- 変更リクエストの申請から承認までのフローがチーム内で共有されているか
スコープマネジメント
- 顧客や関係者の要求をきちんと洗い出せているか
- WBS(作業分解図)が作成されているか
- 成果物の受入基準が明確に定められているか
- スコープの検証や承認プロセス(ゲート)が設定されているか
スケジュールマネジメント
- 作業や成果物の順序を整理し、クリティカルパスを見極めているか
- リスクに備えたバッファ(余裕時間)を設定しているか
- 進捗報告の粒度(週次、月次など)を決めているか
コストマネジメント
- EVM(出来高管理)を定期的に運用しているか
- 予備費や予算の管理ルールを決めているか
品質マネジメント
- 品質を確認するための指標(品質メトリクス)が定められているか
- 検査やレビューの計画を作成しているか
- 問題が発生したときの是正処置を記録し、改善策の状況を追跡しているか
資源マネジメント
- 各担当者の役割と責任(RACIチャート)が整理されているか
- 作業量や工程を調整し、担当者の負荷が偏らないようにしているか(負荷平準化)
- プロジェクトに必要なスキルが誰にあるか把握できているか(スキルマトリクスの活用)
コミュニケーションマネジメント
- 各ステークホルダーへの伝達事項や目的、連絡方法(メール、会議など)、頻度を整理しているか
リスクマネジメント
- リスクごとに定性的・定量的な分析を実施しているか
- リスク対応策や担当者を具体的に割り当てているか
- どのイベントや状況で対応が必要か(トリガー)を明確化しているか
調達マネジメント
- 契約のタイプ(定額、出来高など)を適切に選んでいるか、根拠が説明できるか
- SOW(作業範囲記述書)が十分に具体的で漏れがないか
- 変更や追加に備えた条項が契約に含まれているか
ステークホルダーマネジメント
- 各ステークホルダーの影響力や関心度をマッピングしているか
- それぞれのステークホルダーの目標や期待値に合わせてエンゲージメントの方法を定めているか
このチェックリストを使いながら、日々の業務を進めてみてください。どんな規模や業種のプロジェクトでも、知識エリアごとの視点を意識することで、失敗を防ぎやすくなります。