目次
はじめに
「プロジェクトが予定どおり進まない」「メンバーが同じ仕事で手待ちになる」そんな悩みを抱えていませんか?本記事は、リソースの制約を踏まえてプロジェクトを効率化する手法、クリティカルチェーン・プロジェクト管理(CCPM)をやさしく解説します。
まずCCPMは、タスクの順序だけでなく、人や設備といったリソースの使い方に注目します。これにより、無駄な待ち時間や納期遅れのリスクを減らし、プロジェクトの完了を早めることを目指します。
この記事では、理論的背景、特徴、実践のポイント、従来手法との違い、導入時の利点と注意点、具体的な運用例まで、全8章で段階的に説明します。プロジェクト管理を改善したい現場の方や、日々の業務で納期管理に悩むリーダーに役立つ内容です。
読み進めることで、CCPMがどのような場面で効果を発揮するか、実際にどう使えばよいかがつかめるはずです。ぜひ気軽に読み進めてください。
この記事でわかること
- クリティカルチェーン・プロジェクト管理(CCPM)の基本概念と目的
- クリティカルパス法(CPM)との違いとリソース制約への対応方法
- CCPMの導入手順と実践ポイント(バッファ管理・リソース平準化など)
- 導入によるメリットと現場での課題・対策
- 製造・IT・建設など分野別の活用事例と適用のポイント
クリティカルチェーンとは何か
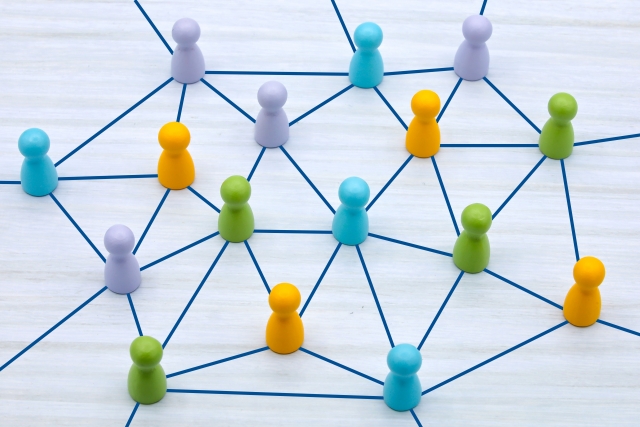
定義
クリティカルチェーンとは、プロジェクトの中で「進行を最も制約する仕事のつながり」を指します。タスクの順序(依存関係)だけでなく、同じ人や設備などのリソースが使えるかどうかも考えます。これにより、実際の遅れ要因を見つけやすくなります。
クリティカルパスとの違い
従来のクリティカルパス法はタスクのつながりだけを見ますが、クリティカルチェーンは『誰が・何を使うか』を加味します。例えば、複数のタスクが同じ専門家に依存していると、その人がボトルネックになりやすい点を重視します。
具体例(製品開発)
新製品の設計で、電気設計と機構設計が順番に必要で、さらにテストは専門技術者が担当する状況を想像してください。たとえタスクの順序が短くても、専門技術者が不足すると全体が遅れる可能性があります。ここで重要なのがクリティカルチェーンです。
簡単な見つけ方
- タスクと依存関係を洗い出す
- 各タスクに必要なリソースを明記する
- リソースの競合で遅れる可能性が高い連鎖を特定する
なぜ重要か
リソースの制約を取り込むことで、現場で起きる遅延を未然に防げます。結果として、納期の信頼性が高まり、無駄な余裕時間を減らせます。
CCPMの背景と特徴

背景:なぜ生まれたか
CCPMはエリヤフ・ゴールドラットが提唱したTOC(制約理論)に基づく手法です。従来のCPM(クリティカルパス法)は作業間の順序を重視しますが、現場では人や機械といった"リソース"の制約や、見積もりの不確実性がスケジュール遅延の主原因になることが多いです。例えばエンジニアが複数案件を掛け持ちすると、担当の切替で全体が遅れます。CCPMはこの点に着目しました。
基本の考え方
各タスクを最短で見積もり、余裕は個々に入れずにまとめて『バッファ』として置きます。さらにリソースの競合を避けるため、重要な経路(クリティカルチェーン)に着目して作業順や割り当てを調整します。これによりムダな安全余裕を減らしつつ、全体の遅延に備えます。
主な特徴と具体例
- タスク見積もりを短くする:個別の余裕を削り、現実的な最短見積もりで管理します。例:デザイナーの作業を短めに見積もる。
- バッファを集約する:プロジェクトバッファ(最終納期保護)とフィーディングバッファ(重要経路への影響防止)を設けます。例:複数ページの制作終了前にまとめて余裕を置く。
- リソース平準化:人の多重作業を減らし、優先順位で割り当てます。例:限られたエンジニアをクリティカル作業に集中させる。
- 進捗はバッファ消費で見る:予定との差ではなく、バッファの残りで健全さを判断します。
留意点
実践には習慣の変化が必要です。個々のタスクに安全余裕を戻す誘惑を抑え、バッファの消費をこまめにチェックする運用が求められます。それでも、導入すればリードタイム短縮や納期安定化といった効果が期待できます。
クリティカルチェーン法の実践ポイント

プロジェクトでクリティカルチェーン法(CCPM)を実践する際の具体的なポイントを、現場で使える形でまとめました。
1. クリティカルチェーンの特定
まず、タスクの順序と担当リソースを見て最長の制約列を探します。例:同じエンジニアが続けて関わる作業が遅れると全体が遅れる場合、その流れがクリティカルチェーンです。
2. 個別バッファをなくしプロジェクトバッファを設定
各タスクの余裕時間を取り除き、プロジェクト終端にまとめたプロジェクトバッファで遅延を吸収します。これにより各担当者が余裕に頼らず、作業に集中できます。
3. リソース平準化(リソースレベリング)
担当者や設備の重複を避けるために作業開始日時を調整します。たとえば、同じ設計者に仕事が集中するなら順番をずらし、待ち時間を減らして遅延リスクを下げます。
4. フィーディングバッファの配置
クリティカルチェーンに合流する枝分かれ箇所にはフィーディングバッファを置きます。合流での遅れがチェーン全体に波及しないようにする工夫です。
5. 日常運用ルール
・優先順位はクリティカルチェーンにあるタスクを最優先にする
・マルチタスクを減らし一つを完成させる習慣をつける
・毎日の短い進捗確認でバッファ消費を報告する
6. モニタリングと対応
バッファ消費率を見える化し、消費が進んだら速やかに原因対応します。目安はプロジェクトバッファが半分以下になった段階での優先的な対策です。
7. よくある落とし穴
・個々のタスクに安全余裕を残すと全体効率が下がる
・マルチタスク放置で遅延が拡大する
現場では短いルールと可視化を徹底し、小さな改善を積み重ねることが大切です。
クリティカルチェーンとクリティカルパスの違い

概念の違い
クリティカルパス法(CPM)は作業の順序と最長経路に注目し、スケジュールの最短化を図ります。クリティカルチェーン法(CCPM)は順序に加えて人員や設備といった“資源”の取り合いも考慮します。例:一人の設計者が複数タスクを抱える場合、CPMは見落としがちです。
バッファ管理の違い
CPMは各タスクに余裕時間を持たせます。一方CCPMは個別の余裕を削り、プロジェクト全体の「プロジェクトバッファ」と、経路を守るための「フィーディングバッファ」で安全余裕を集中管理します。結果、無駄な先延ばしを減らせます。
リソース競合への対応
CCPMはリソースの優先順位を決め、同じ人や設備が並行するタスクで滞りを起こさないよう調整します。現場では機械や専門技術者がボトルネックになるケースで特に効果を発揮します。
どちらを選ぶかの目安
- 人や設備が頻繁に共有される現場:CCPMを推奨
- 依存関係が極めて強く、資源に余裕がある現場:CPMで十分
導入時の実務的な注意点
CCPMはバッファの設定と運用ルールが重要です。バッファ消費を可視化し、優先順位に基づく割り当てを徹底すると効果が出やすくなります。
CCPM導入のメリットと課題

概要
CCPM(クリティカルチェーンプロジェクトマネジメント)は、プロジェクト全体の遅れを減らすために「余裕時間(バッファ)」を戦略的に使う手法です。本章では導入で期待できる効果と現場で出やすい課題を分かりやすく説明します。
メリット
- 遅延リスクの早期発見:バッファの消耗状況で問題を把握できます。早く対策を打てます。
- 無駄な待ち時間の削減:リソースが長時間待機する状況を減らし、作業をスムーズに回せます。
- 全体最適化:個別のスケジュールよりプロジェクト全体を優先し、納期を守りやすくなります。
具体的な効果(例)
- 開発チーム:複数人が同じテスト環境を待つ時間を減らし、リードタイムを短縮します。
- 製造現場:部品の供給遅れに対し、バッファで吸収してライン停止を回避します。
主な課題と対策
- 正確な状況把握が必要:誰がどの作業をしているかをリアルに把握できないと効果が落ちます。対策として、日次の進捗報告や簡易な可視化ツールを導入します。
- バッファ運用の定着:バッファを守る文化がないとすぐに浪費します。運用ルールを明確にし、教育や小さな試行で習慣化します。
- 依存関係の整備:作業の前後関係を正確に定義する必要があります。関係者とのワークショップで洗い出します。
導入のポイント
現場の声を取り入れ、まずは一部プロジェクトで試行します。効果を数値で示し、成功事例を積み重ねて全社展開へつなげると導入が進みます。
具体的な運用例・活用シーン

製品開発プロジェクト
設計→試作→評価→量産という流れで、専門チームが順に作業します。各段階の所要時間を専門家の稼働率に合わせて計画し、設計遅延や評価での手戻りはプロジェクトバッファで吸収します。例:電子機器開発で基板設計者の作業がボトルネックなら、設計バッファを設けて試作やテストの遅れを回避します。
IT・システム開発
複数部署が並行して作業するとき、リソース競合を管理します。バックエンド担当とフロント担当、QAが順に機能を受け渡す場面で、統合バッファを置くと統合時の遅延を吸収できます。実務では、担当者の割り当てを固定してマルチタスクを減らすと効果が高まります。
建設・製造業
クレーンや専門技能者の重複利用が多い現場で有効です。例えば躯体工事と設備工事で同じ技能者を使う場合、技能者に依存する工程をクリティカルチェーンに組み込み、機材バッファや作業順序を調整して待ち時間を減らします。
小規模・研究開発チーム
人手が限られる場合は、タスクを短く区切って優先順位を明確にし、バッファで緊急対応を賄います。中断を減らし、一人当たりの集中時間を確保すると成果が出やすくなります。
運用の実務ポイント(簡潔)
・重要資源(人・設備)を特定して保護する
・バッファの消耗を定期的に監視する
・短い計画サイクルで修正を繰り返す
・視覚化してチームで共有する
これらを現場に合わせて調整すれば、遅延の早期発見と安定した納期管理につながります。
まとめ:クリティカルチェーンはどんな現場で有効か

概要
クリティカルチェーン(CCPM)は、依存関係が複雑で、限られた資源を複数の作業が争う現場で効果を発揮します。進捗のばらつきや遅延リスクをバッファで管理し、リソースを集中させて効率化します。
有効な現場(具体例)
- 製造の組立ライン:部品や技能者が共有され、順番待ちが発生する現場で短縮効果が出やすいです。
- ソフトウェア開発:複数チームが同じテスト環境や専門家を待つ場合に有効です。
- 建設・設備工事:機械やクレーンなどの高価な資源を効率的に回す必要がある現場。
- 研究開発:不確実性が高く、フェーズ間の依存が強いプロジェクトに適します。
導入時のポイント
- まず小規模なプロジェクトでパイロット実施し効果を確認してください。
- タスクの依存関係と資源割当を正確に洗い出します。
- バッファは過度に大きくせず、実績で調整します。
- 経営層や現場の理解を得て、割り込みや多重タスクの抑制を徹底します。
向かない場面
短期で単純な作業や、リソースに余裕があり競合がほとんどない場合は、導入効果が小さいです。
最後に
複雑な依存とリソース競合があるプロジェクトでは、従来の管理手法よりも実践的な改善が期待できます。まずは試験導入で運用感を掴み、段階的に広げると良いでしょう。