この記事でわかること
- プロジェクトマネジメント業務委託の仕組みと特徴
- PM/PMO委託の契約形態(請負・準委任)の違い
- 外部委託のメリット・デメリットと注意点
- 委託人材・会社の選び方と契約書作成のポイント
- フリーランスPM/PMO市場の最新動向と今後の展望
目次
プロジェクトマネジメント業務委託とは

プロジェクトマネジメント業務委託とは、企業が自社のプロジェクトを円滑に進めるために、外部からプロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の人材を業務委託契約で迎え入れる方法です。従来は、プロジェクトの責任者を自社の社員が担うケースが一般的でした。しかし、近年では、より高い専門知識や豊富な経験を持つ外部プロフェッショナルを起用する流れが広がっています。
この業務委託形態では、委託されたPMやPMO人材は、特定のプロジェクト期間中だけ業務に携わるのが特徴です。例えば、新しいシステムの導入プロジェクトや、会社の大規模な改革プロジェクトなど、期間限定で成果が求められる場面で活用されています。
雇用契約と異なり、業務委託は会社と個人または外部企業が対等な立場で契約を結びます。委託を受けた側は自身の専門性を活かして、独立した視点から課題解決を支援します。働く側もフリーランスや他社所属者として、より柔軟で自律的な働き方ができるのが特徴です。
このプロジェクトマネジメント業務委託を活用することで、企業は社内にないノウハウや人材リソースを効率的に補うことができ、プロジェクトの成功確率を高めることができます。
次の章では、「PM/PMO委託の主な契約形態」について詳しく解説します。
PM/PMO委託の主な契約形態
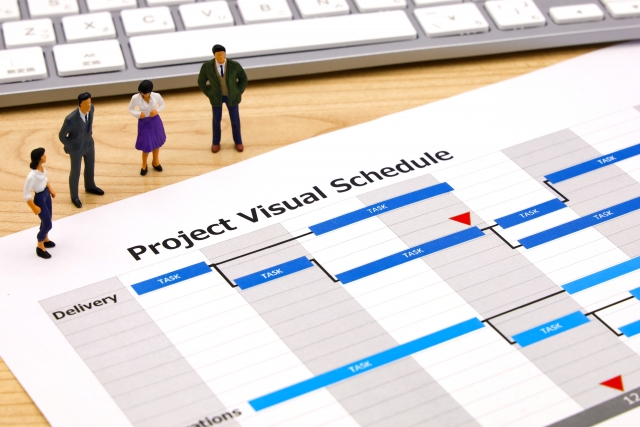
契約形態の違いについて
PM/PMO(プロジェクトマネージャー/プロジェクトマネジメントオフィス)の業務委託では、大きく分けて2つの契約形態があります。ひとつは「請負契約」、もうひとつは「準委任契約」です。ここでは、それぞれの特徴と違いについて分かりやすく解説します。
請負契約
請負契約とは、成果物(たとえばシステム、書類、製品など)の納品が前提となる契約です。発注側は「この日までにしっかり成果を出してください」と依頼し、受注側は内容・品質・納期を守る責任を持ちます。例えば「○月○日までに、プロジェクトの進捗報告書を完成させてください」といった具合です。この契約形態は、業務のゴールや、どんな成果を出せばよいかがはっきりしている場合に向いています。
準委任契約
一方で準委任契約は、成果物そのものの納品が必ずしも求められません。「業務をきちんと進行すること」自体に対して報酬が発生します。例としては「毎週定例会に参加し、進捗管理や関係部署との調整をしてください」といった業務です。そのため、日々の進行状況の管理や、会議調整、資料作成など、プロジェクトの運営そのものを支える仕事に適しています。成果物で評価しにくい業務の場合、より柔軟に業務範囲を調整できる点が特長です。
PM/PMO業務に多い契約形態
PM/PMOの業務は、資料作成やスケジュール管理、体制づくりや会議運営など、「進め方」や「過程」に重きを置くことが多いです。したがって、成果物よりも業務の過程や支援内容を重視する準委任契約が選ばれるケースが多くなっています。ただし、プロジェクトによっては一部業務のみ請負契約とする場合もあり、状況に合わせて契約形態を使い分けます。
具体例
たとえば新しいITシステム導入プロジェクトでは、「計画書の作成・納品」は請負契約で発注する一方、「各種会議の運営や日々の進捗管理」は準委任契約で依頼することもあります。このように、実際のプロジェクト現場では複数の契約を組み合わせることも珍しくありません。
次の章では、PM/PMO委託のメリット・デメリットについて解説します。
PM/PMO委託のメリット・デメリット

PM/PMO委託の主なメリット
まず、外部のプロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に業務を委託することには、いくつかの大きな利点があります。自社で即戦力となるPM人材を採用し、育成するには時間やコストがかかりますが、外部委託を活用することでその負担を大きく減らすことができます。また、短期的なプロジェクトや特定の時期だけ専門家が必要な場合にも、必要な期間だけ外部の力を借りることができ、無駄のない人材活用が可能です。
さらに、委託先のPMやPMOには多岐にわたる業界やプロジェクト経験があります。たとえば、異なる分野のプロジェクトを多数経験してきた専門家を呼ぶことで、自社にはないノウハウや新しい手法、客観的な視点を取り入れることができます。これにより、自社のプロジェクト運営のレベルアップや問題解決につながるケースも多く見られます。
PM/PMO委託の主なデメリット
一方で、外部委託には注意点もあります。外部の専門家が自社の文化や業務に精通するまでには時間がかかります。そのため、プロジェクトによっては細かな業務の理解が十分でないまま対応しなければならないこともあります。
また、企業の大切な情報を外部に共有することになるため、情報管理や機密保持の観点で細かいルール設定や契約管理が欠かせません。たとえば、プロジェクトの進捗や成果物に関する情報を漏らさないよう、秘密保持契約を必ず結ぶなどの工夫が必要です。
さらに、外部委託の活用は、あくまで「必要な期間だけ専門家を呼ぶ」という側面が強いため、自社の担当者がノウハウを身につけたり、組織全体のスキル向上につなげたりすることが難しい場合があります。長期的に見ると、自社メンバーの成長やナレッジの蓄積が進みにくいという点は、意識しておきたいポイントです。
次の章では、PM/PMO委託の業務内容と求められるスキルについて説明します。
PM/PMO委託の業務内容と求められるスキル
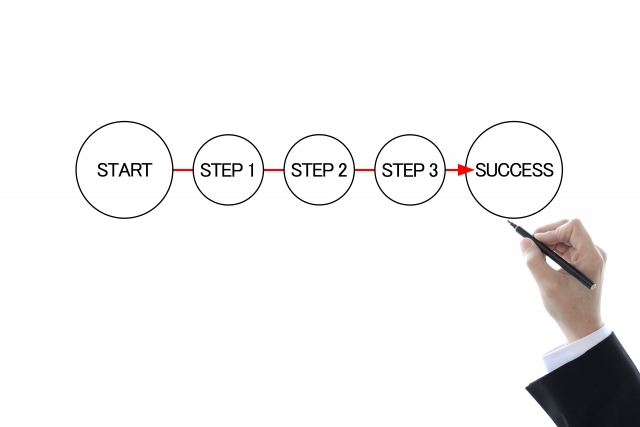
PMおよびPMOの業務委託は、多岐にわたる業務が含まれているのが特徴です。ここでは、主な業務内容とそれに対応するスキルについて具体的にご紹介します。
主な業務内容
まず、プロジェクトの目的やゴールを明確にし、計画を立てることが基本です。この段階では、プロジェクトが目指す成果や達成したい期限、必要となる資源を整理します。
次に、プロジェクトの進み具合を定期的に確認し、予算や品質を管理します。たとえば、スケジュール通りに進んでいるか、コストが計画以上にかかっていないか、成果物が期待通りの品質かを見守る役割です。
また、メンバーの役割分担やリソースの配分も重要な仕事となります。チーム全体が効率よく働けるように、それぞれの得意分野や状況を考慮して業務を割り振ります。
さらに、関係者(ステークホルダー)とコミュニケーションをとり、要望や意見の調整、進捗状況の報告を行います。ここでは、クライアント企業の担当者や外部パートナーと密にやり取りをすることが求められます。
加えて、突発的なトラブルやリスクが発生した場合の対応も重要です。課題等が見つかった際には、迅速に解決策を考え、プロジェクト全体に及ぼす悪影響を最小限に抑える必要があります。
最後に、プロジェクトチームの目標を明確にし、メンバーの士気を高めながら進行をリードすることもPMやPMOの重要な役割です。
求められる主なスキル
これらの業務を円滑に進めるためには、いくつかのスキルが求められます。
まず、プロジェクト管理の手法についての知識が必要です。例えば「WBS(作業分解構成図)」や「ガントチャート」といった道具を使って、作業の流れやスケジュールを分かりやすく可視化する力が役立ちます。
続いて、調整能力や交渉力、コミュニケーション力が不可欠です。たとえば、メンバーや関係者の意見に耳を傾け、互いの意見の違いを理解し、最適な解決策を提案する場面が多々あります。
また、リーダーシップも大事な要素です。チームメンバーの意見を引き出し、ときには背中を押しながら、プロジェクトの成功に向けてまとめ上げる力が求められます。
さらに、ITや製造業など、さまざまな業界や業種に対応できる柔軟性や適応力も評価されます。プロジェクトによっては、専門用語や独自の商習慣にも素早く慣れ親しむことが重要です。
次回は、「PM/PMO委託会社・人材選びのポイント」についてご紹介します。
PM/PMO委託会社・人材選びのポイント

信頼性や過去実績の確認
まず、委託会社や人材を選ぶ際は、その信頼性と過去の実績をしっかり確認することが大切です。例えば、これまでにどのようなプロジェクトを手がけたのか、プロジェクトの規模や業界、得意とする管理手法などを具体的に調べましょう。実際の導入企業名やプロジェクト事例をホームページや資料で公開している場合もあります。
コミュニケーション力や柔軟性
次に重視したいのが、コミュニケーション力です。PMやPMOは多くの関係者と橋渡し役を担うため、相手の立場を理解し、円滑にやりとりできることが不可欠です。さらに、突発的な課題にも柔軟に対応できる姿勢があることも、プロジェクト成功につながります。例えば、仕様変更や急なトラブル時にも落ち着いて対応する力を確認しましょう。
コストパフォーマンス(料金体系・費用対効果)
費用の面でも、料金体系や費用対効果を比較検討することが必要です。単に金額だけでなく、提供されるサービス内容と結果をしっかり見極めましょう。例えば、月額固定料金と成果報酬型の違い、追加費用が発生する場合の条件なども事前に把握しておくと安心です。
自社プロジェクトへの専門性・適合性
最後に、自社のプロジェクトニーズに合った専門性を持つ人材・会社かどうかを見極めることが重要です。例えば、ITシステム導入であればIT分野の実績や知識があるか、製造業プロジェクトなら業種特有のノウハウが求められます。自社の業界経験や過去案件の内容を面談や提案書でしっかり確認しましょう。
次の章に記載するタイトル:業務委託契約書作成の注意点
業務委託契約書作成の注意点
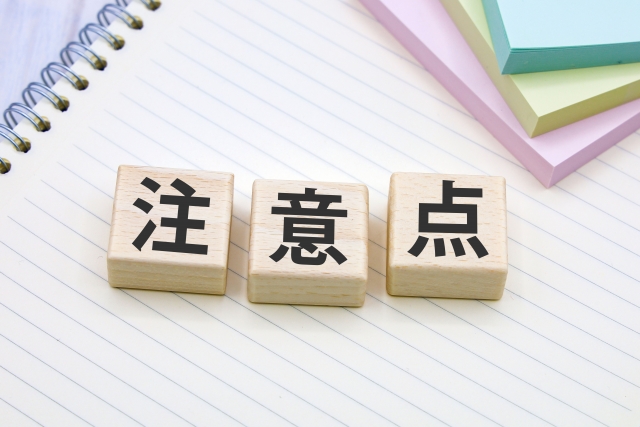
プロジェクトの目的・範囲を明確にする
契約書には、プロジェクトで何を達成したいのか、どこまでが業務範囲かを具体的に記載します。例えば「新しいシステムの導入」といった大枠だけでなく、「A部署とB部署の業務を対象とする」「既存システムとの連携も含める」など、できるだけ細かく定めておくことが大切です。
業務内容とスケジュールの具体化
どのような作業を、いつまでに、どのような順序で進めるのかを明確にします。たとえば「要件定義」「進捗報告の頻度」「納品のタイミング」など、工程ごとに具体的な内容を書きます。これにより、お互いのイメージ違いによるトラブルを防ぐことができます。
成果物・納品物の定義
完成とみなす条件や、納品するもの(例:報告書、システム設計書など)を事前に決めておくことが重要です。あいまいな表現を避け、「成果物Aは○○の機能を持ち、テスト完了後に納品」といったかたちで明記しましょう。
報酬・支払い条件を明確に
報酬の金額や支払い時期・方法を細かく決めておくことで、金銭トラブルを防ぎます。例えば「月末締め翌月末払い」「成果物ごとに分割して支払い」など、支払いのルールを明確にします。
機密保持・知的財産権の取り扱い
契約期間中や納品後に知り得た情報を外部に漏らさないよう、機密保持条項を設けることが一般的です。また、契約で作成した成果物の権利がどちらに帰属するかもはっきり記載しておく必要があります。
契約期間・解約条件
契約の有効期間や、途中で契約を終了したい場合の手続き方法(例:事前通知の有無や期間)をルール化しておきましょう。これにより、予期しない中断時もスムーズに対応できます。
変更管理・リスク対応手順を設定する
プロジェクトの途中で仕様変更や予想外のトラブルが起きた場合に備え、どのように合意形成を図るか、対応手順や責任分担も定めておきます。たとえば「仕様変更は書面で合意し、追加費用についても協議する」などの規定を契約書に盛り込みます。
次の章に記載するタイトル:市場動向・フリーランスPM/PMOの活躍
市場動向・フリーランスPM/PMOの活躍

IT業界におけるPM/PMO委託の広がり
近年、IT業界を中心としてプロジェクトマネジメント業務の委託案件が大きく増えています。特にシステム開発やサービス導入など、専門性や多様なノウハウが求められる現場では、外部のPM(プロジェクトマネージャー)やPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)を活用する動きが定着しています。
在宅・リモート型業務の増加
以前はプロジェクト現場への常駐が一般的でしたが、最近ではテレワークの普及により、在宅やリモート形式でPM/PMO業務を行う案件が多くなっています。会議や書類作成、進捗管理などをオンラインで完結できるため、遠隔地からでも十分に活躍することが可能です。
フリーランス・副業人材の活用
企業は多様なプロジェクトに対し、社内リソースだけでなく外部のフリーランスPM/PMOや副業キャリア人材の力を借りるケースが増えています。専門性や経験を持つ人が、複数の現場でノウハウを発揮することで、効率的かつ柔軟な体制を構築できます。
例えば、ある大手企業が新しいシステムを導入するとき、リーダー役となるPMを週数日だけ外部から招き、必要に応じて副業人材がデータ整理や会議運営を分担する、といった事例が増えています。こうした働き方が認められることで、雇用の枠にとらわれない多様なキャリア形成も可能となっています。
今後の展望
プロジェクトの複雑化と多様化により、専門スキルを持ったフリーランスPM/PMOへのニーズは今後も高まると考えられます。企業側も必要な期間・人材を柔軟に選びやすく、働く側も自分の専門分野や希望条件に合わせて案件を選びやすくなっています。
次の章に記載するタイトル:まとめ
まとめ

これまで、プロジェクトマネジメント業務委託について、その具体的な形態、メリット・デメリット、必要なスキルや人材選びのポイントなど、さまざまな観点から解説してきました。プロジェクトマネジメントの業務を外部に委託することで、社内リソースの効率的な活用や専門的なノウハウの導入が可能になります。とくに近年では、柔軟な働き方や外部の専門性が重視される傾向が強まっており、多様なバックグラウンドを持つプロジェクトマネージャーやPMOが活躍しています。
業務委託を成功させるためには、委託の目的や自社の課題を明確にすることが重要です。そして、信頼できる人材やパートナー会社の選定、納得のいく契約内容の締結がプロジェクト推進の大きなポイントとなります。見積書や契約書などの書類には細心の注意を払い、業務範囲や責任の明確化も忘れないようにしましょう。
業務委託は、単なるコスト削減策ではなく、プロジェクト成功のための戦略的な選択肢です。これらのポイントを意識して、社内外の力を最大限に活かし、ぜひプロジェクトマネジメントの効率化や成功に役立ててください。