目次
- ISO 21500とは何か—プロジェクトマネジメントの国際規格の全体像
- ISO 21500の構成—プロセス群とサブジェクト(知識)グループ
- PMBOKとの関係—「事実上の標準」と「国際規格」の役割分担
- JIS Q 21500(ISO 21500)でのPMとPMOの定義
- 組織標準化への適用—ISO 21500を使って成熟度を高める
- 認証はあるのか—第三者認証と実務上の意味
- ISO 21500ファミリーとガバナンスの含意
- 国内での位置づけ—JIS Q 21500と関連フレーム
- 用語・知識の参照リソース
- 能力開発と資格—ISO 21500/PMBOKの学習と証明
- 実務適用のステップガイド(例)
- 補足情報源の信頼性と使い分け
- 補足情報源の信頼性と使い分け
ISO 21500とは何か—プロジェクトマネジメントの国際規格の全体像
ISO 21500とは、プロジェクトマネジメント(PM、つまりプロジェクトの計画から実行、完了までを管理すること)について、国際的に共通した枠組みを示す規格です。ISO(国際標準化機構)が策定しており、業種や会社の大きさに関係なく、誰でも参照できるガイドラインを提供しています。たとえば、建設会社が大規模なビルの建設を進める場合も、IT企業が新しいサービスの立ち上げを管理する場合も、共通した考え方や手順を使って進めることができます。
日本では、この国際規格がJIS Q 21500:2018として採用されています。これは、ISO 21500:2012の内容を日本の実情に合わせて国内規格としたものです。そのため、国内の企業や団体でも「世界基準」のマネジメント方法に基づいてプロジェクトを進めることができるという利点があります。
また、ISO 21500は「ファミリー」と呼ばれる一連の関連規格の中の最初の規格でもあります。プロジェクトだけでなく、複数のプロジェクトをまとめて管理する「プログラム」や、さらに大きな単位で戦略的に複数のプロジェクトやプログラムを束ねる「ポートフォリオ」を対象とした規格も順次整備されてきました。ISO 21500はこうした体系の中核をなす存在です。
さらに、この規格は単にプロジェクト個別の進め方だけでなく、組織の日常業務(オペレーション)とプロジェクト活動の関係や、全体としてのガバナンス体制(経営から見た管理の仕組み)についても指針を与えています。経営陣から現場担当者まで、幅広い視点でプロジェクトを支えるための基本とされるものです。
次の章では、ISO 21500の具体的な構成について解説します。
この記事でわかること
- ISO 21500(JIS Q 21500)の概要と国際的な位置づけ
- PMBOKとの関係と使い分け方
- PM/PMOの定義と組織標準化への活用法
- 認証・ガバナンス・国内規格との関係
- ISO 21500を実務に適用するための具体的ステップガイド
ISO 21500の構成—プロセス群とサブジェクト(知識)グループ

ISO 21500は、プロジェクトマネジメントを体系的に学ぶうえで、とても分かりやすい構成になっています。大きな特徴として、プロジェクト実施の流れを「プロセス群」と「サブジェクト(知識)グループ」に分けて整理している点が挙げられます。
5つのプロセス群
ISO 21500のプロセス群は、プロジェクトを始めるところから終わらせるところまでの「流れ」に沿っています。具体的には、以下の5つです。
- 立上げ(Initiating):プロジェクトの目的や進め方をはっきりさせ、関係者の合意を得る段階です。
- 計画(Planning):具体的な計画やスケジュール、リスク対策などを決めます。
- 実行(Implementing):計画に基づいて、実際の作業を進めるステップです。
- 監視・コントロール(Controlling):進み具合をチェックし、必要なら軌道修正します。
- 終結(Closing):プロジェクトを成功裏に締めくくり、成果をまとめます。
これらの流れを押さえることで、プロジェクトがどんな段階を経て進んでいくのか、一目で把握できます。
10のサブジェクト(知識)グループ
サブジェクトグループは、プロジェクト運営で押さえておくべき"テーマ"をまとめたものです。たとえば「スコープ管理」(やることの範囲の管理)や「リスク管理」(問題が起きる前の備え)、他にも「タイム」、「コスト」、「品質」などがあります。それぞれのテーマごとにポイントを押さえて、プロジェクトがスムーズに進みやすくなっています。
用語・定義の充実と図解
ISO 21500では、16の主要な用語をわかりやすく定義しています。これにより、用語の誤解が少なくなり、プロジェクトを進めるうえでの共通認識が持てます。また、プロセス群とサブジェクトグループの関係や、各プロセスの入出力、相互作用などを図で示しているため、全体像が直感的に理解しやすいのも特徴です。
こうした仕組みにより、実際の現場でISO 21500を使う際にもチーム全体で認識を揃えやすくなります。次の章では、「PMBOKとの関係—『事実上の標準』と『国際規格』の役割分担」について解説します。
PMBOKとの関係—「事実上の標準」と「国際規格」の役割分担

プロジェクトマネジメントの分野では、PMBOK(Project Management Body of Knowledge)が長らく“事実上の標準”として世界中の多くの企業や組織で採用されてきました。PMBOKは、プロジェクト管理に関する知識やノウハウを体系立てて整理したもので、現場で役立つ具体的な手法やツールが豊富に紹介されています。たとえば、進捗管理のガントチャートやリスク分析といった実践的な方法がPMBOKには詳しくまとめられています。
一方、ISO 21500は「国際規格」としての役割を果たしています。ISO 21500は、世界各国で通用する共通の土台となることを目指し、より上位の視点からプロジェクトマネジメントの全体像や基本的な原則、組織構造との関係などを示しています。例えて言えば、PMBOKが“詳細な設計図”だとすると、ISO 21500は“その設計図を使うためのルールブック”のような存在です。
両者は対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。現場でPMBOKを使って具体的なプロジェクト管理を実践しつつ、その根拠や基本方針をISO 21500で定める、という使い分けが可能です。日本国内でも、ISO 21500はJIS Q 21500:2018として位置づけられ、公式ガイドでは「PMBOKをベースとする国際規格である」と明記されています。
このように、詳細な知識体系としてのPMBOKと、共通ルールとしてのISO 21500は、それぞれの強みを持ちながらプロジェクト管理を支え合っています。
次の章に記載するタイトル:JIS Q 21500(ISO 21500)でのPMとPMOの定義
JIS Q 21500(ISO 21500)でのPMとPMOの定義

JIS Q 21500(ISO 21500)の規格では、プロジェクトマネジャー(PM)とプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の役割を明確に定義しています。
プロジェクトマネジャー(PM)の定義
PMは、「プロジェクトの活動を指揮し、マネジメントして、プロジェクトの完了に説明責任を負う」というのが公式な定義です。つまり、PMはプロジェクトの実行を主導し、計画の作成から現場の指揮、関係者との調整、目標の達成に向けた推進まで、幅広い責任を担っています。たとえば、新しい商品を開発するプロジェクトであれば、PMは開発スケジュールの策定、進捗管理、関係各所とコミュニケーションをとりながら全体の意思決定に責任を持ちます。
プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の定義
一方で、PMOは「ガバナンス、標準化、教育訓練、計画、監視などの多彩な活動を遂行できる組織的機能」とされています。PMOは個別プロジェクトを直接指揮するのではなく、複数のプロジェクトを横断的にサポートし、プロジェクトの成功率を高めるための仕組みづくりやルール定着をリードします。
具体的には、プロジェクト全体で使う統一ルール作りや、PM向けの研修、進捗データの一元管理、リスク対策方針の策定などがPMOの仕事です。このように、PMが個々のプロジェクトの目標達成に集中する一方で、PMOは組織全体のプロジェクト管理力向上を後押しします。
両者の役割の違い
両者はプロジェクトマネジメントに関わるという共通点がありますが、責任の領域が異なります。PMは“現場”の責任者で、直接成果を出す役割です。PMOは“組織”の視点からルールや支援を提供し、間接的に成果をサポートします。
次の章に記載するタイトル: 組織標準化への適用—ISO 21500を使って成熟度を高める
組織標準化への適用—ISO 21500を使って成熟度を高める

ISO 21500を使う意味とは
ISO 21500は、プロジェクト管理のための国際標準です。これを使うことで、組織全体のプロジェクトマネジメント手法を統一し、品質や進捗の管理がブレにくくなります。社内のプロジェクトごとにやり方が異なると、結果にムラが出やすいですが、共通のフレームワークを設ければ、誰でも迷わず実行できます。
標準化の進め方(ギャップ分析)
まず、あなたの組織の現状を整理しましょう。現場で実際に行われているプロジェクト管理のやり方と、ISO 21500に記載されたプロセス群や知識エリア(サブジェクト)とを比較します。たとえば、「進捗管理」や「リスク対応」「情報共有」など、ISO 21500で示されている項目が、自社でどう実施されているかを確認します。その差(ギャップ)が、改善余地のあるポイントです。
PMOの活用による定着・成熟度向上
組織標準を作るだけでは、現場に浸透しないことも多いです。そこで、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の役割が重要になります。PMOは、標準化された手法を社内に広めて教育し、プロジェクト遂行中の監督やサポートも担います。また、定期的なプロジェクトレビューも実施することで、運用状況をチェックし、継続的に改善につなげていく役割もあります。
規模や業界に関係なく活用できる
ISO 21500には、特定の業界やプロジェクトの大きさに限定される記述はありません。中小企業から大手企業まで、独自のやり方に適度にカスタマイズして導入できます。例えばIT開発はもちろん、建設・サービス・製造業など幅広い分野で、プロジェクト運営の基礎を整えたいときにも役立ちます。
次の章に記載するタイトル:認証はあるのか—第三者認証と実務上の意味
認証はあるのか—第三者認証と実務上の意味

多くの方が「ISO」と聞くと、ISO 9001のような認証取得を思い浮かべるかもしれません。しかし、ISO 21500は品質マネジメント規格と異なり、プロジェクトマネジメントの「ガイダンス」、つまり指針に位置づけられています。そのため、ISO 21500そのものには第三者による公式な認証制度が用意されていません。
実際の現場では、この規格を直接「取得」するのではなく、内容を自社のプロジェクト管理ルールや手順として取り入れ、それらがISO 21500の考え方に基づいていることを示すことが主な活用方法です。例えば、社内基準を整備した上で「当社のプロジェクト管理はISO 21500に準拠しています」と自己適合宣言をしたり、外部から説明を求められた際に「このルールは国際規格に沿っています」と説明したりします。
また、自社で運用するプロジェクトマネジメントの仕組みを、監査やレビューの場でISO 21500との整合性を確認することも推奨されます。こうした実践によって、社内外への信頼性や説明責任を果たす材料として活用できるのが特徴です。
ただし、ISO 9001のような型通りの公式審査や認証書の発行は、ISO 21500には原則として存在しません。万が一、「ISO 21500認証取得」としている場合は、その内容や根拠をよく確認しましょう。
次の章に記載するタイトル:ISO 21500ファミリーとガバナンスの含意
ISO 21500ファミリーとガバナンスの含意

ISO 21500ファミリーとは何か
ISO 21500をもとにした規格には、通常「ファミリー」と呼ばれる一連の関連規格が存在します。たとえば、プロジェクトのみを対象にせず、プログラムや複数プロジェクトを束ねるポートフォリオに関する指針も含めます。これらを合わせて、PPP(プロジェクト・プログラム・ポートフォリオ)と呼びます。それぞれが独立して存在するのではなく、互いに関連し合って、組織全体の戦略実現や運営の中で調和して働きます。
組織ガバナンスとの関係
これまでは「一つのプロジェクトを成功させる」ことに主眼が置かれがちでした。しかし、ISO 21500ファミリーの考え方では、プロジェクトは組織の目標や方針、戦略に沿って実施する必要があるとされています。つまり、プロジェクト単独で完結せず、プログラムやポートフォリオといった“上位の枠組み”に組み込まれており、経営や組織運営(ガバナンス)の一部として管理されます。
実感しやすい具体例
たとえば、企業が新商品を開発する場合、その商品開発プロジェクトだけでなく、同時進行する他の商品開発(プログラムの一部)、全体の事業戦略(ポートフォリオ)との調整が必要です。さらに、品質確保やリスク管理、倫理面への配慮といったガバナンスも重要となります。
求められる発想の転換
これにより、プロジェクトマネージャーや運営に関わる人たちには、単にプロジェクトをうまく運営すればよいという考え方では足りません。組織全体の方針や戦略にそって活動し、他のプロジェクトや事業の動きも踏まえたうえで最適な成果を目指す必要があります。
次の章に記載するタイトル:国内での位置づけ—JIS Q 21500と関連フレーム
国内での位置づけ—JIS Q 21500と関連フレーム

JIS Q 21500は、日本国内向けのプロジェクトマネジメント標準規格です。これは、国際的なISO 21500:2012を基に2018年に導入されました。この規格は、プロジェクト運営の基本的な流れや考え方を整理したものです。企業や団体が自分たちのプロジェクト運用方法を標準化しやすくなるように支援しています。
日本独自の特徴として、JIS Q 21500に加えて、他にもいくつかの有力なフレームワークが使われています。例えば、「P2M(プロジェクト&プログラムマネジメント標準)」は、日本プロジェクトマネジメント協会が定めている指針で、社会インフラや大規模な業務改革など、より複雑で幅広いプロジェクトにも対応できるよう設計されています。また、情報システムの分野では、IPAが策定した「共通フレーム(SLCP)」が活用されており、システム開発に必要な手順や成果物を明確にしています。
このように、JIS Q 21500は国際標準の枠組みを日本の現場向けに調整したものですが、現場での運用ではP2Mや共通フレームといった補完的な基準も一緒に利用されることが多いです。プロジェクトの種類や組織の特性によって、複数のフレームワークを組み合わせ、最適な管理方法を模索する土壌が日本国内にはあります。
次の章に記載するタイトル: 用語・知識の参照リソース
用語・知識の参照リソース
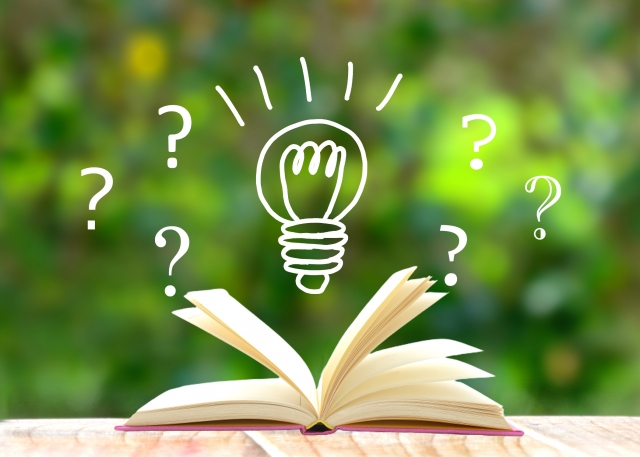
プロジェクトマネジメントに登場する「プロジェクトライフサイクル」や「PMIS(プロジェクトマネジメント情報システム)」、「プロジェクトマネジメント計画書」、「PMO」、「PM」などの基礎的な用語は、しっかり理解することが重要です。これらの用語は、主にPMBOK(Project Management Body of Knowledge)に基づいた用語集で、日本語と英語の対訳の形で整理されています。
このような用語集は、ISO 21500とPMBOKとを比較しやすくし、国際基準との整合を確認する助けにもなります。実際にPMBOKに登場する用語はISO 21500でも多く使われているため、用語を正しく押さえることで、異なる基準間でも混同せずに理解できます。
用語集の例としては、PMI日本支部や、一般社団法人プロジェクトマネジメント学会が公開している資料があります。これらの資料では、日英対訳だけでなく、その用語の定義や使い方も説明されており、初心者でも分かりやすいです。また、JIS Q 21500(ISO 21500の日本工業規格版)自体の末尾にも正式な用語対応表が載っている場合があります。
このようなリソースを参照しながら学ぶことで、プロジェクトマネジメントの知識を体系的に深めることができます。
次の章に記載するタイトル: 能力開発と資格—ISO 21500/PMBOKの学習と証明
能力開発と資格—ISO 21500/PMBOKの学習と証明
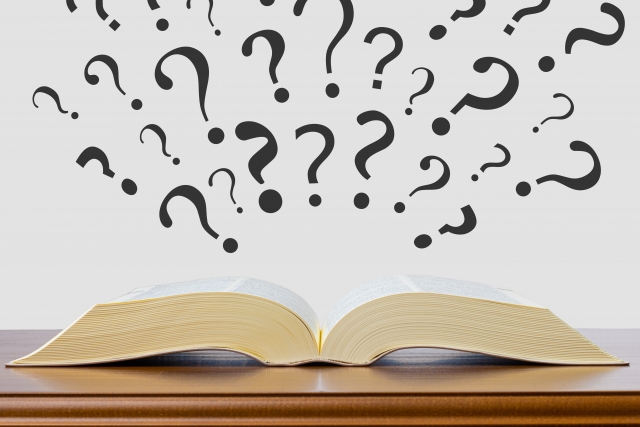
プロジェクトマネジメントの能力を開発する方法
プロジェクトマネジメントの知識やスキルは、実務経験と体系的な学習の両方で養えます。例えば、プロジェクトの進行管理や課題対応といった現場の経験に加え、ガイドラインとしてISO 21500やPMBOKの内容をテキストや研修で学ぶことが重要です。書籍やオンライン講座には具体例やケーススタディが多く、未経験者にもイメージしやすい内容が揃っています。
国家資格と国際資格の違い
日本の「プロジェクトマネージャ試験(IPA)」は、情報処理技術者試験の一つでIT分野に特化しています。毎年春・秋に実施され、論述も必要なため、本格的な対策が求められます。合格すると、IT系のプロジェクトマネジメント能力保有を公的に証明できます。
一方、PMP(Project Management Professional)はPMIが運営する世界的な資格です。PMBOK(ピンボック)というガイドラインに沿って出題され、取得のためには実務経験や講習の受講が必須です。幅広い分野で通用するため、IT以外の業界にも活用できます。このような資格は国境を越えたビジネスでも評価されやすい点が特徴です。
資格取得の意義と社内体制
資格取得は、個人のスキルだけでなく組織の標準化や品質向上にも寄与します。たとえばPMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)がある企業では、社員の能力開発を積極的に推進し、ISO 21500に即したルール策定や教育プログラムを展開することができます。こうした取り組みにより、複数プロジェクトを円滑に進め、トラブルを未然に防ぐ体制作りが可能です。
次の章に記載するタイトル:実務適用のステップガイド(例)
実務適用のステップガイド(例)

1. 現状診断の進め方
まず、自社のプロジェクト管理の現状を把握しましょう。ISO 21500は「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」という5つのプロセス群と、10のサブジェクト(知識分野)で構成されています。実際に行っているプロジェクトの進め方をこのフレームで棚卸ししてみてください。たとえば、「計画」プロセスでリスクの対応策をきちんと検討しているか、「監視・コントロール」プロセスでKPIを活用しているかなど、項目ごとに現状・不足・重複・不整合を洗い出すことが大切です。
2. 標準設計のポイント
次に、ISO 21500やJIS Q 21500が示す考え方に沿って、自社で使う「標準」を設計します。ここではPM(プロジェクトリーダー)やPMO(プロジェクト管理事務局)が担う作業・責任範囲をはっきり分けましょう。プロジェクト計画書、WBS(作業分解図)、リスク登録簿といった必要な文書フォーマットや、チェックリストを用意すると実務に根付きやすくなります。プロジェクトの進み具合を判定する「ゲート」や「レビュー」のタイミングを明確にしておくと、一人ひとりの役割の理解が深まります。
3. ロールアウトの取り組み
標準ができたら、すぐ現場に展開しましょう。PMOが主体となって、関係者向けの教育や説明会を実施するのが効果的です。また、作ったテンプレートやガイドを実際のプロジェクトで活用してもらい、PMOが定期的にレビューや監視を行います。プロジェクト横断で進み具合を見える化するKPIを使い、全体的な改善に役立ててください。
4. ガバナンスとの接続
最後に、これらの取り組みを自社の経営や全体戦略とつなげます。PMOが経営層と密に連携し、プロジェクトの優先順位付けや資源の配分、事業戦略との整合などの意思決定に反映しましょう。これにより、プロジェクトマネジメントの仕組みが単なる現場ルールではなく、全社一丸で推進できる仕組みとなります。
次の章に記載するタイトル:留意点—PMBOK第7版との読み替え
補足情報源の信頼性と使い分け

ISO 21500やPMBOKを学ぶ際には、さまざまな参考書籍やウェブサイト、講座が存在します。しかし、すべての情報源が同じ水準で信頼できるわけではありません。たとえば、書店で入手できる解説書は、著者の背景や発行年によって内容や重点が異なることがあります。また、ウェブ検索で見つかる記事は、必ずしも公式な解釈や最近のガイドラインを反映していない場合があります。そのため、情報を利用する際は、発行元や著者が誰か、情報の日付が新しいか、内容が公式文書と整合性があるかなどを丁寧に確認しましょう。
また、信頼のおける情報源としては、国際規格や日本産業規格(JIS)、PMIやIPMAなどの公式資料が挙げられます。これらは最も原典に近く、各種説明や翻訳も正確性が高い傾向にあります。独学の場合には、まず公式資料や公的機関が発信するガイドラインに目を通し、不明な点を補完的な書籍やセミナーで補う方法が効果的です。公式と二次的な情報をうまく使い分けることで、誤解なく学び進められます。
次の章に記載するタイトル:補足情報源の信頼性と使い分け
補足情報源の信頼性と使い分け

プロジェクトマネジメントに関する標準やガイドラインを理解・活用する際、参照する情報源の信頼性と選び方は重要です。ISO 21500の解説については、公式文書やEUOCI(欧州公式解説)が標準の骨子や構造、PPP(プロジェクト・プログラム・ポートフォリオ)やガバナンスに関して最も基礎的で正確な情報を示しています。ですので、原則としてこれらの原典に基づく確認が推奨されます。
一方、国内での適用やJIS化、PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)やPM(プロジェクト・マネジャー)の定義に関しては、日本語の解説書やJIS Q 21500を紹介するサイト、またPMO専門サイトなどの情報も有効です。日本の状況に即した実例や行政の立場が分かるため、標準文書と合わせて利用することで現場での具体化がしやすくなります。
認証や第三者機関による審査については、各機関が独自の審査スキームやガイドラインを持っています。情報は分散しやすく、ひとつの文献だけでは分かりづらい場合があります。実際に認証取得を検討する際は、必ず複数の審査機関や最新の公式資料を確認し、分からない点は問い合わせるなど慎重な対応が求められます。
また、解説記事や専門家のコラムからは、実務現場での応用や注意点、PMBOKとの役割分担など、現場で役立つ知恵が得られます。ただし、執筆者の経験や主観が入ることも多いので、公式文書との整合性を意識しながら参考にしてください。
このように、補足情報源は目的や状況にあわせて使い分けることが大切です。公式の標準書を基盤としつつ、国内の実情や現場の声を補強材料としてバランスよく活用していくと、ISO 21500関連の知識や運用がより確かなものとなります。