はじめに
この記事の出発点
本ドキュメントは、三井ホームのプロジェクトマネジメントグループについて、組織の役割、実際のプロジェクト推進事例、キャリアパス、今後の展望をわかりやすくまとめます。あわせて、三井ホームグループの事業展開と技術的な強み、グループ横断の大規模プロジェクトを支える管理体制、チームワークの大切さ、サステナビリティへの取り組みも取り上げます。
目的
- 三井ホームグループの全体像と、その中でのプロジェクトマネジメントグループの位置づけを理解していただくこと
- 現場での推進事例を通じて、仕事の進め方や価値を具体的にイメージしていただくこと
- 社内でのキャリアパスや身につくスキルを知り、働き方の参考にしていただくこと
- 企業としての将来像とサステナビリティの考え方を、実務と結びつけて捉えていただくこと
対象読者
- 住宅・建設分野やものづくりの仕事に関心がある方
- プロジェクトの進め方に興味がある新入社員・就職活動中の方
- 部門横断での連携やマネジメントの工夫を知りたい社内外の関係者
キーワードの簡単な説明
- プロジェクトマネジメント:限られた期間と予算で目標を達成する進め方です。例として、家づくりで「設計」「材料の手配」「工事の調整」「引き渡し」の段取りを整えることが挙げられます。
- グループ横断:部門や会社の枠を越えて協力することです。たとえば、設計部・施工部・営業部が同じ計画表で動くイメージです。
- サステナビリティ:環境や社会に配慮して長く続けられる取り組みです。省エネの設計や廃材の削減など、日々の実務に置き換えて考えます。
読み方のガイド
- まず全体像をつかみたい方は、次章の「グループの概要と事業展開」から読むと理解が進みます。
- 実務のヒントを得たい方は、「プロジェクトマネジメントグループの役割」と「推進事例」を中心にご覧ください。
- 働き方や学びに関心がある方は、「キャリアパス・業務内容」を先に読むと具体性が増します。
この記事でわかること
- 三井ホームグループの事業概要と技術的な強み
- プロジェクトマネジメントグループの役割と特徴
- 実際のプロジェクト推進事例と成果
- 社員のキャリアパスと日々の業務内容
- サステナビリティと今後の展望
三井ホームグループの概要と事業展開

前章のふり返り
前章では、本記事の狙いと読み進め方を示し、家づくりを支えるプロジェクトの全体像をやさしく紹介しました。読者の疑問を整理し、具体例を交えながら「人」と「しくみ」が連動する大切さを確認しました。この流れを受けて、本章ではグループ全体の姿と事業領域を見ていきます。
企業の位置づけと理念
三井ホームは、三井不動産グループの住宅部門を担う大手ハウスメーカーです。企業理念は「暮らし継がれる よろこびを未来へ」。住まいを長く大切に使えることを軸に、家族の変化や地域とのつながりまで視野に入れたものづくりを進めています。
主要な事業領域
- 戸建注文住宅: 家族構成やライフスタイルに合わせて、一邸ずつ設計します。例えば、共働き世帯に合わせた回遊動線や、在宅ワークに配慮した静かな書斎など、暮らし方から間取りを決めます。
- 賃貸住宅: アパートや長屋などの集合住宅を企画・設計・施工します。入居者の安心とオーナーの運用を両立させるため、防音や断熱、維持管理のしやすさに配慮します。
- 公共・商業施設の木造建築: 保育園、クリニック、店舗などを木造で建てます。木の温かみを活かしながら、使いやすさや安全性を重視します。
- 大規模再開発プロジェクトへの参画: 複合開発の一部で木造の強みを活かし、住宅や関連施設の計画・建設に取り組みます。まちづくりの視点で品質とデザインを両立させます。
技術の強み: ツーバイフォーとプレミアム・モノコック
- ツーバイフォー工法: 規格化した木材と板材で箱のように面を作り、家全体を支える工法です。面で支えるため地震や風に強く、気密・断熱の取りやすさにもつながります。
- プレミアム・モノコック構法: 卵の殻のように「面」で力を受け止める考え方をさらに高め、骨組みと面材を一体化させて剛性を高めます。これにより、耐震性、断熱性、静音性、耐久性のバランスを高い水準で保ちやすくなります。
グループ会社と一貫体制
グループには、三井ホームリンケージ、三井ホームエンジニアリング、三井ホームエステート、三井ホームデザイン研究所などがあります。これらの会社が連携し、設計、施工、賃貸管理、技術研究までを一貫体制で支えます。例えば、設計段階での技術検証が施工の精度向上につながり、建物引き渡し後の管理・運用の知見が次の設計や技術研究に戻るといった循環が生まれます。
一貫体制が生む価値
- 品質のばらつきを抑える: 設計の意図が施工や検査にまで通じ、仕上がりを安定させます。
- スピードと見通しを高める: 部門間の連絡が速く、計画変更があっても影響範囲を早く見極めます。
- 長期の安心を提供する: 住み始めてからの点検・修繕・運用まで同じグループが関わるため、相談先が明確です。
事業展開の広がりと身近な例
木造の技術を核に、個人の住まいから地域の施設まで幅広く対応します。例えば、子どもの安全と居心地を大切にした保育園、静けさと清潔感が求められるクリニック、周辺景観に配慮した店舗など、用途に合わせた設計で価値を高めます。住まいづくりで培った断熱や耐震の考え方を、これらの施設にも応用します。
次の章に記載するタイトル: プロジェクトマネジメントグループの役割と特徴
プロジェクトマネジメントグループの役割と特徴

前章の振り返りと本章の位置づけ
前章では、三井ホームグループの全体像や事業領域、グループ各社が連携して価値を生む仕組みを紹介しました。その土台の上で、横断的にプロジェクトを動かす要の存在がプロジェクトマネジメントグループです。本章では、その役割と特徴を分かりやすく解説します。
なぜ「プロジェクトマネジメントグループ」が必要か
大規模案件や複数社が関わる取り組みでは、担当ごとの最適化だけでは全体がばらけやすくなります。たとえば、設計・施工・オフィスづくり・運用の担当者が、それぞれの都合で進めると、スケジュールやコスト、品質のバランスが崩れます。これを防ぐために、全体を見渡し、関係者の力を一つに束ねる司令塔が必要です。
中心的な役割(司令塔としての具体像)
- 全体計画の設計と更新:プロジェクト全体の予定表(マスタースケジュール)を作り、遅れや重複を早期に調整します。
- 合意形成の推進:意思決定のポイントを事前に明確化し、関係者の意見を整理して「いつ・誰が・何を決めるか」をはっきりさせます。
- リスクと課題の管理:発生しやすい懸念を洗い出し、優先順位をつけて対策を実行します。例:部材の納期遅延に備えた代替案の準備。
- 資源の最適配置:グループ内のノウハウや人材、外部パートナーを統合し、最適なチームを素早く編成します。
- コミュニケーション設計:会議体、報告フォーマット、共有ルールを整え、情報の行き違いを減らします。
特徴(三井ホームグループならではの強み)
- 領域横断の連携力:三井デザインテックと三井ホームグループのメンバーが、役割や領域を超えて連携します。設計と施工、オフィスづくりと働き方の議論を同じテーブルで進めます。
- 意思決定の速さ:意思決定の順番と条件をあらかじめ合意することで、迷いを減らします。
- 見える化の徹底:進捗、課題、責任者をシンプルなボードや一覧で共有します。専門用語を減らし、誰でも理解できる表現に整えます。
- 利用者視点:完成した空間や仕組みを使う人の体験を軸に、設計・施工・運用の判断を統合します。
具体例でみる役割の発揮
2024年に実施した「三井ホームグループ5社の本社オフィス統合プロジェクト」では、限られた期間の中で、全体の予定表どおりに完遂しました。成功の鍵は「チームワーク」と「領域横断の協力意識」です。
- チーム編成:必要な専門家を早期に招集し、役割を明確化。重なりや抜けをその場で調整。
- 意思決定の見取り図:決める順番(例:働き方の方針→レイアウト→設備仕様)を先に共有し、戻り作業を抑制。
- 連携の場づくり:定例会議に加え、短時間の立ち会いミーティングで悩みを即時解消。
- 完成像の共有:コンセプトと利用シーンをイラストやモックで可視化し、検討を前に進めました。
日々の進め方(シンプルな運用の例)
- 週:全体の予定表を更新し、優先課題を3つに絞って合意します。
- 日:担当者ごとのタスクを確認し、遅延の芽があればその日のうちに対策を打ちます。
- 会議体:意思決定会議と作業調整会議を分け、会議の目的を明確にします。
- 情報共有:1ページの要点資料で、経営層・現場・外部パートナーに同じ事実を伝えます。
よくある誤解と本当の役割
- 誤解:「タスク管理をする人たち」
- 実像:タスクや進捗の管理に加え、グループ各社の知見とリソースを統合し、最適な意思決定を導く存在です。目的は、スピード・品質・コストのバランスを保ちながら成果を最大化することです。
関係者にもたらす価値
- 経営層:判断材料が整理され、決定が速くなります。
- 現場担当:迷いが減り、手戻りが少なくなります。
- 利用者:使いやすさを起点に設計が進むため、完成後の満足度が高まります。
実際のプロジェクト推進事例
実際のプロジェクト推進事例
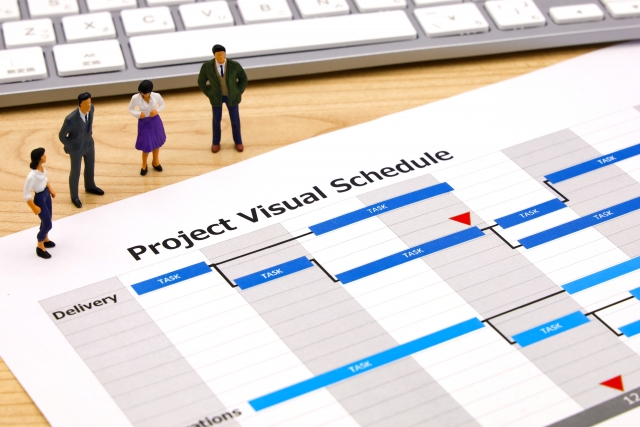
前章の振り返りと本章のねらい
前章では、プロジェクトマネジメントグループの役割と特徴を、組織横断の調整力と、品質・コスト・スケジュールを同時に管理する進め方という観点から紹介しました。本章では、その実像が伝わるように、2024年の本社移転プロジェクトの進め方を具体的にお伝えします。
プロジェクトの背景とゴール
移転先は「新木場センタービル」です。グループ5社を1拠点に統合し、次の50年を見据えた経営基盤を強くすることが大きな目的でした。単なる引っ越しではなく、働き方やオフィスの価値を見直す機会として位置づけました。
推進体制とコミュニケーション
プロジェクトマネジメントグループが中心となり、設計・施工・運営計画を一体で管理しました。
- 意思決定の場を定例化し、誰が何を決めるかを明確化
- 週次の進捗会議で課題を早期共有し、担当と期限を即時設定
- 変更点は「なぜ必要か」「影響範囲はどこか」をセットで説明
フェーズ別の進め方
1) 構想・計画フェーズ
- 各社の業務量と人数、来客パターンを調査
- フロア配置と動線を複数案で比較検討
- 基本方針(集中・協働・交流のバランス、木材活用の考え方)を策定
2) 設計・調達フェーズ
- 会議室や執務席の標準寸法・設備条件を統一
- 重要工事は相見積もりでコストを確認
- 試作(モックアップ)で机やブースの使い勝手を事前検証
3) 施工・内装フェーズ
- 現場確認を定期化し、写真とチェックリストで品質を記録
- 仕上材や家具の色味・質感を日中光で確認
- 設備の試運転と避難導線の動作確認を実施
4) 移転実行フェーズ
- 週末に段階的に移動して業務停止を最小化
- 搬入動線とエレベーター予約を事前に調整
- ネットワークと電話の切替テストを本番前に実施
5) 稼働後の安定化
- 1カ月・3カ月で利用サーベイを実施
- 混雑するスペースを可視化し、席や会議室の配分を調整
- 小さな不具合の受付窓口を一本化し、対応時間を短縮
管理の工夫(スケジュール・品質・コスト・リスク)
- スケジュール管理:主要な節目(設計完了、引渡し、移転日)を見える化し、遅延の芽を週次で摘み取りました。
- 品質管理:モックアップで「実際の見え方」と「使い心地」を確認し、図面上の齟齬を現物で解消しました。
- コスト管理:高額項目に上限を設定し、見積りが超えた場合は代替材や仕様の再整理で調整しました。
- リスク管理:「もし〇〇が起きたら」を事前に洗い出し、停電・輸送遅延・天候悪化などに備えた手順を用意しました。
具体シーンで見る工夫
- 会議室仕様の統一:5社でバラバラだったコンセント位置や画面接続方式を一本化し、どのフロアでも同じ感覚で使えるようにしました。
- 段階移転:部署ごとの繁忙期を避けて順番に移動し、問い合わせ窓口を暫定と本番で分けることで混乱を最小化しました。
- 木材の活用:受付や共有ラウンジに木の仕上げを採用し、手触りと香りで来訪者・社員の心理的な落ち着きを高めました。
- 再利用と循環:使える家具は修繕して再配置し、廃棄物を抑えました。結果としてコストと環境負荷の双方を軽減できました。
サステナブルなワークプレイスの創造
木の可能性を活かすため、構造材だけでなく、パーティションや什器にも木質要素を取り入れました。室内の反射や音の響きを抑え、集中と対話の両立を図りました。素材の来歴が追えるものを優先し、長く使える設計と交換しやすい部材構成で、将来のレイアウト変更にも備えています。したがって、働き方の変化に合わせてムダなく進化できるワークプレイスになりました。
成果と得られた学び
5社が同じビルに集まり、日常の連携が自然に生まれやすくなりました。移転直後は設備の使い方に戸惑いが出ましたが、現場での簡単な説明会と動画ガイドで早期に解消しました。プロジェクトマネジメントグループは、意思決定の速さと現場の安心感を両立させることの重要性を再確認しました。これは今後の拠点開発や改修にも生きる学びです。
次に記載するタイトル:組織内でのキャリアパス・業務内容
組織内でのキャリアパス・業務内容

前章の振り返りと本章の位置づけ
前章では、実際のプロジェクト推進事例を取り上げ、計画づくりから引き渡しまでの流れと、社外設計士・現場・社内の連携方法、品質を守るための工夫を紹介しました。本章では、その土台を踏まえ、プロジェクトマネジメントグループに所属する社員のキャリアパスと日々の業務を具体的にお伝えします。
配属直後の役割(アシスタント期)
入社・異動直後は、先輩PMのもとで小さなタスクから担当します。
- 会議設定と議事録作成:決定事項と宿題を誰でも追える形で整理します。
- 図面・資料の整理:最新と旧版を取り違えないように管理します。
- 社外設計士との連絡補助:依頼内容を簡潔にまとめ、回答期限を明確に伝えます。
- 品質チェック表の更新:チェック結果を一覧化し、抜け漏れを防ぎます。
この段階で、柔軟なコミュニケーションと段取り力の基礎を身につけます。
中堅期の役割(小〜中規模案件のPM)
経験を重ねると、小〜中規模案件で設計PMを担います。設計PMとは、設計の進み具合を管理し、関係者の合意を整え、次の工程へ渡す役割です。
- 進行管理:週次の計画をつくり、遅れの芽を早めに潰します。
- 変更管理:要望変更が出たら、費用・工期・品質への影響を見える化します。
- 成果物レビュー:図面や仕様書を読み、矛盾や抜けを指摘します。
- 設計監理:現場で「設計どおりにできているか」を確認します。
- 工事推進:職人さんやメーカーの段取りをそろえ、工期を守ります。
外部の設計士とは、依頼書の明確化、キックオフの合意形成、中間レビュー、最終確認の4つの節目を大切にします。
上級期の役割(大規模案件・複数案件の統括)
上級者は、複数案件の全体最適を図ります。
- 体制設計:案件の難易度に応じて、設計PM・工事側のPM・監理担当を組み合わせます。
- リスクレビュー:契約前・設計確定前・着工前などの節目で第三者目線の点検を行います。
- 標準化:よくある課題に対し、チェックリストやテンプレートを整えます。
- 育成:若手とペアを組み、実案件で学べる機会をつくります。
社内設計担当が「チェック機構」として機能するよう、ダブルチェックや現場パトロールを仕組み化します。
キャリアパスの選択肢
一人ひとりの強みを生かせるよう、複数の道があります。
- マネジメント系:大型案件の統括PM、組織運営、品質審査のリーダー。
- 専門系:意匠・設備・コストなど特定分野の深掘りで社内の相談役に。
- 横断系:営業支援、標準仕様づくり、設計支援ツールの導入など。
途中で道を行き来することも可能です。小規模案件で広く経験し、その後に専門性を磨く流れが一般的です。
日々の業務の流れ(例)
- 朝:当日の優先順位を3つに絞り、関係者と共有します。
- 午前:外部設計士との図面レビュー。指摘は重要度順に伝えます。
- 午後:現場確認。写真と簡潔なコメントで記録します。
- 夕方:進捗の差分を整理し、翌日の計画に反映します。
求められる力と身につけ方
- コミュニケーション:相手が動きやすい指示を出す練習をします。
- 課題発見と解決:起こりそうな問題を「見える化」し、対策を先に打ちます。
- 図面読解:図面間の矛盾を見つける力を鍛えます。
- 文書化:決定事項・根拠・期限を短く正確に残します。
育成は、OJT、メンター制度、レビュー会、外部研修を組み合わせます。
評価と成長の目安
- 納期遵守と手戻り削減
- 品質指標の達成(不具合件数の低減など)
- 顧客満足度と再依頼
- 改善提案の数と定着度
成果だけでなく、プロセスの透明性やチーム貢献も評価対象です。
外部設計士との連携ポイント
- 依頼内容は「目的・範囲・納期・判断基準」を1枚にまとめます。
- キックオフで役割分担と連絡ルールを合意します。
- 中間レビューで方向性を早めに修正します。
- 設計変更は履歴を残し、最新版を一目で分かるようにします。
案件規模別の担当範囲(例)
- 小規模(店舗改装など):設計PMが設計・監理・工事段取りまで広く担当します。
- 中規模(オフィス改装など):設計PMと工事側PMで役割を分担します。
- 大規模(複合施設など):統括PMのもとで設計PM、工事PM、監理担当がチームで動きます。
つまずきやすい点と乗り越え方
- 要件の曖昧さ:最初に「やらないこと」も明確にします。
- 関係者の合意形成:決定に必要な人だけを集め、期限を先に決めます。
- スケジュール遅延:前倒しで確認し、代替案を常に2つ用意します。
今後の展望とサステナビリティ
今後の展望とサステナビリティ

前章の振り返り
前章では、組織内でのキャリアパスと業務内容を取り上げ、現場での経験と学びが人材の成長を生み、その成長がプロジェクトの質を高める好循環を紹介しました。育成の仕組みや横のつながりが、実務の強さにつながる点をお伝えしました。
サステナブルな木造が拓くこれから
三井ホームグループは、木の持つ再生可能性と温かさを軸に、まちと人にやさしい建築を広げていきます。木は成長過程で二酸化炭素を吸収し、建物になっても長く蓄えます。私たちは、この性質を活かした住まい・オフィス・公共施設を増やし、暮らしの質と環境価値を同時に高めていきます。
脱炭素への具体策
- 省エネと創エネの両立:断熱性の高い外皮と高効率設備を標準化し、屋根や外構での発電を組み合わせます。
- ライフサイクルでの削減:設計段階から資材量を抑え、工場で部材をあらかじめ作る方法で無駄を減らします。
- 長寿命化:更新しやすい構造・設備とし、手入れをしながら長く使える建物を目指します。
木造マンションの推進
都市でも木の建物が当たり前になる未来を見据え、耐火・耐震の工夫を積み重ねて安全性を高めます。例えば、階ごとに振動を抑える仕組みを取り入れたり、耐火被覆で火に強い層を作ったりします。暮らし心地の面では、木の質感をいかした共用部や、可変性のある間取りで長く愛される住まいを計画します。
人が主役のワークプレイス
働く場は、集中と交流を切り替えやすい設計が鍵です。木質の内装で落ち着きをつくり、光・風・音の環境を丁寧に整えます。使い方が変わっても対応できる可動家具や配線計画を用い、在宅と出社が混ざる働き方にもフィットさせます。
プロジェクトマネジメントグループの役割
グループ各社の強みを横断して束ね、品質・コスト・スケジュールを見える化します。共通ルールやチェックリストを整え、成功事例と失敗事例を蓄積して次に活かします。木造マンションやワークプレイスの横展開では、設計・調達・施工・運用まで一気通貫で調整し、社会的価値と事業性の両立を導きます。
地域と森を育てるパートナーシップ
国産材の活用を進め、伐って、使い、植える循環を地域と一緒に育てます。産地との長期契約や苗木からの支援、物流の効率化など、現場に近い工夫を積み上げます。住む人・働く人にも、木の来歴やCO2削減量を分かりやすく伝え、選ぶ力を高めていただきます。
指標と見える化
プロジェクトごとに、CO2削減量、再生可能エネルギーの比率、木材使用量、運用時の電気使用量、利用者満足度などを追いかけます。数字で確かめ、現場の声で磨き、次の案件に素早く反映します。
リスクと備え
木材供給の変動、コスト高、技能者不足といった課題に対し、複数ルートの調達、標準ディテールの整備、研修と資格の支援で備えます。必要に応じて段階的な導入を選び、無理なく成果を積み上げます。
ともに進むために
私たちは、住まい手・働き手・地域・パートナー企業のみなさまと、環境にやさしく、誇りを持てる建物づくりを進めます。小さな改善を積み重ね、次の世代につながる選択を増やしていきます。