この記事でわかること
- 日本のプロジェクトマネージャ国家資格(PM)の概要と特徴
- 合格率・難易度・出題範囲・学習時間の目安
- 国際資格PMPとの違いと受験要件の比較
- 資格の活用場面・キャリアアップ・年収への影響
- 合格までの学習計画と実践的アクションプラン
目次
日本のプロジェクトマネジメント国家資格の概要

日本でプロジェクトマネジメントの国家資格といえば、「プロジェクトマネージャ試験(PM)」が代表的です。この資格は、IPA(情報処理推進機構)が実施しており、IT分野の専門職に大変人気があります。
プロジェクトマネージャ試験は、経済産業省が認定する国家試験の一つです。主な目的は、ITを活用したプロジェクトの計画や実行、進捗管理やリスク対策など、幅広いマネジメント能力を認定することにあります。
この試験では、単なる知識だけでなく、実際の業務に活用できる判断力や、現場での問題解決力も重視されます。たとえば、納期遅延などのトラブル発生時の対応策や、多様な利害関係者の調整法など、実践的な内容が問われます。
また、受験するための前提条件が特に設けられていないため、誰でもチャレンジできる点が特徴です。IT業界でキャリアアップを目指す方や、プロジェクトリーダーを目指す方にも幅広く支持されています。
次の章では、プロジェクトマネージャ試験(PM)の難易度・合格率・特徴について詳しく解説していきます。
プロジェクトマネージャ試験(PM)の難易度・合格率・特徴

プロジェクトマネージャ試験(PM試験)は、日本の情報処理技術者試験の中でも特に難しい部類に入る資格です。毎年春と秋に実施されており、合格率はおよそ13~15%前後で推移しています。直近では、2023年秋の試験で合格率が13.5%と発表されています。この数字からも、多くの受験者が苦戦していることがわかります。
PM試験は「高度情報処理技術者試験」と呼ばれるものの中でも、最難関とされる「レベル4」に分類されています。これは、応用的な知識だけでなく、深い実務経験やマネジメントスキル、状況対応力が要求される水準を示しています。
特に注目すべき特徴として、PM試験は受験資格に制限がありません。つまり、IT業界での実務経験が無い方でも、誰でも挑戦できるのです。ただし、試験では午後Ⅰ・午後Ⅱに記述および論述問題が出題されます。ここでは実際のプロジェクト管理の流れやリスク対応方法、トラブル発生時の判断など、現場で求められる考え方や対応力を問われます。このため、実際には「実務経験に相当する知識やスキル」が強く求められると言えます。
また、選択問題だけではなく、論述形式の問題も含まれますので、単なる知識だけではなく、自分の思いや考えを文章で分かりやすくまとめる力も重要になります。
次の章では、試験の具体的な形式や出題範囲、そして学習に必要な時間の目安についてお話しします。
試験形式・出題範囲・学習時間の目安

試験の形式について
日本のプロジェクトマネージャ試験(PM)は、単に知識を問うだけでなく、実務的な考え方や判断力も評価される内容になっています。午前・午後と2部構成で、多肢選択問題と記述・論述問題の両方があります。多肢選択問題では、用語や基本知識が問われ、論述問題では自分の経験や状況分析をもとに論理的な考えをまとめて書くことが求められます。たとえば、与えられたトラブル事例に対し、「どのように調整し、問題解決を図るか」といった実務的な設問も見られます。
出題範囲のイメージ
試験範囲は幅広く、マネジメント計画の立案や、要員管理、コスト・進捗管理、品質管理、調達管理、リスク管理、そして複数部門とのステークホルダー調整まで多岐にわたります。さらに「プロジェクトを成功に導くための戦略的視点」も問われます。例えば、「プロジェクト開始前のリスク評価から納品後の評価・振り返りまで、どの場面で何を重視すべきか」など、プロジェクト全体を俯瞰できる力が必要です。
学習時間の目安と計画
合格を目指すためには、200時間以上の学習が推奨されます。働きながら受験する方も多いため、仕事や家事など日常生活と両立できる学習計画が不可欠です。たとえば、1日2時間ずつ学習を積み重ねる場合、約3か月半が必要です。重要なのは、知識のインプットと論述力のトレーニングをバランスよく行うことです。論述問題対策としては、過去問や模範解答を参考に、自分の言葉でまとめる練習を意識しましょう。
合格者の特典
合格すると、情報処理推進機構(IPA)が実施する他の高度情報処理技術者試験の一部免除の特典を得られるのも魅力です。
次の章に記載するタイトル:国際資格PMPとの違いと受験要件の比較
国際資格PMPとの違いと受験要件の比較

国家資格であるプロジェクトマネージャ試験(PM)と、国際資格であるPMP(Project Management Professional)は、それぞれ異なる特徴と受験要件があります。ここでは、2つの資格の違いを分かりやすく整理しました。
日本のプロジェクトマネージャ試験(PM)とは
日本のPM試験は、情報処理技術者試験の一つとして実施される国家資格です。受験にあたって、特別な実務経験や事前研修の参加は必要ありません。試験内容は午前と午後に分かれ、知識問題だけでなく論述試験も含まれます。
国際資格PMPとは
PMPはアメリカのプロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定する国際資格で、世界中で評価されている資格です。内容はPMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)に基づいています。PMPは国家資格ではなく、国際的な標準に則っているのが特徴です。
受験要件の主な違い
- PM(国家資格): 実務経験や学歴、特別な研修は問われません。どなたでも応募可能です。
- PMP: 学歴や実務経験が厳しく問われます。
- 高卒者:5年以上のプロジェクト実務経験、および35時間以上の公式PM研修を修了していること
- 学士号以上:3年以上のプロジェクト実務経験、および同じく35時間以上の公式PM研修を修了していること
試験内容の違い
- PM: 午前と午後に渡る日本語中心の筆記や論述、記述式の問題
- PMP: 英語中心のコンピューターテストで、選択式・穴埋め・マッチング形式の問題
合格後の維持
PM資格は一度取得すれば更新不要ですが、PMPは3年ごとに60PDU(継続教育や実務)の取得と更新が必要です。
次の章に記載するタイトル: 国家資格PMと国際資格PMPの使い分け
国家資格PMと国際資格PMPの使い分け

日本でプロジェクトマネジメントの資格を選ぶとき、国家資格の「プロジェクトマネージャ試験(PM)」と国際資格の「PMP(Project Management Professional)」のどちらが適しているか悩む方が多いと思います。この章では、それぞれの資格がどのような場面で活かせるか、使い分けのコツをご紹介します。
日本国内での活用場面
PM試験は、その名の通り日本の国家資格です。ITを中心としたプロジェクトのマネジメント能力を証明できます。例えば、国内のIT企業や官公庁、地方自治体案件で「国家資格」を持っていることが強みとなる場面が多く見られます。また、PM試験では論述問題があり、実際のプロジェクト経験や論理的思考力をアピールできる点も特徴です。「文章で伝える力」が求められる仕事や、日本独自の資格や基準に対応が必要な場合にはPMが特に役立ちます。
グローバル・業界横断での活用場面
これに対して、PMPは世界中で通用する国際資格です。特にグローバル展開する企業や、外資系、社外との多国籍プロジェクトに参加する場面で高く評価されます。PMPは業界横断の共通言語として使われるため、ITだけでなく建設、医療、製造など幅広い分野で活躍できます。海外企業や国際提携プロジェクトに携わりたい方は、PMPが大きな武器となるでしょう。
資格の併用・ダブルホルダーのメリット
最近では、両資格を持つ「ダブルホルダー」が増えています。国内ではPM試験を取得し、日本独自の書類や成果物に対応できる力を身につけつつ、PMPでプロジェクト管理の国際標準や用語の整合性を押さえる形です。これにより、国内外両方に強い“バランス型”のプロジェクトマネージャーとしてキャリアを広げやすくなります。
次の章に記載するタイトル:他の関連資格について
他の関連資格について

プロジェクトマネジメント分野には、プロジェクトマネージャ試験(PM)やPMP以外にも、いくつかの関連資格があります。ここでは代表的な資格と、その特徴についてご紹介します。
P2M(プロジェクト&プログラムマネジメント資格)
P2Mは、一般社団法人プロジェクトマネジメント学会(PMAJ)が認定する資格です。特に日本のプラント建設や社会インフラ事業など、大規模で複雑なプロジェクトを管理するために生まれました。建設、総合エンジニアリング、公共事業などの分野で重視される資格です。P2Mはプロジェクト単体だけではなく、複数プロジェクトを束ねる「プログラム」の管理手法についても学べるのが特徴です。
IPA高度情報処理技術者試験の関連区分
IPAが主催する国家試験にも、プロジェクトマネジメントに関わる区分が複数あります。たとえば、ITストラテジストやシステムアーキテクトといった資格がそれに該当します。これらはIT戦略の策定や、大規模なシステム開発を計画・推進する知識やスキルを問われます。IT業界でキャリアを築く場合、プロジェクトマネージャ試験と併せて取得すると、視野の広い専門人材を目指せます。
その他の資格
さらに、品質管理やリスク管理など、プロジェクトを円滑に進めるうえで役立つ資格も多数あります。例としては「品質管理検定(QC検定)」や、「リスクマネジメント協会認定資格」などが挙げられます。これらはプロジェクトマネジメントの補完的な資格として位置づけられます。
次の章では、プロジェクトマネージャ試験の具体的な学習計画例についてご紹介します。
プロジェクトマネージャ試験の具体的な学習計画例
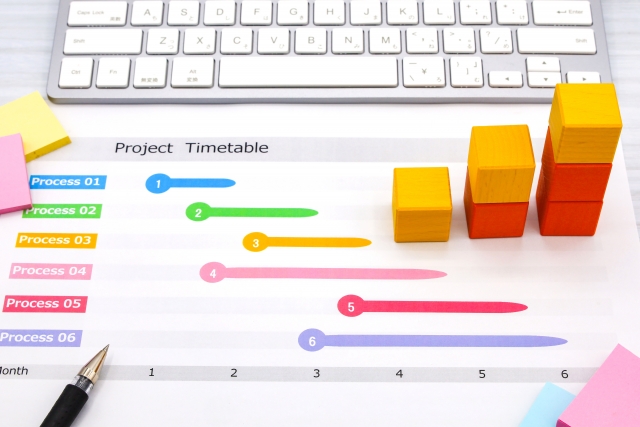
学習開始0~2週目:全体像の把握とテーマ洗い出し
はじめの2週間は、試験の出題範囲を把握することが大切です。公式テキストや過去問題集などを使い、どの分野が出ているか全体を俯瞰しましょう。特に、リスク管理、進捗・コスト管理、品質管理、要員管理、契約形態、ガバナンスなど、よく出るテーマをリストアップします。この段階で、「この分野が苦手そうだ」と感じる部分もメモしておくと、今後の効率的な学習につながります。
3~8週目:過去問演習と論述準備
次の6週間では、午前・午後Iの過去問に取り組み、繰り返し解きます。演習をする中で間違いやすい問題を集め、自分なりの解き方や注意点をノートにまとめましょう。午後IIの論述対策としては、出題されやすいテーマごとに「骨子テンプレート」を作成します。これは、自分の経験や知識をどのようにストーリー立てて書くか、流れを決めておく作業です。
9~12週目:論述練習と仕上げ
ここからは、午後IIの論述問題にしっかり取り組みます。過去の出題テーマに自分の実務経験を当てはめ、事例形式で文章を書いて練習します。書いた論述は自分で見直すだけでなく、家族や仲間にも読んでもらい、客観的なアドバイスをもらうと良いでしょう。また、本番さながらの時間内演習もおすすめです。
学習時間の目安
合格までに必要な学習時間は約200時間を想定してください。例として、平日は2時間学習し、週末は5時間ずつ学ぶと、月に約60時間を確保できます。このペースなら、3~4か月で試験準備が整います。焦らず、計画的に進めることが継続のコツです。
次の章では、PMP試験の具体的な学習計画例について解説します。
PMP試験の具体的な学習計画例

PMP試験に合格するためには、事前準備から本格的な学習、直前期の総仕上げまで一つずつ段階を踏むことが重要です。ここでは、具体的な学習スケジュールの立て方や進め方についてご紹介します。
1. 事前準備(1か月程度)
PMP試験は受験要件として一定のプロジェクトマネジメント実務経験や35時間以上の公式研修受講が必要です。まず、ご自身の実務経験を振り返り、プロジェクト管理作業の時間を集計します。研修はPMI登録の講座(多くはオンライン)で受講することをおすすめします。経験や研修内容を英語・日本語でまとめる必要があるため、申請書類作成にも一定の時間を見積もりましょう。この申請プロセスをスムーズに進めることで、後の学習にも余裕が生まれます。
2. 学習フェーズ(2〜3か月)
学習の中心は『PMBOKガイド最新版』と『アジャイル実務ガイド』です。両方を複数回読み、概要→詳細→要点の順で理解を深めてください。各章ごとに概要ノートを作成したり、練習問題や市販の問題集を解くことで知識の定着を図ります。
加えて、模擬試験を2〜3回実施し、どの「ドメイン(領域)」が弱いかを分析します。苦手分野はガイドを再確認し、理解不足の内容を整理しましょう。また、アジャイルやハイブリッドプロジェクト特有の用語やシナリオにも重点を置くことが重要です。
3. 直前期対策(2週間)
直前期には、模擬問題の解答を時間内に繰り返し行います。特に、シナリオ形式問題やアジャイル・ハイブリッド型の問題で速く正しい判断が出来るよう訓練しましょう。PMBOKの用語やプロセスを短時間で振り返る復習も有効です。
4. 当日までの備え
試験はパソコン(CBT)で180問・230分と長丁場です。模試の際にも時間を測り、集中力を持続させる練習を取り入れてください。当日の持ち物や休憩ポイントも事前に確認しておくと安心です。
5. 合格後の対応
PMPは3年ごとに継続的な学習(60PDU)の取得・申告が必要です。試験合格後も定期的なインプット・アウトプットを怠らず、キャリアアップにつなげていきましょう。
次の章に記載するタイトル:費用・試験日程の比較
費用・試験日程の比較

プロジェクトマネージャ試験(PM:IPA主催)と国際資格PMP(PMI主催)の費用や試験日程について、できるだけわかりやすくご説明します。
プロジェクトマネージャ試験(PM:IPA)
この資格試験は、毎年1回、通常は秋に全国一斉で実施されます。一般的には10月の第3日曜日に行われるため、受験を考えている方はスケジュール調整がしやすいです。受験料は情報処理推進機構(IPA)の規定によって決まっており、近年は7,500円程度です。国家試験としては比較的手頃な価格で受験できるのがメリットです。
PMP(PMI)
一方のPMPは、基本的に通年で受験が可能です。試験はコンピューターによる方式(CBT)で、全国各地の指定試験会場や自宅からオンライン受験も選べます。思い立ったときに受けやすいという特徴があります。
受験料はやや高めで、PMIの一般会員の場合555米ドル、PMI会員になると405米ドルに割引されます。会員費が別途必要ですが、連続して受験する場合やリテイクも考慮する人は会員になるメリットも大きいでしょう。日本円に換算すると、為替によりますが4〜6万円程度が目安になります。
比較まとめ
- PM(IPA):年1回、受験料約7,500円
- PMP(PMI):通年、受験料約4〜6万円(会員割引あり)
このように、費用や受験日程に大きな違いがあるため、ご自身の予算やスケジュール、学習のペースに合わせて選ぶことが大切です。
次の章に記載するタイトル:キャリア・年収に関する示唆
キャリア・年収に関する示唆

プロジェクトマネージャ国家資格がキャリアに与える影響
プロジェクトマネージャ(PM)の国家資格は、企業でのプロジェクト推進能力の証明として評価されやすいです。特にIT業界や製造業など、組織内で複数のプロジェクトを管理・推進することが求められる職場では、社内でのキャリアアップを目指す上で有利になる場合が多いです。人事評価や昇進試験の際、資格保有者が優遇されることもよくあります。
昇進・昇給への直接的な効果
会社によっては、PM資格の取得を昇進条件や昇給要件に盛り込んでいる場合もあります。そのため、資格を取得しておくことで将来的な給与アップや役職昇格のチャンスにつながります。また、自己研鑽や専門知識の証明としても企業内での信頼を得やすくなります。
転職市場での価値
日本国内での転職活動においては、PM国家資格があると書類選考や面接で強みをアピールしやすくなります。求人票にも「プロジェクトマネージャ資格(国家)」があると歓迎される項目として記載されることがあり、転職の際の選択肢が広がります。
国際資格PMPのキャリアメリット
PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)は、外資系企業やグローバル案件に関わる仕事で重視される資格です。国内外の多くの企業でPMP資格を保持していることを重要視する傾向があり、一部では必須条件にもなっています。英語案件や多国籍プロジェクトに携わる場合、PMPを取得することで国際的なキャリアパスを拓きやすくなります。
年収アップの傾向
両資格とも、取得者は年収が比較的高い傾向にあります。特に、PMP資格者は海外クライアントや大規模案件へのアサインが期待されるため、年収アップや好条件職の獲得に直結しやすいです。PM国家資格も、一定の経験と組み合わせることで年収面でプラス評価されるケースが多いです。
次の章に記載するタイトル:受験要件のまとめ
受験要件のまとめ

ここでは、日本のプロジェクトマネージャ国家資格(PM)と、国際資格PMPの受験要件についてまとめます。
PM(IPA)の受験要件
PM試験(IPAが実施)は、学歴・年齢・職歴などに関わらず、受験資格に制限がありません。誰でも出願できるのが大きな特徴です。たとえば、実務経験が浅い新卒社員や、これからプロジェクトマネジメント分野に挑戦したい方でも受験が可能です。必要なのは受験手続きのみですので、「まず学んでみたい」と感じる場合には挑戦しやすい国家資格です。
PMP(PMI)の受験要件
一方、PMP(PMI主催)は、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、
- 最終学歴が「大卒」または「高卒等」によって、必要な実務経験年数が異なります。
- 3~5年以上のプロジェクトマネジメントに関する実務経験(プロジェクトでリーダー的役割を担った期間)が必要です。
- さらに、公式なPM研修を35時間以上受講済みであることが求められます。
例えば「新卒1年目」や「実務経験が少ない方」はすぐにPMPを受験できませんが、実務で経験を積み、研修を受ければチャレンジできます。
比較まとめ
PM(IPA)はどなたでも挑戦できる間口の広い資格である一方、PMPは事前にクリアすべき経験・研修がある分、一定の実務力が求められます。これによって、自分に合った資格選びや受験計画が立てやすくなります。
次の章では、「よくある質問(FAQ)」について解説します。
よくある質問(FAQ)

国家資格はPMPですか?
国家資格とPMPは異なります。PMPは「Project Management Professional」の略で、アメリカのPMI(プロジェクトマネジメント協会)が認定する国際資格です。一方、日本の国家資格はIPA(情報処理推進機構)が主催する「プロジェクトマネージャ試験(PM)」となります。名前が似ているため混乱しやすいですが、取得できる国や機関が異なります。
合格率が高いのはどちらですか?
日本の国家資格であるプロジェクトマネージャ試験(PM)は、合格率がおよそ13~15%前後とされています。一方、PMPの合格率は公式には公開されていませんが、さまざまな受験者の情報から「およそ60%程度」と推定されています。そのため、PMPの方が合格しやすいと考えられますが、両者の出題内容や受験要件が異なるため、一概に比較するのは難しい場合もあります。
実務未経験でも受験できますか?
PM(プロジェクトマネージャ試験)は、実務経験がない方でも受験可能です。資格取得後は、経験者でなくてもプロジェクトマネジメント分野の知識やスキルを証明できます。ただし、より高度な実践力を求められる場面もあり、実務経験があると試験内容を理解しやすい場合もあります。
一方、PMPは実務経験と公式研修の受講が必要です。原則として、プロジェクト管理に関する一定期間の実務経験と35時間以上の公式研修(またはPMP公認の学習)が必須となっています。これに満たない場合、受験することはできません。
次の章に記載するタイトル:次のアクションプラン
次のアクションプラン

プロジェクトマネジメント国家資格やPMP資格を目指す方は、それぞれに応じた具体的な準備を進めることが成功への近道です。ここでは、資格ごとに取り組むべきアクションプランをご紹介します。
国家資格(PM)重視の方
まず、プロジェクトマネージャ試験(PM)合格を目指す場合は、過去問題集の収集が最優先です。出題傾向や問題のレベル感を把握し、自分の苦手分野を明確にできます。次に、約200時間という目安の学習計画を立てましょう。例えば、1日2時間で3ヶ月強、あるいは週末にまとまった時間を利用して計画的に進めることも可能です。定期的に過去問演習と自己評価を繰り返しながら、理解度を深めてください。
グローバル案件や海外志向の方
国際資格であるPMPにチャレンジしたい方は、まずPMI(プロジェクトマネジメント協会)への会員登録を済ませましょう。次に、試験申請に必要な35時間以上の公式研修を計画的に受講し、受験申請の準備を早めに進めましょう。その後は、PMP試験対策講座や英語での模擬試験なども効果的です。申請から受験までのプロセスには、事前準備が多いため早めの行動が重要です。
両方の資格取得を視野に入れる場合
日本国内外での活躍を目指す場合、両方の資格取得が選択肢として有効です。ご自身のキャリアパスや現在の業務環境を踏まえ、どちらを先に取得すべきか計画を立てましょう。学習計画やスケジュール管理は、日々の業務と両立しやすいように無理のない範囲で設定することをおすすめします。
このように、目標に応じて具体的なアクションを明確にし、着実に行動することが資格取得への近道です。ご自身のペースで取り組んでみてください。