はじめに
本記事は、応用情報技術者試験のプロジェクトマネジメント分野に焦点を当て、問題の解き方や実践的な対策をやさしく解説します。出題傾向や頻出テーマ、問題文からのヒントの読み取り方、計算問題のアプローチなど、試験で得点を伸ばすための具体的な方法を紹介します。
この記事の目的
試験で問われる考え方や解法の型を身につけ、短時間で正答にたどり着ける力を養うことを目的とします。例として、WBSは図にして作業の流れを確認する、クリティカルパスは遅延の影響を考えるといった実務に近い感覚で学べるように説明します。
読者対象
- これから対策を始める方
- 過去に得点が伸び悩んだ方
- 実務経験はあるが試験形式に不慣れな方
本記事の使い方
各章で「出題傾向」「解き方のコツ」「練習法」を順に解説します。問題を解く際は、まず設問を図や箇条書きに整理し、設問の要求(何を求めているか)を明確にしてください。例:「工数」を問われたら、まず単位と前提条件を確認します。
進め方の簡単なアドバイス
- 基本用語は図や例で覚える
- 時間配分を意識して模試を解く
- 間違いは解説を写すのではなく、なぜ間違えたかをメモする
「ブログの記事をどう書けばいいかわからない」「記事がうまくまとまらない……」という疑問を持つ方にも応用できる、わかりやすい構成で進めます。
この記事でわかること
- 応用情報技術者試験におけるプロジェクトマネジメント分野の出題傾向と重要ポイント
- 計算・分析・リスク管理など問題の「解き方」の実践的ステップ
- EVM(出来高管理)・バッファ管理など頻出テーマの攻略法
- 効率的な学習法と午後問題対策の具体的アプローチ
- 実務に応用できるプロジェクトマネジメント思考と試験対策のまとめ
プロジェクトマネジメント分野の出題傾向と重要ポイント

概要
応用情報技術者試験のプロジェクトマネジメント分野は、PMBOKに基づく基本概念と現場で使う実務的な計算がよく問われます。単なる用語の暗記だけでなく、与えられた状況から何を読み取るかが重要です。問題文の前提を整理してから解く習慣をつけましょう。
頻出テーマと押さえる点
- 基本概念
- プロジェクトの定義やライフサイクル、ステークホルダーの役割を問う問題が出ます。具体例で関係者の期待を整理する練習をすると理解が深まります。
- スコープ・スケジュール・コスト管理
- 品目交換や変更管理、クリティカルパスの読み取りが頻出です。スケジュールは図にして可視化する癖をつけてください。
- リスク管理
- リスクの特定、定性・定量分析、対応策の選択が問われます。発生確率と影響度を掛け合わせる考え方に慣れておきましょう。
- バッファ管理
- プロジェクトバッファ(全体の遅れ吸収)や合流(フィーディング)バッファの意味を押さえてください。どの工程に置くかで効果が変わります。
- EVM(出来高管理)
- PV(計画値)、EV(出来高)、AC(実コスト)を使った指標がよく出ます。指標の解釈も同時に問われるので計算だけでなく意味を覚えてください。
EVMの簡単な計算例
- 例:PV=100、EV=80、AC=90
- CPI(コスト効率)=EV/AC=80/90≈0.89 → コスト効率が悪い
- SPI(進捗効率)=EV/PV=80/100=0.8 → 進捗が遅れている
出題傾向と解答のコツ
- 問題文の単位(時間・金額・割合)を最初に確認してください。
- 計算問題は途中の数値をノートに書き写し、丸暗記に頼らず論理的に導く習慣をつけましょう。
- 図や表にして考えると誤読を防げます。
- よく出る概念は具体例で覚えると応用が利きます。
プロジェクトマネジメント問題の「解き方」のコツ
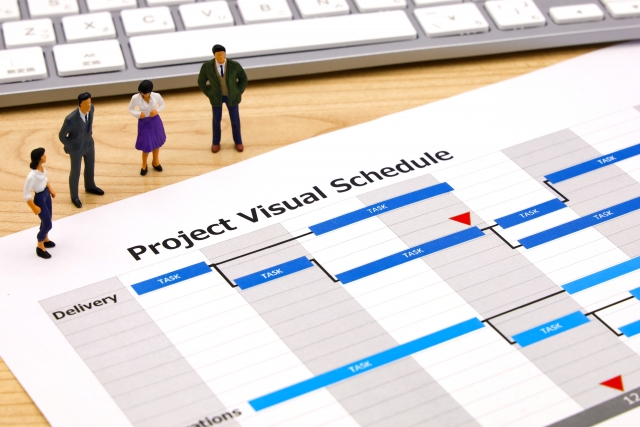
1) 問題文の情報整理とキーワード抽出
問題文を読んだら、まず「与えられた数値」「期限」「役割名」などをメモします。問いに直接結びつく語句(例:遅延、バッファ、クリティカル)を線で引くと見落としが減ります。短いメモで十分です。
2) 計算問題への実践的アプローチ
EVMなど計算問題は、まず用語定義を確認します。例:PV=計画作業量、EV=出来高、AC=実コスト。次に式を決め(SPI=EV/PV、CPI=EV/ACなど)、与えられた数値を代入して順に計算します。途中で単位や桁をチェックするとミスが減ります。
3) バッファ管理の考え方
合流バッファは合流点に置く余裕日、プロジェクトバッファはクリティカルチェーン全体の余裕です。図でスケジュールを描き、どこに余裕があるか視覚化すると判断が楽になります。
4) 選択肢・空欄問題のコツ
答えはシンプルなものを疑ってみてください。空欄の直前後にヒントがあることが多く、並列要素と異なる性質の語が正解になりやすいです。肢を消去する練習も有効です。
最後に、時間配分を決めて解く習慣をつけると、本番で落ち着いて解けます。
効率的な勉強法と実務への応用

序文
PMBOKの基本を押さえると、試験対策だけでなく日々の業務でも役立ちます。ここでは短時間で成果を出す勉強法と、学んだ知識を実務に結びつける具体的な方法を紹介します。
基本を効率よく身につける方法
- 重要概念を図で整理する(プロセス群・知識エリア・成果物の関連図)。視覚化で理解が早まります。
- 用語は最小限にし、具体例で補う(例:スコープ変更=顧客からの仕様追加)。
- 毎回小さな目標を設定して、短時間集中を繰り返す(25分学習+5分休憩など)。
過去問演習の進め方(特に午後問題)
- 過去問は解くだけでなく、解答の根拠を一行で説明する習慣をつける。
- 午後問題は状況把握力が問われます。登場人物の立場、制約、優先順位に注目してください。
- よく出るトラブル例(スコープ膨張、スケジュール遅延、利害関係者の不一致)に対する標準的な対応手順を整理しておくと効果的です。
背景・プロセスまで説明できる練習
- 解答の理由を「なぜ」「どうやって」の観点で説明する癖をつける。
- 自分の言葉で100字以内に要約する訓練を繰り返すと応用力が上がります。
実務への応用例
- スコープ変更:まず影響範囲を洗い出し、関係者合意の手順をテンプレ化する。
- リスク管理:簡易リスク登録表を作り、定例で見直す習慣をつける。
- コミュニケーション:議事録とアクションアイテムを短く明確にするテンプレを用意する。
日々の学習ルーチンの例
- 毎朝30分で過去問1問+解説を自分の言葉で書く。
- 週1回は模試で時間管理の練習をする。
- 学んだ方法はすぐ実務で試し、結果を振り返るサイクルを作る。
以上を繰り返すことで、試験合格と実務で使えるスキルを同時に育てられます。
よく出るテーマと例題アプローチ

EVM(Earned Value Management)
PV(計画値)、EV(出来高)、AC(実績費用)を押さえます。基本式は次の通りです。
- SV = EV - PV(スケジュール差)
- CV = EV - AC(コスト差)
- SPI = EV / PV、CPI = EV / AC(効率指標)
例:PV=100、EV=80、AC=90 → SV=-20(遅れ)、CV=-10(超過)、SPI=0.8、CPI=0.89。数値から原因と対応を考えます(例:SPI<1なら進捗改善、CPI<1ならコスト管理)。
バッファ管理
よく問われるのは種類と役割です。主なバッファは
- プロジェクトバッファ:プロジェクト全体の余裕
- 合流バッファ:複数経路が合流する箇所の余裕
目的に応じて割当てます。例として残作業の10%をプロジェクトバッファにする、など具体的に考えると答えやすくなります。
ケース問題の解き方
1) 問題文の数値・用語を丁寧に拾います。2) 必要ならEVMやバッファ指標を計算します。3) 計算結果を根拠に、実行可能な対応案を複数示して比較します。例:スケジュール遅延とコスト増なら、追加リソース投入、スコープ見直し、納期交渉などを候補に挙げ、SPIやCPIで優先度をつけます。
例題アプローチの手順(簡潔)
- 数値整理(PV/EV/ACなど) 2. 指標計算(SV/CV/SPI/CPI) 3. 解釈と対応案提示 4. 選択肢に数値根拠を添える
この章は数値を当てはめる練習を重ねることが最短の対策です。
まとめと今後の対策

応用情報技術者試験のプロジェクトマネジメント分野で得点を伸ばすには、次の三点を意識すると効果的です。
- 問題文を正確に読む
設問の条件や制約を丁寧に拾う習慣をつけてください。例えば「何を求めるか」「どの前提で考えるか」を問題ごとにメモすると見落としが減ります。
定義・計算式を覚える
PMBOKの基本用語(リスク、スコープ、ステークホルダーなど)やEVMの指標(PV、EV、AC、CPI、SPI)を実務イメージと結びつけて覚えると定着します。具体例を頭に入れておくと、出題の変化にも対応しやすくなります。
過去問でパターンを掴む
- 過去問を時間を計って解き、設問パターンや頻出の計算問題に慣れてください。間違えた問題は解説を読み、間違いの原因をノートに残すと効果的です。
今後の学習プランの例
- 週ごとにテーマを決める(用語週、計算週、過去問週)
- 毎回10問は過去問に触れる
- 模擬試験で時間配分を確認する
最後に一言
基礎を堅実に積み上げ、過去問で得意パターンを増やすことが合格への近道です。この記事が皆さんの対策に役立てば幸いです。