この記事でわかること
- プロジェクトマネジメントにおける「知識エリア」の基本概念
- PMBOK第6版で定義された「10の知識エリア」と実務での使い方
- 試験や学習で頻出する重要な知識エリアとそのポイント
- 第7版での位置づけ変化と「原則重視」への移行
- 実務導入のステップと落とし穴を防ぐ実践的チェックポイント
目次
知識エリアとは何か
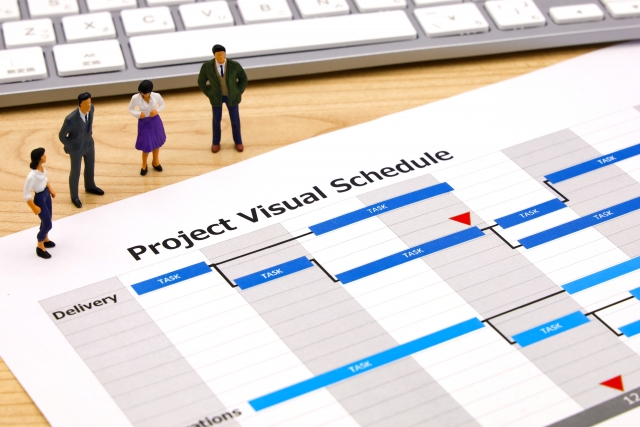
プロジェクトマネジメントにおける「知識エリア」とは
知識エリアとは、プロジェクトを進めるうえで必要な知識やノウハウを、大きなテーマごとに分けて整理した枠組みのことです。たとえば、「どこまでやるのか」を考える範囲(スコープ)や、「いつまでに何をするか」を考えるスケジュール、「誰が担当するのか」を決める資源など、プロジェクトを成功させるために欠かせない要素を網羅的にカバーしています。
知識エリアを理解することで、計画立案や実行、進捗の管理、問題が起きたときの対応、プロジェクトの終了まで、あらゆる場面での意思決定や統制がスムーズになります。
枠組みとしての役割
プロジェクトは複数のタスクや関係者が関わるため、全体を見渡す視点が重要です。知識エリアは、プロジェクト全体で「何を考えるべきか」「どこまでチェックが必要か」を整理し、見落としを防ぐ役割を果たします。たとえば、スコープ管理を怠ると、最初に決めた範囲を超えて作業が増えてしまい、納期やコストに大きく影響することがあります。しかし、知識エリアを意識することで、重要なポイントを適切に押さえることができます。
プロジェクト全体への関わり
知識エリアは、計画段階だけでなく、実際の現場で進捗確認やリスク対応、成果物の確認・引き渡しなど、プロジェクトの最初から終わりまであらゆる場面で活用されます。そして、PMBOKの5つのプロセスグループ(イニシエーション、プランニング、エクゼキューション、モニタリング&コントロール、クローズ)と横断的につながることで、全体像を意識した運営が可能となります。
次の章に記載するタイトル:PMBOK第6版の「10の知識エリア」とは
PMBOK第6版の「10の知識エリア」とは
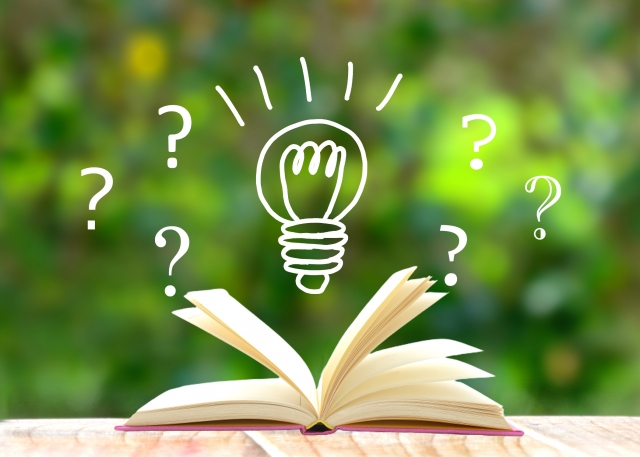
PMBOK第6版では、プロジェクトマネジメントを効率的かつ体系的に進めるために「10の知識エリア」を設けています。これらの知識エリアは、プロジェクトがどのように始まり、進み、完了するのかを整理するうえでの大きな柱となっています。それぞれの知識エリアは、実際の業務で発生しやすい内容に基づいて構成されており、プロジェクトの現場でもよく話題になります。
1. 統合管理
プロジェクト全体を見渡して方針を決め、計画づくりから実行、監視、そして終了までがスムーズにつながるようまとめ役となる分野です。例えば、計画段階での全体方針の決定や、進行中に計画変更が必要になった場合の取りまとめがここに該当します。
2. スコープ管理
プロジェクトで「何を成果物とするか」「どこまでを作業範囲とするか」を明確にし、不明確さや手戻りを防ぐための分野です。たとえば新商品開発では、新機能を追加するかどうかの基準をきちんと決める場面などが該当します。
3. スケジュール管理
作業の流れや順序、所要期間を見積もり、計画どおりにプロジェクトを進めるための分野です。進捗が遅れそうな場合の調整もここに含まれます。
4. コスト管理
プロジェクトにかかるお金の見積もり・配分・使い過ぎないようにする管理を担います。例えば予算超過の予防や、コスト計算の適正化がこのエリアのポイントです。
5. 品質管理
顧客が求める品質を計画し、それを保つための仕組みや点検を行う分野です。例えば、製品検査や手順確認がこの例になります。
6. 資源(リソース)管理
人員や設備、物品などプロジェクト遂行に必要なものについて、計画し、確保し、適切に割り当てていく分野です。スタッフの配置や外部からの物品調達例がイメージしやすいでしょう。
7. コミュニケーション管理
関係者に必要な情報を正確かつタイミングよく伝えたり、意見調整を行ったりする分野です。例えば、全体会議の情報共有や、トラブル発生時の連絡網づくりも含みます。
8. リスク管理
進行中に起こりうるトラブルや課題を予測し、対応策を考えておく分野です。天候不良など外的要因だけでなく、チームの突然の欠員もリスク例です。
9. 調達管理
必要な部品やサービスを外部から購入する際の発注や契約、納品予定の管理を行う分野です。発注先の選定や納品物のチェックがイメージしやすい事例です。
10. ステークホルダー管理
関わる全ての人(顧客やチームメンバー、協力会社など)の期待や要望を把握し、良好な関係を保つための分野です。定期面談やフィードバック機会の設定などが該当します。
次の章では、各知識エリアの実務チェックポイントについて紹介します。
各知識エリアの実務チェックポイント

この章では、プロジェクトマネジメントにおいて重要な10の知識エリアごとに、実務で役立つチェックポイントをご紹介します。現場でよく直面する課題や確認すべきポイントを具体例を交えて解説します。
統合管理
プロジェクトの全体をまとめる役割です。実務では「プロジェクト憲章」の作成と承認、「プロジェクトマネジメント計画書」の策定を必ず行いましょう。計画変更が生じた場合は、必ず統合変更管理プロセスを経て記録と周知を忘れないことが重要です。
スコープ管理
作業範囲を明確にし、漏れや過不足なく進めるために「WBS(作業分解構成図)」で成果物を段階的に分解します。受入基準も事前に明確にし、スコープの変更要求が出た際は統合変更管理に回しましょう。
スケジュール管理
プロジェクトの遅延防止の要です。重要な作業の流れ(クリティカルパス)を押さえ、遅れに備えてバッファ(余裕)を計画しておきます。計画と実績の差分(ベースラインとの差)を定期的にレビューし、問題があれば速やかに対策を考えましょう。
コスト管理
予算超過を防ぐため、見積もり金額や予算をベースラインとして設定し、進捗に対して「EVM(アーンド・バリュー・マネジメント)」を活用してコストとスケジュールのズレ(CV/SV)を監視します。また、最終的にかかる見込み額(EAC)も都度更新します。
品質管理
成果物の満足度を左右します。着手前に品質基準や測定方法を検討・定義し、品質監査を実施して問題点を把握しましょう。フィードバックを継続的に取り入れる仕組み作りも大切です。
資源管理
人や必要なツールの管理です。各担当の役割と責任を明確にし、メンバーのスキルを見える化(スキルマトリクス)しましょう。業務負荷も定期的に確認し、必要に応じて調整します。
コミュニケーション管理
社内外のやり取りを円滑にするため、「誰が・何を・どれくらいの頻度で」報告するか、チャネル(メール・会議など)の定義と、意思決定内容の記録・共有を心がけましょう。
リスク管理
リスク(不確実な要素)を事前にリスト化し(リスク登録簿)、内容の定期見直しが重要です。リスクが発生しそうな際の「トリガー」や、対応担当(オーナー)も明記しておきます。
調達管理
外部企業などから必要な物品やサービスを調達する際には、契約の型(固定価格・出来高払いなど)の選定や、契約内容に「変更対応」の条項があるかを確認します。納品されたものが期待通りか評価する手順も必要です。
ステークホルダー管理
関係者全員との連携がスムーズに進むよう、パワー/関心マトリクスなどで影響度を分析し、関与の仕方を工夫します。期待値を調整するための定期的な対話も欠かせません。
次の章:試験・学習で頻出の知識エリア
試験・学習で頻出の知識エリア

よく出題される知識エリアとは
PMBOKの知識エリアのうち、試験や学習で特に多く取り上げられる分野があります。代表的なのは「統合マネジメント」「スコープマネジメント」「スケジュールマネジメント」「コストマネジメント」「リスクマネジメント」の5つです。
これらの分野は、プロジェクトを計画的に進めるための土台となるため、PMPや応用情報技術者などの資格試験で出題が目立ちます。
各知識エリアごとのポイント
- 統合マネジメント:プロジェクト全体を1つにまとめて管理する役割です。計画の作成や変更管理など、全体を見通すスキルが問われます。
例:複数の作業をスムーズに進めるための調整
スコープマネジメント:どこまでがプロジェクトの仕事なのか、範囲を明確にします。やるべきこと、やらないことの線引きが重要です。
例:必要な機能だけ追加し、それ以外はやらない判断
スケジュールマネジメント:いつまでに何をするか、作業の順番や期間を決めます。
例:納期までに完成させるための工程表作成
コストマネジメント:予算管理を担当します。お金の使いすぎを防ぐチェックが中心です。
例:見積額と実際に使った金額の比較
リスクマネジメント:問題が起きそうなことを事前に洗い出し、対策を立てます。
- 例:納期遅れや追加費用が出る前に、準備をしておく
合格のための押さえ所
プロジェクトは始まりと終わりがハッキリしている一時的な活動であることや、「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」という5つのプロセスグループの流れが重要です。知識エリアとプロセスグループは密接に関係しています。
次の章に記載するタイトル:ライフサイクルとフェーズとの紐づけ
ライフサイクルとフェーズとの紐づけ

プロジェクトには「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」といった複数のフェーズ(段階)があります。PMBOK第6版の10の知識エリアは、これらすべてのフェーズにわたって関わってきますが、その関与度合いや比重は各フェーズによって異なります。
どの知識エリアがどこで活躍するのか
・統合マネジメント、コミュニケーション、ステークホルダーの知識エリアは、プロジェクトの始まりから終わりまで通してずっと重要です。たとえば、関係者との連携や情報共有は、全てのステージで絶え間なく必要なものとなります。
・スコープ(作業範囲)、スケジュール(工程)、コスト(予算)の知識エリアは、とくに計画段階で大きな役割を果たします。この段階で具体的な内容や期間、費用を固めるため、3つのエリアのチェックや調整がプロジェクト成功のカギとなります。
・品質、リスク、資源(人・物資)、調達(外部依頼)の知識エリアは、計画から実行、さらに監視やコントロールのフェーズで繰り返し使います。たとえば、リスク対応策を都度見直したり、必要な資源を適切に配分したりなど、状況に合わせて柔軟に運用することが重要です。
現場での活用のイメージ
たとえば、計画フェーズで決めた内容が実行に移された際に、思わぬトラブルが起きることがあります。その場合、リスク管理や資源の再配分といった知識エリアを活用して問題解決を図ります。またステークホルダー(利害関係者)への丁寧な説明や、進捗状況のこまめな情報共有も欠かせません。
このように、各フェーズごとに重視される知識エリアが異なりますが、全体を通して一体的に運用することがプロジェクトを成功へと導くカギとなります。
次の章に記載するタイトル:PMBOK第7版での位置づけの変化
PMBOK第7版での位置づけの変化

第6版から第7版への大きな変化
PMBOK第6版までは「10の知識エリア」がプロジェクト管理の中心でしたが、第7版ではその構成が大きく変わりました。第7版では、知識エリアという枠組みではなく、「プリンシプル(原則)」を重視しています。つまり、プロジェクト管理の具体的な手順や技法よりも、より広い視点で価値や成果を実現するための考え方や行動指針を強調するようになりました。
プリンシプル駆動・バリューデリバリーへの移行
第7版では、「バリューデリバリー」が大きなキーワードです。これは、単にプロジェクトを進めるだけでなく、顧客や関係者にどのような価値を届けられるかに力点を置いています。また、具体的な作業よりも「状況に応じた最適な方法を選ぶこと」や「チームの自律性・柔軟性」が重視されました。
知識エリアの役割の変化
10の知識エリアは、第6版まで主役でしたが、第7版では「参考として活用する知識」といった位置づけに移りました。プロジェクトの現場では、いまだに知識エリアごとのチェックリストや考え方が役立ちます。しかし、第7版の現場では「こうすべき」という手順より、「どう価値を生むか」が問われます。
実務への影響
実際のプロジェクト現場では、第6版の知識エリアも根強く使われています。第7版の考え方を取り入れつつも、知識エリアに基づく整理や見直しを行うと、より実践的な対応がしやすくなります。よって、今後は「原則と柔軟性」、そして「実績ある知識」の両方をバランスよく取り入れる意識が大切です。
次の章では、「実務導入のステップ(テンプレ適用のヒント)」についてお伝えします。
実務導入のステップ(テンプレ適用のヒント)

1. 立ち上げ:土台作りからはじめましょう
プロジェクトを始める際は、まず「プロジェクト憲章」を作成します。これはプロジェクトの目的や目標、期待される成果物、関わる主な関係者(ステークホルダー)を明確にする文書です。たとえば、店舗リニューアルを企画する場合、「どの店舗で、何を、いつまでに、どれだけ改善するか」が記載されます。また、プロジェクトの成功基準(KPI)を設定し、ステークホルダーとしっかり合意しておくことが大切です。
2. 計画:全体像を具体化しましょう
次のステップは、プロジェクト全体の計画を立てることです。作業分解構成図(WBS)でやるべきタスクを洗い出し、スケジュール表・コスト計画などの「ベースライン」を決めます。品質目標、想定されるリスク、情報共有の方法(コミュニケーション計画)、必要な人やモノ(資源計画)、外部発注がある場合の調達計画、関係者の影響度や巻き込みプラン(ステークホルダー関与計画)も漏れなく検討しましょう。これらをまとめて「PM計画書」として一つのファイルにしておくと、あとで見返す際に便利です。
3. 実行と監視:進み具合を把握し、軌道修正も忘れずに
作成した計画書に基づき、日々のプロジェクトを進めていきます。しかし、進捗やコスト、品質の状況をこまめに確認し、問題があればすぐに関係者と共有しましょう。変更点が出てきたときは、「統合変更管理」プロセスを使って、計画の更新や影響度をしっかり審査します。進捗管理にはガントチャートやバーンダウンチャートを使うと、作業の遅れや残作業が一目で分かります。
4. 終結:振り返りと学びの共有
プロジェクトが終わったら、成果物の受け入れと契約の締結・終了手続きを行います。そして、プロジェクトで得た教訓(レッスンラーニド)を記録し、次回に活かす仕組みも重要です。例えば、どんな課題があり、どう解決したのかをチームで共有すると、組織全体のノウハウが蓄積されます。
次の章に記載するタイトル:よくある落とし穴と回避策
よくある落とし穴と回避策

スコープ管理の落とし穴と対策
スコープが曖昧なまま進行すると、追加要件が次々と発生し、予定していた作業量が膨れ上がることがあります。こうした状況を防ぐには、プロジェクトの受入基準を明確にし、作業分解構成図(WBS)の粒度を細かく設定することが大切です。たとえば、「ユーザー管理画面を作る」だけでなく、「アカウント新規登録機能」「パスワード変更機能」など、具体的な作業単位に落とし込みましょう。
変更管理の注意点
要望や仕様が途中で変わる場合、都度個別に対応してしまうと管理が困難になります。この時、統合変更管理という一元的な仕組みを活用しましょう。必ず変更申請・承認フローを設け「いつ・誰が・なぜ」変更したのかを記録します。こうすることで、計画と実績のズレの原因も追いやすくなります。
リスク管理が形骸化しないために
リスク管理が形式的になり、対策が後回しになることもよくある問題です。リスク登録簿は常に最新に保ち、リスクの発生条件(トリガー)や担当者(オーナー)、具体的な応答計画を明記しましょう。たとえば「サーバーの納品遅延」がリスクに挙がる場合、「納品予定10日前になっても確認できない場合に担当者がベンダーに連絡し、進捗をフォローする」といった対応策まで記入します。
コミュニケーションの量を最適に
関係者(ステークホルダー)ごとに情報を届ける量や頻度が多すぎたり、少なすぎたりすることでトラブルになることがあります。たとえば、進捗報告が週1回では足りない現場もあれば、毎日では負担となる場合もあります。ステークホルダーごとに期待値を整理し、ヒアリングした上で最適な頻度や内容を決めることが有効です。
リソース管理の工夫
「人手が足りず、特定の担当者に負担が集中する」ことも、ありがちな失敗です。担当者一人一人のスキルや作業負荷を可視化し、必要に応じて外部の協力を得ることも効果的です。たとえば、繁忙期だけ外部スタッフに部分的に頼ることでボトルネックを解消できます。また、タスクの割り振りも平準化する工夫が必要です。
次の章に記載するタイトル:参考となる全体像の把握ポイント
参考となる全体像の把握ポイント

10の知識エリアは、プロジェクトマネジメントの全体像を把握するうえで、非常に役立つ道標です。各エリアは、計画から実行、監視や完了までの各段階で「何を意識すべきか」を示しています。たとえば、「スケジュールマネジメント」なら納期、「リスクマネジメント」なら想定されるトラブルへの備え、といった具合に、日々の業務と直結した具体的な視点で全体を俯瞰できます。
また、10の知識エリアで欠かせないのが「統合管理」です。統合管理は、他の全てのエリアをつなぎ、最適なバランスや調整を図る“ハブ”の役割を持ちます。たとえば、コスト・品質・進捗といった各要素のバランスをとりつつ、全体としてプロジェクトが目標へ向かうよう采配します。
第7版では「原則」による価値重視の考え方に再編されましたが、実務を進めるうえでは従来の10エリアの視点が引き続き有効です。つまり、各エリアを「目安」「チェックリスト」「対話のきっかけ」として活用することで、抜けもれなく全体像を把握できます。この視点は、規模や業種問わず、多くのプロジェクトで応用可能です。
プロジェクトマネジメントを進める際は、10の知識エリアの観点で全体を見通し、統合管理を中心に他の要素とどうつなぐかを意識すると、プロジェクトをよりスムーズに進めやすくなります。