この記事でわかること
- PMBOK第6版における「10の知識エリア」とその役割
- 各知識エリアと「5つのプロセス群」の関係性と重要フェーズ
- 統合管理が中核と呼ばれる理由と実務での機能
- 第6版と第7版の違い・学習上の注意点・ハイブリッド活用法
- 実務導入・試験対策・フェーズ別チェックリストによる活用ステップ
目次
PMBOKの「10の知識エリア」とは何か(第6版の全体像)

PMBOKは、プロジェクトを計画的かつ効率的に進めるための知識やノウハウをまとめたガイドブックです。正式名称は「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」といいます。PMI(プロジェクトマネジメント協会)が定期的に内容を見直し、多くの業界で標準として用いられています。
このガイドの特徴は、プロジェクトマネジメントで必要となる重要な知識やスキルが「知識エリア」として整理されている点にあります。PMBOK第6版では、この知識エリアが10個に分かれており、それぞれプロジェクトの様々な側面を管理する役割を持っています。たとえば、スケジュールの管理や、コストの管理、質を担保する管理など、実際の仕事で発生する課題に個別に向き合えるよう配慮されています。
さらに、PMBOKは「5つのプロセス群」—立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結—を定めており、プロジェクトの進行に応じて必要となる作業や対応が整理されています。10の知識エリアは、これらのすべてのプロセス群に横断的に関わりますが、各知識エリアが主に重視されるプロセス群は異なります。
こうした構成により、PMBOKはプロジェクトマネジメントの初心者から経験者まで、誰でも実践に役立てやすい体系となっています。次の章では、10の知識エリアの具体的な一覧とそれぞれの役割について、簡単にご紹介します。
10の知識エリア一覧と役割(エッセンス早見)

プロジェクトを成功させるためには、10の知識エリアそれぞれが果たす役割を理解しておくことがとても大切です。ここでは、一つひとつのエリアがどのような仕事を担い、どの場面で特に重要になるのか、概要を押さえておきましょう。
1. 統合管理
プロジェクトの方針決定や全体調整を担当します。他の9つのエリアをまとめあげる、いわば司令塔の役割です。全プロセスで関与し、全体をコーディネートします。
2. スコープ管理
どんな成果物をどこまで作るか(範囲)を明確にし、途中で脱線しないように防ぎます。とくに計画段階で力を発揮します。
3. スケジュール管理
作業手順や順序づけ、期間の見積もり、進行状況の確認を行います。遅れや抜けがないように進めるうえで不可欠です。
4. コスト管理
予算の立案やコストの見積もり、費用の使いすぎを防ぐ監督など「お金」の流れを管理します。
5. 品質管理
決められた品質基準にきちんと達しているかを確認し、より良いものを作る工夫も計画・実行・監視の各段階で行います。
6. 資源管理
人員や設備、材料などの配分と、チーム作り・育成が主な役割です。計画と実行で中心になります。
7. コミュニケーション管理
情報の計画的な共有や、関係者とのやりとり・報告・調整を行います。ミスやトラブルを防ぐために終始大切です。
8. リスク管理
発生しうる問題や不確定要素を見つけて評価し、その対策を立てていきます。場合によっては好機の発見にもつながります。
9. 調達管理
外部の会社やサービスに仕事を依頼する際の手配・契約・進行状況のチェックを担当します。
10. ステークホルダー管理
関係する様々な人や組織の特定と、その期待をすり合わせながら良い関係を保つための活動です。
これら10の知識エリアは単体ではなく、お互いが関係し合いながらプロジェクト全体を支えています。
次の章では、知識エリアとプロセス群の関係や、どのフェーズで重みが高まるのかを解説します。
知識エリアとプロセス群のひも付け(どのフェーズで重みが高いか)

知識エリアはプロジェクトのどの段階で活躍するのか
PMBOKの「10の知識エリア」は、プロジェクトの5つのフェーズ(立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結)と密接に関係しています。各知識エリアがどのフェーズで特に重要になるかを知ることで、プロジェクト進行時に注力すべきポイントが見えてきます。
すべての段階で大切な知識エリア
「統合管理」「コミュニケーション管理」「ステークホルダー管理」は、プロジェクトの始まりから終わりまで継続的に必要とされる知識エリアです。たとえば、プロジェクト全体の方向性を決めたり、関係者と情報をしっかり共有したり、関わる人の期待や要望を早期につかんだりする活動は、どの段階でも欠かせません。
計画フェーズで重みが増す知識エリア
「スコープ管理」「スケジュール管理」「コスト管理」「リスク管理」「資源管理」「調達管理」は、計画フェーズで特に重要です。ここでは、プロジェクトで何をどこまでやるか(スコープ)、どのようなスケジュールで進めるか、予算はどれくらい必要か、予想されるリスクや必要な人・モノの調達まで、細かく計画します。この計画がしっかりしていないと、後の実行や監視フェーズでトラブルが生じやすくなります。
品質管理は複数フェーズで活躍
「品質管理」は、計画段階で施策を練り、実行しながら品質を守り、監視して問題がないかを常にチェックする役割です。お客様の満足やトラブル防止のため、絶えず目を配る必要があります。
実務で特に注意したいポイント
たとえば、はじめにスコープ(作業範囲)の定義が曖昧だと、後からスケジュールやコストがズレたり、調達やリスク管理も後手に回ってしまうことがあります。ですので、スコープやリスクの早期計画を徹底することで、遅延や予期せぬトラブルを減らすことができます。計画の内容はそのまま実行や監視のフェーズにも影響を及ぼすため、最初の計画段階から丁寧に取り組みましょう。
次の章では、「統合管理が“中核”と呼ばれる理由」について解説します。
統合管理が「中核」と呼ばれる理由

1. 統合管理とは何か
統合管理は、プロジェクト全体を一つにまとめる機能です。プロジェクトには、スケジュール作成やコスト管理、リスク対応など様々な活動があります。そのどれもが大切ですが、ばらばらに進めてしまうと、全体としてのバランスが崩れてしまいます。統合管理は、プロジェクトの方向性や優先順位をはっきりさせ、全体を調整しながらまとめていく役割を持ちます。
2. プロジェクトの基盤づくり
まず、統合管理は「プロジェクト憲章」という文書を作るところから始まります。これは「なぜこのプロジェクトを実施するのか」「どこに向かうのか」を明確にする大切な出発点です。さらに、どのようにプロジェクトを進めるかまとめた「マネジメント計画書」の作成も担当します。どちらもプロジェクト全体のコンパスのようなものです。
3. 日々の調整と決断
プロジェクトの現場は、想定通りに進むことばかりではありません。新たな課題や変更の提案が出てくることもしばしばです。このとき統合管理は、変更要求が全体にどんな影響を与えるかを評価し、実施するかどうかを判断します。計画の一貫性や関係者間の合意を守るために、こうした調整や優先順位付けが欠かせません。
4. 他の知識エリアとの関係
統合管理は「ガバナンス(総合調整)」の役割を持ち、他の9つの知識エリアに大きな影響を与えます。たとえば、スケジュールやコスト、品質の目標が競合した時に、どれを優先するかを決定します。もし統合管理が適切に働かないと、たくさんの知識エリアで努力しても、それぞれがばらばらな方向に進み、結果として効果が薄れてしまいます。
このように、統合管理はプロジェクト運営の中心として、全体をまとめ上げる役割を果たしています。
次の章:各知識エリアの要点(定義・主なプロセス・典型アウトプット)
各知識エリアの要点(定義・主なプロセス・典型アウトプット)

1. 統合管理
プロジェクト全体の方向性を決め、全体の調和を図る役割です。最初にプロジェクト憲章を作成し、プロジェクト管理計画書を整えます。その後、日々の進行を指揮し、問題や変更にも一元的に対応します。主なアウトプットは、プロジェクト憲章や管理計画のほか、各種レポート類や終結報告です。
2. スコープ管理
何を作るか、どこまでやるかを明確にし、迷いのない進行や成果物作りをサポートします。要求事項の収集、作業分解(WBS作成)、スコープの確認と制御が柱になります。成果物やWBS図、スコープ管理計画などが典型的なアウトプットです。
3. スケジュール管理
作業計画の作成と進捗管理がポイントです。作業内容を洗い出し、順序やかかる時間を見積もり、現実的なスケジュールを設計します。進捗状況を随時モニタリングし、調整を行います。スケジュール表やガントチャート、進捗レポートがよく使われます。
4. コスト管理
予算の計画、コスト見積もり、実績管理を行い、プロジェクト全体の費用を最適化します。そのために、予算配分表やコスト管理計画書、コストパフォーマンス指標(EVM)などが作成されます。
5. 品質管理
成果物や業務プロセスの品質を確保し、継続的な改善を目指します。品質計画書、監査結果、改善アクション案などを作成します。
6. 資源管理
チームや設備などの資源を適切に割り当て、効果的に活用します。人員配置表、チーム育成計画、資源割当リストなどが成果物となります。
7. コミュニケーション管理
関係者の間で必要な情報を円滑にやり取りし、期待のずれを防ぎます。コミュニケーション計画書や定例レポート、連絡記録などが主なアウトプットです。
8. リスク管理
リスク(不確実性)を洗い出し、分析・対応策を決めて実施状況を常に注視します。リスク登録簿、対応計画、リスク対応結果の記録が使われます。
9. 調達管理
外部企業などに業務や物品を発注し、それらのコントロールを担います。調達計画書、契約書類、受入・検収レポートなどが主な成果です。
10. ステークホルダー管理
関係者の特定、関与度の計画や調整を行い、円滑な協力体制を築きます。ステークホルダーリスト、関与度評価表、エンゲージメント計画などが典型的なアウトプットです。
次の章に記載するタイトル:第6版の10エリアと第7版の位置づけ(学習上の注意)
第6版の10エリアと第7版の位置づけ(学習上の注意)
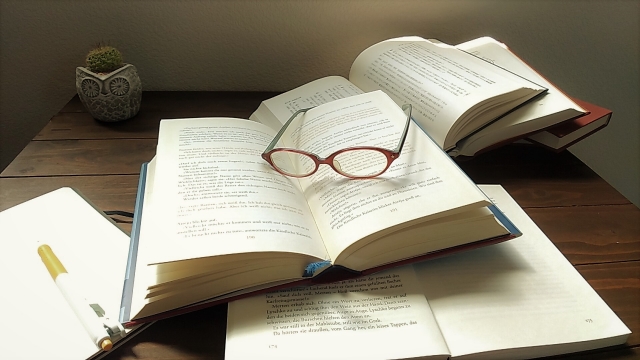
第6版と第7版の違いを知る
PMBOKの第6版では、「10の知識エリア」が明確に定義されています。これらはスコープ・スケジュール・コスト・品質など、プロジェクトマネジメントの業務を詳細に分けて説明しています。一方で、最新の第7版は「価値提供」を主軸とし、原則やシステム思考、適応性といった考え方を中心に据えています。そのため、全体像が「型」から「考え方」に大きく変わりました。
第6版を学ぶ意義
第6版の10エリア学習は今でも有効です。なぜなら、多くの現場やプロジェクトが“どこに何が必要か”を知識エリアの枠組みで考えているからです。たとえば「スケジュール管理」「コストコントロール」「リスク対応」など、具体的な手法やプロセスがしっかり紹介されており、実際の管理の場面ですぐ役立ちます。
第7版の考え方との合わせ技
現在は第7版の「原則型」と第6版の「プロセス型」をうまく組み合わせることが求められています。例えば、従来の計画主導型だけでなく、変化に柔軟に対応する“アジャイル”的な進め方も頻繁に現場で使われています。ですから第6版のベースライン管理や変更管理、EVM(出来高管理)などのスキルと、第7版の「価値」「チームワーク」「柔軟性」といった観点を両立することが大切です。
学習時の注意
第6版だけ・第7版だけ、どちらか片方を丸暗記するのではなく「両方の良さを活かす」つもりで学習を進めましょう。たとえば、リスクマネジメントの手法を第6版から学びつつ、状況の変化には原則思考で対応するなど、実務でも試験でも両側面が問われる場合が多いです。
次の章に記載するタイトル:試験対策・実務スキルとしての活用ポイント
試験対策・実務スキルとしての活用ポイント

試験合格に向けた重点ポイント
PMBOKの知識エリアを学ぶ際、試験対策として特に押さえておきたいのは「統合」「スコープ」「スケジュール」「コスト」「リスク」「コミュニケーション」の6領域です。応用情報技術者試験やPMP試験では、計画の立案や変更管理、トラブル時の対応方法などを中心に、実戦的な知識が問われます。
たとえば、WBS(作業分解構成図)の作成やクリティカルパス(遅れると全体に影響が出る作業の流れ)の特定、リスク洗い出しの優先順位付けなどが出題されます。試験問題は、理論だけでなく、典型的なプロジェクトの課題場面にどう対応するかまで問われるのが特徴です。普段から具体的な事例にあてはめて覚えることで、得点力が高まります。
実務で役立つ使い方のヒント
日々のプロジェクトマネジメント業務で知識エリアを活用するとき、実際に「どう使うか」が重要です。重要な6領域について、具体的なポイントを紹介します。
- スコープ管理: 最初にWBSを使ってやるべき作業を細かく分けます。これにより「やった・やっていない」が明確になり、トラブルが減ります。
- スケジュール管理: 重要な作業の順番や、どこが全体を遅らせる決定要因か(クリティカルパス)を確認しましょう。作業遅れをカバーする「バッファ(余裕時間)」も必ず設定します。
- コスト管理: EVM(出来高管理)という方法を使い、お金や作業進捗のズレを早めに見つけます。月ごとに進捗とコストの差分を計算して「うまくいっているか」を確かめます。
- リスク管理: 小さな兆候も見逃さず早期にリストアップします。誰がどのリスクに対応するかを“担当者(オーナー)”単位で決めておくと、対策が実行されやすくなります。
- コミュニケーション管理: RACIモデル(誰が責任者か、相談役か、要連絡先かを分類)で役割をはっきりさせます。さらに、週単位など定期的な進捗報告リズムを決めて、情報の漏れを防ぎます。
- 統合管理: プロジェクトの進行中に「計画と違うこと」が発生した場合、すぐに対策を決められる“変更管理ボード”を設けておきましょう。意思決定が速くなり、混乱を防げます。
これらのポイントを日々意識して取り入れることで、試験にも実務にも強い力が身につきます。
次の章に記載するタイトル:フェーズ別チェックリスト(適用の仕方)
フェーズ別チェックリスト(適用の仕方)

はじめに
前章では、プロジェクトを立ち上げてから終結までの各フェーズで重視すべき主な活動とポイントを簡潔にご紹介しました。本章では、その内容をもう一歩深め、実際に現場で役立つ「チェックリスト」として整理します。どのフェーズでも抜け漏れなく進めるためのガイドとしてご活用ください。
立ち上げフェーズ:準備の土台固め
- プロジェクト憲章を作成しましたか?(目的や範囲、責任者が明確になっているか)
- 最初にスコープを大まかに定めましたか?
- 主要な関係者(ステークホルダー)を特定し、役割や期待を整理できていますか?
- リスクとして思いつくものを洗い出していますか?
- プロジェクト運営のルール(ガバナンス)を用意しましたか?
計画フェーズ:進める道筋を設計
- スコープ、スケジュール、コストの「計画書」ができていますか?
- 品質要求や資源(人・物)の割当て案も整えていますか?
- 外部から調達がある場合、契約や調達方法を明確にしましたか?
- チーム内外とのコミュニケーション手順が確認できていますか?
- リスク管理計画を作り、リスクへの対応方法も用意していますか?
- どんな変更が発生しても対応できるよう、変更管理手順(ルール)を決めていますか?
実行フェーズ:計画を現実にする
- チームの体制を整え、必要に応じて教育や説明を行っていますか?
- メンバーとの日々の情報共有がスムーズに進んでいますか?
- 調達(購入・外部委託等)の手続きが予定どおり進行していますか?
- 定期的に品質チェックや業務指導を行い、良い状態を維持していますか?
- 予想外の問題やリスクへの対策を確実に実行していますか?
監視・コントロールフェーズ:状況の把握と修正
- 進捗はスケジュール、予算と比べてどれくらい合っているか確認していますか?
- 進捗報告にEVM(出来高管理)や定量的な指標を使っていますか?
- 品質や成果物の検査も欠かさずに実施?
- 新しい課題や変更要求が出た際、正しく処理する流れができていますか?
- リスクを定期的に見直し、必要な対策を追加していますか?
- ステークホルダー(関係者)の期待や不安を意識して応対していますか?
終結フェーズ:成果の確実な引き渡し
- 全ての納品物や成果が関係者に受け入れられていますか?
- 契約の締結・終了手続きが済んでいますか?
- プロジェクトで得た教訓や知識を整理・記録し、次回以降に活かせるようにしていますか?
- 成果や資料の引き継ぎが完了していますか?
次の章に記載するタイトル:初学者むけ用語メモ
初学者むけ用語メモ

WBS(Work Breakdown Structure)
WBSとは、大きな仕事を小さな作業にわかりやすく分ける方法です。たとえば、家を建てるなら「基礎工事」「壁の組み立て」「屋根の設置」「内装」といった具合に、全体のゴールにつながる作業を細かく整理します。WBSを作ることで、見落としや作業の重複を防ぎ、やるべきことが誰の目にも明確になります。
クリティカルパス
クリティカルパスは、すべての作業の中で一番時間がかかる道筋のことです。この経路にある作業が遅れると、プロジェクト全体が遅れてしまいます。例えるなら、駅伝でバトンをつなぐコースの中で、一番時間を食う区間がどこかを知っておき、そこを重点的に管理するようなイメージです。
ベースライン
ベースラインは、最初に「この内容・この期間・この予算で進めます」と決めた約束ラインです。スコープ(やるべき内容)、スケジュール(進行の順番や期間)、コスト(予算)の3つを中心に定めます。途中で変更したい場合は、このベースラインと見比べて「どこが、どれだけ違うか」をはっきりさせるための基準として使います。
EVM(Earned Value Management)
EVMは、どこまで仕事が進んでいるか、かかったお金はどうか、計画と比べて順調かを一体的にチェックする管理手法です。たとえば、今日までにやるはずだった分の進捗と実際に終わった作業、それに使った費用を比べて「遅れ」や「予算オーバー」をわかりやすく数字で教えてくれます。
次の章に記載するタイトル:実務導入のステップ(小さく始めて定着させる)
実務導入のステップ(小さく始めて定着させる)

1. 最初に取り組むべきは「スコープ」と「WBS」
プロジェクトを導入する際、まずは何を作るか・どこまでやるかという範囲(スコープ)を明確にします。ここでは、作業分解構成図(WBS)の作成が役立ちます。例えば、イベント開催プロジェクトなら「会場予約」「案内状送付」など、一連の作業を細かく分けて洗い出しましょう。これにより、抜け漏れ防止と関係者の認識あわせがしやすくなります。
2. 「スケジュール」と「クリティカルパス」を可視化する
次に、それぞれの作業をいつ・どの順番で進めるかをスケジュールに落とし込みます。ポイントは、納期に直結する重要工程(クリティカルパス)を見極めることです。ガントチャートなど視覚的ツールを使うと、プロジェクト全体の流れが一目で分かります。
3. 「コスト予実管理」と「EVMライト」の導入
ある程度作業とスケジュールが見えてきたら、コスト管理も始めましょう。計画に対して実際の費用がどう動いているかを、シンプルなExcel表などで記録します。「EVMライト」とは、必要最小限の要素で実績値を簡易的に記録し比較する方法です。
4. 「リスク登録簿」を作る
プロジェクトに潜むリスク(問題の芽)は、気付いた時点で「リスク登録簿」に書き出しておきます。例えば「天候による会場変更」など、今後の対策が立てやすくなります。
5. 「コミュニケーション計画」で連携強化
情報共有のルールを決めることで、関係者全員に必要な情報が行き渡ります。例えば「週1回進捗会議」「チャットでの連絡」などを、プロジェクト開始時に決めておきましょう。
6. 「変更管理フロー」=統合管理を仕組みに
最後に、計画変更への対応手順を明確にしましょう。作業や納期の見直しが必要になった時、どのような手順で関係者と合意形成するかを決めて「統合管理」として組み込みます。
成熟度向上は「レトロスペクティブ」から
プロジェクト終了時には、振り返り(レトロスペクティブ)を実施し、うまくいった点や改善点を洗い出します。得られた教訓は、次回以降に活かせるよう「テンプレート」や作業ツールの標準化につなげてください。カンバンやガントチャートも運用例を基に標準化を図ることで、組織全体の成熟度が高まります。