目次
この記事でわかること(主要5点)
- フレームワークとは何か
プロジェクトを成功に導くための「設計図」のような役割と、その価値が理解できる。 - 代表的なフレームワークの種類と特徴
PMBOK・ウォーターフォール・アジャイル/スクラム・WBS/PERT・CCPM・P2M・PPMなど、主要手法の使いどころがわかる。 - 最新のPMBOK第7版と活用のポイント
従来との違いや、他の手法との組み合わせ方を押さえられる。 - 現場での選び方と組み合わせ方
プロジェクトの特性やリソースに応じて、最適なフレームワークを選定・併用する実務のヒントを学べる。 - よくある失敗と回避策
形骸化やリソース偏りなど、現場で起きやすい落とし穴を防ぐ方法を知ることができる。
プロジェクトマネジメントの「フレームワーク」とは何か

プロジェクトを成功に導くためには、計画から完了まで、効率的かつ一貫した管理が欠かせません。この一貫管理を実現するための「枠組み」となるのが、プロジェクトマネジメントのフレームワークです。
フレームワークとは何か?
フレームワークとは、プロジェクトの始まりから終わりまでを体系化し、どのように進めていくかを示すガイドラインのようなものです。ただ手順を羅列するのではなく、計画・実行・監視・制御・完了の各段階ごとに「何を」「どのように」行うかを明確にします。
たとえば、家を建てるときには設計図が必要です。設計図があれば、大工さんや電気工事士など、さまざまな職種が連携して作業を進めることができます。プロジェクトマネジメントのフレームワークも同じ役割を持ちます。設計図のように透明性が高く、関係者が共通の理解をもちやすくなるのが特徴です。
フレームワークの核心的な価値
フレームワークの最大の利点は、チーム内で認識がそろい、協力しやすい点です。さらに、これまでの失敗や成功の経験(ベストプラクティス)が凝縮されているため、「何から手をつければいいかわからない」などと迷う場面を減らしてくれます。また、進行状況の見える化や問題発生時の対応ルールも整備されているため、スムーズなプロジェクト運営が可能になります。
さまざまな代表的フレームワーク
プロジェクトの規模や特性により、適切なフレームワークは異なります。代表例をいくつかご紹介します。
- PMBOK(ピンボック):世界的に有名な標準的ガイドライン
- ウォーターフォール:段階ごとの明確な進行方法
- アジャイル・スクラム:変化に強い柔軟な進行方法
- WBS/PERT:計画やプロセスの可視化・分解に特化
- CCPM、P2M、PPM:リソース調整や全体最適化に強み
これらを単体で使ったり、組み合わせて運用することで、各組織やプロジェクトのニーズに最適なマネジメントを実践できます。
次の章では、「PMBOK: 世界標準の知識体系を“土台”にする」についてご紹介します。
PMBOK: 世界標準の知識体系を“土台”にする

PMBOKとは?
PMBOK(ピンボック)とは、「Project Management Body of Knowledge」の略で、プロジェクトマネジメントの方法を体系的にまとめた“教科書”のような存在です。世界中で使われており、プロジェクトに関わる人なら一度は耳にする名前です。本のように章立てされていて、「計画」「実行」「監視」「完了」というプロジェクトの流れを段階ごとに具体的な手順とともに解説しています。
第7版で何が変わった?
従来のPMBOKは細かな工程やツールの説明がメインでしたが、第7版は「価値をしっかりと生み出すこと」と「原則に忠実であること」に重きをおいています。そして時代や現場の状況に合わせて、柔軟に活用できる内容へと進化しました。たとえば、「プロジェクトごとに最適なやり方を選ぶ」のが大切だと強調しています。
どんなときに役立つ?
PMBOKは、以下のような場面で効果を発揮します。
- 会社やチームで使う「言葉」を統一したい
- プロジェクトの手順を見落としたくない
- 様々なやり方(ウォーターフォール・アジャイルなど)を自分たち流に組み合わせたい
たとえば、新しいシステムを導入するとき、PMBOKの手順や用語を参考にすると担当者同士で意思疎通がスムーズになります。また計画段階だけでなく、進行中のチェックポイントや見直し方法まで整理されているため、“抜け漏れ”が起きにくくなります。
他の手法と両立できる?
PMBOKは、独立して使うだけでなくアジャイルなど他のフレームワークとも併せて利用できます。実際、最近はウォーターフォール型とアジャイル型の良い部分を組み合わせて実施するプロジェクトが増えています。その基盤作りにぴったりなのがPMBOKです。
次の章に記載するタイトル:ウォーターフォールとアジャイル/スクラムの使い分け
ウォーターフォールとアジャイル/スクラムの使い分け
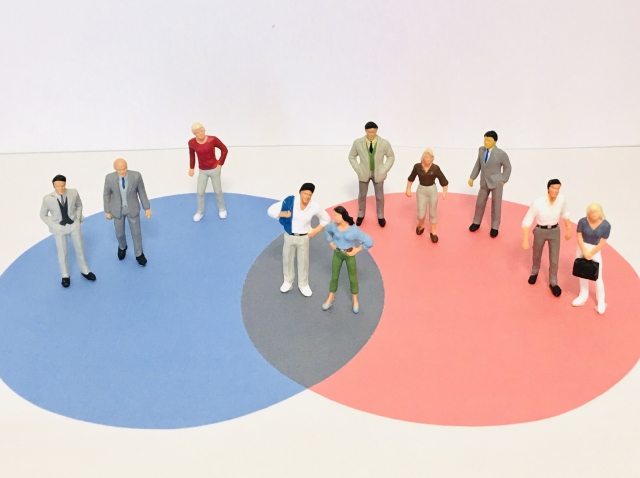
代表的な進め方の違い
プロジェクトをどのように進めるかは、その特性によって最適な方法が異なります。「ウォーターフォール」と「アジャイル」は、その代表的な手法です。
ウォーターフォールは「滝」のように、要件定義・設計・実装・テスト・納品といった工程を順番に進めていきます。たとえば家を建てるように、設計図が決まってから基礎を作り、順番に仕上げていくイメージです。この方法は、要件が最初から明確で変更も少ないときに向いています。橋やビルの建設、一部のシステム開発などが具体例です。
一方、アジャイルは途中の仕様変更やお客様からのフィードバックに柔軟に対応できる進め方です。短い期間ごとに計画→実施→振り返りを繰り返しながら徐々に完成形へ近づけていきます。身近な例でいえば、料理を作りながら味見をし、必要に応じて調味料を足す、というイメージです。
スクラム・かんばんの特徴
アジャイルの代表が「スクラム」です。チーム内で役割(ロール)を分け、2週間ほどの「スプリント」と呼ばれる短い期間単位で仕事を区切り、定期的な会議(イベント)で状況や改善点を話し合います。例えばアプリの新機能を追加する際、毎スプリントで「どこまでできたか」「何に困っているか」を全員で確認します。
また、「かんばん」や「スクラムばん」は仕事の進み具合を見える化し、人や仕事の流れを最適化することに重きを置いています。タスクをボードに貼り出し、「今やっている」「完了」などステータスごとに分けていきます。これにより、手詰まりや負荷の偏りにすぐ気付きやすくなります。
どちらを選ぶ?選定のポイント
- 要件(やること)が最初からはっきりしていて、大きく変わらない→ウォーターフォール
例:公的機関向けのシステム開発、大型建設工事など。途中で手戻りすると手間もコストも大きい場合に適します。
要件が曖昧、変更が多い/マーケットやユーザーの声を素早く取り入れたい→アジャイル/スクラム
- 例:スマホアプリ開発、新サービスの立ち上げ、小さなチームでのプロジェクトなど。何度も作り直しながら精度を上げていく時に力を発揮します。
また、どちらにも合わないケースや、工程ごとに適切なやり方を選んだ方が良い場合もあります。最近では設計はウォーターフォール、開発はアジャイル、といった「ハイブリッド型」も増えています。
次の章に記載するタイトル: WBS・ガント・PERT: 計画と可視化の基本ツール
WBS・ガント・PERT: 計画と可視化の基本ツール
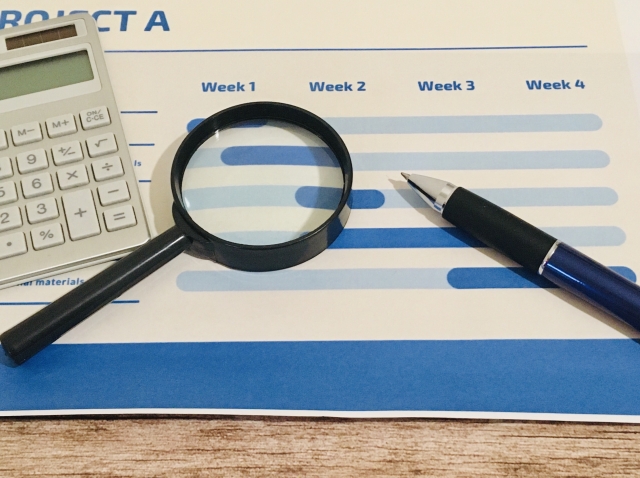
WBS(作業分解構成図)で仕事を“見える化”する
WBSは「Work Breakdown Structure」の略で、プロジェクトでやるべき作業を一つひとつ段階的に分解して図表化する手法です。例えば、家を建てる場合、「設計」「材料準備」「基礎工事」「建て方」「内装工事」などの大きな作業をまず挙げ、さらにその中身を「水道配管」「床張り」など細かい単位まで分けます。すると、どの作業をいつまでに誰がやるか明確になり、抜け漏れを減らせます。マイルストーン(達成点)を設定すれば、プロジェクトの途中段階でも進捗を確認でき、計画の確実性が高まります。
ガントチャートで全体のスケジュール管理
ガントチャートは作業ごとに横長のバーを描き、左から右に時間が流れるようにして表示します。一覧表にして並べることで、全体のスケジュールや作業と作業の関係性(前後関係、同時進行など)を一目で把握することができます。例えば、旅行の準備スケジュールを立てる場合、「航空券予約」「ホテル手配」「現地での観光計画」などを日付に沿ってバーで表し、進捗を簡単に共有できます。ガントチャートは個人のToDo管理にも応用可能で、会議資料としても使いやすいです。
PERTで不確実性のある計画に備える
PERT(Program Evaluation and Review Technique)は、タスクをネットワーク図にして順序や依存関係を可視化し、それぞれの作業期間を“最短・最長・最もありそう”の3パターンで見積もります。これにより、実際のプロジェクト期間の予測がしやすくなります。例えば、新商品開発プロジェクトなら、「試作品の設計」「検証テスト」「量産準備」など、どこで遅れや問題が起こりやすいか事前に洗い出しておけます。
この3つのツールを使い分けることで、計画の抜け漏れ防止から進捗把握、不確実性への備えまで、プロジェクト遂行の精度を高めることができます。
次の章に記載するタイトル: CCPM: リソース制約下のスケジュール最適化
CCPM: リソース制約下のスケジュール最適化

CCPMとは?
CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)は、プロジェクトのスケジュールを最適化するための手法です。他のスケジューリング方法と違い、CCPMは人や設備などリソース(資源)の不足や重複が引き起こす遅延リスクに注目します。たとえば一人の担当者が同時に二つ以上の作業を頼まれた場合、どうしても片方が遅れる可能性が高くなります。こうしたリソースの重なりを事前に見つけ、本当に一番大切な工程(クリティカルチェーン)を明確にすることで、スケジュール全体を効率よく進められるようにします。
バッファでスケジュールの遅れを吸収
CCPMの特徴的な考え方の一つに「バッファ」があります。バッファとは、タスクごとに設定する余裕時間のことです。しかし、CCPMではタスクひとつひとつに細かく余裕を取るのではなく、全体の流れの中で要所要所にバッファ(時間のクッション)をまとめて配置します。たとえば、納品までの間に予想外のトラブルや遅れが発生しても、その分の遅れを全体バッファが吸収し、全体スケジュールを守ることが目指せます。
マルチタスクの抑制がポイント
プロジェクトを進めながら複数の作業を同時に抱えると、集中力が分散して効率が悪くなります。CCPMでは、できるだけ一つの作業に専念できるよう工程とリソースを再配置します。たとえば、ある担当者がAとBの作業を並行して進めるのではなく、まずAに100%集中してからBにシフトする、というアイディアです。これにより各作業の完了速度が上がり、結果として全体のスケジュール遅延も減らす効果があります。
バッファ管理と進捗指標
進捗管理の指標には「バッファ消費率」がよく使われます。これは、すでに使ったバッファの割合を示す指標です。最終納期までにどれくらい余裕が残っているか、誰でも一目で分かるようにグラフなどで見える化します。バッファの減りが早い場合は、そのタイミングで原因の洗い出しと対策を迅速に行うことができます。
実際の活用例
CCPMは大規模なIT開発や工場のライン設計、複数の部門が並行して進めるプロジェクトなど、複雑でリソース調整が難しい現場でよく活用されています。たとえば建設現場では、工程ごとに異なる専門スタッフが入れ替わり作業を進めますが、一部のスタッフが遅れると後工程にすぐ影響が出てしまいます。こうした場合でもCCPMを活用すると、限られた人数・資源で効率よく全体を進行できるのです。
次の章では、日本発のフレームワーク「P2M」について解説します。
P2M: 日本発、プロジェクトからプログラムまでを一体設計
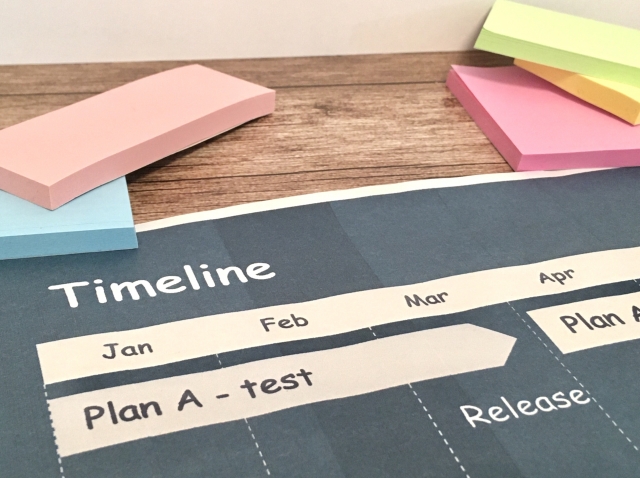
P2Mとは何か?
P2M(プロジェクト&プログラム・マネジメント)は、日本で開発されたプロジェクト管理のフレームワークです。この手法は単一のプロジェクト管理だけでなく、企業の大きな目標に向けて複数のプロジェクトをまとめ、全体としてコントロールする考え方を重視します。たとえば、企業が新しい製品を開発し、研究(R&D)から量産・販売、さらにはサービス展開まで段階をふんで価値を創り出す場合、P2Mによる統合的な管理が有効です。
プロジェクトから「プログラム」へ
P2M独自の強みは、関連する複数のプロジェクトを「プログラム」として一括管理できることにあります。具体例として、サプライチェーン全体の改革や、全社を挙げたデジタル変革(DX)の推進が挙げられます。個々のプロジェクトがバラバラに進むのではなく、相互の関連やリソース配分を調整しながら最適化します。そのため、部門をまたぐ大きな取り組みや長期間の変革には特に力を発揮します。
日本企業に合った理由
P2Mは日本の経営環境や商習慣に合わせて開発されました。チームで協働する文化や、時間をかけて慎重に段階をふむ進め方、関係者の合意形成を重視する点などが特徴です。たとえば、技術開発とマーケティング、製造部門が連携するような現場では、価値創造成果を中長期的に追っていくP2Mの考え方がフィットしやすいです。
どんな場面で活用できる?
P2Mは、特に次のようなシーンで活躍します。
- 複数部門が共同で進める新規事業の創出
- 技術開発(R&D)から事業化までのプロセス管理
- サプライチェーン全体の見直しや効率化
- 会社全体での構造改革やイノベーション推進
これらはどれも、複数のプロジェクトや部署を横断し、総合的な計画と調整が必須となる事例です。
次の章に記載するタイトル:PPM: 全社のプロジェクト投資を最適化する
PPM: 全社のプロジェクト投資を最適化する

PPMとは?
PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、会社全体で動かしている数多くのプロジェクトを「投資の集合体」としてまとめて管理する仕組みです。個々の案件をバラバラに進めるのではなく、組織戦略に合わせて優先順位をつけ、会社の経営資源(人・時間・お金)を無駄なく配分することを目指します。
どんな場面で役立つ?(具体例)
たとえば、IT企業やメーカー、銀行、コンサルのように同時にいくつものプロジェクトを抱える会社の場合、全体の“最適化”が難しいことが多いです。現場ごとに案件が増えて混乱したり、リソース配分が偏ったり、重要な案件に人員を割けなくなったりすることもあります。PPMを導入することで、経営戦略にマッチしたプロジェクトだけを選ぶ、限られた人員や予算を効率よく割り振ることができるようになります。
重要な選定基準
PPMでプロジェクトを選ぶ際は、主に3つの基準を使います。
- 組織の戦略との適合性(そのプロジェクトは会社の将来像に合っているか?)
- ROI(投資対効果)は十分か?
- リスク(失敗したときのダメージや不確実性)は許容範囲か?
たとえば、新しい製品開発と既存サービスの改善案件を比べたとき、経営方針が“新市場開拓”を重視していれば新製品案件の優先度が上がります。
段階ゲート(ステージゲート)でのチェック
プロジェクトを進める中で定期的に「段階ゲート(ステージゲート)」で見直しを行います。これは、「一度決めた投資を惰性で続けない」ための仕組みです。たとえば、企画段階→開発初期→試作→本格リリースなど、各段階ごとに“続行するかどうか”を再評価します。これにより、リスクの大きなプロジェクトを早めにストップする判断もできるようになります。
キャパシティ計画と可視化の工夫
複数案件を管理するには、会社全体の人材や予算など“キャパシティ”を見える化することが大事です。具体的には、「今、どの人材や部署がどれだけ案件を抱えているか」「予算の残りはどのくらいか」などを一覧できるダッシュボードを作ります。最近はカンバン方式(案件ごとに進み具合を“カード”で管理)がよく使われ、進行状況やリソースの偏りも一目で把握できます。
次の章に記載するタイトル:クリティカルパス、PRINCE2、シックスシグマも押さえる
クリティカルパス、PRINCE2、シックスシグマも押さえる
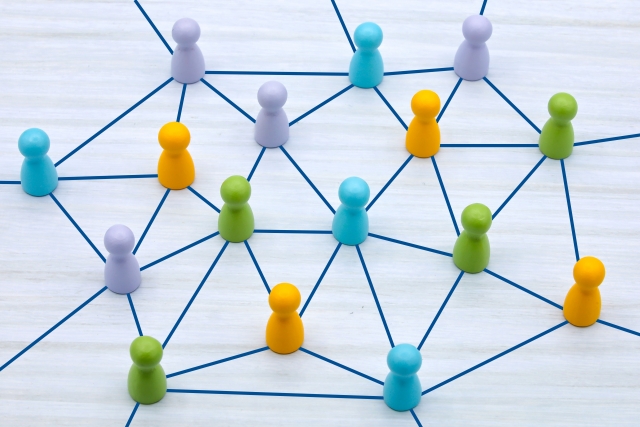
クリティカルパス法(CPM):最長経路で全体期間をコントロール
プロジェクトの計画や管理の際、必ず耳にするのが「クリティカルパス法(CPM)」です。クリティカルパスとは、プロジェクト全体の作業の中で、最も時間のかかる作業の連なり、つまり最長経路を指します。この経路上のどれか一つでも遅れると、プロジェクト全体の完成が遅れてしまいます。例えば家の建設プロジェクトでは、基礎工事、壁の設置、屋根の設置が順に進む必要があり、この順番がクリティカルパスとなることが多いです。短縮したい場合は、この最長経路上の作業を見直すのが効果的です。
PRINCE2:原則に基づく管理手法
PRINCE2(プリンス・ツー)はイギリス発のプロジェクト管理手法で、公共機関や大企業で広く使われています。特徴は、7つの原則、7つのテーマ、7つのプロセスという枠組みでプロジェクト全体を管理することです。たとえば「常にビジネスの価値があるか?」という観点を重視したり、「プロジェクトの途中で状況が変わった場合は見直しを行う」といった原則をはっきりさせています。そのため、関係者間の合意や責任分担を明確にしたい場合や、大きな組織の中でしっかりと管理したいときに役立ちます。
シックスシグマ:品質改善のための手順重視の方法論
シックスシグマは元々製造業で生まれた品質管理・改善の方法で、今ではサービスやITの現場でも取り入れられています。強みは「数字やデータ」に基づいて問題点を明らかにし、改善策を進める点です。代表的な手順としてDMAIC(定義・測定・分析・改善・管理)やDMADV(定義・測定・分析・設計・検証)があり、それぞれプロジェクトのタイプに合わせて活用します。例えば新しい製品開発ならDMADV、既存プロセスの改善ならDMAICといった使い分けがあります。
次の章に記載するタイトル:フレームワーク選定の実務ガイド(チェックリスト)
フレームワーク選定の実務ガイド(チェックリスト)

プロジェクトを成功させるためには、状況に合わせて適切なマネジメントフレームワークを選ぶことが重要です。この章では、実際にどのような基準で選定すれば良いか、具体的なチェックリストの形でご紹介します。
1. 要件の安定度と変更頻度を確認
まず、プロジェクト要求がどの程度安定しているかを見極めます。もし最初に仕様がほとんど固まり、変更が少ない場合は「ウォーターフォール型」が適しています。一方、途中での仕様変更や新しい要素の追加が多い場合は「アジャイル」や「スクラム」方式が有効です。
例: 商品カタログのシステム開発など、仕様が事前に決まりやすいものはウォーターフォール。新製品アイデアの試作やサービスの改善プロジェクトなど、動きながら柔軟に内容を調整したい場合はアジャイルが便利です。
2. リソースのボトルネックを調べる
人員や設備に制約がある場合は、スケジューリングの工夫が大切です。「CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)」の手法を使い、遅延リスクを吸収するバッファ(余裕期間)を設けることが有効です。
例: 工場の生産ラインで特定の工程が渋滞しやすい場合や、少人数でプロジェクトを進める必要がある場合にCCPMが役立ちます。
3. 複数プロジェクトの管理と戦略との整合性
同時に多数のプロジェクトが動いていたり、会社全体の方針とのバランスを重視したい場合は、「PPM(プロジェクトポートフォリオマネジメント)」や「プログラム管理」を用いるのが効果的です。
例: IT部門で複数のアプリ開発や改修案件を一括して優先順位付けしたい場合、PPMによる全体最適が助けになります。
4. ガバナンスや規制対応の必要性
社内ルールや外部規制に厳格に従う必要がある場合は、「PRINCE2」や段階ゲート管理(ステージゲート)の仕組みが役立ちます。レビューや承認イベントを明確に設け、抜け漏れを防ぎます。
例: 金融や医療、不動産取引など、コンプライアンス重視のプロジェクトでおすすめです。
5. 工程最適化と品質重視の取組
製造や設計など“工程”が複雑なプロジェクトや、品質確保が最重要なときは、工程を細かく分析する「CPM」「PERT」や、全体のプロセス改善をはかる「シックスシグマ」との併用が有効です。
例: 製品開発で設計~生産まで多くのステップを管理するケース、出荷前検査の品質向上などで活用できます。
6. 共通基盤づくり
どのフレームワークでも共通して役立つのが、PMBOK(ピンボック)の原則や用語です。チームの共通言語として使い、WBS(作業分解図)やガントチャートで計画を見える化しましょう。
次の章に記載するタイトル: 併用アーキテクチャの例(ハイブリッド実装)
併用アーキテクチャの例(ハイブリッド実装)

複数のフレームワークを組み合わせて使う
実際の現場では、ひとつのフレームワークにこだわるよりも、それぞれの強みを活かして「併用」することが重要です。例えば、プロジェクト全体の共通言語や進め方にはPMBOKの標準プロセスを参照します。専門用語や手順を共通化することで、異なる部署や担当者間でも意思疎通がスムーズになります。
開発現場 vs 経営層で分けて考える
現場のソフトウェア開発チームにはアジャイル/スクラムを採用し、短いサイクルで成果を出しやすくします。一方、経営層や複数プロジェクトをまとめる立場ではPPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)を使い、会社全体としてどのプロジェクトに力を注ぐかを決めます。
工程ごとに使う道具を変える
スケジューリングにはCCPM(クリティカルチェーン法)やクリティカルパス法(CPM)を使って、人的リソースや工程の重なりを考慮しながら無駄を省きます。計画書やタスク管理にはWBS(作業分解構成図)やガントチャートを利用し、進捗や課題の見える化を徹底します。品質向上にはシックスシグマの手法を要所で導入することで、エラーやムダの削減も狙えます。
過剰なルールには注意
このようなハイブリッド実装で大事なのは、組織やチームの実力、文化に合わせて“必要なだけ”の仕組みを取り入れることです。ルールが多すぎると、かえって動きが鈍くなってしまいます。無理のない範囲で可視化と意思決定の速さを両立し、現場の成長に合わせて少しずつ取り入れるのがコツです。
次の章に記載するタイトル:すぐ使える実装ヒント
すぐ使える実装ヒント

WBSの使い方:分解からスケジュール化まで
WBS(作業分解構造)は、プロジェクトの全体像をつかみやすくする基本ツールです。まず、大きな成果物をいくつかの細かいブロックに分ける「成果物分解」をします。その後、これらの成果物を作るために必要な具体的作業に「作業分解」していきます。このとき、担当者や期限を各タスクごとに割り当て、重要な節目となる「マイルストーン」も決めておくと、チーム全員がゴールに向けて動きやすくなります。
分解した作業同士の「依存関係」も整理しましょう。つまり、「この作業が終わらないと次に進めない」といった順番を明確にします。最後に、ガントチャートなどの見える化ツールを使って、全体の流れをスケジュールに落とし込みます。こうすることで、進捗確認もしやすくなります。
かんばん可視化:進み具合をひと目で管理
タスクの見える化でよく使われるのが「かんばん方式」です。タスクを「To Do(やるべきこと)」「Doing(進行中)」「Done(完了)」の3つに区分してボードに並べます。この各列に載せる数をあらかじめ制限する(WIP制限)ことで、同時進行のしすぎによる混乱を防げます。
問題が起きて進めないタスク(ブロッカー)は特別なマークをつけてすぐ分かるようにしましょう。また、それぞれのタスクがどのくらいの日数で進むか(リードタイム)も記録しておくと、後の作業効率アップが狙えます。
CCPMバッファ設計:ムダな余白を見直す方法
CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)は、プロジェクトを速く終わらせたいときによく使います。タスクごとの見積もり時間から「安全余裕」を半分に減らし、その余裕をまとめてプロジェクト全体のバッファとして確保します。これにより、1つずつタスクのムダが減り、全体の時間を効率化できます。
バッファには「プロジェクトバッファ」(納期を守るための余裕)と「フィーディングバッファ」(他作業の遅れ対策)があり、それぞれ明確にしましょう。バッファがどれくらい消費されているかを定期的にチェックすれば、遅れそうな場合でも早めに対処できます。
PPMダッシュボード:複数プロジェクトをまとめて監視
複数のプロジェクトを同時に動かす会社やチームでは「PPMダッシュボード」が役立ちます。各プロジェクトの合計点を「戦略整合度スコア」や「期待される利益(ROI)」として表示し、チームや人的資源の余裕(キャパシティ)、それぞれの進捗に合わせて「リスクヒートマップ」を使って危険度を色分けします。
さらに、重要な段階ごとに合格・不合格を記録できる「段階ゲート」も使えば、時期ごとに優先度の高いプロジェクトにリソースを集める判断がしやすくなります。
次の章に記載するタイトル:よくある失敗と回避策
よくある失敗と回避策

1. フレームワークの過信と形骸化
プロジェクト管理フレームワークは、便利な道具ですが、決して万能ではありません。時として「型」にこだわり過ぎて、本来の目的や現場の実情を見失うケースが多くあります。例えば、計画書の作成が目的化し、日々の実践や問題解決につながっていない状況です。
このような形骸化を防ぐには、現場からのフィードバックを積極的に取り入れる仕組みを用意しましょう。定期的な「振り返り」や「レトロスペクティブ」と呼ばれる会議を設け、小さな改善を積み重ねることが大切です。たとえば、週1回の短い時間でも、現場メンバーから「困っていること」「うまくいったこと」を出し合い、具体的なアクション改善につなげることで、フレームワークの運用が活きたものになります。
2. 用語や手順の乱立と不統一
異なるフレームワークをいくつも導入すると、現場で用語や手順がバラバラになってしまうことがあります。例えば、同じ進捗管理でも「進捗率」と「完了率」といった言葉が混在するとコミュニケーションが齟齬をきたします。
回避策として、PMBOKを参考に共通の用語集やテンプレートを整備し、全員で使い方を統一するのが有効です。定期的に「用語の認識合わせ」を行い、共通の理解を持つことで意思疎通の齟齬を減らせます。
3. リソースの見える化不足
誰に、どのくらい仕事が割り振られているかが分からないと、負担が偏ったり、ボトルネックが見落とされたりします。実際には、特定のメンバーにタスクが集中してプロジェクトが停滞することも珍しくありません。
この課題には、タスクごとの「作業中(WIP)」数を制限する、進捗を可視化するガントチャートやリソース負荷ビューを活用するなど、早めに対策を取ることが重要です。CCPMやCPMの発想を応用して、ボトルネックとなる工程や人物を特定する仕組みを取り入れましょう。
4. ポートフォリオの優先度が不明確
複数のプロジェクトを同時に抱えると、「どれを優先すべきか分からない」「経営の意向が現場に伝わらない」といった事態が起こりがちです。結果として、曖昧な基準でプロジェクトが進み、期待通りの成果が得られないこともあります。
こうした場合は、PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)の考え方を活用し、経営層が明確な判断基準を設定することが不可欠です。例えば、「売上インパクト」「戦略性」「実行可能性」など、事前に評価軸を決めて意思決定をサポートすることで、現場の迷いを減らせます。
次の章に記載するタイトル:ケース別おすすめ組み合わせ
ケース別おすすめ組み合わせ

プロジェクトマネジメントのフレームワークは、多様な現場や案件ごとに最適な組み合わせを考えることで、最大の効果を発揮します。ここでは、よくある3つのケースに分けて、おすすめのフレームワークの組み合わせと活用ポイントを紹介します。
1. 新規プロダクト開発(不確実性が高い場合)
新しいサービスやシステム開発など、ゴールや要件が変化しやすいプロジェクトでは、柔軟な管理方法が重要です。スクラムなどのアジャイル開発手法と、作業の見える化や負荷調整ができる「かんばん」を組み合わせると、進行中の課題解決や優先順位付けがスムーズです。また、投資判断やリソース配分にはPPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)を使うことで、全体のバランスが取れます。組織内で標準的な手順やルールを整えるにはPMBOKを参照し、品質面を簡単に改善したいときは、軽量なシックスシグマのツールを活用すると良いでしょう。
活用例:
- スクラム:2週間ごとにスプリント(作業の区切り)を実施し、定期的にお客様に見せて評価をもらう
- かんばん:タスクごとに「作業中」「レビュー待ち」などの状態をチームで可視化
- PPM:アイデアや機能ごとにリソースや予算を配分し、途中で注力分野の見直しも可能
- PMBOK:作成するドキュメントや手続きの標準を策定
- シックスシグマ(簡易版):トラブル分析や工程改善に、シンプルなグラフや集計表を使う
2. 受託開発(要件が明確な場合)
お客様から仕様が決まった状態で受けるシステム開発やWebサイト制作には、ウォーターフォール型がしっかりハマります。タスクの順番や締切を明確にするために、WBS(作業分解構成図)やガントチャートを使い、進捗の“見える化”をします。期間やコストの計算、重要な手順の洗い出しにはクリティカルパス法(CPM)やPERTを取り入れるのがおすすめです。また、お客様から追加要望が発生しやすい場合は、あらかじめ変更管理のルールを固めておくことで、トラブルを防ぐ効果があります。
活用例:
- ウォーターフォール:要件定義→設計→製造→テスト→納品と段階的に進行
- WBS/ガント:全体スケジュールの視覚化、部署や担当ごとの進み具合を管理
- CPM/PERT:納期が遅れそうな要注意タスクや、作業の順番を整理
- 変更管理:追加要件の発生時は影響範囲・コスト・納期の再評価ルールを運用
3. 複数部門横断の改革プロジェクト
大規模な組織変更や複数の部門をまたぐシステム導入など、関わる人や部署が多いプロジェクトには、全体の「プログラム管理」が大切です。P2Mは日本発の手法で、関連プロジェクト群を一体で見渡せます。どのプロジェクトから着手するか、どこに最優先で投資するかはPPMで適切に判断します。また、多数のタスクや担当者が絡むため、リソース(人・時間)の制約管理としてCCPMを併用することで、実現可能な計画を立てやすくなります。
活用例:
- P2M:各部門の業務改革や新システム導入を、ひとつの「プログラム」として統合管理
- PPM:部門ごと、プロジェクトごとに優先順位と投資配分を整理
- CCPM:人員や設備などの制約をふまえ、現実的なスケジュールで推進
プロジェクトの特徴に応じて、フレームワークを組み合わせることで成果を最大化できます。自社・自チームの状況を見極め、最適な「道具箱」を作っていきましょう。