目次
はじめに
システム開発契約における「プロジェクトマネジメント義務」と「協力義務」完全ガイド
ITシステムの導入や開発の現場では、プロジェクトの進行がスムーズにいくかどうかが大きな関心事です。その成否を左右するのが「プロジェクトマネジメント義務(PM義務)」と「協力義務」です。本ガイドでは、これらの義務について、法的な背景や契約書での記載方法、実際の運用で注意すべき点までをわかりやすく解説します。企業の情報システム部門や開発ベンダーの担当者はもちろん、初めて契約に携わる方にも役立つ内容となっています。
この記事でわかること
- プロジェクトマネジメント義務の法的位置づけと実務範囲
- 協力義務との関係と双方の責任分担
- 契約書に明記すべきPM義務の具体項目と運用ポイント
- 紛争を防ぐための証拠化・記録管理の実践手法
- ベンダー・ユーザー双方に必要な実務チェックリストと予防策
1. プロジェクトマネジメント義務とは何か(法的位置づけ)

システム開発やIT関連のプロジェクトを外部の業者(ベンダー)に委託する際、よく聞くのが「プロジェクトマネジメント義務(PM義務)」という言葉です。PM義務とは、受託者―すなわちベンダー―が契約した開発業務を円滑かつ計画的に遂行するため、プロジェクト全体の進行管理や課題の把握、関係者との調整などを適切に行うべき責任のことを指します。
しかし、民法などの法律に「PM義務」を明確に規定した条文はありません。そのため、法的には「受託者は善良な管理者の注意義務を負う」といった一般的な規定を根拠に、契約や過去の判例、業界の慣行などから具体的な内容が定められます。この性質上、どのような範囲や内容の義務をベンダーに求めるかは、案件ごとに違いが生じやすいです。
そのため、実際の契約では「どんな内容のプロジェクトマネジメント義務があるのか」「どこまでやれば足りるのか」を、できるだけ明確に記載することがトラブル防止のカギとなります。たとえば、「進捗報告やリスク管理を行う」「問題発生時には速やかに報告する」など、具体的義務をあらかじめ契約書で合意しておくことが大切です。
次の章では、ユーザー側が負う「協力義務」とPM義務の関係について解説します。
3. 判例・実務資料が示すPM義務の射程
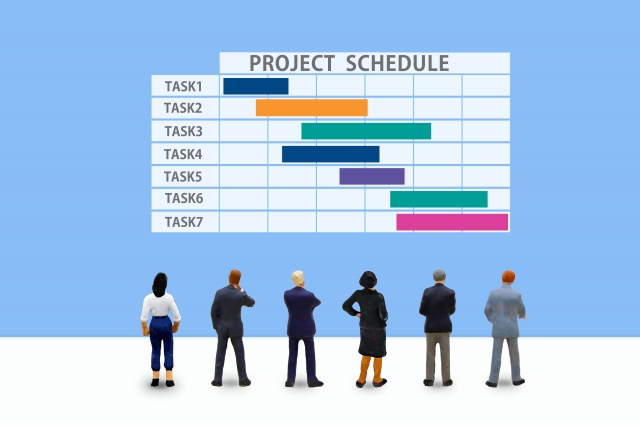
プロジェクトマネジメント義務(PM義務)に関する考え方は、主に裁判例や実務上のガイドラインにもとづいて形成されています。ここでのポイントは、PM義務がどの範囲まで求められるかという「射程」=守るべき内容と範囲です。
判例が示すPM義務の守備範囲
実際の裁判例では、「プロジェクト全体の円滑な進行管理」や「問題が発生した際の早期報告」、「関係者への適切な情報提供・調整」などの基本的な行為がPM義務であると認められています。たとえば、システム開発のトラブルで、「受注側(ベンダー)がユーザーと十分な協議やリスク説明を行わなかった」ことが問題とされ、ベンダー側の過失と判断された事例があります。こうしたケースでは、「最低限の進捗管理」や「合意事項の記録」、「仕様変更の合意形成」などがPM義務に含まれると考えられます。
実務上のガイドライン・通達等
また、業界団体や公的機関が出すガイドラインなどでも、PM義務について「リスク予見」「客観的な判断に基づく進行管理」「ユーザーへの説明責任」など、幅広い内容が例示されています。特に、「顧客がシステム利用できるよう最善を尽くすこと」「途中で困難があった場合には早期にアラートを挙げること」など、実務的な観点が重視されています。
どこまでやれば義務を果たしたといえるのか
PM義務の範囲については、「できる限りの対策を尽くせば足りる」という一種の“努力義務”の色合いがありますが、客観的な基準やプロジェクトの性質に応じて具体的な求められる行動が変わります。ユーザーとの協力が十分でなかった場合は、ベンダー側のPM義務が軽減されることもあり、両者がともに役割を果たすことが不可欠です。
次の章では、契約書にどのようなPM義務の内容を明記すべきか、具体的な項目例を紹介します。
4. 契約書に明記すべきPM義務の具体項目(例)

プロジェクトマネジメント(PM)義務が紛争回避や実務運用において重要であることについて、これまでご説明しました。ここでは、実際の契約書にどのようなPM義務を明記すべきか、その具体的な項目についてご紹介します。
1. スケジュール管理・進捗報告
ベンダーは、事前に合意した工程ごとに進捗報告を行う義務を明記すると良いでしょう。たとえば「週次で進捗報告書を提出し、重要な課題やリスクは逐次説明すること」といった具合です。これによって遅延や問題発生時の早期発見が可能になります。
2. 変更管理の手続き
ユーザーからの要望変更や仕様追加があった際、所定の手続きに従って記録・協議し、変更による納期や費用への影響を明確に説明することを契約書に記載しましょう。「変更管理会議の開催と議事録作成・承認」など、現場で曖昧になりやすい部分まで具体的に取り決めておくことが重要です。
3. 問題・リスクの共有
開発途中で発生する問題点や予見されるリスクについては、両者間で共有し協議する義務を明文化します。「一定規模以上の障害や課題は、速やかにユーザーへ報告する」などを記載すると、後々のトラブル予防につながります。
4. コミュニケーション方法
定期会議の開催や連絡担当者の指定など、日常的な情報共有の仕組みも契約に盛り込むことが有効です。メールやチャット、オンライン会議ツールの利用範囲まであらかじめ決めておくことで連絡漏れを防げます。
これらの項目は一例ですが、業務内容や事案に応じてカスタマイズしてください。契約締結時にPM義務の具体項目を明記することで、責任範囲がはっきりし、後の齟齬や紛争を未然に防ぐ効果が高まります。
次の章では、実務運用の要点(訴訟予防・証拠化重視)について解説します。
5. 実務運用の要点(訴訟予防・証拠化重視)

プロジェクトマネジメント義務を契約書に明記しただけで安心するのは危険です。実務では、その内容を日々どのように運用し、あとから証明できる形に残すことがとても重要です。以下では、特に訴訟予防と証拠化の観点から、PM義務の実務運用で押さえておきたいポイントを解説します。
1. 合意内容の文書化と保管
どんな話し合いも、メールや議事録、チャットのログなど、文書で記録することが鉄則です。例えば、要件の変更や仕様の追加・削除などがあった場合は、必ず誰と誰が、いつ、どのように合意したかを残しましょう。文書の保管場所や保存ルールも、関係者全員であらかじめ決めておくと安心です。
2. 進捗・課題・リスク管理の「見える化」
進捗報告や課題管理表、リスク一覧などは、できるだけ共有のツールやフォーマットを使いましょう。経緯が一目で分かるように残せば、後日「言った言わない」のトラブルを防げます。また、報告や承認の期限も具体的に定めておき、遅延時はすぐにエスカレーションするルールを守ることが大切です。
3. ユーザー協力義務の履行管理
ユーザー側の協力や作業提供が遅れた場合、その記録も必ず残しましょう。たとえば「レビューの日程変更」「資料提供の遅延」といった事実を、できるだけ客観的な証拠として記録します。そのうえで、遅延がプロジェクト全体に与える影響についても、都度ユーザーに説明し了承を取ることが望ましいです。
4. 変更管理プロセスの適正運用
変更が発生した際は、その影響分析・合意・履歴の記録を徹底します。「どの変更が、どのタイミングで、どのように認められたのか」「納期や費用の変更が生じたか」など、その流れを文書で追えるようにしておいてください。これにより、不本意な無償対応や紛争リスクの低減につながります。
5. 訴訟リスクを見据えた記録と説明
万一トラブルや訴訟になった場合に備え、第三者が見ても分かる形の記録を意識しましょう。たとえば、主要なやり取りや決定事項は「合意済み」「承認済み」と明記しておく、郵送や電子署名の活用なども有効です。また、説明責任をきちんと果たしていることを示す記録(定例会での説明、通知履歴等)も残しておくと安全です。
次の章では、PM義務の実務的内実(PM職務との重なり)について解説します。
6. PM義務の実務的内実(PM職務との重なり)

PM義務の実態とPM職の違い
プロジェクトマネジメント義務(PM義務)は、日々のプロジェクト管理業務と密接にリンクしています。実際には、PM(プロジェクトマネージャー)が通常行う職務内容と重なる部分が多いです。しかし、単に日々の管理作業をしているだけでは、法的責任を果たしたとは言えません。重要なのは、「なぜ」「どのように」対応したかを記録し、証拠として残すことです。
実務場面で期待される具体的行動
例えば、進捗遅延や不具合が発生した場合、PMは状況を整理し、速やかにその内容やリスクを関係者へ説明する義務があります。また、計画の見直しが必要になれば、その理由と新たな提案内容を文書化し、合意を得る流れを作ることが求められます。これらは、日常的な管理業務のように見えますが、法的観点からは「責任を伴う説明と合意形成」が重要なポイントとなります。
コミュニケーション・管理資料のポイント
議事録や週次報告などの定期的なドキュメントは、PM職務としての基本ですが、これをPM義務の観点から“訴訟などの有事にも通用する形”にする工夫が求められます。例えば、会議後すぐに内容をまとめ関係者の了承を取る、重要意思決定は承認証跡を残す、リスクや課題管理は担当・期限・対応結果まで分かるよう記録する、などです。
PM義務と現場業務の折り合い
PM義務を適切に果たすためには、作業負担の増加を防ぐ工夫も必要です。たとえば、テンプレート化やシステムでの管理を活用して、記録や報告を効率化できます。実務では、“やるべきこと”を明確にして優先順位をつけ、肝心な場面で確実に証拠・記録を残せる体制を築くことが大切です。
次の章に記載するタイトル:よくある紛争ポイントと回避策
7. よくある紛争ポイントと回避策

システム開発でよく起こるトラブル例
システム開発におけるプロジェクトマネジメント(PM)義務は重要ですが、実際には多くの現場でトラブルが発生しています。よくある紛争のポイントとしては、以下のような例が挙げられます。
- 進捗遅延:計画通りにプロジェクトが進まない場合に、「PMは適切に管理を尽くしたのか」という点が問題になります。
- コミュニケーション不足:ベンダーとユーザーの間や、プロジェクト内チーム間で情報共有が不十分な場合、責任の所在が曖昧になりがちです。
- 仕様変更への対応:途中でユーザーから追加要望が発生し、これにどう対応したかが争点になることがあります。
- 証拠不足:後になって「言った・言わない」や、どの時点で何が決まったか分からなくなることが多いです。
実際の紛争事例(簡単な例示)
たとえば、大型システム開発の途中で大幅な仕様変更が発生し、追加費用や納期変更をめぐりベンダー側とユーザー側で意見が対立するケースがあります。また、進行管理の記録や議事録が残っていないため、どちらに落ち度があるのか明確にできず、裁判などで紛糾するケースも見られます。
紛争を回避するための具体策
このようなトラブルを防ぐには、次のような方法が有効です。
- 定期的な進捗報告や会議を設定し、必ず議事録を作成・保存します。
- 仕様変更など重要な決定事項は必ず書面で記録し、関係者の合意を取りましょう。
- 問題発生時には、原因分析と対応策を明確に文書化し、関係者で共有します。
- もめごとになりそうな場合は、専門家や第三者の意見を早期に取り入れましょう。
- 契約時に、争点になりやすい事項(進捗報告方法や変更手続きなど)を明記すると、後の紛争予防につながります。
これらを実践することで、万が一トラブルが起きても、事実関係を証明しやすくなり、公平な解決に寄与します。
次の章では、「契約条項のドラフト例(抜粋・要素案)」について解説します。
8. 契約条項のドラフト例(抜粋・要素案)

代表的な契約条項例
ここでは、プロジェクトマネジメント(PM)義務に関わる契約条項の一例と、その盛り込むべき要素についてご紹介します。それぞれ、前章で解説した紛争ポイントを回避するための実務的工夫を反映しています。
1. プロジェクト管理義務の明記
- 例:「ベンダーは、本契約に基づき、納期遅延等が発生しないよう、進捗管理、リスク管理、課題管理を適切・継続的に行うものとする。」
- ポイント:管理項目(進捗・リスク・課題など)を明記し、抽象的な表現を避けます。
2. 変更管理プロセス
- 例:「仕様変更等が生じた場合、書面による変更申請と、双方の承認による正式な変更契約の締結を要するものとする。」
- ポイント:必ず書面手続きを要求し、口頭合意によるトラブルを防ぎます。
3. ユーザー協力義務(具体化)
- 例:「ユーザーは、ベンダーの求めに応じ、合理的な期限内にレビュー・承認・意思決定等を行う。また、担当者の指名および決裁期限を事前に定めるものとする。」
- ポイント:ユーザーの対応遅延によるプロジェクト停滞リスクを契約上予防します。
4. スコープ記述・変更手順
- 例:「本契約の対象範囲を明確にし、契約書別紙に詳細な業務範囲(含む・除外項目)を記載する。追加業務要求時には別途見積り・合意手続きを経るものとする。」
- ポイント:想定外業務の押し付け・無償対応を防ぎます。
5. 議事録・合意記録
- 例:「進行中の打合せ等は、議事録を作成し、相手方の確認・承認をもって合意とする。承認意思表示が所定期間内にない場合は、合意扱いとする場合がある。」
- ポイント:言った・言わない論争を避けるため、記録の承認ルールを具体的に決めましょう。
6. 追加費用・再見積りルール
- 例:「契約範囲外業務に関し、所定の単価表(変更単価・T&M単価)を適用する。追加業務が一定額・工数を超える場合、再度見積りを実施し、書面合意のうえ対応する。」
- ポイント:追加費用発生時の取扱いルールを明確にして、後の揉め事を回避します。
次の章に記載するタイトル:ベンダー・ユーザー双方の実務チェックリスト
9. ベンダー・ユーザー双方の実務チェックリスト

プロジェクト契約の円滑な運用や紛争予防のためには、契約書だけでなく、日々の実務の中で確認・実行しておくべき事項があります。ここでは、ベンダー(受託者)・ユーザー(発注者)各々の立場で、プロジェクトマネジメント義務を適切に果たすための実務チェックリストをまとめます。
ベンダー(受託者)側のチェックリスト
- 契約で定めたプロジェクトマネジメント義務の各項目(計画、監視、統制)が担当者間で共有されているか
- スコープ・変更管理のルールが現場にも正確に伝達されているか
- 変更要求があった際、影響分析を速やかに行い、記録を残しているか
- 定例会や会議の議事録作成・送付を期限内に実施しているか
- 進捗報告(進捗・課題・リスク)を定期的かつ明確に行っているか
- 遅延や問題が発生した場合、その要因や関係者の対応を記録しているか
- ユーザーに要請した協力内容・期限・返答状況を整理して証拠化しているか
ユーザー(発注者)側のチェックリスト
- 要件定義、レビュー、テスト等自社の責任範囲を事前に明確化しているか
- ベンダーからの協力要請や情報提供依頼に、期限までに対応しているか
- 会議体の設定やレビュー結果などを公式な記録として残しているか
- ベンダーへの承認・差戻しの意思表示を、合意の運用ルールどおり行っているか
- プロジェクトの遅延や課題が生じた場合、自社として対応・協力姿勢をどのように示したか記録しているか
- 責任分界に曖昧な点が生じた場合、速やかにベンダーと協議・確認しているか
このような日常的なチェックをチーム内で習慣化しておくことで、契約違反や紛争のリスクを大幅に減らすことができます。
次の章に記載するタイトル:まとめのポイント(実務指針)
10. まとめのポイント(実務指針)

本章では、プロジェクトマネジメント義務について、実務上大切なポイントを分かりやすくまとめます。
プロジェクト成功のカギは「協働」にあり
ベンダー側がプロジェクト管理を徹底しても、ユーザー側の協力がなければプロジェクトは円滑に進みません。双方が「自分事」として責任を持ち、確認や意思決定、情報提供を機敏に行うことが重要です。
契約・記録をしっかり残す
プロジェクトの節目ごとに、議事録や変更管理表などの記録を必ず残しましょう。万が一問題が生じた場合、「言った・言わない」ではなく、記録が揃っていることでトラブル防止や解決に役立ちます。
チェックリストで役割分担を明確に
前章で紹介したチェックリストのように、やるべき作業と期限を明確にし、担当者をはっきりさせることで混乱を避けられます。情報共有のルールも早めに決めておくと安心です。
予防重視・早めの相談を忘れずに
トラブルが起きる前に「どうすれば避けられるか」を常に考え、困った時はすぐに上司や専門家へ相談しましょう。初動が早いほど大事にはなりにくいです。
次の章に記載するタイトル:補足(用語の位置づけの違い)
補足(用語の位置づけの違い)

プロジェクトマネジメントに関する用語は、実務や立場によって解釈が異なる場合があります。特に「プロジェクトマネジメント義務」という言葉は、状況や文脈によって強調される意味合いが変わります。
ベンダー側とユーザー側での捉え方の違い
- ベンダー側:納期管理やリスク対応など、実際の作業進行・品質確保といった「実務的な管理」が強調されやすい。
- ユーザー側:進捗確認や変更内容の伝達など、「情報共有や意思決定支援」としての側面が重要視される。
PM職務記述と法的義務の違い
- PM職務記述:人事評価や採用基準で用いられるもので、「進捗管理を行う」「リスクを特定する」といった具体的な仕事内容やスキルを示す。
- 法的なPM義務:契約や法律に基づき最低限求められる責任や行動基準を指し、紛争時の判断基準となる。例:合理的な管理を行い、遅延を防ぐ努力義務。
実務における相互参照
現場では、職務記述に基づいた行動(例:進捗報告の書面化、課題の適切なエスカレーション)が、そのまま法的義務を果たす手段ともなることがあります。
そのため、両者は混同しないことが大切ですが、実務ではしばしば重なり合って解釈されます。
トラブル防止のために
PM関連用語には解釈の幅があるため、関係者間で意味を共有することが不可欠です。
- 契約書や会議で「この用語は今回こういう意味で使う」と明示する
- 責任範囲を事前にすり合わせる
こうした確認を積み重ねることで、誤解や紛争のリスクを大きく減らせます。
参考にした主な根拠

この章では、これまで解説してきたプロジェクトマネジメント(PM)義務に関する法的位置づけや実務運用、契約書への具体化、協力義務との関係性などの根拠となった主な資料や文献をまとめます。専門用語は避け、どなたでも理解しやすいようにご紹介します。
主な参考資料・文献
『IT取引の法律実務Q&A』(商事法務)
ITシステム開発をめぐる契約、トラブル、協力義務などの分かりやすい解説が豊富です。『システム開発紛争の法律実務』(中央経済社)
多数の裁判例やシステムトラブルの実例が収録され、トラブルの原因や回避策について説明しています。『情報システム取引契約書作成の手引』(経済産業省監修)
標準契約書例や、ベンダー・ユーザー双方に必要なPM義務や協力義務について具体的な指針を示しています。主要な裁判例
PM義務やユーザーの協力義務に関しては、「東京地裁平成14年6月27日判決」「東京地裁平成28年12月19日判決」などが参考になります。IPA(情報処理推進機構)発行資料
システム開発プロジェクトにおけるリスクや、訴訟事例、変更管理の重要性などをまとめたガイドラインがあります。
参考資料の選び方について
本記事で取り上げた資料や文献は、主に以下の3点に重きを置いて選びました。
- 契約や実務を担当する現場の方にも実践しやすい具体例を多く挙げていること
- できるだけ最新の実務・判例をカバーしていること
- 専門家だけでなく一般の方にも理解しやすい説明がされていること
まとめとしては、これらの資料を活用しながら、自社やプロジェクトの実情に合わせて必要なルールや証拠を整備し、リスクを予防することが重要です。