この記事でわかること
- プロジェクトマネジメントの基本構造と5つのプロセス
- 各フェーズ(立ち上げ〜終結)の流れと実務ポイント
- PMBOK第6版の知識エリアと現場での活用法
- 実務で役立つツール・手法とPMの役割
- よくある失敗・注意点・チェックリストによる改善方法
目次
プロジェクトマネジメントプロセスとは何か

プロジェクトマネジメントの基本的な考え方
プロジェクトマネジメントとは、限られた「時間」「予算」「人員」などのリソースの中で、決められた目標を達成するための一連の活動です。例えば、新しい製品を開発する、イベントを開催するなど、ゴールが明確で期限がある活動がプロジェクトにあたります。
なぜプロジェクトマネジメントが必要なのか
プロジェクトは日常業務と違い、「いつも通り」が通用しません。想定外のトラブルや仕様変更も発生しやすいため、計画を立てて進み具合を確認し、必要なら修正することが重要です。もし計画せずにただ進めてしまうと、納期遅れや予算オーバー、品質の低下などリスクが高まります。
5つの基本フェーズ
プロジェクトマネジメントの流れは、大きく分けて5つのフェーズに整理されています。具体的には「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」の順番で進みます。
- 立ち上げ:何をやるかを決め、プロジェクトの開始を正式に認めます
- 計画:どうやって進めるかの計画を立てます
- 実行:計画どおりに作業を進めます
- 監視・コントロール:進行状況をチェックし、計画とのズレがあれば調整します
- 終結:プロジェクトを正式に終わらせ、学びを残します
この5つの流れは、国際的なガイドラインであるPMBOK(Project Management Body of Knowledge)第6版でも標準的な方法として紹介されています。
QCD目標とは何か
プロジェクトの進行では「QCD(品質・コスト・納期)」がよく話題に上がります。
- 品質(Quality):期待された水準を満たしているか
- コスト(Cost):予算内で収まっているか
- 納期(Delivery):期日までに完成できるか
これらをバランスよく達成することが、プロジェクトマネジメントの大きな目的です。
次の章では、プロジェクトマネジメントの5つのフェーズがどのようにつながっているのか、その全体像を解説します。
5フェーズの全体像(PMBOK第6版の枠組み)

プロジェクトを進めるためには、大まかに5つの主要な流れがあります。これは世界的な標準ガイドであるPMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)第6版でも整理されているものです。5つのフェーズとは、「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール(進行管理)」「終結(完了)」です。
5つのフェーズとは
- 立ち上げ:プロジェクトを正式に開始する段階です。目的や範囲、関係者を明確にし、プロジェクトそのものの承認を得ます。
- 計画:実際に作業を進める前に、目標やスケジュール、コストの計画を細かく立てる段階です。やるべきことや達成したいことを数値や計画書に落とし込みます。
- 実行:計画に沿って、チームが作業を進めていくフェーズです。実際に手を動かしてアウトプットを作っていきます。
- 監視・コントロール(進行管理):計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じて修正するフェーズです。予定からズレが出た場合は適切に調整します。
- 終結(完了):プロジェクトが終わった後、成果を正式に受け取り、学んだことをまとめる段階です。
フェーズ間の柔軟な往来
プロジェクトは上記の順番通りに進みますが、実際には一度進めば終わりではありません。例えば実行中に問題が出た場合、もう一度計画フェーズに戻って内容を見直すこともあります。このように、各フェーズは何度も行き来しながら進むことが普通です。
特に計画や実行の段階では、現場の状況により計画を修正しなければならない場面も多くあります。柔軟な対応がスムーズなプロジェクト完了のカギです。
次の章では、「立ち上げ:目的・範囲・関係者を定義し、公式承認を得る」について詳しくご紹介します。
立ち上げ:目的・範囲・関係者を定義し、公式承認を得る

プロジェクト立ち上げの役割
プロジェクトを始める時、まずやらなければならないのが「立ち上げ」です。この段階で、プロジェクトの大まかな目的や目標を決め、どんな成果物を作るのか、どこまでをプロジェクトで対応するのか(範囲)、どんな制約や条件があるのかを明らかにします。
何を決めるのか
具体的には、以下の点をしっかり整理します。
- 目的(ミッション):なぜこのプロジェクトを実施するのか。例えば「新しい製品を半年以内に開発する」「顧客満足度を向上させる」といった内容です。
- 範囲(スコープ):何をやるのか、どこまでやるのか。例えば「A機能の開発まで含むが、B機能は対象外」と明示します。
- 成果物:プロジェクトの最終的な形やアウトプットです。例としては「新しいウェブサイト公開」や「分析レポート提出」などです。
- 制約:予算や期間、使える人員などです。「3か月以内」「予算100万円」「3人チームで対応」など、現実的な制約条件を設定します。
プロジェクト憲章とは
これらの内容をひとまとめにして文書化するのが「プロジェクト憲章」です。プロジェクト憲章は、プロジェクトを公式に認めるための書類であり、これをもとに行動します。
ステークホルダーの特定と賛同
もうひとつ重要なのは「誰が関係者か」を明らかにすることです。ステークホルダー(関係者)には、依頼者や上司、チームメンバー以外にも、プロジェクトの結果に影響を受ける人すべてが含まれます。立ち上げ時点でしっかり全員の賛同を得ることで、後々のトラブルを防ぎます。
ODSCの整理
実際の現場では「ODSC(目的・成果物・スコープ・制約)」を表にまとめたり、チームで確認し合ったりします。こうした整理が、プロジェクトの全体像を見失わないコツとなります。
次は「計画:QCD目標を数値化し、実施計画と管理計画を作る」について解説します。
計画:QCD目標を数値化し、実施計画と管理計画を作る

QCD目標の明確化と数値化
プロジェクトを成功させるには、目標を具体的な数字(定量)で設定することが重要です。ここでいう「QCD」とは、Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の3つを指します。例えば「品質」は不具合率を何パーセント以下にする、「コスト」は○万円以内で収める、「納期」は◯月◯日までに完了するといった具合に、誰が見ても分かる数値で表します。
作業の分解とWBS作成
計画段階では、まず最初に全体の作業を細かく分けて洗い出します。これは「WBS(作業分解構成図)」と呼ばれ、プロジェクトの全体像をモレなくダブりなくリスト化します。例えば、Webサイト制作なら「企画」「デザイン」「コーディング」「テスト」などです。それぞれの作業をさらに細かく分けて、誰が何を担当するかを明らかにします。
スケジュールとリソースの計画
つぎに、それぞれの作業にいつ・誰が・どれだけ取り組むかを決めます。スケジュール表を作って、作業ごとの期限や順序を可視化しましょう。また、必要な人材や設備、予算といった「リソース」も明確にします。休暇や繁忙期を考慮し、実現可能な計画を立てることがポイントです。
リスクとコスト・品質の管理計画
実際に計画どおり進まないことも多いため、「何が起きそうか」を予想し、事前に対策を考えることも大切です。これを「リスク管理計画」と言います。たとえば「天候不良で作業が遅れるかもしれない」など、危険なポイントを書き出して、優先順位をつけておきます。また、コストや品質の管理も計画の段階でしっかり決めておくと、後々トラブルを減らせます。
主要な必要文書
これら計画の成果物として「プロジェクト計画書」「WBS」「スケジュール表」「リスク管理計画書」などを作成します。これらの文書が、今後のプロジェクト成功の指針になります。
次の章に記載するタイトル:実行:計画に基づく遂行とチームマネジメント
実行:計画に基づく遂行とチームマネジメント

実行フェーズの概要
実行フェーズでは、前の計画フェーズで決定した方針や内容に従い、実際に作業を進めて成果物を作り出します。プロジェクトの“現場”として、計画を実践に移す要の段階です。
進捗の推進とコミュニケーション
この段階で重要なのは、メンバーとしっかりコミュニケーションを取りながら、作業の進み具合を確認しあうことです。例えば、毎朝の短いミーティングや、週ごとの進捗共有会など、誰がどこまで進んでいるか、困っていることはないかを把握します。この積み重ねが、問題の早期発見やスムーズな協力につながります。
リーダーシップとリソース配分
プロジェクトマネージャーは、チームのやる気や集中力を保つ工夫も求められます。明るい雰囲気づくりや、適度な休憩・フォローアップが効果的です。同時に、各メンバーの得意分野や負荷を見ながら、仕事の割り当てや調整を行います。人手や予算、時間といったリソースを最適に活用し、無理・無駄を防ぐことがプロジェクト成功のカギです。
想定外の事象と変更管理
いくら綿密に計画しても、実行時には予期しない出来事が起こることがあります。たとえば、納期ぎりぎりで仕様変更が発生したり、必要な資材が手配できなかったりする場合です。こうした時は、まず影響範囲を調査し、必要に応じて計画の見直しや関係者への説明を行います。大きな変更が必要な場合は、変更管理のプロセスを活用し、プロジェクトの基準(ベースライン)を再設定します。
個々のメンバーへの気配り
進捗の確認や調整だけでなく、一人ひとりのコンディションやモチベーションにも目を配ります。悩みや不安を抱えていそうなメンバーとは個別に話し、早めの支援を心がけます。これによってチーム全体のパフォーマンスが安定します。
次の章に記載するタイトル:監視・コントロール(進行管理):差異の検知と是正
監視・コントロール(進行管理):差異の検知と是正

プロジェクトが実際に動き始めると、計画通りに進めることが理想ですが、現実には大小さまざまな問題やズレが発生します。この章では、そのズレ=「差異」をどう見つけて、どのように対応していくかを解説します。
進捗の見える化と確認
まず大切なのが、進捗状況を定期的に把握することです。たとえば、毎週の進捗会議や、進捗表(ガントチャートなど)を使って「どこまで作業が完了したか」を明確にします。予定より遅れている部分や、早く終わったタスクがあればここで発見できます。
品質・コスト・スケジュールのチェック
進行管理では、「品質」「コスト」「スケジュール」の3つの観点で差異をチェックする必要があります。
- 品質:作ったものや成果物が基準を満たしているか確認します(例:試作品を実際に使ってみる、チェックリストで確認するなど)。
- コスト:予算の中でプロジェクトが進んでいるか、支出状況を定期的に確認します。
- スケジュール:当初の計画通りに作業が進んでいるか、遅れがあれば理由を調べます。
差異の是正(ズレへの対応)
差異が見つかった場合、早めに対応することが重要です。たとえば、スケジュールの遅れが見つかれば、追加の人員を手配したり、作業手順の見直しを検討します。コスト超過の場合は無駄遣いがないかを精査し、必要なら優先順位をつけて経費を抑えます。品質に問題があれば、担当者にフィードバックを伝えたり、再作業を行ったりします。
リスク対応と変更管理
プロジェクトが進行する中で、新たなリスク(トラブルの可能性)が見つかることもあります。その場合は、どのくらい影響が出るかを判断し、事前に対策を講じます。また、計画そのものを変更しなければならない場合もあります。これが「変更管理」です。変更の際は、関係する関係者とよく話し合い、正式な手続きを取って進めることが大切です。
次の章では、「終結(完了):正式終了と学びの蓄積」について解説します。
終結(完了):正式終了と学びの蓄積

プロジェクトの終結フェーズでは、これまでの作業や成果物が計画通りに完了しているかを確認し、関係者と共に正式なプロジェクト終了の手続きを進めます。この段階は、ただ作業が終わったというだけではありません。活動全体を振り返り、得られた知見を次回に活かすための重要なプロセスです。
完了の確認と承認
まずは、プロジェクトで約束した内容(成果物)がすべて計画や契約通りに仕上がっているかを丁寧にチェックします。たとえば、新しいシステムの導入なら、テストを終えたソフトウェアや運用マニュアル、ユーザートレーニングが全て揃っているかを確認します。不足や不具合があれば修正対応を終え、納品先の承認(公式検収)を得て、完了となります。
成果物・情報の整理と保管
プロジェクトで作成した資料や成果物は、後から見直すことができるよう、指定のフォルダやストレージに保存します。ドキュメントをきちんと整理して保管しておくことで、今後似た内容のプロジェクトが発生した場合にも参考にでき、再利用がしやすくなります。
振り返り(レトロスペクティブ)と学びの蓄積
最後に、チーム全体で振り返りの会議(レトロスペクティブ)を行います。プロジェクト中にうまくいったこと、課題と感じた点、改善できることをまとめ、今後に活かせるようにします。たとえば「段取りが良かったからスムーズだった」「途中の依頼変更への対応で苦労した」など、具体的な体験談を共有し、学びとして組織内で記録します。
これら終結のステップをきちんと踏むことで、一つひとつのプロジェクトが組織の成長につながります。
次の章に記載するタイトル:PMBOKの知識エリアとの関係(要点)
PMBOKの知識エリアとの関係(要点)

PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)第6版では、プロジェクトマネジメントの実践に必要な項目を「プロセス群」と「知識エリア」という2つの軸で整理しています。前章までで説明した5つのプロセス群(立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結)は、プロジェクトのライフサイクルを段階ごとに表しています。
一方で「知識エリア」とは、プロジェクト管理で管理すべきテーマごとの分野を指します。例えば、プロジェクトのやるべき範囲を明確にする"スコープ(範囲)管理"、スケジュールの計画や遅れの管理を担う"スケジュール管理"、費用のコントロールを行う"コスト管理"など、全10分野があります。これらは、日々の業務で「どの部分に気を付けて進めるべきか」という指針となります。
知識エリアの主な例:
- 範囲管理(スコープ)
- スケジュール管理
- コスト管理
- 品質管理
- リソース管理(人・モノ・時間)
- コミュニケーション管理
- リスク管理
- 調達管理
- ステークホルダー管理
- 統合管理
これらの知識エリアは、1つのプロセスにだけ関わるのではなく、プロジェクトの様々な場面で横断的に考慮します。例えば計画フェーズでは"スケジュール策定"や"リスクの洗い出し"を行い、監視・コントロールでは"進捗(スケジュール)"や"コスト"を評価し、必要に応じて軌道修正をします。
第7版では価値提供と原理志向へ大きく変わりましたが、第6版の5プロセス×10知識エリアの構造は今も現場でよく使われています。知識エリアを意識することで、やり忘れや偏りのない管理が可能になります。
次は「実務で用いる代表的ツール・手法(プロセスとのひもづけ)」について解説します。
実務で用いる代表的ツール・手法(プロセスとのひもづけ)

プロジェクトマネジメントの現場では、各フェーズでさまざまなツールや手法を活用します。ここでは、主要なものをプロセスごとに具体的に紹介します。
立ち上げ段階
この段階では「プロジェクト憲章」という文書を作成します。これはプロジェクトの目的や範囲、関係者(ステークホルダー)を整理し、上位者からの公式な承認を得るための要となるツールです。また「ステークホルダー分析」では、プロジェクトにかかわる関係者を洗い出し、影響度や関心度を評価します。たとえば、表形式で関係者とその役割、注意点をまとめることがよくあります。
計画段階
計画づくりでよく登場するのが「WBS(作業分解構成図)」です。プロジェクト全体を細かな作業単位に分け、進行を整理しやすくします。「ガントチャート」は作業ごとの期間や順番を見える化する表で、進捗管理の代表例です。「マイルストーン」は“ここまで終われば重要”という節目をカレンダーに設定します。また、「リスク登録簿」では起こりうる問題を一覧表で管理し、「コミュニケーション計画」では誰と何をどの方法で伝えるかを整理します。「QCD(品質・コスト・納期)目標のKPI化」は目的達成を数値で追うためのコツで、例として“月末までに80%完了”などの目標設定が挙げられます。
実行段階
計画に沿って動く段階では「進捗会議」を定期的に開催し、全員で現状を共有します。「課題管理」は出てきた問題をリスト化し、担当者や対応策を明確にします。「リソース調整」は、人や物の手配を効率よく行う作業です。さらに日々の「チームコミュニケーション」も大切で、雑談含めたこまめな情報共有が成功のカギです。
監視・コントロール段階
進捗が予定通りか、品質などの基準を満たしているかを確かめるため「EVM(出来高管理)」を使う場合があります。これは“進み具合”と“使ったコスト”を比べて、予定と差がないかを見ます。「品質レビュー」で成果物をチェックし、「変更要求と承認フロー」では計画変更があれば誰がどう承認するかを明確にして混乱を防ぎます。
終結段階
最終チェックでは「受入判定」「契約・調達クローズ」など、決められた基準に従いプロジェクトが完了したことを正式に確認します。最後に「成果と教訓のナレッジ化」で成功例や反省点をまとめ、次のプロジェクトに活かせる知識として残します。
次の章に記載するタイトル:役割と責任(PMの基本)
役割と責任(PMの基本)

プロジェクトマネージャー(PM)の主な役割は、プロジェクトの運営全体を責任もってまとめることです。PMは成果物の品質や納期を守るだけでなく、計画通りにプロジェクトが進むよう導くリーダーです。そのため、単に進行を見守る立場ではなく、現場で起きている課題やメンバーの動向に常に目を配り、適切な判断と調整を行う必要があります。
フェーズごとのPMの主な責任
- 立ち上げ段階:関係者(ステークホルダー)の意見を集約し、プロジェクトの目的や範囲を定義します。この段階での説明力や調整力が、後々の混乱を防ぐカギとなります。
- 計画段階:ゴール(成果物・納期・費用)を明確に示し、メンバーそれぞれが担当や課題を理解できるよう計画を作成します。具体的な行動計画や、トラブルが起きた場合の対策も準備します。
- 実行段階:計画に沿って進行状況を管理し、遅延や品質の問題などが発生した際は迅速に対応策を講じます。また、チームメンバーの相談を受けたり、進捗報告を関係者に伝えたりするなど、コミュニケーションが重要です。
- 監視・コントロール段階:計画と現実の状況の差異を見極め、必要に応じて修正方針を決めます。「なぜ遅れているか?」「どこが難しいか?」といった現場の声をくみ取ることもPMの大切な仕事です。
- 終結段階:納品や成果確認の手続きを行い、プロジェクトの経験をチームに共有します。特に、良かった点や改善点を次回に生かすためにも、ふりかえり(振り返り)の場を設けることが望ましいです。
チーム内外との橋渡し役
PMは、現場だけでなく社内外の関係者と情報をつなぐ「橋渡し役」も担います。顧客や上司、他部門との調整や報告をしながら、プロジェクトの状況や課題を伝え、協力を依頼することもしばしば発生します。専門用語が多い場面でも、分かりやすく説明する力も求められます。
責任の重さとやりがい
PMの責任はとても大きいですが、その分プロジェクトが成功した時や、難しい局面を乗り越えた時のやりがいも大きなものです。メンバーの成長やチームワークの強化にも深く関わり、全体を導くリーダーシップが問われる役割です。
次の章に記載するタイトル:よくある失敗と注意点
よくある失敗と注意点

1. 立ち上げ段階の落とし穴
プロジェクトの最初の段階で目的や範囲、関係者が曖昧なまま進めてしまうと、その後の工程で頻繁な変更や手戻りが発生します。例えば、始めに「何を達成するか」「誰がこのプロジェクトに関わるか」を十分に話し合わず進めてしまったケースでは、後から重要な関係者が抜けていたことに気づいた、想定外の作業が発生した、というトラブルがよく起こります。最初に時間をかけて全員で認識を揃えることが失敗防止の第一歩です。
2. 計画段階の落とし穴
計画作成時にQCD(品質・コスト・納期)の目標値が明確でない場合、後から「これで十分か」「予算オーバーかどうか」といった判断が曖昧になります。例えば、「できるだけ早く」「そこそこの品質で」など抽象的な表現で進めると、チーム内でも認識がブレやすく、優先順位や意思決定が不透明になりがちです。具体的な数値(○月○日までに、コスト上限は○万円、品質指標は○○など)を明確にしましょう。
3. 実行段階での注意点
計画に沿って動き始めてからも、チーム間のコミュニケーションが不足すると個々の課題や遅れが表面化しません。タスクの進捗や困りごとを定期的に共有する機会を作り、遠慮なく相談できる雰囲気づくりが大切です。例えば、週1回のミーティングや、チャットツールでの情報共有を活用すると、課題の早期発見につながります。
4. 監視・コントロールの盲点
「予定通り進んでいるはず」と思い込み、進行状況や予算をチェックしないまま進めてしまうと、気づいたときには問題が大きくなっていることも。進行状況(進捗)やコスト、品質について定期的に確認し、予定との差があればすぐ対策を立てましょう。たとえば、進捗表を使い、「遅れがどこに出ているか」を見える化することが有効です。
5. 終結段階の手抜かり
プロジェクトが終わったとき、「とにかく終わったから次へ」と振り返りをせずに進めてしまうと、同じ失敗を繰り返すリスクがあります。どんな失敗や工夫があったか、次回に活かすために記録として残しましょう。数分でも良いのでメンバーで話し合い、学びを整理する時間を取りましょう。
次の章に記載するタイトル:情報管理・検索の最適化(プロジェクト円滑化のコツ)
情報管理・検索の最適化(プロジェクト円滑化のコツ)

なぜ情報管理が大切なのか
プロジェクトが進行するにつれて、会議資料や進捗レポート、メール、設計書など、さまざまな情報が日々蓄積していきます。これらの情報がまとまっていないと、必要な情報を探すために無駄な時間を使い、業務効率が低下してしまいます。そのため、情報管理と検索しやすさの工夫が大切です。
タグ付け・分類の基本
効果的な情報管理の第一歩は、すべてのドキュメントやファイルにタグや分類名をつけることです。例えば「日報」「議事録」「設計」「決定事項」などのシンプルなタグを事前に決めておき、ドキュメント名や保存場所にも一貫して使用します。
具体例
- 議事録には「議事録」タグ、設計関連資料には「設計」タグを追加します。
- ファイル名は「日付_内容_タグ」のようにシンプルに統一します。(例:20240601_週次会議_議事録.pdf)
キーワードやカテゴリの事前定義
プロジェクト固有の用語やグループ(例:プロジェクトの略称、メンバー名、業務種別)をリスト化して事前に決めておきます。また、大事な資料ほど複数のタグを付けることで、さまざまな切り口で検索できるようにします。
検索精度と速度を高める工夫
情報を探しやすくするために
- フォルダを階層化し、関連資料をまとめて管理します
- 定期的に不要なファイルを整理し、最新の情報だけを残します
- 検索機能のあるツール(例:Googleドライブ、Teamsなど)を活用し、キーワードで素早く検索します
これらの取り組みにより、知識の蓄積や再利用もしやすくなります。
次の章に記載するタイトル:実践チェックリスト(各フェーズの主要アウトプット)
実践チェックリスト(各フェーズの主要アウトプット)

プロジェクトマネジメントを効率よく進めるためには、それぞれのフェーズで残すべき成果物や記録をしっかり押さえることが大切です。ここでは、各フェーズごとに「最低限これだけは用意・確認しておきたい」といった主要なアウトプット項目をチェックリスト形式で紹介します。
立ち上げフェーズ
- プロジェクト憲章
プロジェクトの概要や目的、最終的な目標を書類に残します。例えば「このプロジェクトは〇〇システムの導入を成功させるために発足した」といった記録です。 - ステークホルダー一覧・利害分析
影響を受ける・与える関係者を洗い出し、その立場や利害を整理します。 - 上位承認
プロジェクトの開始に対し、上層部や関連部署から経営的な承認を得た証拠を残しましょう。
計画フェーズ
- プロジェクト計画書
スコープ(範囲)、スケジュール、コスト、品質、リスク、コミュニケーション、調達、ステークホルダー管理など、それぞれの分野ごとに計画内容を統合した文書を作成します。 - WBS(作業分解構成図)
大きな仕事をより小さな作業に分割し、一覧にします。 - ガントチャート
作業スケジュールを一目で把握できるよう、横棒グラフで表します。 - KPI設定
目標達成度を測るための具体的な数値(例えば「〇月までに△件完了」のような基準値)を決めます。
実行フェーズ
- 成果物のインクリメント
実際に作ったものや、目に見える進み具合の記録(例えば、画面設計書の完成・アプリのテストバージョンの納品など)です。 - 課題台帳
発生した問題や未解決事項を記録、対応状況も明確にしておきます。 - 進捗報告
メンバーや関係者全員へ現状を定期的に伝える資料です。 - 変更要求
仕様や日程などの修正希望があった場合に正式な記録を残します。
監視・コントロールフェーズ
- EVMレポート(進め方が狙い通りかをお金や工数で記録)
- 品質監査記録
品質に問題がないかを評価した記録です。 - リスクレビュー
新たなリスクや対策状況の定期確認記録。 - 変更履歴
どのような変更があったのか、誰が承認したかの記録。
終結フェーズ
- 受入証跡
成果物が求める基準を満たしていると確認できる証拠資料。 - 契約クローズ
取引先やメンバーとの契約がすべて終了した証拠を残します。 - 振り返り報告(レッスン・ラーニド)
上手くいった点や反省点をまとめた記録です。 - アーカイブ
全資料を整理・保管して、必要な時に見返すことができるようにします。
次の章に記載するタイトル:補足(用語・最新動向の位置づけ)
補足(用語・最新動向の位置づけ)
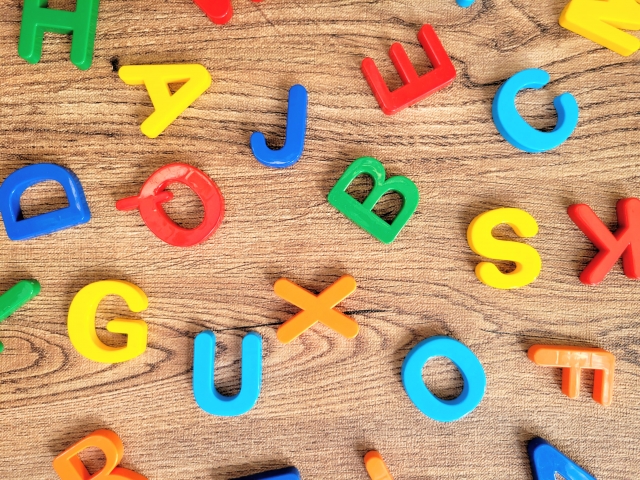
PMBOK第6版と第7版の違いについて
プロジェクトマネジメントのガイドラインであるPMBOK(ピンボック)には、第6版と第7版があります。第6版は「5つのフェーズ(立ち上げ・計画・実行・監視・終結)」に分かれており、流れに沿った進め方を重視しています。日本国内での多くの解説や実務は、この第6版の区分を前提にして進めることが多いため、まずはこの5つのフェーズで考えると全体像がつかみやすいです。
一方で、第7版では枠組みを「原理や価値観」に変えており、『成果』を重視した柔軟なプロジェクト進行を提案しています。具体的な手順やフェーズの枠を超えて、状況や目標に応じてプロセスをカスタマイズする考え方です。実務では、第6版で大まかな流れをつかみ、第7版の価値観も取り入れて柔軟に運用する方法が現実的です。
よく使う用語の補足
- QCD(Quality・Cost・Delivery):品質、コスト、納期。プロジェクトの目標設定によく使います。
- KPI(Key Performance Indicator):進捗や成果を数値で測る指標。
- ステークホルダー:プロジェクトに関わる全ての関係者。
- WBS(Work Breakdown Structure):作業を細かく分解した一覧表(タスクの見える化)。
これらの用語は簡単な英単語や日本語表現が付くことも多いので、チームに合わせて分かりやすく説明することが大切です。
具体的な実務での使い方
プロジェクトの現場では、「目的の明確化→タスク洗い出し→スケジュール決定→進捗管理と見直し」といった簡単なステップで進めても問題ありません。専門用語や複雑な手順にとらわれすぎず、わかりやすく・効率的に進めることが最も重要です。
このブログでご紹介したプロセスやチェックリストも参考に、皆さん自身のプロジェクトで役立てていただければ幸いです。