この記事でわかること
- プロジェクトネットワーク図の基本と目的
- ADMとPDMなど主要な種類と構成要素
- クリティカルパスの考え方と特定方法
- 作成手順と実務での活用ポイント
- ガントチャート・WBSとの違いと使い分け
目次
プロジェクトネットワーク図とは何か

プロジェクトネットワーク図は、プロジェクトの進行に必要な作業やタスク同士のつながりや順番を視覚的に整理した図です。たとえば、家を建てるプロジェクトを例に考えてみましょう。最初に土地を整え、その後土台を作り、屋根や壁を建てていくといった流れが必要になります。これら一連の工程を、どの作業の後に何をするべきかが分かるように、四角や丸のマーク(ノード)で表し、矢印(アロー)でつないで作ります。
この図の最大の目的は、作業の順番やそれぞれの依存関係――つまり「Aが終わらないとBが始められない」といった関係――を一目で分かるようにすることです。たくさんのタスクが絡み合う大きなプロジェクトでも、ネットワーク図を描くことで全体像を把握しやすくなります。
また、ネットワーク図を活用することで、どの作業が遅れると全体のスケジュールに影響が出てしまうのか、あるいは少し余裕を持って進められそうな作業はどれなのか、といった重要な情報も得られます。こうした特長から、プロジェクトの効率的な管理やトラブルの予防に役立つ道具として、多くの業界で活用されています。
次の章では、ネットワーク図の主な種類と構成要素について詳しく解説します。
ネットワーク図の主な種類と構成要素
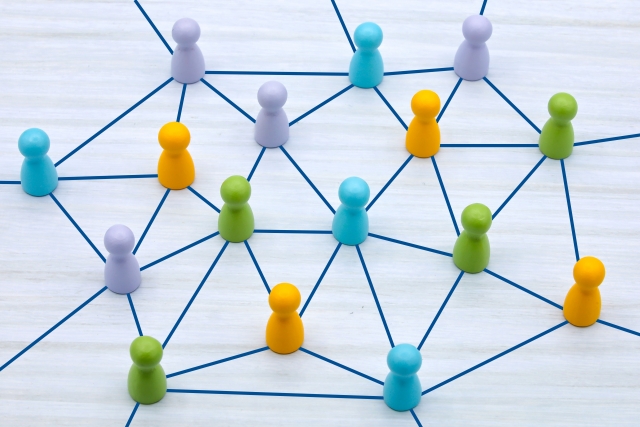
ネットワーク図にある2つの代表的な種類
ネットワーク図には、大きく分けて2つの種類があります。一つ目は「アローダイアグラム法(ADM)」です。これは、作業の流れを矢印で表現し、それぞれの矢印がタスクを示します。例えば、家を建てる工程で「基礎工事→壁を作る→屋根をつける」など、作業が順番に続くイメージが明確になります。ノード(丸や四角い点)は、そのタスクの開始や終了といったイベントを指します。
もう一つは「プレシデンスダイアグラム法(PDM)」です。こちらでは、タスクそのものをノード(四角や丸)として描きます。ノード同士を矢印でつなぎ、タスク間の関係性や順序を表現します。先ほどの家づくりの例なら、「基礎工事」「壁を作る」「屋根をつける」とそれぞれの作業がノードになり、どれが終われば次に進めるかを矢印で示します。PDMは、現場でよく使われる工程表にも近い見た目です。
構成要素
ネットワーク図を構成する基本的なパーツは以下の通りです。
- ノード(アクティビティ/タスク):具体的な作業やプロジェクトの各工程を示します。例えば「資材の搬入」や「組立作業」などです。
- アロー(矢印):タスク同士の依存関係や、進むべき順番を表します。「これが終わったら次はこれ」という流れが直感的にわかります。
- 開始ノード・終了ノード:プロジェクトの始まりと終わりをはっきり示します。「スタート地点」と「ゴール地点」がわかることで、全体像もつかみやすくなります。
次の章では、ネットワーク図を使うとどのようなメリットや効果が得られるのかを詳しくご説明します。
ネットワーク図のメリット・効果

タスク間の依存関係や優先順位が明確になる
ネットワーク図は各タスクがどの順番で進むべきか、またどの工程が他の工程に影響するのかを図式的に示します。例えば、家を建てるプロジェクトでは「基礎工事」と「屋根工事」は直接関係がなさそうですが、基礎が完成しないと壁を立てられず、壁ができないと屋根も作れません。このような前後関係を一目で把握できます。
プロジェクト全体の流れや構造を把握しやすい
ネットワーク図を使うことで、スタートからゴールに至るまでの道筋が可視化されます。作業の抜けや重複がないか、全体の流れに無理がないかも確認しやすくなります。たとえば、多人数が関わるイベントの準備では、役割分担や作業のつながりを整理するのにとても有効です。
クリティカルパスの特定が容易になる
複数の工程が関わる場合、全体の所要時間を短縮したり遅延を防いだりするためには、どのタスクが全体に影響するかを知ることが重要です。ネットワーク図を使うと、最長となる経路(クリティカルパスといいます)が明確になり、そこに注意を集中できます。
リソース配分やスケジュール調整が効率的に行える
ネットワーク図によって、どの工程が並行して進められるかも明らかになります。これにより、作業員や機材の配置を最適化したり、遅延した場合の調整も具体的に考えることができます。たとえば、作業内容を管理する担当者が、重複する工程に人員や道具が偏らないように割り振りを調整できます。
潜在的な問題やボトルネックを早期発見できる
タスク同士のつながりや進行順序が明確になることで、どこが遅れると全体に影響が出るのか、どこの負荷が高いかなども早めに発見できます。たとえば、短期間に多くの作業が集中する時期や、特定の人や設備に任せきりになる箇所などが見つかりやすくなります。
関係者間で進行状況や課題を共有しやすい
ネットワーク図を使えば、口頭や文章で説明するよりも分かりやすく関係者と情報を共有できます。これにより、プロジェクトチーム内の認識ずれを防ぎ、円滑な協力や意思決定につなげることができます。
次の章に記載するタイトル: クリティカルパスとネットワーク図
クリティカルパスとネットワーク図
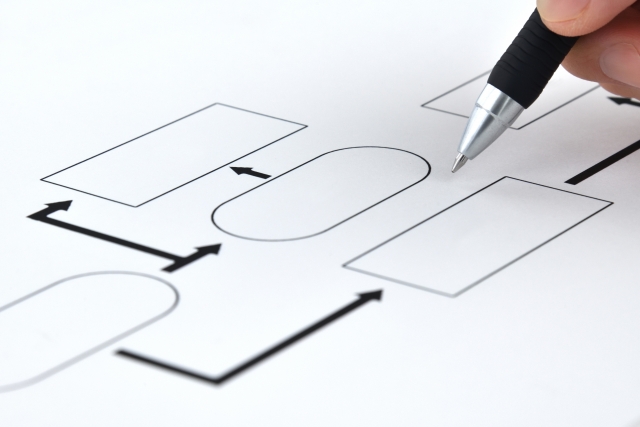
ネットワーク図の大きな特徴のひとつが「クリティカルパス」を明らかにできる点です。クリティカルパスとは、プロジェクト内のいくつもの作業の中で、最も長く時間がかかる作業の連なり(経路)を指します。この道のり上にあるタスクがひとつでも遅れると、プロジェクト全体の完了も遅れてしまいます。逆に、クリティカルパス以外のタスクには多少の「余裕期間(フロート)」が存在します。これは、そのタスクが多少遅れても全体の納期には影響しない時間のことです。ネットワーク図を使うことで、各タスクがクリティカルパスにあるのか、どの程度の余裕があるのかを図で視覚的に把握できます。
例えば、学校の文化祭の準備を例にとります。ステージ装飾、プログラム作成、出演者のリハーサルなどが複数の作業として存在します。それぞれの開始・終了の順序や所要時間を一覧表ですべて管理するのは大変ですが、ネットワーク図を使って図解すると、一目でどの作業が全体進行に直結するかが分かります。結果として、遅らせてはいけないタスクや優先順位付けも明確になります。
さらに、クリティカルパス上のタスクには特別な注意が必要です。管理者やリーダーは、ネットワーク図をもとに重要度の高い作業やトラブルが発生しやすい部分を早めに発見しやすくなります。こうした視覚的な管理は、スムーズな進行や計画修正にも大きく役立ちます。
次の章では、ネットワーク図の具体的な作成手順や現場で役立つ実践的なポイントをご紹介します。
作成手順と実践的ポイント

ネットワーク図を使いこなすには、作成の基本的な流れと現場で役立つポイントを押さえることが大切です。ここでは、具体的な手順を分かりやすく説明します。
1. タスクの洗い出し
まず、プロジェクト内の作業を一つひとつリストアップします。家の建設で例えると、"基礎工事"や"壁の組み立て"など、工程ごとに分解するイメージです。
2. タスクの前後関係を把握
洗い出したタスク同士のつながりを考えます。例えば、"壁の組み立て"は"基礎工事"が終わらないと始められません。各タスクを矢印などで結び、前後関係を図で表します。
3. 所要時間の見積もり
次に、それぞれのタスクがどれくらい時間がかかるかを大まかに決めます。例えば、"基礎工事は5日"、"壁の組み立ては3日"というように書き出します。
4. ネットワーク図の作成
これまでの情報をもとに、実際にネットワーク図を描きます。紙と鉛筆でも良いですし、表計算ソフトや専用ツールも利用できます。シンプルな四角や丸でタスクを書き、矢印で関係性を結びます。
5・6. フォワードパスとバックワードパス
フォワードパスでは、各タスクが最も早く始められる時期を順に計算します。逆にバックワードパスは、全部が遅れないためにはいつまでに終えないといけないかを後ろから計算します。このステップを丁寧に行うと、余裕や遅延リスクが見えてきます。
7. クリティカルパスの特定
前後の計算をもとに、全工程の中でも特に遅らせられない大事な作業の流れ(クリティカルパス)を探します。そこに注意を払うことで、スムーズな進行が実現できます。
8. 必要に応じたガントチャートへの展開
ネットワーク図が完成したら、横棒グラフ形式のガントチャートに展開することで、スケジュール全体を一目で把握できます。これはメンバー同士で進捗を共有する際にも便利です。
次の章に記載するタイトル:ネットワーク図と他の工程管理ツールとの違い
ネットワーク図と他の工程管理ツールとの違い

ガントチャートとの違い
ガントチャートは、縦軸にタスク名、横軸に日付を並べて、作業のスケジュールや進捗を視覚的に管理できるツールです。たとえば建設現場やイベント準備など、いつ・どの作業を始めるのか一目でわかります。しかし、ガントチャートでは各タスクの“つながり”や“依存関係”が分かりにくい場合が多いです。「Aの作業が終わったらBを始める」という順番など、一部のツールでは矢印で表示できる場合もありますが、多くはスケジュール重視になりがちです。
一方、ネットワーク図は全ての作業(タスク)がどのようにつながっているかを“流れ図”のように描きます。各作業が互いにどんな順番で関係しているか、特に「どの作業が終わらないと次に進めないのか」という依存関係がひと目でわかります。例えば、複雑なプロジェクトで「どこが遅れると全体に影響するのか」=クリティカルパスを見つけやすいのが特徴です。
WBS(作業分解構成図)との違い
WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクト全体を細かい作業単位まで分解して、一覧として整理する方法です。たとえば「イベント企画」を「会場手配」「機材準備」「スタッフ調整」などに分け、さらにそれぞれをさらに細かく切り分けていきます。
WBSは、作業全体の抜け漏れ防止や担当割り振りに便利ですが、「どの作業がどの作業に依存するか」「どれが先でどれが後か」といった流れや関係性は明確にしません。作業内容の整理に特化している点が、ネットワーク図との違いです。
ネットワーク図ならではの強み
このように、ガントチャートはスケジュール管理重視、WBSは作業内容の整理重視ですが、ネットワーク図は作業同士の“つながり”や“順序関係”をひと目で確認できる点が最大の特長です。特に「どこが遅れると全体に影響するか」「重要な工程がどこか」といった分析に強いので、プロジェクト管理の中でも要所で活用されます。
次の章では、ネットワーク図を活用する際の注意点やデメリットについてご紹介します。
活用の注意点とデメリット

プロジェクトネットワーク図は、プロジェクトの全体像やタスクの関係性を視覚的に整理するのに役立ちます。しかし、いくつか注意すべき点やデメリットも存在します。
複雑なプロジェクトでは作成や管理が大変
簡単なプロジェクトならば、ネットワーク図も短時間で作成できます。しかし、タスクが多く複雑なプロジェクトの場合、手書きや表計算ソフトを使ったネットワーク図は非常に煩雑になってしまいます。タスク同士の関係を線で結ぶ必要があるため、図がごちゃごちゃして分かりにくくなったり、作成に時間がかかることがあります。
進捗の「量」を把握しにくい
ネットワーク図はタスクの順序や関係を示す点には優れていますが、タスクの進捗度や全体の完了率を“量的”に見える化するのは得意ではありません。たとえば、棒グラフ的にタスクの進行状況を一目で確認したい場合は、ガントチャートの方が適しています。そのため、進捗管理まで網羅的に行いたい場面では、ネットワーク図だけでなく他のツールも併用すると便利です。
頻繁な更新が手間になる場合も
プロジェクトが進行すると、スケジュールや工程、タスクの内容が変わることがあります。ネットワーク図は変化に対応して随時修正が必要なので、変更が多い現場では手間が増します。特に、手動で管理している場合は、修正漏れが生じやすくなります。
このように、ネットワーク図には便利な一方で、利用時にはいくつかの注意点やデメリットがあります。活用方法や他ツールとの併用をよく考えながら、プロジェクトに適した方法を選びましょう。
次の章ではネットワーク図の活用シーンと実務上のポイントについて解説します。
ネットワーク図の活用シーンと実務上のポイント

ネットワーク図が活躍する現場とは
ネットワーク図は、特にタスク同士の関係や順序が複雑なプロジェクト現場で欠かせないツールです。たとえば、建設工事やシステム開発、イベント運営など多くの工程が連動して動く場面では、全体の流れを一目で把握することが重要だからです。プロジェクトに多くの担当者やチームが関わる場合も、それぞれの作業内容やスケジュールを整理しやすくなります。
活用の具体的ステップ
一般的には、まずプロジェクト全体を細かいタスクに分解します(これをWBSと呼びます)。その後、それぞれのタスクの順番や依存関係、必要な期間などを整理し、ネットワーク図として可視化します。図として表現することで、どの作業が同時進行できるか、どこが遅れると全体に影響するかなどを明確にできます。
実務での工夫と注意点
ネットワーク図を実際のプロジェクトで活用する際は、明確で分かりやすい表記にすることが大切です。記号や矢印の使い方を統一し、誰が見ても理解できるよう心がけましょう。また、プロジェクトが進むにつれて状況が変化することもあるため、ネットワーク図も定期的に見直し、最新の状態に更新することが成果につながります。
標準手法との関係
PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)など、世界的なプロジェクトマネジメント手法でもネットワーク図が推奨されています。これにより、国内外のさまざまな現場で共通言語として活用できる利点があります。標準的な手法と自社やプロジェクトの特性とを組み合わせて、柔軟に運用しましょう。