目次
はじめに
有名なプロジェクトマネージャーの山口周氏によると、プロジェクトを成功させるためには開始前の準備が非常に重要です。まず、プロジェクトが始まる前の段階で、その成否のおよそ半分が決まってしまうと述べています。これは、目的の設定やチーム構成、意思決定の仕組みなど、初期の土台作りが極めて大切だという意味です。
具体的には、「なぜこのプロジェクトをやるのか」という意味のある目的の定義、「どこまでやればよいのか」という期待値の調整、プロジェクト全体を統括する意思決定者を一人置くこと、誰に何を任せるかという人の配置、プロジェクトの流れや段取りの設計などが成功のカギとなります。
また、困難な要求やリスクへの備え、不安が生じた際の共有やSOSの出し方なども、開始前から意識しておくことが大切です。プロジェクトが途中で「炎上」するのを避けるためには、勝てるプロジェクトを見極める目と、適切な人材を選ぶことに全力を尽くす必要がある、と山口氏は説いています。
この記事でわかること
- プロジェクト開始前に成否が決まる理由と準備の重要性
- 意味のある目的設定と期待値コントロールの方法
- 成功を導く意思決定・人選・舞台設定のポイント
- 炎上を防ぐ「断る勇気」と「目利き力」の実践法
- これから求められる「ニュータイプのプロマネ」とは
開始前に成否の半分が決まる
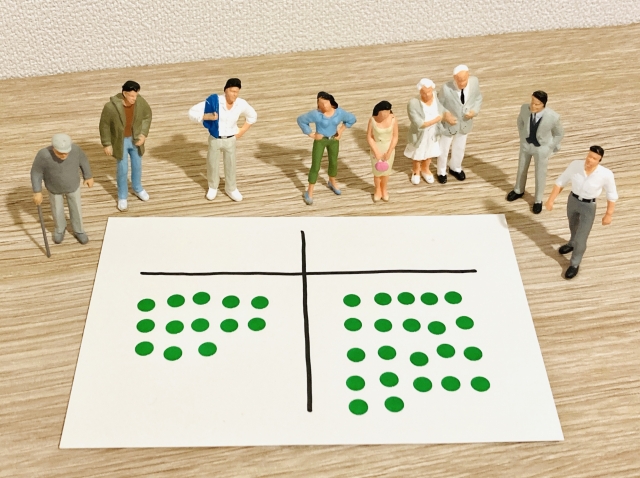
始める前の準備にどれだけ力を入れられるかで、プロジェクトの成果は大きく左右されます。多くの場合、プロジェクトが迷走したり失敗してしまう原因は、最初の段階で十分な状況把握や計画がなされていない点にあります。たとえば、家を建てる時に土地の調査や設計が甘いと、後から大きな問題が発覚することと同じです。
この章で伝えたいのは、「始める前に勝負は半分決まっている」という事実です。最初にしっかりとした準備や設計ができていれば、途中で生じるトラブルも最小限に抑えられます。一方、勢いだけで始めてしまうと、問題発生後の手戻りや余計なコストの発生につながり、プロジェクト全体が苦戦を強いられることになります。
プロジェクトを成功させるには、「どの案件に取り組むか」を見極める目が必要です。これは、プロジェクトの目利きとも言えます。何でも引き受けるのではなく、手を付ける前に内容・難易度・関わるメンバーやリソースを冷静に判断し、「勝てるプロジェクト」を見極めることが重要です。この見極めができれば、その後の進行も格段にスムーズになります。
次の章では、プロジェクトに取り組む上で欠かせない「意味のある目的の定義」について深く掘り下げていきます。
意味のある目的の定義

「意味のある目的」とは何か
「意味のある目的」とは、ただのお題目やスローガン以上のものです。プロジェクトに関わる全てのメンバーが納得し、日々の行動や意思決定の基準になる、具体的な指針として言語化された目的を指します。たとえば「売上アップ」や「業務改善」だけでは、その具体的な道筋や優先順位が分かりません。一方、「既存顧客の契約更新率を2割向上する」という目的なら、誰がどんな動きをすればよいかが明確になります。
なぜ明確な目的が重要なのか
プロジェクトに関わる人は立場や役割が異なります。そのため、各自が自分だけの解釈で動いてしまうと、作業の方向性がバラバラになりやすくなります。「意味のある目的」は全員の認識を合わせ、無駄な摩擦や後戻り作業を減らす役割を果たします。たとえば、途中で仕様の追加依頼が来た場合も、「この追加は“契約更新率アップ”に本当に寄与するか」という基準で判断できるため、賢く取捨選択できます。
どうやって「意味のある目的」を作るか
まず、目的を短い言葉で表した後、「この目的はなぜ必要か」「その成果は誰にどう役立つか」といった質問を繰り返してください。関係者と議論し、「それって具体的には何を目指すの?」というやり取りを経ることで、解像度が高くなります。もしメンバーから質問や異論が出てきたら、それはむしろ意味のある目的へと近づく好材料です。
一例:曖昧な目的と明確な目的
- 曖昧な例:「お客様満足度の向上」
- 明確な例:「問い合わせから24時間以内に80%以上の問い合わせに回答し、お客様アンケートで満足度4.5以上を目指す」
このように具体的に目的を設定すると、誰もが共通のゴールを見据え、効果的な打ち手が打てるようになります。
次の章に記載するタイトル:「期待値を「低め」に設計して成功を引き寄せる」
期待値を「低め」に設計して成功を引き寄せる

期待値をコントロールする重要性
プロジェクトの成功を左右する大きな要素のひとつが「期待値」です。期待値とは、プロジェクトに対して関係者が持つ“こうなるはず”“これぐらいやってもらえるだろう”という予想値のことです。多くの場合、これが高すぎることで現場には過度なプレッシャーがかかったり、不満やトラブルの火種になったりします。
過大な約束がもたらすリスク
よくあるのが、“最初から全部できます!”“短期間ですべて終わらせます!”と大きな約束をしてしまうことです。一見前向きに見えますが、期待が膨らみすぎると、実際の成果がどんなに良くても「思ったほどじゃなかった」という印象を与えやすいのです。結果として、努力以上に評価が下がってしまい、メンバーの士気低下や信頼失墜にもつながります。
期待値を「低めに設計」するとは
ここで有効なのが、最初から“できる範囲”と“最低ライン”を明確に伝えておくことです。つまり、「今回はこれだけやります」「初回リリースではここまで」など、実現可能な範囲で小さく始めるイメージです。こうすることで、ハードルを上げすぎず、目標達成時にむしろ「思ったよりすごい!」「ちゃんと間に合った!」と前向きな評価が得やすくなります。
初回リリースを抑えて「早い勝ち」を積む戦術
たとえば新しいアプリを作る時、「多機能な完成形を最初から目指す」のではなく、「まずは最小限動くものを早く出す」ことを第一目標にします。これにより、開発メンバーの負担も減り、関係者からの信頼も積み重なっていきます。また、早期に改善すべきポイントも見つかるので、軌道修正がしやすく成功確率が上がります。
次の章では、「最終意思決定者は1人に」することの重要性についてお話します。
最終意思決定者は1人に

プロジェクトがスムーズに進行するかどうかは、意思決定の速さと確実性による部分がとても大きいです。複数人で最終的な判断を下す体制にすると、一見民主的に見えます。しかし実際には、意見の食い違いや調整作業が増え、判断そのものが遅れがちになる傾向が強まります。
なぜ「最終意思決定者の一人化」が必要か
たとえば、飲食店で何を注文するか3人組で悩むと「やっぱりこっち」「いや、私はこれ」と話が長引く経験は誰でもあるはずです。ビジネスの現場でも同様で、全員の納得や合意を待つほど、進行は遅くなります。意思決定が伸びれば、その分プロジェクトの進捗や成功率に悪影響を及ぼします。
決裁ルートの明確化の効果
責任と権限がきちんと整理されていれば、現場の混乱も減ります。誰が最終的にゴーサインを出せるかが明確になれば、調整や確認の回数が激減し、スピードが上がります。決裁ルートが明瞭になれば、途中で迷いも少なくなり、質の高い仕事につながりやすくなります。
実践の例
例えば「まとめ役はAさん」と最初に全員で合意しておけば、「これはAさん判断でOK」「Aさんに聞けば決まる」と周りも納得しやすい空気になります。大企業でも、この原則が守られているチームは成果が出やすく、逆に曖昧なチームは遅れやすいものです。
複数の意見は「参考情報」に
もちろん、他のメンバーからの意見・提案を聞くことは非常に重要です。しかし、最後の決断と責任の所在は一本化しましょう。この仕組みづくりが、結果的には全体の満足度や信頼感にもつながります。
次の章に記載するタイトル:プロジェクトをうまく回す「舞台設定」
プロジェクトをうまく回す「舞台設定」

プロジェクトが順調に進むかどうかは、事前の「舞台設定」に大きく左右されます。「舞台設定」とは、プロジェクトが動き出す前に、関係者や仕組み、情報の流れなどをあらかじめ整えることを意味します。この準備が不十分だと、途中で混乱が生じたり、認識のずれや手戻りが発生しやすくなります。ここでは、プロジェクトを円滑に進めるための具体的な舞台設定のポイントについて解説します。
1. チーム編成と人の配置
成功するプロジェクトには、適切な人選が必要不可欠です。たとえば、新しいシステムを導入する際、専門知識を持つメンバーが足りないと、意思疎通が難しくなったり、決めごとが後回しになったりします。ですから、まず最優先で「この人となら安心して進められる」という信頼できる人材を確保しましょう。これが、舞台設定の最も大きなレバー(てこ)となります。
2. 会議体の設計と明確な役割分担
会議や打ち合わせの頻度・メンバー・目的を明確に決めておくと、情報が正しく伝わります。たとえば、進捗会議は週1回、意思決定会議は必要なときだけリーダーが招集する、というようにルールを明示します。また、各自の役割と責任範囲を事前に定め、誰が何を決めるのかをはっきりさせましょう。これにより、責任のなすりつけ合いや迷いが減ります。
3. 情報の流れと権限委譲の仕組み
誰がどの情報にアクセスするか、どこまでの判断を誰に任せるか――この仕組みを事前に整理することも重要です。たとえば、作業手順書や進捗資料を共有フォルダにまとめておくだけで、無駄な確認や伝言ミスが大幅に減ります。また、全ての判断をマネージャーが行うのではなく、小さな案件は現場責任者に任せるなど、権限移譲も「舞台設定」の一部です。
このように、プロジェクトをうまく回すためには、単なる進め方ではなく、「最初の段階でどれだけ理想の舞台を整えられるか」がカギとなります。
次の章では、プロジェクト開始初期の「開幕ダッシュ」について解説します。
初期フェーズの「開幕ダッシュ」

プロジェクトが始まったばかりの頃は、まだ全員が手探り状態です。この時期こそ、スピード感を持った行動が成果につながりやすいタイミングとなります。立ち上げの初期段階で素早くアウトプットを出すことで、チームのモチベーションを高め、プロジェクトを推進する原動力を作りましょう。
早期のプロトタイピングと可視化
初期フェーズでは、まだ最終的な完成形が見えていないことも多いです。ここで役立つのが、簡単な試作品(プロトタイプ)やイメージ図です。たとえば、手書きのスケッチや簡単な資料を作って形にしてみると、関係者はイメージしやすくなります。これにより、メンバー間のイメージのズレを早く発見でき、同じ目標に向かって一丸となりやすくなります。
認識の違いや対立を早期にあぶり出す
プロジェクトの序盤では、各メンバーの考え方や期待する成果に違いが生じやすいものです。この段階で遠慮せず意見をぶつけ合うことで、表面化していなかった認識のズレや対立が明らかになります。たとえば、会議の場で「それぞれが思う成功のイメージ」を全員が発表するだけでも、大きなヒントが得られることがあります。初期の衝突は後々の軌道修正につながるので、恐れず話し合いましょう。
トラブルを未然に防ぐために
初期のダッシュによって小さな対立や違和感を素早く拾い上げておくことで、後半に起きがちな“プロジェクトの大火事”を防げます。方向性ややり方にちょっとした違和感がある場合でも、この時点で率直に伝え合うことが長い目で見ると大きな安心材料となります。
次の章に記載するタイトル:無理難題は「いったん断る」が鉄則
無理難題は「いったん断る」が鉄則

なぜ無理難題を断るべきか
プロジェクトを進めていると、時に「それは無理だ」と思うような要求を受けることがあります。例えば「1週間で大きなシステムを完成させてほしい」とか、「予算は半分に減らして中身はそのまま実現してほしい」といったケースです。このような時、目の前の相手に良い顔をしたくて、つい「何とかします」と答えたくなりますが、これは最も危険な対応です。
一度受けてしまうと起こる問題
一度、無理な要求を受け入れてしまうと、その後に発生するトラブルの責任をプロジェクトリーダーやメンバーが背負うことになります。プロジェクトが途中で頓挫したり、品質が大きく下がってしまえば、信頼関係を損ねるのは避けられません。長期的に見れば、「その場しのぎの受諾」が一番のリスクになります。
「断る」ことは信頼を守ること
無理なお願いを一度断ることで、自分やチームだけでなく、クライアントや関係者全体の利益を守れます。例えば「現状のリソースでは実現できません」「代替案を検討したいです」と伝えると、「このプロジェクトが失敗に終わるリスク」を減らせます。そして相手から本当に必要な条件や優先順位を引き出し、案外、落としどころが見つかることも少なくありません。
具体的な断り方の工夫
ただし、きっぱり「無理です」と言い切るだけでは角が立ちます。感情的にならず「現時点では難しいですが、こうすれば近づけます」といった代替案や、条件調整の提案を添えることで、信頼関係を築く第一歩になります。たとえば納期短縮の依頼には「この機能を削減できれば可能です」と返す方法です。
まとめ
無理難題は「いったん断る」と決めることで、プロジェクトのリスクを大きく減らすことができます。受け入れる前に冷静に立ち止まり、条件を整理し直す姿勢が、長期的な信頼につながります。
次の章に記載するタイトル:不安の共有とSOSの発信
不安の共有とSOSの発信

プロジェクトを進めていく中で、リーダーやメンバーが「何かおかしい」「うまくいっていないかも」と不安を感じる場面は少なくありません。しかし、その不安を自分一人で抱え込むことは、リスクが高まる原因となります。チーム全体の力を最大限に活かすためには、不安や違和感をできるだけ早く共有し、適切なSOSを出すことが大切です。
不安を見える化する効果
不安や課題を声に出して共有することで、「自分だけが心配しているのではない」と気づくことができます。たとえば、納期遅れが心配な場合、早期にみんなで話し合えば、作業分担の見直しや増員の検討など具体的な対策が可能です。
また、不安を隠し続けた結果、問題が表面化した時にはすでに手遅れになっているケースも少なくありません。逆に、小さなうちに相談することで、軽い対応で済む場合が多いのです。
SOS発信のポイント
危機の兆候を感知したら、なるべく早く「危ないかもしれない」「助けが必要」と伝える勇気が重要です。SOSを出すことは決して弱さの表れではなく、問題解決に向けた大きな一歩です。
たとえばプロジェクトが予定より遅れてきた場合、「今は大丈夫」と思い込み、誰にも相談しないまま進めてしまうと、最終的に大きなトラブルにつながります。早めの段階で状況を説明すれば、上司や他部門から応援を得たり、方針を柔軟に変更したりする選択肢が広がります。
チームで悩みを共有する文化づくり
リーダー自らが不安をオープンにし、悩みや困難をチームで共有することを心がけましょう。会議の冒頭で「今気になっていること」を話題にする、定期的な1on1ミーティングを設けるなど、話しやすい雰囲気作りが大切です。
不安や問題を見える化し、みんなで乗り越える文化は、チーム全体の安心感にもつながります。万が一のときも隠蔽せず、すぐに対応できる体制を意識しましょう。
次の章に記載するタイトル:炎上させない「たった一つのコツ」=勝てるプロジェクトの目利き
炎上させない「たった一つのコツ」=勝てるプロジェクトの目利き

炎上を防ぐカギは「目利き力」にあり
前章では、不安や問題の兆しを早めに共有し、周囲にSOSを出すことの重要性について説明しました。実は炎上を未然に防ぐ本質的なコツは、プロジェクトの「目利き」にあります。ここでいう目利きとは、「勝てるプロジェクト」を見極める力のことです。
特別なスキルや裏技より「選ぶ力」
多くの人は、プロジェクトがうまくいく理由をリーダーの経験や知識、スキルに求めがちです。しかし山口氏は、「プロジェクトの炎上を防ぐ最大の要因は、そもそも成功する可能性の高い案件だけを選んでやること」と明言しています。「特殊なテクニックを使ったのでは?」と期待する方には拍子抜けかもしれませんが、実際には重要なポイントです。
案件選定こそが成否を分ける
案件の質は、プロジェクトの成功確率を大きく左右します。例えば、人手も技術も時間も足りない、関係者の意見がバラバラ、といった「勝ち目の薄い」案件を無理に引き受ければ、どんな優秀なプロマネでも消耗戦になりがちです。逆に、リソースや協力が揃っていて「勝てる」条件を満たしていれば、進行も円滑になります。
受注・着手前の「スクリーニング」に重点を
山口氏が強調するのは、プロジェクトが始まる前段階で「案件をしっかり見極める」ことです。たとえば、
- 依頼者の目的が明確か
- チームに必要なスキルが揃っているか
- スケジュールは現実的か
こういった条件を満たしているかどうかを、受注前や初期段階で確認しておくのが大切です。
「断る勇気」で未来を守る
もし、どう考えても厳しい条件が揃ってしまっている場合は、安易に引き受けず「断る」決断も必要です。これはプロフェッショナルとして、自分やチームの未来を守る大切な選択です。「案件の選定眼」を磨くことこそ、プロジェクト炎上を防ぐための一番の近道だと言えるでしょう。
次の章では、炎上を防ぐもう一つの重要なコツである「人選への全力投資」について詳しく解説します。
炎上させない「もう一つのコツ」=人選に全力投資

プロジェクトの成否を左右する大きな要素の一つは「誰がメンバーになるか」です。よくある間違いとして、すでに配属されたメンバーのままで進行するケースがあります。しかし、ジム・コリンズ氏の有名な言葉「まず人、次に計画」にあるように、優れたメンバーが揃えば、たとえ厳しい状況でも成功に近づけるのです。
なぜ「人選」が重要なのか
例えば、ポジティブな発想を持ち、周囲と協力ができるAさんと、受け身で消極的なBさんがいたとします。もし、プロジェクトにAさんのようなメンバーが多ければ、困難やトラブルが起きてもチーム一丸となって乗り越えやすくなります。逆にBさんタイプばかりだと、問題が起きても行動が鈍く、炎上しやすくなるのです。
配属を前提にせず「粘る」こと
多くのリーダーは「与えられたメンバーでやるしかない」と諦めがちですが、ここで全力を尽くして体制を整えることが、成功への大きな分かれ道になります。同じ仕事量でも、適材適所で配置すれば負担が軽くなり、メンバーもやりがいを持って取り組めるようになります。
実践例:社内異動や外部支援の検討
例えば、ITプロジェクトで専門性が不足していた場合、社内の他プロジェクトから経験者を一時的に引き抜いたり、社外パートナーを活用することも一つの手です。「今いる人以外は頼れない」と思い込みがちな場面でも、粘って交渉すれば、より良いチーム編成ができる可能性があります。
このように、人選への“粘り”が、後の炎上リスクを大きく下げるのです。
次の章に記載するタイトル:「実務で使えるチェックポイント(抜粋)」
実務で使えるチェックポイント(抜粋)

プロジェクトを現場で進める際、着手前・初期フェーズ・実行中の各タイミングで押さえておきたい「チェックポイント」をまとめます。これらを意識するだけで、失敗しづらく、成果に繋がる動きができるようになります。
着手前のチェックポイント
- 目的の明確化:プロジェクトの目的が「意思決定基準」として機能するレベルで言葉になっているか確認しましょう。単なるスローガンではなく、判断に迷ったときその目的を参照すれば答えが出せる状態が理想です。
- 勝てる案件の見極め:安易に全て請け負うのではなく、「勝てる案件かどうか」を最初に見極める姿勢が大切です。過去に成功した案件や、自分たちに合った規模・内容かをチェックしましょう。
- 意思決定者の設計:「最終的に誰が決めるか」を1人に決めておくと、スムーズな進行につながります。複数人で迷うとプロジェクトが停滞しやすいためです。
- キー人材の見通し:要所を担う人材が確保できるかどうかを早い段階で見立てておきましょう。難しい場合は、代替案も含め人物のあてを2つ以上持っておくと安心です。
初期フェーズのチェックポイント
- 期待値の調整:参加者の期待値が高すぎる場合、一度「できる範囲」に現実的に調整しなおしましょう。初回の成果をしっかり出して流れを作ることが成功のカギです。
- 早期の認識合わせ:できるだけ早いタイミングで成果物のイメージや方向性を共有します。図やサンプルを作って話し合うことで、ズレを早期に発見できます。
- 争点の開示:議論が生まれそうな部分は、後回しにせず先に出し切ることが重要です。見通しの悪い地雷を避けるためにも、率直な意見交換を前倒しで行いましょう。
実行中のチェックポイント
- リスク共有の徹底:不安やリスクが見つかったときは、メンバー全員で共有する習慣を持ちます。悩みが隠れると、問題の発覚が遅れてしまいます。
- エスカレーションの明確化:最終的な判断を仰ぐ時、意思決定者へすぐ相談できるルートを作っておきましょう。どこまで自分で判断し、どこから上に相談するかルールを決めると安心です。
- 無理難題への対応:要望が明らかに難しい場合は、無理に飲まず「一度断る」ことを徹底します。そのうえで、どんな条件なら可能なのか冷静に話し合いましょう。
これらを手元にチェックリストとして備えておくことで、プロジェクト運営の安心材料になります。
次の章に記載するタイトル:関連書籍と基本情報
関連書籍と基本情報
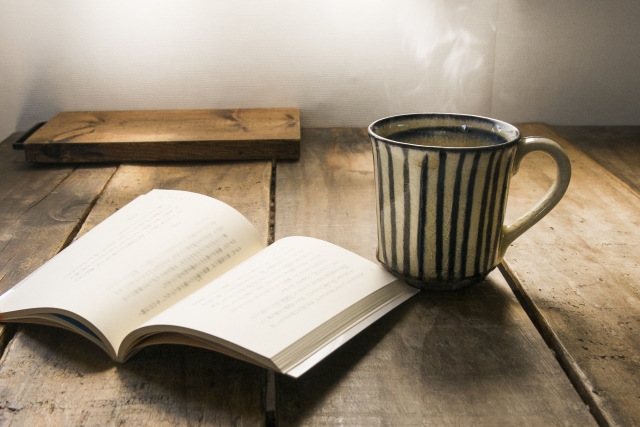
プロジェクトマネジメントの実務に関心がある方に、参考書として新装版『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』(著者:山口 周、出版社:大和書房)をご紹介します。本書は2023年6月15日に発売されており、税込価格は目安として1,650円です。Amazonなどのネット書店や大型書店、中古書籍店でも入手できます。中古品の流通も広く行われているため、入手がしやすい一冊です。
この書籍は、PM(プロジェクトマネージャー)やPL(プロジェクトリーダー)など、プロジェクトを進行管理する立場の方々の間で、高評価を得ています。各種ガイドやWEB記事でも推薦図書として取り上げられており、初学者から経験者まで幅広く読まれています。
注意点としては、一部のECサイトやマーケットプレイスでは、ISBNや商品情報に表記の揺れや誤記が見られる場合があります。確実に正しい情報を得たい場合は、出版社(大和書房)の公式サイトや正規の書店で確認することをおすすめします。
次の章に記載するタイトル:なぜ今「ニュータイプのプロマネ」か
なぜ今「ニュータイプのプロマネ」か

プロジェクトマネジメントの時代背景
今、世の中では「ルーティンワーク」だけでは仕事が立ち行かなくなっています。複雑で予測困難な「VUCA時代」に突入し、計画通りに進むこと自体が珍しくなりました。こうした中、業種や職種にかかわらず、プロジェクトという動き方がますます中心になっています。
例えば米国では、GDPの半分以上をプロジェクトワークが生み出しているといわれます。その背景には、日々変化する状況とニーズに対して、柔軟に対応する必要性があり、その先頭に立つ人のスキルが問われる社会になっているという現実があります。
「ニュータイプ」のプロマネへの期待
これまでのプロジェクトマネージャー像は、計画の進捗を管理したり、タスクを割り当てたりする「指示・管理型」が主流でした。しかし今求められるのは、変化を前提に、チーム全体を巻き込んで共に目的に向かって進むリーダーです。立場や役割を超えた対話力や状況に応じて道を切り拓く柔軟性が重要視されています。
また、現場の困難に正直に向き合い、前章でご紹介した「SOSの発信」「目利き力」「人選」など、従来テーマになかった新しい力も欠かせません。このようなプロジェクトマネジメントの進化系、それが「ニュータイプのプロマネ」です。
今求められる理由
今後ますます、予測できない課題や新しい連携、時には利害の異なる人々との協働が増えていきます。そのなかで、単なる管理役ではなく、目的を正しく捉え、成果に導く力がすべての業界で求められています。
プロジェクトマネジメントは特定の職種ではありません。これからの時代、誰もが「ニュータイプのプロマネ」として思考・行動することが、より良い未来を切り拓くカギになることは間違いありません。