この記事でわかること
- リスク管理表の基本構造とプロジェクトでの役割
- 作成の5ステップと実務での活用方法
- 効果的な運用・共有のポイントと課題管理表との違い
- PMBOKに基づくリスク管理プロセスとリスクマップの使い方
- リスク管理表を活用したプロジェクト成功の実践ポイント
目次
記事内容の詳細調査

本記事では「プロジェクトマネジメントに必須!リスク管理表の作り方と運用のポイント徹底解説」と題して、プロジェクトにおけるリスク管理表の基本から応用までを分かりやすく解説します。リスク管理表は、プロジェクトを進行するうえでの“想定外のトラブル”に対する備えとして非常に重要です。しかし、作り方や活用方法について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、リスク管理表の基本的な役割や、作成から運用、応用的な使い方まで、初めての方にも理解できるよう丁寧にご説明します。
まず、リスク管理表とは何か、なぜ必要なのかについてご紹介します。そして、実際に表を作成する際の基本的なステップや記載例、運用のコツなど、実務で役立つ知識を具体的な例とともにまとめました。また、関連するリスクマップとの併用方法や、国際標準であるPMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)の考え方も分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、リスク管理表の全体像とその実際の活用イメージがつかめ、日々のプロジェクト遂行に役立つ知識を身につけることができます。リスクに対して「何を、どこまで管理すれば良いのか」がわかるようになるため、初心者から経験者まで幅広い方におすすめです。
次の章では、プロジェクトマネジメントにおけるリスク管理表とは何かについてご説明します。
プロジェクトマネジメントにおけるリスク管理表とは

プロジェクトマネジメントにおいて、リスク管理表は非常に重要な役割を担っています。リスクとは、プロジェクトを進めるうえで予想外の出来事や問題が発生する可能性がある要素のことです。例えば、作業が遅れてしまう、予算を超えてしまう、メンバーが体調を崩す、必要な資材が届かないなどがリスクとして考えられます。
リスク管理表は、それらのリスクを一覧にして整理するための表です。この表を作成することで、どんなリスクがあるのかを事前に把握でき、どのリスクが起きた場合にどのような影響があるかを具体的に考えるきっかけになります。加えて、リスクが実際に発生した場合の対応策をあらかじめ決めておくことで、いざというときも落ち着いて対処できるようになります。
また、リスク管理表はプロジェクトの計画段階だけでなく、実際の運用中や進行中にも活用します。定期的に表を見直し、状況の変化に応じて新しいリスクを追加したり、対応策を修正したりすることで、プロジェクト全体のリスクを最小限に抑えることができます。こうした作業は、チーム全体でリスク意識を共有し合ううえでも効果的です。
次の章では、「リスク管理表を作成する5つの基本ステップ」について詳しく解説します。
リスク管理表を作成する5つの基本ステップ

プロジェクトでリスク管理表を作成する際には、いくつかの基本的なステップに従うことで、効率よく分かりやすい表を作ることができます。ここでは、その5つの基本ステップを具体例とともに解説します。
1. 記載項目の選定
最初に、リスク管理表に記載する項目を決めます。たとえば、「リスクの内容」「影響度(リスクが起こった場合の被害の大きさ)」「発生確率(どのくらいの頻度で起こりそうか)」「対応策(リスクに備えるための行動)」などがあります。さらに「担当者」や「対応期限」なども加えると、実際の運用がスムーズになります。
2. リスクの洗い出し
次に、どのようなリスクが考えられるかをリストアップします。過去の類似プロジェクトの失敗事例を参考にしたり、チームメンバー同士で意見を出し合ったりすることで幅広くリスクを集めることができます。例えば、品質面では「テストの遅延」、コスト面では「予算の超過」、スケジュール面では「納期遅延」といった具合に、分野ごとに分類すると分かりやすくなります。
3. リスクの分析
洗い出したリスクについて、それぞれ「発生確率」と「影響度」を評価します。このとき、点数(例えば、1~5段階)で評価すると、あとで優先度を決めやすくなります。たとえば、「予算の超過」は発生確率3、影響度4といった形で記載します。
4. リスクの評価
評価した発生確率や影響度をもとに、どのリスクから優先して対応するべきかを判断します。評価が高いリスクは、プロジェクト全体への影響が大きいため、早めの対策が重要です。逆に評価が低いリスクは、緊急度も低いため、後回しにするか経過観察に留めます。
5. リスク対応策の決定
最後に、リスクごとに具体的な対応策を考えます。例えば「納期遅延」であれば「人員を増やして作業を分散する」「進捗状況をこまめに確認する」といった予防策や、「実際に遅延が発生した場合は顧客に早めに連絡する」といった発生時対応策を決めます。また、対応する担当者や実施期限も明記しておくと、責任の所在がはっきりします。
次の章では、リスク管理表の基本フォーマットと具体的な記載例について解説します。
リスク管理表の基本フォーマットと記載例
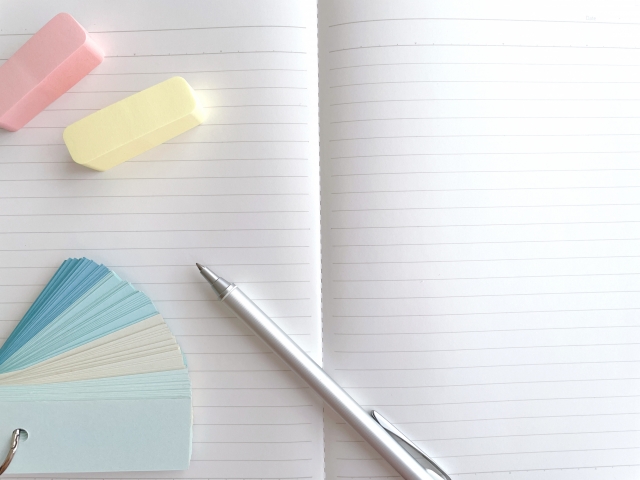
リスク管理表は、プロジェクトのリスクを整理し、効果的に管理するための重要なツールです。ここでは、一般的なリスク管理表の基本フォーマットと、具体的な記載例についてご紹介します。
基本フォーマットの主な項目
リスク管理表には、次のような項目を記載します。
- リスク番号:リスクを識別するための番号。
- リスク内容:具体的なリスク事象の説明。
- 発生区分:リスクが起きる可能性がある工程やタイミング。
- 発生確率:リスクが発生する可能性を数値や定性で示します。(例:高・中・低、または0.1〜1.0など)
- 影響度:リスクが発生した際のプロジェクトへの影響の大きさ。
- 優先度:発生確率×影響度により、対応の優先順位を決定します。
- トリガー:リスクが現実化する際のサインとなる出来事。
- 対応策:リスクを減らすための事前の工夫(予防策)、あるいは発生時の具体的な対応案(対応策)を分けて記載します。
- 担当者:リスクの監視・対応を任されたメンバー。
- 状況:現在の対応状況(未対応・対応中・完了など)。
記載例
以下は、リスク管理表の一部の記載例です。
| リスク番号 | リスク内容 | 発生区分 | 発生確率 | 影響度 | 優先度 | トリガー | 予防策 | 対応策 | 担当者 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 資材納期遅延 | 資材発注 | 中 | 高 | 高 | 納品スケジュール変更 | 仕入先と事前に納期を確認する | 他業者の活用、工程再調整 | 田中 | 対応中 |
| 002 | 予算超過 | 見積もり | 低 | 高 | 中 | 支出が予算を超えそうな時 | 事前に余剰予算を設定する | 必要経費の見直し | 佐藤 | 未対応 |
| 003 | 仕様変更による手戻り | 要件確定 | 高 | 中 | 高 | 顧客からの仕様変更依頼 | 変更手順を文書で明確にし承認を取る | 工程変更の影響を即時に周知、再スケジュール | 鈴木 | 完了 |
このような形で、各リスクを明確に分類・対策をまとめておくことで、プロジェクト開始後の混乱や後手対応を予防できます。
次の章では、リスク管理表の運用と活用ポイントについて説明します。
リスク管理表の運用と活用ポイント

リスク管理表の定期的なレビューと更新
リスク管理表は、一度作成して終わりではありません。プロジェクトが進むにつれて、新しいリスクが見つかったり、既存のリスクの影響が変わったりします。そこで、定期的にリスク管理表を見直し、必要に応じて内容を更新することが大切です。たとえば、毎週の定例会議でリスクについて話し合い、リスクが現実化しそうな場合や影響度が変化した場合は、すぐに管理表に反映させます。こうした運用により、プロジェクト全体の安定と進行のサポートにつながります。
チームでの情報共有と認識合わせ
リスク管理表は、一部のメンバーだけが使うものではありません。効果的な活用には、プロジェクトに関わる全員で内容を共有し、同じ認識を持つことが重要です。プロジェクト会議でリスク一覧を確認し、チーム全体で「どのリスクが今重要か」「どんな対策が必要か」を話し合う時間を設けましょう。たとえば、開発チーム全員が集まり、リスクについて短時間で意見交換をするだけでも有効です。こうした習慣が、予期せぬトラブルの早期発見や、対策の質向上につながります。
課題管理表との違いを理解し使い分ける
リスク管理表は「まだ起こっていないが将来起こりうる問題」を記録するものです。これに対し、課題管理表は「すでに発生してしまった問題」や「現在進行中の課題」を管理するための表です。たとえば、「部品の納期遅れが生じるかもしれない」という段階ではリスク管理表に記録し、「実際に部品が遅れてしまった」場合は課題管理表に移します。両者を正しく使い分けることで、問題に柔軟に対応できるようになります。
次の章に記載するタイトル:リスク管理表のテンプレート・事例
リスク管理表のテンプレート・事例

テンプレート例のご紹介
リスク管理表の作成には、一目で情報が分かるシンプルなテンプレートが便利です。ここでは、実際に現場でよく利用されているテンプレートの一例を紹介します。
【リスク管理表の代表的な項目】
- 課題番号:各リスクや課題に独自の番号を付けて管理しやすくします。
- 課題名:リスクの内容や懸念点を簡単に記載します。
- 優先度:そのリスクがどれくらい重要かを“高・中・低”などで記します。
- 担当者:リスクについて管理・対応する人を明示します。
- 期限:いつまでに対策や対応を終える必要があるか記載します。
- リスク評価:リスクが発生する可能性や影響度を点数やランクで記載します。
- リスク対応策:リスクを減らすためにどんな行動を取るか具体的に記述します。
- 状況:現在の進捗や、対策後の状態を更新します。
このように項目ごとに整理すると、誰でもリスクや課題の状況を把握しやすくなります。
具体的なリスク事例
たとえば、プロジェクトでよくある課題とリスク管理表への記載例は以下の通りです。
- クライアント資料の翻訳遅延
- 課題番号:001
- 課題名:資料翻訳の納期遅延
- 優先度:高
- 担当者:鈴木
- 期限:6月15日
- リスク評価:発生確率80%、影響度大
- リスク対応策:外部翻訳サービスの併用検討
状況:外部依頼済み
年次報告書のチェック漏れ
- 課題番号:002
- 課題名:年次報告書の内容誤り
- 優先度:中
- 担当者:佐藤
- 期限:7月1日
- リスク評価:発生確率30%、影響度中
- リスク対応策:ダブルチェック体制の導入
- 状況:チェック工程実施中
このように、具体的な課題に対してテンプレートを活用することで、プロジェクトメンバーが現状や今後の対応をすぐに確認できます。
次の章に記載するタイトル:PMBOKに基づくリスク管理表作成プロセス
PMBOKに基づくリスク管理表作成プロセス

PMBOKとは
PMBOK(ピンボック)とは、「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」の略で、プロジェクトマネジメントにおける世界的な標準をまとめたガイドラインです。リスク管理に関しても体系的なプロセスが整理されています。
1. リスク・マネジメントの計画
まず最初にリスク・マネジメントの計画を立てます。これは、どのようにリスクを管理するか(手順や体制、使用ツールなど)を決めるステップです。例えば「毎週の進捗会議でリスク管理表を更新する」といったルールを決めます。
2. リスクの特定
次に、プロジェクトで発生しそうなリスクを洗い出します。チームで集まって意見を出し合ったり、過去のプロジェクト例を参考にしたりする方法も効果的です。たとえば「納期遅延」「必要な部品の調達遅れ」といった具体的なリスクを挙げます。
3. リスクの定性的分析
特定したリスクを「重大性」「発生確率」など、ざっくりとした尺度で評価します。たとえば「影響が大きい」「発生するかも」などと判断し、優先順位をつけて管理します。
4. リスクの定量的分析
必要に応じて、リスクごとに数値データを使ってさらに詳しく評価します。例えば、そのリスクが発生した場合の損失額や発生確率を数値で示し、対策の優先順位を明確にします。
5. リスク対応策の計画
リスクごとに対応策を考えます。たとえば「納期遅延の場合は外部パートナーに依頼」「調達遅れは早めに発注」などの具体策を管理表に記載します。
6. リスク対応策の実施・監視
計画した内容が実際に効果を発揮しているか、定期的に確認します。リスク状況の変化があれば、管理表もその都度見直していきます。このサイクルを繰り返すことで、プロジェクトの安定運営につながります。
次の章に記載するタイトル:リスクマップとの併用
リスクマップとの併用

リスク管理表に加えてリスクマップを活用すると、リスク管理がさらに効果的になります。リスクマップとは、各リスクを「発生する確率」と「影響の大きさ」の2つの軸でマトリクス状に整理した図です。
リスクマップの役割
リスクマップは、リスク一覧を視覚的にまとめ、どのリスクに優先して対応すべきかをひと目で把握できるようにするものです。たとえば、発生確率が高く影響も大きいリスクは真っ先に対策が必要とわかります。色分けを使うことで、さらに理解しやすくなります。
管理表とマップの効果的な使い方
リスク管理表にはリスクひとつひとつの詳細や対応策を記載しますが、リスクマップと組み合わせることで、全体の状況やバランスを俯瞰できます。例えば、どのリスクが最も注意すべきか、あるいは対策の優先順位を決める時に役立ちます。
リスクマップの作り方(簡単な例)
- リスク管理表のリスクごとに「発生確率」と「影響度」を1~5などで評価します。
- 縦軸に「発生確率」、横軸に「影響度」を取り、表に各リスクを書き込んでいきます。
- 高リスク(確率・影響が大きいもの)は赤、中リスクは黄色、低リスクは緑といった色分けが一般的です。
具体的な活用シーン
プロジェクトの計画や定例会議で、マップを使って現在のリスク状況を全員で確認できれば、意識合わせや共通理解が深まります。また、リスク対応の優先順位を議論する際も、マップがあると意思決定がスムーズです。
次の章に記載するタイトル:まとめ
まとめ

この記事を通じて、プロジェクトマネジメントにおけるリスク管理表の重要性とその活用方法についてご紹介しました。リスク管理表は、プロジェクトを円滑に進め、想定外のトラブルを防ぐための大切なツールです。作成には明確なステップがあり、チームで協力しながら取り組むことが求められます。
また、リスク管理表を一度作成して終わりではなく、実際のプロジェクト推進に合わせて定期的に見直し・更新することが、リスクの低減や対応力の向上につながります。テンプレートや記入例、PMBOKなどの標準ガイドラインを活用することで、誰でも効率よくリスク管理表を運用できます。
プロジェクトの規模や特性にあわせて柔軟に工夫し、現場にとって最も使いやすい形に整えることを意識しましょう。リスク管理の習慣が根付くことで、プロジェクトの成功率は大きく高まります。みなさんの現場でも、ぜひ積極的にリスク管理表を活用してみてください。