この記事でわかること
- プロジェクトマネージャ試験の概要と難易度
- 効率的な勉強法と参考書選びのポイント
- 合格者に人気の基本書・総合対策本
- 論述・過去問対策に最適な実践トレーニング本
- 学習を続けるための書籍選びのコツと合格へのステップ
目次
- プロジェクトマネジメントにおけるステークホルダー完全ガイド:特定・分析・関与・運用の実践知
- ステークホルダーとは何か、なぜ重要か
- ステークホルダーマネジメントの全体プロセス
- ステップ1:ステークホルダーの特定と分析
- ステップ2:関与(エンゲージメント)とコミュニケーション計画
- ステップ3:エンゲージメント実行(協業と合意形成)
- ステップ4:モニタリングと調整
- うまくいかない時の典型リスクと回避策
- PMBOK観点と実務への落とし込み
- アジャイルにおけるステークホルダーの役割
- プロダクトマネージャー視点の実践的コツ
- 現場で使えるチェックリスト(基本)
- ステークホルダーマネジメントの効果(得られる価値)
- キーメッセージのまとめ
- 出典の主なポイント
プロジェクトマネジメントにおけるステークホルダー完全ガイド:特定・分析・関与・運用の実践知

プロジェクトを円滑に進め、目標を達成するには「ステークホルダーマネジメント」が欠かせません。ステークホルダーとは、プロジェクトに直接・間接的に関わるすべての人や組織を指し、顧客やユーザーはもちろん、社内の関係部門、外部の協力会社など多岐にわたります。各々の利害や期待が異なるため、それらを把握し適切に調整することが、プロジェクト成功のカギとなります。
本ガイドでは、ステークホルダー特定・分析・関与・調整の4つの主要ステップと、必要なポイントをわかりやすく解説します。また、PMBOKの標準的な手法だけにとどまらず、アジャイル型のプロジェクトやプロダクトマネージャーの視点、現場で役立つ工夫やチェックリストまで幅広く紹介します。実践的かつ今日から使える知識として、初学者の方から現場で悩む方まで役立てていただけます。
次の章に記載するタイトル:ステークホルダーとは何か、なぜ重要か
ステークホルダーとは何か、なぜ重要か

ステークホルダーの意味を簡単に解説
ステークホルダーとは、プロジェクトや事業の計画や運営に直接・間接的に関係する「利害関係者」のことを指します。具体的には、株主や経営層だけでなく、現場で働く従業員、商品やサービスを使うお客様、納入業者やパートナー企業、地元の住民など、プロジェクトの影響を受ける人すべてが含まれます。
ステークホルダーの具体例
例えば、新しい商品を開発する場合を考えましょう。このとき、開発チームはもちろん、営業担当やマーケティング部門も利害関係者です。さらに、商品を買ってくださるお客様や、部品を納入する外部企業も関わります。一見して無関係に思える近所の住民も、工事の音や交通の変化などで影響を受けることがあるため、関係者と言えるのです。
なぜステークホルダーが重要なのか?
プロジェクトを成功させるには、こうした多様な関係者一人ひとりの期待や懸念を理解し、その協力を得られるように動くことが大切です。関係者の意見を無視して進めると、後で思わぬトラブルや反発が生じてしまいます。逆に、ステークホルダーの声に耳を傾け、早い段階で巻き込んでいけば、方向性が明確になり、問題も早期に発見でき、よりスムーズに物事が進みます。
ステークホルダーマネジメントの意義
こうした背景から、PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)でも、ステークホルダーとの関係づくりは独立した重要な分野としてまとめられています。適切なマネジメントをすることで、意思決定がしやすくなり、社内外の協力も得られやすくなるため、最終的にプロジェクトの成功確率が上がります。
次の章に記載するタイトル:ステークホルダーマネジメントの全体プロセス
ステークホルダーマネジメントの全体プロセス

プロジェクトを成功させるためには、関わる人々(ステークホルダー)と上手につきあい、協力し合うことが欠かせません。その際に役立つのが「ステークホルダーマネジメント」という進め方です。では、具体的にどんな流れで進めるのでしょうか?ここでは、全体のプロセスを順を追ってご紹介します。
ステークホルダーマネジメントの流れ
ステークホルダーマネジメントは、主に4つのステップで進めます。
ステークホルダーの特定と分析
最初に、プロジェクトに関わる全ての人や組織をリストアップし、それぞれがどのような立場や考え方を持っているのか、どの程度プロジェクトに影響力を持つのかを分析します。例えば、実際の例としては「開発チーム」「お客様」「取引先」「上司」など多様な関係者が考えられます。関与(エンゲージメント)とコミュニケーション計画
続いて、特定した各ステークホルダーにどのように関心を持ってもらい、プロジェクトに協力してもらえるか、そのための計画を立てます。たとえば、「どのくらい頻繁に連絡するか」「どう説明を伝えるか」など、具体的なコミュニケーション方法もここで決めます。エンゲージメント活動の実行
計画した内容を実際に行動に移します。必要に応じてミーティングを開いたり、定期的な報告や意見交換の場を設けたりして、関係を築いていきます。モニタリングと調整
プロジェクトの状況は常に変化するため、ステークホルダーの関心や影響力にも変動が生じます。そのため、定期的に状況を見直し、必要に応じて対応を調整することが大切です。
これらのステップは一度きりではなく、状況に応じて何度も繰り返し行います。プロジェクトが進む中で新しい関係者が現れたり、古くからの関係者の立場や意見が変わったりすることも多いためです。このサイクルを回し続けることで、プロジェクトをスムーズに前進させやすくなります。
次の章では「ステークホルダーの特定と分析」について詳しくご紹介します。
ステップ1:ステークホルダーの特定と分析

ステークホルダーを洗い出すには
プロジェクトが始まると、まず誰が関わってくるのかを整理することが大切です。ステークホルダーとは、プロジェクトの進行や成果に興味を持ったり、影響を及ぼす可能性のあるすべての人や組織を指します。たとえば、社内であればプロジェクトメンバー、上司、経営陣、関連部署。他にも、協力会社や取引先、必要に応じて顧客やユーザーまで広く目を向けることが必要です。
代表的な例として、ITシステム刷新プロジェクトなら「利用部門」「情報システム部」「経理部」「ITベンダー」「ユーザー代表」などが考えられます。広い視点で洗い出すことで、後から大きな影響を及ぼす存在を見落とすリスクを減らせます。
各ステークホルダーの分析ポイント
ステークホルダーをリストアップしたら、一人ひとり、一社ずつの立場や動機を具体的に把握していきます。主に以下の観点で分析することが基本です。
- どんなことに関心を持っているのか(例:コスト削減、納期の厳守、最新技術の導入など)
- プロジェクトへの影響力はどれくらいあるのか
- 何を期待しているのか、どんな成果を望んでいるのか
- 他のステークホルダーとどのような関係や依存があるのか
- 否定的な意見や懸念を持っていないか
たとえば、経営層は全体のコストや効率性を気にする一方、現場担当者は日々の使いやすさや業務負担の軽減に関心があることが多いです。また、取引先は自社への影響や契約面を重要視するケースもよく見られます。
見落としを防ぐためのコツ
ステークホルダーは「一元的」に扱わず、それぞれ固有の事情や期待、影響度を考えて整理することが成功のカギです。否定的な意見や懸念を持つ人もなるべく早い段階で把握し、プロジェクトを通じて丁寧に対応していく姿勢が信頼感につながります。
社内の非公式な意見交換やアンケート、ヒアリングを活用すると、表面には現れにくい本音や懸念も把握しやすくなります。
次の章に記載するタイトル:関与(エンゲージメント)とコミュニケーション計画
ステップ2:関与(エンゲージメント)とコミュニケーション計画

ステークホルダーの特定と分析が終わった後は、それぞれのステークホルダーとどのように関わっていくのかを計画する段階に入ります。ここでは、関与(エンゲージメント)とコミュニケーションの具体的な計画について解説します。
エンゲージメントの基本方針
ステークホルダーとの関わりは、単に情報を伝達するだけではなく、双方向のコミュニケーションが重要です。プロジェクト責任者(プロジェクトマネージャー)は、ステークホルダーの意見や懸念に耳を傾け、その力を借りる姿勢で関わることが成功のカギとなります。
コミュニケーション計画のポイント
コミュニケーション計画では、以下の要素を整理します。
- 誰と(対象ステークホルダー)
- どの頻度で(例:週1回、月1回など)
- どのチャンネルで(例:メール、会議、チャット、説明会)
- どんな内容を共有するか(プロジェクトの進捗、課題、決定事項、変更点など)
たとえば、経営陣には月例の進捗レポートが適していますが、現場担当者にはチャットで日々のコミュニケーションが効果的です。
期待調整の重要性
プロジェクトの初期や節目ごとに、お互いの期待がズレていないか確認する時間を設けることが大切です。お互いに「何をゴールとするのか」「どんな情報を欲しいのか」をすり合わせておくと、後々のトラブル防止につながります。
意思決定とエスカレーションの仕組み
問題が発生したとき、誰にどのように相談したらよいか(エスカレーション経路)をあらかじめ決めておくと安心です。また、意思決定が必要な場面では、ステークホルダーをうまく巻き込み、合意形成できるような場づくりも重要です。
フィードバックの収集
定期的なアンケートや1on1ミーティングなどを活用し、ステークホルダーからのフィードバックを得る仕組みを作ると、プロジェクトの改善につながります。小さな意見も拾いやすくなり、関係の質が良くなります。
次の章に記載するタイトル:エンゲージメント実行(協業と合意形成)
ステップ3:エンゲージメント実行(協業と合意形成)

プロジェクトでステークホルダーと良好な関係を築くためには、単に情報を伝達するだけでなく、実際に一緒に行動することが重要です。ステークホルダーエンゲージメントの実行段階では「協業」と「合意形成」を具体的な行動に移します。
定期的なコミュニケーション
プロジェクト進行中は、ステークホルダーと定期的にコミュニケーションをとります。例えば、週に一度の進捗報告や質問会を設けることで、情報の行き違いを防ぎ、課題があれば早期に拾い上げることができます。口頭でのミーティングやチャットツールでのやりとりも活用します。小さな疑問や意見も拾い上げることでステークホルダーに安心感を与えます。
レビュー・デモの実施
システム開発やサービス改善などの現場では、定期的なレビュー会やデモンストレーションが効果的です。実際の成果物を見せて、フィードバックを受けとることでステークホルダーの期待値を調整できます。たとえば「新しいアプリ画面のテスト版を見ながら意見をもらう」といった流れです。このような場を通じ「一緒に作っている」「自分の意見が反映されている」と感じてもらうことが大切です。
意思決定会議の設計
重要な事項についてはステークホルダーが納得できる形で意思決定プロセスを設計します。会議の議題や意思決定の基準を事前に共有し、参加者全員が積極的に意見を述べられるように工夫します。例えば「多数決」よりも「合意形成」を重視するラウンドテーブル方式も効果があります。このようなプロセスを繰り返すことで、関係者の納得感と協力度が高まります。
課題・リスクの透明化と合意の反復
問題やリスクがある場合、隠さず早めに共有します。「現状こういう課題があり、乗り越えるためにこのような協力をお願いしたい」という形で伝えます。ステークホルダーからのフィードバックをもとに協力体制を調整しながら、課題ごとに小さな合意形成を積み重ねていきます。
プロジェクトチームが「自分たちだけ」の集まりにならないよう、「一緒に支える」「共に成功を目指す」といった結束力を作る活動が欠かせません。これが、ステークホルダーとの絆を強め、支援意欲を高める秘訣です。
次の章に記載するタイトル:モニタリングと調整
ステップ4:モニタリングと調整

プロジェクトが進行する中で、ステークホルダーの関心や影響力、満足度は変化しやすいものです。そのため、定期的なモニタリングと柔軟な調整が非常に重要です。
1. ステークホルダーの現在地を把握する
定期的にステークホルダーへのヒアリングや簡単なアンケートを実施し、現在の関心度や不安点を確認します。たとえば、直近の会議後に「疑問点はありませんか?」と小さな声かけをするだけでも、意見を引き出しやすくなります。
2. コミュニケーション方法の見直し
当初はメール中心だったものの、ステークホルダーが忙しくなれば短いミーティングへ切り替えるなど、情報の伝え方も状況に応じて変化させましょう。情報の内容も、全体像を重視する人にはまとめ資料、細かい部分が気になる人には技術詳細など、相手に合わせる工夫が大切です。
3. 関与度合いの調整
一部のステークホルダーがプロジェクトへの興味を失いかけていると感じたら、決定事項への参加を促したり、重要な場面で意見を求めるようにします。反対に、懸念や不安ばかり主張してプロジェクトを進めにくくしている場合は、追加説明や質疑応答の機会を設けて納得感を高める努力も必要です。
4. 状況を記録し次につなげる
誰がいつ、どのような意見や要望を出したか、変化点をシンプルに記録しておきます。これによりチーム全体で情報を共有しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップできます。
次の章では、うまくいかない時に起こりやすいリスクやその回避策について解説します。
うまくいかない時の典型リスクと回避策

プロジェクトでステークホルダーと良好な関係を築くことは理想ですが、現実にはうまくいかない場面も少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンと、その対処法についてわかりやすくご紹介します。
1. 期待のズレが生じるリスク
ステークホルダーごとに立場や関心ごとは異なります。しかし、皆をひとまとめに扱ってしまうと、「思っていたのと違う」と感じる人が出やすくなります。例えば、経営層はプロジェクトの収益に注目しますが、現場担当者は業務の具体的な負担増加を気にしています。こうした違いを無視すると、不満や抵抗につながります。
回避策
ステークホルダーごとに関心やニーズを整理し、それぞれに合わせた説明や情報提供を心掛けます。定期的なヒアリングやアンケートを活用して、ギャップが生じていないかを確かめることが大切です。
2. エンゲージメントの低下
関与が乏しいと、ステークホルダーはプロジェクトに対して距離を感じがちです。意見を聞かれない、説明が不十分などの理由で、「自分事」と思わなくなることがあります。このような状態では、協力を得にくいだけでなく、トラブル時の対応も遅れやすくなります。
回避策
積極的にフィードバックを求め、成果や経過を「見える化」することで、関わりを強く意識してもらいましょう。定例会議やワークショップを設け、一方通行でなく双方向のやりとりを意識するのも効果的です。
3. コミュニケーションの断絶
情報共有を怠ったり、難しい話を専門用語で固めたりすると、理解しづらくなります。加えて、反対意見を持つステークホルダーを避けてしまうと、本来早めに解決すべき問題が後で大きくなることも少なくありません。
回避策
わかりやすく丁寧な説明を心掛け、専門用語の使用を控えます。また、反対意見や疑問にも耳を傾け対話の機会を設けることで、未然にトラブルの芽を摘むことができます。状況に応じて、個別面談の時間をつくるのも有効です。
次の章に記載するタイトル:PMBOK観点と実務への落とし込み
PMBOK観点と実務への落とし込み

PMBOKにおけるステークホルダー管理の位置づけ
プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK)は、プロジェクトをうまく進めるための世界的なベストプラクティス集です。その中で、ステークホルダー管理は「知識エリア」の一つとして明記されています。PMBOKでは、関係者の特定、把握、関与の計画、関与の促進、継続的な見直しという一連のプロセスが紹介されています。
特に重要なのは、コミュニケーション管理とステークホルダー管理が密接に結びついている点です。例えば、プロジェクトの進捗状況や意思決定の背景など、関係者にとって必要な情報がタイミングよく、適切な方法で提供されることが求められます。
実務への落とし込み方
知識だけでなく、実際の現場ではどう活かせばよいのでしょうか。たとえば、利害関係者リストを可視化し、影響度や関心ごとを整理することで、誰にいつ、どのような情報共有や意見交換が必要か明確にできます。さらに、定例会議やメール報告だけでなく、突然の相談や懇親の場を通じた非公式なコミュニケーションも、実は意思疎通を円滑にする重要なポイントです。
また、ステークホルダーの「期待値」を確認し、すれ違いがあれば早期に調整することが成功のカギとなります。例えば、顧客が求める納期と、開発チームが想定する作業期間に差がある場合、双方の認識を合わせて現実的な着地点を見つけましょう。
効果として得られるもの
PMBOKで示されている方法を実務に当てはめることで、プロジェクトの目的がより明確になり、関係者の満足度や成果物の品質も高まります。結果として、判断ミスや無駄な手戻りも減少し、プロジェクトの成功確率が着実にアップします。
次の章に記載するタイトル:アジャイルにおけるステークホルダーの役割
アジャイルにおけるステークホルダーの役割

アジャイル時代、ステークホルダーは「共に創る存在」へ
アジャイル開発では、ステークホルダーの関わり方が従来のウォーターフォール型プロジェクトと大きく異なります。ステークホルダーは計画段階だけでなく、開発の各サイクル(スプリントやイテレーション)ごとに継続的に協力します。
反復開発と協力のサイクル
アジャイルでは、短い期間ごとに成果物を作り、ステークホルダーと「デモ」や「レビュー」を実施します。たとえば、2週間ごとに新しい機能のデモを見せて、意見や要望を聞きます。このやり取りで、価値観のずれや期待のギャップを早期に発見でき、すぐに修正ができます。
ステークホルダーの意見をどう扱うか
全員の意見が同じとは限りません。そこで「プロダクトオーナー」などの役割が、皆の意見を聞き、優先順位をつけて、価値の高いものから開発チームに伝えます。一方的ではなく対話を重ねることで、納得感や信頼関係も生まれます。
アジャイルにおける具体例
たとえば、新しい社内システムを導入するとき、「現場の担当者」「経営層」「IT部門」など多様な人がステークホルダーになります。定期的なレビュー会議の場で、「使いやすさ」や「コスト」など様々な観点からの意見が上がります。現場の声をすぐに反映し、小さな改善を繰り返すのがアジャイルの特長です。
アジャイルのメリット
・完成まで待たなくても途中で成果を確認できる
・期待と実際のズレを早く解消できる
・ステークホルダーの納得感とプロジェクトの達成度が上がる
これらは、アジャイルにおけるステークホルダーの積極的な関与による成果です。
次の章に記載するタイトル:プロダクトマネージャー視点の実践的コツ
プロダクトマネージャー視点の実践的コツ

ステークホルダーの特徴を把握する
プロダクトマネージャーが現場でステークホルダーマネジメントを成功させるためには、それぞれのステークホルダーの特徴や役割、そして何を求めているのかを知ることが大切です。例えば、営業部門は「納期」や「顧客満足度」を重視し、システム担当は「安定性」や「運用のしやすさ」を気にしています。このように、関係者が重視するポイントや期待する成果には違いがあります。
役割の明確化で混乱を防ぐ
プロジェクトの序盤に「誰が何を決めるのか」「最終的な責任者は誰なのか」といった役割分担をはっきりさせておくことで、後々のトラブルを減らすことができます。例えば、Aさんが仕様決定、Bさんが予算管理、といった形で一覧にして共有すると分かりやすくなります。
効果的なコミュニケーション設計
さまざまな関係者がいるプロジェクトでは、全員に同じ内容や頻度で情報を発信しても効果的とは限りません。一次的な報告はメールでまとめ、重要な議題はミーティングできちんと説明する、といった住み分けを意識しましょう。営業には進捗をわかりやすく、開発には技術的背景も添えるなど、相手に合わせて説明方法を調整するとスムーズです。
意思決定者の特定と合意形成
プロジェクトの進捗や政策を左右する意思決定者が誰なのか、早い段階で把握しておくことが重要です。また、何をもって「成功」とするか成功指標(KPIや達成目標)を関係者と合意できていれば、後戻りや認識ズレを予防できます。具体例として、プロダクトリリースの時点で「社内評価90点以上」といった基準をみんなで決めておくと良いでしょう。
次の章に記載するタイトル:現場で使えるチェックリスト(基本)
現場で使えるチェックリスト(基本)

ステークホルダー台帳の整備
まず着目したいのは、関係者(ステークホルダー)のリストがきちんと整理されているかです。関係者は「誰が関わり、どんな関心事があり、プロジェクトへどう影響するのか」を明確にしておきましょう。例えば、システム導入プロジェクトなら「経営層」「現場担当者」「情報システム部」など、それぞれ利害や期待が違います。さらに「リスクになる懸念点」や「期待されている支援内容」まで記載できると、実際の意思疎通や対応がスムーズです。
コミュニケーション計画の文書化
関係者ごとの話し合いの頻度、使う連絡手段(メール・対面・チャットなど)、誰が主に説明・報告を担うか、話がこじれたときの対応(エスカレーション手順)、相手から意見をもらう場の設計が準備できているかを確認します。これらが明文化されていれば抜け漏れなく対応できます。チーム内で簡単な表やシートにまとめて共有するだけでも、安心感が高まります。
反対・中立ステークホルダーへの関与
全員が最初から前向きとは限りません。反対意見や積極的には関わらない中立的な立場の人への働きかけ方法も事前に考えておきましょう。例えば「意見交換の機会を個別に設ける」「小さな成功体験を一緒に作る」など、相手に合った関与戦略を持っているかをチェックしてください。
定期的な関心度・満足度の振り返り
プロジェクトは進めていくうちに、関係者の気持ちや優先事項が変わることも多いものです。一定の区切り(たとえばスプリント終了時や大きなマイルストーン達成時)で、「今の状況に満足しているか」「何か困っていることはないか」と関係者に振り返りの時間をとりましょう。この小さな積み重ねが、大きなトラブル防止や信頼構築につながります。
次の章に記載するタイトル:ステークホルダーマネジメントの効果(得られる価値)
ステークホルダーマネジメントの効果(得られる価値)

プロジェクトマネジメントにおいてステークホルダーマネジメントを適切に行うと、具体的にどのような価値が得られるのでしょうか。この章では、その主な効果をわかりやすく解説します。
方向性の明確化
関係者全員の要望や期待を整理し、プロジェクトの目指すべきゴールを明確にできます。例えば、開発チームと営業部門で意見が食い違う場合でも、早い段階で調整することで無駄な作業を減らせます。
リスクの早期特定
様々な立場の人から情報が集まるため、潜んでいた問題点やリスクを早い段階で発見しやすくなります。仮にユーザーが使いにくいと感じている部分も、現場の声を拾えれば改善できます。
コミュニケーションの質向上
あらかじめ誰に・何を・どのタイミングで伝えるかを決めておけば、連絡ミスや行き違いを減らせます。具体例としては、進捗共有の場を設けておくことで、開発の遅れを早期に共有できます。
意思決定の改善
色々な視点や専門知識が集まることで、より良い選択がしやすくなります。例えば、新製品の仕様を決める時、利用者や運用担当者の意見も聞くことで、現実的かつ最適な仕様に近づけます。
成功確率の向上
これらすべての積み重ねにより、プロジェクト失敗のリスクを減らし、成功に導く可能性が高まります。
失敗の防止
ステークホルダーマネジメントを怠ると、関係者が無関心になったり、納品物の品質が下がったり、コミュニケーション不足による失敗が目立つようになります。このようなリスクを事前に防ぐ役割も果たします。
次の章に記載するタイトル:「キーメッセージのまとめ」
キーメッセージのまとめ

これまでの内容を振り返ると、プロジェクトやプロダクトを成功に導くカギは「ステークホルダーとの適切な関係構築」にあります。ステークホルダーは、プロジェクトに直接・間接的に影響を及ぼす広範な人々や団体です。例えば、社内外の上司や同僚だけでなく、お客様や協力会社、地域社会もステークホルダーとなり得ます。
特に重要なのは、肯定的な意見だけでなく、否定的な意見や懸念も早期に把握しておくことです。否定的な声もプロジェクト推進のヒントになりますし、事前に調整することで大きなトラブルを未然に防げます。そのために「特定」「分析」「関与の計画」「実行」「モニタリング」という流れでステークホルダーマネジメントを進め、状況に応じて柔軟に調整していくことが大切です。
アジャイル開発の場合、短い作業サイクルで素早く意見を聴き、価値が生まれているかを確認し続けるというプロセスがより一層重要になります。プロダクトやプロジェクトの責任者は、誰がどのような役割で何を望んでいるのかを明確にし、信頼関係を築いてこそ、協力を得られ成功確率が大きく高まります。
次の章に記載するタイトル:出典の主なポイント
出典の主なポイント
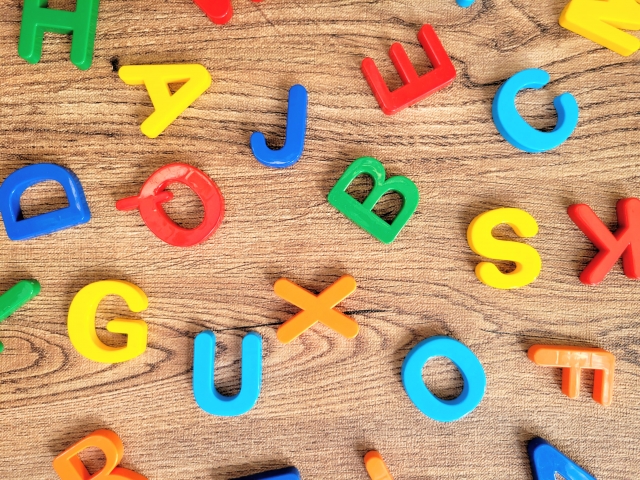
本章では、記事で参考にした主な出典から、読者の実務に役立つポイントをまとめます。
Schoo
Schooでは、ステークホルダーの定義を「プロジェクトの成果に何らかの影響や関心を持つあらゆる人」と広くしています。また、否定的な意見を持つ人も含めて管理すべきだと強調しています。これにより、プロジェクトの見落としや想定外のトラブルを防ぐ重要性がよく分かります。
Sqripts
Sqriptsの記事では、4つの実践的なステップ—特定、計画、関与、モニタリング—に基づく進め方が提案されています。それぞれのステップごとに「誰を巻き込むか」「どのように情報を伝えるか」など具体的な方法を示しており、現場ですぐに使えるフレームとして参考になります。
TimeCrowd
TimeCrowdは、PMBOK(プロジェクトマネジメント標準ガイド)でのステークホルダー管理の位置づけと、その重要性を分かりやすく整理しています。理論的なフレームワークと、実務への紐付けを意識した説明が特徴です。
ONES
ONESのまとめでは、ステークホルダーの重要性や基本的な4ステップ、そしてマネジメントをおこなうことでどのような効果が得られるかが整理されています。基礎から応用まで体系的に理解したい方に有用な内容です。
Platinum Edge
Platinum Edgeの情報では、アジャイル型のプロジェクトにおいてステークホルダーがどのような役割を持ち、関与するかが解説されています。従来型と異なり、関与の頻度やフィードバックサイクルに違いがあることが大きな特徴です。アジャイル導入時の注意点として参考にできます。
Product Managers Club
Product Managers Clubでは、現場で役立つコツとして「関係者の役割を明確にする」「ニーズを丁寧に把握する」「こまめなコミュニケーション」の3点が紹介されています。どの職種の方にも実践しやすい内容で、日々の仕事に取り入れやすい知恵です。