この記事でわかること
- 体制設計で決めるべき要素と重要性
- 組織構造3型(機能・マトリクス・プロジェクト)の特徴
- 良い体制図の作り方と注意点
- PM・PL・PMOの役割と違い
- 規模に応じた体制拡張と運用ポイント
目次
体制設計の出発点:何を「体制」で決めるのか

体制設計の重要性
プロジェクトやチームを進める際、最初に考えるべきことは「体制」です。体制とは、誰が、どのような立場で、何を担当するかを決めるルールや枠組みのことです。ただメンバーを集めればよいわけではありません。計画的に体制を考えることで、仕事の流れがスムーズになり、混乱やミスを減らせます。
体制で決めるべき5つのポイント
体制設計で決定すべき内容は、主に次の5つです。
- 指揮命令系統
- どのメンバーが誰から指示を受けるのか、誰に報告するのかを明確にします。たとえば、プロジェクトマネージャー(PM)がリーダーとなり、メンバーはPMの指示を受ける、というイメージです。
- 役割・責任(R&R)
- 各人の担当業務や責任範囲を決めます。たとえば、「資料作成はAさん、スケジュール管理はBさん」といった割り振りを指します。
- 意思決定権限
- どこまで自分で決めてよいか、どこから上司の承認が必要かを決めます。意思決定のルールをはっきりさせておくと、トラブルを防げます。
- 報告・連絡の経路
- 誰が誰に、どんなタイミングで連絡・報告するのか決めます。これにより、情報がきちんと伝わる仕組みが作れます。
- 必要な人材と人数(編成)
- チームにどんなスキルを持つ人が何人必要かを具体的に考え、バランスよく配置します。
体制図でイメージを共有
体制図は、こうした体制の内容を図にして表すものです。例えば、リーダー・メンバー・サポート役・外部関係者といった登場人物を四角い枠で描き、それを線で結びます。上から下に向かう線は「命令が下りていく流れ」、横の線は「情報共有」などを表します。この図があると、誰がどの立場で、どことつながっているかが一目で分かります。
体制を図や言葉で明確にしておくことで、役割分担や責任範囲が可視化され、意思疎通や運営の効率がぐんと高まります。
次の章では、プロジェクト組織の主なタイプについてご紹介します。
プロジェクト組織構造の3類型:機能型・マトリクス型・プロジェクト型

プロジェクトの体制を考えるとき、どのような組織構造を取るかは非常に重要です。代表的な3つの型、「機能型」「マトリクス型」「プロジェクト型」には、それぞれに特徴とメリット、注意点があります。ここでは身近な例を交えながら、それぞれの型についてわかりやすくご紹介します。
機能型組織とは
機能型組織は、従来の「部門ごと」に仕事を分担する形です。たとえば、大きな会社では「営業部」「開発部」「品質管理部」など部門単位で仕事を進めています。この場合、部門のリーダー(マネージャー)がメンバーの業務を管理し、プロジェクトが立ち上がると、各部門からそのプロジェクトを兼任で担当するメンバーが選ばれることが多いです。
この型の特徴は、専門性の高い人材が部門でまとまりやすい点です。一方、複数部門の調整が難しく、プロジェクト側からのお願いごとが「部門の都合」で後回しになりやすい面も持っています。
例:
・営業部が「新しい商品企画」のプロジェクトを担当し、必要な時に開発部や品質管理部へ協力依頼をする。
マトリクス型組織とは
マトリクス型組織は、1人が2つの上司(例:部門マネージャーとプロジェクトマネージャー)を持つ構造です。縦軸に「所属部門」、横軸に「プロジェクト」の双方から指示や報告があります。
この型の最大の特徴は、リソースの柔軟な使い回しと、部門・プロジェクト双方の最適化を目指せることです。反面、指示系統が重なることで、指示がバッティングして混乱を招いたり、調整に時間がかかることも起きやすいです。
例:
・開発部のAさんが、普段は開発部の業務を担いながら、期間限定で「新サービス開発プロジェクト」にも携わる。
プロジェクト型組織とは
プロジェクト型組織では、プロジェクトごとに専任スタッフが集まり、全員がそのプロジェクトにだけ取り組みます。この場合、プロジェクトマネージャー(PM)が唯一の直属上司のような立場となり、決定権限も集中します。
この方式のメリットは、集中度が高く、意思決定も早い点です。短期間で大きな成果を求める場合や、新規事業の立ち上げなどに向いています。一方、専任メンバーの確保が必要なため、人材コストが高くつくこともあります。
例:
・大型システムの開発プロジェクトチームが発足し、メンバー全員が一定期間その開発だけに専念する。
次の章では、「体制図(組織図)の作り方:良い・悪いの分岐」について解説します。
体制図(組織図)の作り方:良い・悪いの分岐

体制図(組織図)は、プロジェクトの運営に欠かせない基本的な資料です。ここでは、良い体制図の作り方と、ありがちな失敗例について具体的に解説します。
正しい体制図のポイント
良い体制図とは、プロジェクトの全体像が一目で分かるものです。まず、指揮命令系統を一本化した上で、上から下へと流れる形で作成します。たとえば、一番上にプロジェクトオーナー、その下にプロジェクトマネージャー(PM)、さらにその下にプロジェクトリーダー(PL)やチームメンバーを配置します。
役職や担当者の名前、人数が明記されていることも大切です。例えば「開発リーダー:田中太郎(1名)」のように、誰がどの立場で、何人いるのかを明確に書きます。また、各役職がどのグループや個人に指示を出すのか、線を引いて管理関係を見せることで、誰が誰へ指示・報告するかがはっきりします。
加えて、ステークホルダーや顧客、サポートスタッフなども漏れなく記載し、それぞれがどのぐらい関与しているのかを示すことが大切です。
悪い体制図のありがちな例
悪い体制図によくあるのは「誰に報告・相談すればよいか分からない」状態です。たとえば、管理者が複数人いるのに線が交差していたり、同じような役割が重複していたり、逆に一部の役割が抜けていたりすると、現場で混乱が生じます。
また、組織図が古いままで変更が反映されていなければ、実際の運用とズレが生じやすく、不信感や混乱の原因になります。文字が多すぎたり、線がごちゃごちゃしていて見づらい図も良くありません。
良い体制図を作成するための設計原則
・指揮命令系統を一本化する
・役割(ロール)は明確に書く
・役職ごとの人数・氏名も記載
・ステークホルダーが分かるように外部も含める
・設計変更や人事異動があれば、すぐに反映する
・図のレイアウトはシンプルかつ見やすく
体制図は、単なる資料ではなくプロジェクトを「動かす」ための設計図です。作成時には上記の原則を守り、読み手の立場に立って分かりやすく整えることが重要です。
次の章では、「主要ロールの役割と責任(R&R)の明確化」について説明します。
主要ロールの役割と責任(R&R)の明確化

主要な役割(ロール)を知る
プロジェクトをスムーズに進めるためには、「誰が」「どこまで責任を持つのか」をはっきりさせることが大切です。この章では、プロジェクト進行でよく登場する主要な役割と、それぞれの責任について具体的に説明します。
プロジェクトマネージャー(PM)の役割
プロジェクトマネージャーは、プロジェクト全体の責任者です。具体的には、スケジュールの管理、予算の調整、人材配置や全体の品質管理など、あらゆる面で全体を見渡します。計画に変更が必要なときは柔軟に修正し、トラブルが起きた際には解決に向けて現場をリードします。また、成果物や進捗のレビュー、上層部や関係者への定期的な報告も担います。
―実例―
進捗が遅れている場合には、PMがすぐに問題点を見つけ、追加のサポート要員を確保するなど迅速に対応します。
プロジェクトリーダー(PL)の役割
プロジェクトリーダーは、実際の現場でチームを動かす役割です。それぞれの担当グループの「現場監督」と考えると分かりやすいでしょう。PLは、メンバーそれぞれの進捗管理や作業指示を出し、計画が予定通り進むよう導きます。問題があれば、PMと相談して調整します。
―実例―
複数チームが動く大型プロジェクトでは、PLが日々の朝会でタスクの進み具合を確認し、優先順位を整理して遅れが出ないよう管理します。
PMOの役割
PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は、PMやPLをサポートする存在です。会議や進捗管理の資料作成、課題やリスクの洗い出し・解決案の整理、関係者との情報共有を行います。ひとことで言うと、「プロジェクト運営の潤滑油」です。PMOは直接その判断を下しませんが、PMやPLがスムーズに仕事を進められるよう全体のサポートを担います。
―実例―
課題が複数ある場合は、PMOが一覧表にまとめて優先順位付けし、全体ミーティングで共有します。
ステークホルダー/顧客/サポートの役割
プロジェクトには、成果に関わるさまざまな関係者が含まれます。これを「ステークホルダー」と呼びます。顧客やクライアント、製品やサービスの利用者だけでなく、バックオフィスやサポート部門も含みます。彼らの要望や期待をしっかり体制に反映し、組織図(体制図)にその位置を明確に示しましょう。
次の章:立ち上げ〜運用の実務フロー(手順)
立ち上げ〜運用の実務フロー(手順)
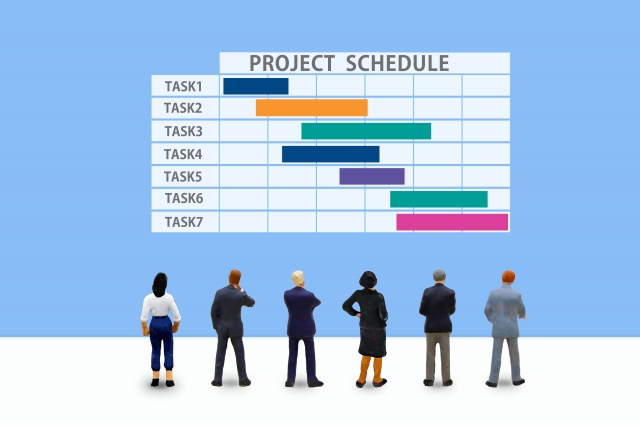
はじめに
プロジェクトを円滑に進めるためには、「実際にどう進めるのか」という具体的な手順を明確にしておくことが欠かせません。この章では、計画スタートから実際の運用、そして必要な体制変更までの流れを、具体例も交えながらご説明します。
1. 計画立案のステップ
まず、プロジェクトマネージャー(PM)が中心となり、プロジェクトの「目標」と「ゴール」を全員にわかりやすく決めます。例えば「新サービスを半年でリリースする」「お客様からの満足度を80%以上に伸ばす」など、具体的で測れるものを設定します。
この時点で、実際にどんな作業(タスク)が必要かを洗い出します。続いて、いつまでに何を終わらせるのかという「スケジュール」も決めましょう。このとき、大切なのがQCD、つまり「品質」「コスト」「期間」のバランスです。チーム全員で相談し、どのポイントを重視するのか合意を取るのがポイントです。
計画したことは「計画書」や「スケジュール表」として文書化し、だれでも見返せるようにします。
2. 体制図・組織図の作成
次に、「どんな人がどんな役割を持つのか」を、わかりやすい図で示します。実際の例としては、表や矢印を使った組織図(体制図)が有効です。例えば、PM一人の下に、リーダー、メンバー、事務担当などを分けて描きます。
この組織図では、指示や相談の流れ(指揮系統)を一本にまとめるのがポイントです。役割や担当範囲も明確に記載しましょう。また、人事異動や体制変更があった場合は、「そのつどすぐに更新する」よう徹底します。
3. 稼働とガバナンス(運用と管理)
プロジェクトが動き始めると、社内報告や会議が必要になります。ここで重要なのは、どのような報告経路(報告ライン)をとるのか、会議体をいつ・どう開くのかを事前に決めておくことです。たとえば、毎週1回の「進捗会議」、月1回の「課題レビュー会議」などを設定する方法があります。
組織構造のタイプや、PM・PMO(プロジェクト管理担当)の役割によって、報告内容や頻度は変わります。組織の実態に合った方法で設計しましょう。
4. 継続的な更新と改善
プロジェクトは計画通りに進むとは限りません。担当者の入れ替えや、方針の変更が発生することもあります。体制図やスケジュールは、変化があれば「すぐ反映する」ことがポイントです。誰がいまどの役割なのか、権限はどう変わったのか、いつでも誰でも確認できる状態を保ちます。
次の章では、「組織構造の選び方:意思決定のスピード・リソース共有・ガバナンスのトレードオフ」についてご紹介します。
組織構造の選び方:意思決定のスピード・リソース共有・ガバナンスのトレードオフ

組織構造には特徴がある
プロジェクトの組織体制は、大きく「機能型」「マトリクス型」「プロジェクト型」に分かれます。それぞれに強みと課題があるため、プロジェクトの目的や状況に合わせた選択が大切です。
機能型:専門性とリソースの共有がしやすい
機能型は、各部門ごとに役割が分かれ、日頃からその分野で知識やリソースを蓄積できます。この体制は、多くの専門家が集まる大きな組織に適しています。例えば「開発部」「営業部」「デザイン部」など、専門性の高い作業を任せやすいです。ただし、意思決定には複数の部門をまたぐ連携が必要な場面が増えるため、時間がかかりやすい傾向があります。また、プロジェクトマネージャー(PM)の指示よりも部門長の方針が優先されやすく、PMの権限が弱まりがちです。
マトリクス型:柔軟だが、調整が重要
マトリクス型は、既存の部門(機能軸)とプロジェクトチーム(目的軸)の両方に所属する形です。各担当者にとって指揮命令系統が2つできるため、より柔軟なリソース配分や全体最適を目指しやすくなります。たとえば、新製品の開発プロジェクトで、技術部および販売部から人材を集めて運営する場合です。しかし役割の重なりや目標の優先度で衝突が発生しやすく、間に立つPMや管理職の調整力が求められます。報告先がふたつになるため混乱も起きやすいですが、うまく機能すればバランスの取れた運営が可能です。
プロジェクト型:スピード重視と集中
プロジェクト型は、専任のメンバーだけでチームを構成し、プロジェクトに集中できる体制です。意思決定が早く、PMの権限が強くなります。たとえば、短期間で成果を求められる新サービス立ち上げや、緊急度が高いシステム移行などに向いています。専任化のため人件費が増える、日常業務との経験共有がしづらいといったデメリットもありますが、スピードや明確な責任体制を重視したい場合に有効です。
トレードオフをどう考えるか
どの型にもメリット・デメリットがあるため、「プロジェクトの規模」「緊急度」「リスク」「専門性」「既存組織の成熟度」といった要素を総合的に見て選びます。例えば、長期的な開発なら機能型、スピード重視ならプロジェクト型、両者のバランスを求めるならマトリクス型、という具合です。また、体制を選んだあとで、PM/PMOの権限の強さや会議などの運用ルール、評価指標などもきちんと設定しましょう。
次の章に記載するタイトル:体制図に具体的に書き入れる内容(チェックリスト)
体制図に具体的に書き入れる内容(チェックリスト)

体制図は、プロジェクトや組織の全体像を一目で把握できるようにまとめる資料です。ここでは、体制図に実際にどのような情報を書き加えればよいのか、そのチェックリストを具体的に解説します。
1. 役職と氏名・人数
最初に明記すべきは、プロジェクト内の主な役職です。例えば「プロジェクトオーナー」「プロジェクトマネージャー(PM)」「リーダー(PL)」「各チームメンバー」「PMO」「サポート担当」など、それぞれ誰が、何人いるのかを分かりやすく記載しましょう。氏名を書くことで責任の所在が明確になります。
具体例:
- PM:山田 太郎(1名)
- PL:佐藤 花子(2名)
- 開発チーム:7名(リスト記載)
- サポート:鈴木 次郎(1名)
2. 指揮命令・エスカレーションの線
役職同士を線でつなぎ、誰が誰に指示を出すのか、問題発生時にどこに報告・相談するのかを図で示します。例えば、PM→PL→チームメンバーの順に矢印を引く形です。エスカレーション(上位報告)経路も明示してください。
3. 意思決定権限レベル
各ポジションごとに決定できる事項を短く記載します。スコープ変更や予算変更の際、最終判断者が誰かを明記すると、混乱を防げます。
具体例:
- 予算変更:PMOとプロジェクトオーナー
- スコープ変更:PMが提案、PMOが承認
4. ステークホルダー配置とコミュニケーションライン
顧客や外部協力者など、関係者がどこに位置づけられるのかを示し、プロジェクト内外の連絡経路も図示します。例えば、顧客窓口→PM経由→開発チームという流れです。
5. チーム構成と会議体対応
チームの組み方(所属グループごとか、役割横断か、専任か)に応じて、どの会議に誰が参加するかも記載すると運営がスムーズです。
6. 変更管理のための基本事項
体制図には、作成日や最終更新日、版数、有効期間を必ず記載しましょう。これにより、古い情報のまま行動するリスクを小さくできます。
次の章に記載するタイトル:失敗パターンと回避策
失敗パターンと回避策

プロジェクト体制の構築や運用には、多くの落とし穴があります。よく見られる失敗例と、その回避方法について解説します。
1. PM権限と実際の責任が一致しない問題
名ばかりプロジェクトマネージャー(PM)の現象が、この分野で頻繁に発生します。例えば、PMにプロジェクト推進の責任があるものの、実際の意思決定権は持っていないケースです。これでは責任と権限がミスマッチとなり、物事が前に進みません。
回避策: 体制図や関連ドキュメントには、意思決定権限を明確に記載しましょう。また、会議体の中で、その裏付けがとれるように会議の目的や意思決定の流れを書き出して全員が理解できる形にすることが必要です。
2. マトリクス型組織の二重指揮による混乱
マトリクス型組織では複数の上司を持つことになりやすく、指示系統が重複しがちです。例えば、営業部と開発部のそれぞれから矛盾した指示がくる場合、現場は戸惑ってしまいます。
回避策: 優先順位の決定者が誰なのか、また紛争が生じた場合の解決フローをあらかじめ決めて、体制図や業務マニュアルに明文化することが不可欠です。
3. ステークホルダーの漏れや配置不備
プロジェクト実行時、顧客や外部ベンダー、法務や経理といった他部門を体制に入れ忘れることがあります。この結果、重要な意見が反映されなかったり、必要な調整が遅れることが起こります。
回避策: 全ての関係者を体制図に入れる、チェックリストで抜けがないかあらためて確認しましょう。顧客や外部のパートナーも明示的に枠組みに入れることで、連携の質が向上します。
4. 体制の陳腐化
一度作った体制図が古くなり、現実と乖離してしまうことも失敗原因です。組織や担当者の変更が反映されなければ、誰に頼ればよいか分からなくなります。
回避策: バージョン管理を行い、体制図の更新責任者を必ず設定してください。変更があった際は速やかに最新版へ反映し、関係者にも通知しましょう。
次の章に記載するタイトル:PM/PL/PMOの違いを短く整理
PM/PL/PMOの違いを短く整理

プロジェクトの体制でよく耳にする「PM」「PL」「PMO」には、それぞれ異なる役割と責任があります。ここでは、日常的な言葉で端的に説明します。
PM(プロジェクトマネージャー)
PMはプロジェクト全体の責任者です。プロジェクトが目指すゴールを決め、その達成のために計画を立てます。進捗や予算を管理し、トラブルが起きれば解決案を考えます。また、社内外の関係者と調整や交渉も行います。たとえば、新しいシステム導入プロジェクトなら、PMが「いつ・誰が・何をするか」という全体計画を作り、軸となって動きます。
PL(プロジェクトリーダー)
PLはチームの実働リーダーです。実際に手を動かす現場をまとめ、メンバーに指示を出し、手順や作業の進め方を細かく見守ります。進捗の遅れがあればフォローし、技術的な問題があれば解決策を考えるのもPLの役目です。たとえば、開発チームのPLはメンバーのタスクを細かく管理し、日々の問題点を拾い上げます。
PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)
PMOは支援に特化した組織または担当者です。プロジェクト運営の手順やルールを決めたり、複数のプロジェクトの進捗を横断して管理したりします。PMやPLが本来の仕事に集中できるように資料作成を助けたり、全体の標準化を進めたりして、プロジェクトの成功確率を高める役割です。具体的には、定例会議の運営や、プロジェクト共通の資料作成ルールなどを整え支援します。
次の章:プロジェクト組織(Project Organization)の基本理解
プロジェクト組織(Project Organization)の基本理解

プロジェクト組織とは何か
プロジェクト組織とは、明確な目標や成果物を達成するために一時的に構成される組織形態です。日常業務を扱う通常の部署とは違い、開始と終了が明確に定められており、その目的が達成されれば組織自体も解散します。たとえば、新しい商品を開発する、システムを導入する、大規模イベントを計画・運営するなどがプロジェクト組織の典型例です。
特徴:柔軟性とスピード
プロジェクト組織の最大の特徴は、状況や課題に合わせた柔軟な人員配置や、目標達成に向けた迅速な意思決定ができる点です。日々のルーチンワークに縛られないため、短期間で成果を出す必要がある活動で特に優れた効果を発揮します。例えば、通常の部署から専門スキルを持つ人材を選抜してチームを作ることで、多角的に課題へ取り組むことが可能です。
体制図とその整備の重要性
プロジェクト組織では、「誰が・何を・どこまで」責任を持つのかを明確にすることが重要です。そのために体制図(組織図)を作成します。体制図には、プロジェクトリーダーやメンバー、必要なサポート役の配置が記載され、それぞれの役割と責任がひと目で分かるようになっています。これにより、役割の重複や抜け漏れ、意思決定の遅れなどを防ぎ、スムーズな連携が実現できます。
権限と責務の明確化
プロジェクト組織は短期間で動くからこそ、権限と責務の曖昧さが現場の混乱や失敗に直結します。「リーダーがどこまで決められるのか」「メンバーは自主的に動ける範囲はどこまでか」をあらかじめ決めて明示することで、各自が自信を持って役割を果たせるようになります。これは、体制図の整備とあわせて計画段階で準備しておくべき大切なポイントです。
次の章に記載するタイトル:実務テンプレート(文章での構成例)
実務テンプレート(文章での構成例)

プロジェクト組織図や体制表を文書でまとめる際の標準的なテンプレート構成についてご紹介します。以下のような項目を押さえておくことで、誰がどの立場で参画し、どこに報告・相談すべきかが一目で分かるようになります。
1. 基本情報(ヘッダー)
プロジェクトの冒頭には、必ず以下の内容を記載します。
- プロジェクト名
- 版数(バージョン番号)と発行日
- 作成者(プロジェクトマネージャー)
- 承認者(最終的な責任者、一般的にプロジェクトオーナーやスポンサー)
この部分を明確にすることで、文書の管理やバージョン管理がしやすくなります。
2. 体制図(本文上段)
上部には、プロジェクトの全体像が俯瞰できるよう、主な役割をレイヤーごとで配置します。
- 最上段:プロジェクトオーナー → PM(プロジェクトマネージャー) → PMO(事務局や進行管理担当)
- その下段:各領域のPL(プロジェクトリーダー)を配置(例:アプリ開発、インフラ、品質保証(QA)など)
- さらに下段:各機能ごとの主要メンバー(担当者名と人数)を明記します。
3. 関連部門・主要ステークホルダー(本文右側)
体制図の右側には、以下のような社内外の重要関係者を配置します。
- 顧客担当者、法務、調達、カスタマーサポート(CS)、外部パートナーなど
- それぞれの連絡ルート(誰が誰に報告/相談するのか)を矢印や線で示します
4. 会議体・権限・エスカレーション(フッター)
最後に、体制図の下部には以下の要素を記載します。
- 定例会議体(例:週次の進捗会議、課題審議、変更管理会議など)
- 意思決定権限表(予算やリスク等について、どこまで誰が判断できるかの「閾値」を具体的に)
- エスカレーション経路(問題やリスクが発生した場合、どの順序でどこに報告・相談するのか)
5. 補足・注意書き
- 役職名だけでなく、必ず担当者の氏名や人数を記載します。
- 文書下部には更新履歴欄を設け、いつどのような修正・追加を行ったかを記録します。
実際のプロジェクトでは、上記テンプレートを利用することで、組織の見通しや情報伝達が格段にスムーズになります。
次の章に記載するタイトル:立ち上げ時に合わせて設計すべき運用要素
立ち上げ時に合わせて設計すべき運用要素

プロジェクト組織の立ち上げ時は、単に人を集めるだけでなく、日々の運用を円滑に進めるためのルールや仕組みを設計することが重要です。この章では、成功する組織運営のために最初に考えておきたい運用要素について解説します。
報告リズム・フォーマットの決め方
仕事の進み具合や課題の発見・共有は、組織の要です。「毎週◯曜日に進捗メールを送る」「月1回ステータス会議を実施する」など報告のリズムを決めましょう。
さらに、伝える内容についてもルール化します。例えば、進捗状況、重要KPI(売上や達成率など目標数値)、また課題台帳(問題点・担当者・対応状況の一覧)をシンプルなフォーマットでまとめ、チームや関係者がすぐに見られる状態が望ましいです。提出先も明確に決めておきましょう。
変更管理のルール設定
プロジェクトは途中で計画が変わる場合もよくあります。「変更したい内容を誰が起票するか」「誰が承認し、どの段階でPMO(プロジェクト管理担当)のレビューを挟むか」などプロセスを定めておくと混乱が防げます。例えば、担当者が変更依頼書を作成し、リーダー承認後にPMOレビュー、といった流れです。
リスク・課題レビューの方法
トラブルやリスクの洗い出しは継続的に行う必要があります。「週1回の会議で全体共有する」「重大度・影響度が高い場合は即時報告」などしきい値(基準)も設定しておくと、素早い対応につながります。
ステークホルダーと情報共有の計画
関係者ごとに必要な情報の種類やタイミング、伝える手段(メール、会議、チャットなど)も整理が不可欠です。「月1回、経営層には概要資料を提出」「日常的な連絡はグループチャット」など、誰に・何を・いつ・どうやって伝えるかをあらかじめ計画に含めましょう。
こうした運用要素を立ち上げ時に設計し、早めに全員で共有しておくことで混乱や手戻りを減らせます。
次の章に記載するタイトル:組織成熟に合わせたスケール戦略
組織成熟に合わせたスケール戦略

組織やプロジェクトが成長するにつれて、最適な体制や管理方法も変わります。どれだけの規模か、どれほどのリスクがあるのか、どのくらいのスピードで進める必要があるのかに応じて、体制設計のアプローチを柔軟に調整しましょう。
小規模・低リスクのケース
まだ人数が少なく、案件も限定的な段階では、「機能型」組織で十分なことが多いです。各担当が自分の専門領域を持ち寄り、PMOやPLも軽めの体制で対応できます。例えば、5名規模のチームでエンジニア・デザイナー・企画担当がそれぞれ役割を明確にし、PLが進捗や問題を適宜管理する形です。
中規模・中リスクのケース
人数が増えて複数の案件を並行管理する場合、「弱マトリクス」や「平衡マトリクス」型の導入がおすすめです。これにより、リソースの最適配分がしやすくなり、PMOによる業務プロセスの標準化や情報共有も進みます。たとえば20〜30人規模になると、エンジニア部門やデザインチームの横断調整が必要になります。PMOの担当者が週次会議や共通ルールを設け、プロジェクト間の連携を強化する形です。
大規模・高リスク・期限厳守のケース
開発規模が大きく、納期や品質リスクが高い場合は「プロジェクト型」体制を強化します。PM(プロジェクトマネージャー)の権限を高め、リーダー陣も専任化します。専任のPMOが進捗・課題・予算を常時チェックし、変化や遅延に迅速対処できる体制が求められます。100名以上が関わる大きなプロジェクト、社会的責任が大きい案件などが該当します。
このように、組織のフェーズやリスクレベルによってアプローチを調整することで、無理なくスムーズに事業を拡大できます。
次の章に記載するタイトル:参考の要点の再掲
参考の要点の再掲

この章では、これまで解説してきたプロジェクト組織体制設計のポイントを振り返ります。
体制図・組織図で何を明示するか
体制図には「役職」「人数」「氏名」などを具体的に書き、それぞれの担当範囲を線でつなぎます。これにより、誰が何を決める立場なのか、判断や相談の流れが一目でわかります。実際の現場では、体制図にミスや曖昧さがあると、トラブルの元になります。
組織の類型の理解
プロジェクト組織には、機能型・マトリクス型・プロジェクト型の3タイプがあります。それぞれに向き・不向きがあり、意思決定の速さや専門性の活かし方も異なります。例えば、スピード重視ならプロジェクト型、専門知識を横断的に活用したいならマトリクス型が効果的です。
PM/PL/PMOの役割の明確化
PM(プロジェクトマネージャー)、PL(プロジェクトリーダー)、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は役割が似ていて混同しがちです。PMは責任者、PLは現場リーダー的な立場、PMOは現場を支える事務局や横断支援の役割になります。プロジェクトの成功には、PMOによる全体最適の視点が欠かせません。
会議体や業務の流れの設計
体制設計は単に図を描くだけで終わりません。実際には「計画→体制図作成→会議体と指標・ルールの構築→運用スタート→状況に応じた見直し」という流れを段階ごとに踏みます。これに沿って進めれば、トラブル発生時もすぐに見直し・調整ができます。
これらを押さえることで、「何を決める体制なのか」「どこに問題が生じやすいか」といったポイントに迷わず対応できるようになります。読者の皆さんも、ぜひ自分の現場に合った体制づくりに役立ててみてください。