目次
この記事でわかること
- PMBOKとは何か
世界標準の「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」の役割と基本概念。 - 5つのプロセス群と10の知識エリア
プロジェクトの流れ(立ち上げ~終結)と、管理すべき領域のチェックリスト。 - 第6版と第7版の違い
プロセス中心から原則(プリンシプル)中心へ変化した背景とポイント。 - 現場での活かし方
PM/PMOが使うベストプラクティス(ベースライン管理、変更統制、可視化、ステークホルダー対応など)。 - 実践につなげる学び方
小規模プロジェクトからの導入、テンプレート活用、数値管理や振り返りによるスキルアップ方法。
PMBOKとは何か—プロジェクトマネジメントの「標準ガイド」を短時間で把握する

PMBOKはプロジェクト管理の“教科書”
PMBOK(ピンボック)は、英語で「Project Management Body of Knowledge」と言い、日本語では「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」と呼ばれます。簡単にいえば、仕事や事業プロジェクトを計画し、実行し、完了させるためのやり方やコツを、世界中で多くの人が共有できるようにまとめた本です。このガイドは、アメリカのPMI(プロジェクトマネジメント協会)が作成しており、初版が1987年に登場して以来、多くの企業や現場で標準のやり方として支持されています。
どんな内容なのか
PMBOKには、「プロジェクトをスムーズに進めるにはどんな手順が必要か」「どこに注意すれば失敗を防げるか」といった考え方や方法が、体系的にまとめられています。実際には、タスクの洗い出しやスケジュール作り、進捗の確認、問題発生時の対応など、現場で役立つ項目が盛りこまれています。
たとえば、「旅行の幹事」を例に考えると、出発前の計画(誰がどこに行くか、予算はいくらか)、当日の運営(移動手段や集合時間の調整)、トラブル対応(交通遅延や追加の出費)など、すべての順序や注意点をガイドブックにまとめたもの——それがPMBOKのイメージです。
どう使われているのか
PMBOKは、プロジェクト管理の基礎を学ぶ際の定番ツールです。世界中の多くの会社が新人研修や社内認定に使い、プロジェクトマネージャー資格(PMP)取得にもこの内容が重視されています。特定の業界にしばられない幅広い内容なので、IT、建設、製造など、どんな分野でも活用できます。
変化し続けるガイド
PMBOKは2021年現在、第7版が最新版です。これまで数年ごとに改訂を重ね、時代に合わせた内容へ進化しています。初心者の方は、まず第6版の「プロセス群と知識エリア」で全体像をつかむのが無理なく始められる方法です。次に第7版との差や新しい考え方を知ることで、現場での応用力が高まります。
次の章では、「PMBOKの骨格—5つのプロセス群でプロジェクトの流れを掴む」についてご説明します。
PMBOKの骨格—5つのプロセス群でプロジェクトの流れを掴む

プロジェクトマネジメントをスムーズに進めるためには、全体の流れをつかむことが重要です。PMBOK(ピンボック)は、プロジェクトの進行を5つのプロセス群に分けて体系立てています。これにより、どの段階で何を行うべきかが明確になります。それぞれのプロセス群の役割と、どのようにつながっているのかを具体例を交えて紹介します。
立ち上げ
プロジェクトが始まるときには、まず「立ち上げ」プロセス群があります。ここでは、プロジェクトそのものが必要かどうかを確認し、正式な承認を得ます。例えば新しい商品開発なら、「本当にこの商品を作る価値があるか?」「誰が関わるのか?」といったことを明確にします。ステークホルダー(利害関係者)を識別するのもこの段階です。
計画
正式承認後は「計画」プロセス群に移ります。プロジェクトで何を、どのような順番で、どのくらいのリソースやお金を使って進めるのかを決めていきます。例えばイベントの運営なら、日程、予算、必要なスタッフや備品などを細かく決めていくイメージです。計画がきちんとできていないと、後でトラブルになりやすいので、この段階が非常に重要です。
実行
「実行」プロセス群では、計画に基づいて実際の作業を進めます。成果物を作ったり、進捗を管理したりします。都度、作業内容やパフォーマンス指標を見直すことで、計画通りに進んでいるかを確認できます。例えばWebサイト制作であれば、ページを作成しながら納期や品質を意識して進めていきます。
監視・コントロール
作業が進む中で、「監視・コントロール」プロセス群が重要になります。進捗状況をチェックし、当初の計画からズレがあれば早めに対応します。例えば予算オーバーや納期遅れの兆しがあれば、軌道修正を行うのです。小さなズレも見逃さず、現場に反映していくことで、プロジェクトを正常な状態に保ちます。
終結
すべての作業が終わり、成果を受け入れる段階が「終結」プロセス群です。この段階では、完成した成果物が期待通りかどうかを最終確認します。また、プロジェクトを振り返り、得られた学びを他のプロジェクトへ引き継ぐことも大切です。正式な終了手続きを行うことで、関係者への説明責任も果たせます。
5つのプロセス群は循環する
この5つのプロセス群は直線的ではなく、状況に応じて繰り返し行われます。たとえば、途中で計画に修正が必要になれば、「計画」「実行」「監視・コントロール」を何度も回すことがあります。また、変更が発生した場合でも、5つのプロセス群内で適切に管理し、整合性を維持できます。
次の章では、具体的に何を管理するかを整理する「10の知識エリア」についてご紹介します。
10の知識エリア—何を管理すべきかのチェックリスト

どんなプロジェクトでも「何を管理するか」が明確でなければ、うまくいきません。PMBOKはこの「何を管理するか」を10の知識エリア(テーマ分野)で示しており、これは管理のためのチェックリストにもなります。
1. 統合マネジメント
全体をまとめる役割です。たとえば、プロジェクトの最初に「こう進めます」というプロジェクト憲章を作成したり、途中で起きる様々な変更を、関係者に説明し同意をとったうえで統合的に管理します。会社でいえば「司令塔」のような存在です。
2. スコープマネジメント
「どこまでやるか」「何をやるか」を明確にします。顧客や関係者から要件を集めてリスト化し、それを細かく分解(WBS:作業分解構成図)します。「やらなくていいこと」が増えやすいので、境界線も確認しながら進める必要があります。
3. スケジュールマネジメント
仕事の流れや順番、期間を管理します。各作業(アクティビティ)を並べて「どこが遅れると全部止まるか(クリティカルパス)」や「どこで作業を同時並行できるか」を見極め、逆に無理が出そうなときはスケジュールの組み直し(クラッシングやファストトラッキング)も必須です。
4. コストマネジメント
予算配分や使いすぎの防止が目的です。計画段階で費用を見積もり、進捗ごとに実際の支出と照らし合わせます(EVM:出来高管理)。予算内で収めるためには、小まめなコストチェックが求められます。
5. 品質マネジメント
「でき上がったものが約束通りか」を管理します。仕様に合っているかどうかの確認や、工程ごとの見直し(監査)も含まれます。たとえば、できあがったシステムをお客様がテストする場面も、このマネジメント領域です。
6. リソースマネジメント
人・モノ・設備をどう活かすかを考えます。チームの編成や、誰にどの仕事を任せるのか、労働時間や人数をうまく割り当てるのもリソースマネジメントの役割です。チームワークの強化や負荷の偏り調整にもつながります。
7. コミュニケーションマネジメント
関係者に「どの情報を・いつ・どのように伝えるか」を計画し、報告や連絡がスムーズに流れるようにします。たとえば、お客様には毎週進捗レポートをメールで送り、チーム内では日次でミーティングを行うなど、情報の流れを意識します。
8. リスクマネジメント
「悪いことが起きる前に」準備します。失敗が見えたときに慌てるのではなく、リスクを事前に想定し、起こりそうなことへ対応計画を用意します。リスクの洗い出しや、影響度の評価、発生時の対応策決定などが含まれます。
9. 調達マネジメント
他社や外部パートナーとの付き合い方を管理します。必要な作業やサービスを外部に発注する際の契約内容やベンダーとの調整、納品物の受入れチェックなども担当範囲です。
10. ステークホルダーマネジメント
プロジェクトに影響する全ての人を洗い出し、それぞれの期待や要望を整理します。「誰がこのプロジェクトから何を期待しているのか」「誰にどう協力してほしいか」を明確にし、関わる人たちとの調整を行います。
この10の知識エリアをおさえておけば、どんなプロジェクトでも「管理すべきこと」を見落としにくくなります。
次の章に記載するタイトル:第6版と第7版の違い—プロセス重視からプリンシプル重視へ
第6版と第7版の違い—プロセス重視からプリンシプル重視へ

プロセス中心からプリンシプル中心への変化
PMBOKガイドは、時代や現場のニーズに合わせて進化を続けています。第6版までは「5つのプロセス群」と「10の知識エリア」を組み合わせて、プロジェクトを上手に管理する手順が中心にありました。たとえば、「計画」や「実行」といったプロセスごとに、やるべきことを細かく分解して記述していました。このアプローチは、役割分担や進捗管理が明確で、特に初心者が全体像をつかむのに適しています。
一方、第7版では考え方が大きく変わりました。決まった手順(プロセス)よりも、「原則(プリンシプル)」を重視するスタイルに切り替わったのです。たとえば、「関係者との協調を大切にする」「価値を中心に置く」といった普遍的な考え方を示し、それぞれの現場にあわせて柔軟に対応できるようになっています。
なぜこの変化が起きたのか
近年のプロジェクトは、分野も規模も多様化しています。そのため、どんな仕事にも全く同じ手順が合うとは限りません。さらにITやアジャイル開発、リモートワークなど、従来の「計画通りに進める」手法だけでは対応しきれない現場が増えています。このため、第7版では具体的な手順より「プロジェクトの価値を高める考え方」や「状況に応じて選ぶ柔軟性」を重視しました。
実際の現場での使い分け
全体像をつかむには、第6版の枠組み(5プロセス群×10知識エリア)が今でも役立ちます。新しいプロジェクトを始めるときや、進め方に迷ったときは、第6版の体系的な流れが頼りになります。その一方、第7版の原則を参考にすることで、「臨機応変な判断」や「価値を意識したマネジメント」がしやすくなります。例えば、イレギュラーな事態や働き方の変化にも、柔軟に対応できるのがポイントです。
次は「PMBOKを現場で活かす—PM/PMOのベストプラクティス」についてご説明します。
PMBOKを現場で活かす—PM/PMOのベストプラクティス

1. ベースラインを明確にしてぶれを防ぐ
プロジェクトが混乱しないためには、最初に"どこまでやるか(スコープ)"、"いつまでに終わらせるか(スケジュール)"、"いくらまで使えるか(コスト)"の3つをはっきり決めておくことが大切です。この基準を“ベースライン”と呼びます。たとえば、建物を建てるなら「2階建て(スコープ)」「8月末までに完成(スケジュール)」「1千万円以内(コスト)」という具合です。この基準がぶれると、後で大きな手戻りになってしまうため、最初に全員で共有しましょう。
2. 変更はしっかり統制—統合変更管理
計画の途中で「やっぱりここを変えたい」という話が出てくるのは珍しくありません。ただし、何でも簡単に変えてしまうと混乱が生じます。そこで役立つのがPMBOKでいう“統合変更管理”です。たとえば「仕様を一部変更したい」という要望があれば、その影響(コストや納期など)を分かりやすく整理してから、チーム全体でしっかり合意のうえで進めます。
3. 見える化のコツ—指標・マイルストーン・課題管理
進捗がうまくいっているかどうかを数字や一覧で"見える化"することも重要です。たとえば“SPI(進捗指標)”や“CPI(コスト指標)”といった数値で遅れやコストオーバーを早めに察知できます。さらに、プロジェクトの区切り=“マイルストーン”を設定して、途中経過をみんなで確認しましょう。また、問題(課題)やリスクも一覧にして、誰がいつまでにどんな対応を取るか決めて記録するのがコツです。毎週の定例ミーティングなどでこれらをチェックして、小さなズレのうちに修正することが“早期是正”につながります。
4. 利害関係者(ステークホルダー)とのコミュニケーション
プロジェクトには多くの関係者がかかわります。最初に「誰がどんなことに関心があるか」「どんな情報が必要か」などをリストアップし、関係者ごとに伝えるべきことやタイミングを決めましょう。これを“コミュニケーション計画”と呼びます。途中で期待と現実にずれが生じないように、進捗状況など定期的に説明・相談し、信頼を保つ努力が大切です。
5. 予測型とアジャイル—領域に応じた使い分け
変化の少ない部分(たとえば建物の基礎工事など)は、きっちり計画を立てて進めたほうが効果的です。一方、仕様が変わりやすい部分(たとえばデザインや新機能)は、小さく作って早く検証(=アジャイル)を何度もくり返すと効果的です。プロジェクトごとに部分的にやり方を選び、うまく組み合わせて活用しましょう。
6. PMOの存在意義—仕組み化とナレッジ共有
組織全体でプロジェクト運営を底上げしたいなら、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の出番です。具体的には、良いひな形(テンプレート)や合格基準(ゲート)、共通の指標(メトリクス)をそろえて、みんなが迷わないようにします。また、過去プロジェクトの体験談や反省点(レトロスペクティブ)をデータベースに残し、次に生かせるようにナレッジを蓄積していきましょう。
次の章に記載するタイトル:他手法との関係—WBS/PERT/CCPM/PPMとPMBOKの使い分け
他手法との関係—WBS/PERT/CCPM/PPMとPMBOKの使い分け

PMBOKと他手法の関係
PMBOKは、プロジェクトマネジメントの全体像や共通的な考え方を示した枠組みです。この中には「これを必ず使いなさい」という指定は少なく、実際の進め方は状況に応じて道具(手法)を選ぶイメージです。ここで登場するWBS、PERT、CCPM、PPMは、それぞれ特徴のある「道具箱のツール」と考えると理解しやすいでしょう。
WBS:プロジェクトの分解に
WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクトの作業内容を細かく分解する技法です。例えば「新製品の開発プロジェクト」なら、設計・製造・テスト・リリースと大きな仕事を順に分け、それぞれをさらに具体的な作業に細分化します。WBSの目的は、「抜け漏れなくやるべきことを整理すること」です。PMBOKの知識エリア「スコープ管理」において中心的な技法となっています。
PERT:不確実な所要時間の見積もりに
PERT(Program Evaluation and Review Technique)は、各作業の所要時間がはっきりしない場合に活用する見積もり技法です。例えば「楽観的・最頻・悲観的」という3つの見積もりを使い、より現実に近いスケジュールを算出します。不確実性の高い研究開発や初めての業務など、見積もりが難しい場面で特に役立ちます。PMBOKの「スケジュール管理」で推奨される手法のひとつです。
CCPM:バッファを管理して納期を守る
CCPM(Critical Chain Project Management)は、工程ごとの「余裕(バッファ)」に注目した進捗管理の手法です。「どうしても遅れがちなタスク」や「リソースの競合」があるプロジェクトで、全体の遅延を防止するためにバッファ配置とモニタリングを行います。従来のスケジュール管理が苦手なリソース調整にも強みがあり、PMBOKでは応用的なスケジューリング手法の一つとされています。
PPM:複数プロジェクトの選定やバランスに
PPM(Project Portfolio Management)は、企業などで複数のプロジェクトを同時に管理するときの考え方です。どのプロジェクトを優先するか、全体として投資のバランスを取るかなど、経営的な視点で判断します。PMBOKは「1つのプロジェクト」を軸にしていますが、PPMはそれらを束ねて最適化を目指す際に有効な技法です。
技法の使い分けポイント
それぞれの手法は「どの課題に対して使うか」で選びます。
- WBS:プロジェクト内容を整理したい時
- PERT:所要時間の予測が難しい時
- CCPM:遅延やリソース競合が気になる時
- PPM:プロジェクトが複数並行する時
これらをPMBOKの枠組みの中で「必要に応じて組み合わせて使う」という考え方を身につけると、現場での活用度が一気に高まります。
次の章に記載するタイトル:「プロジェクトが思い通りに進まない」を減らす—10の観点からの実践チェック
「プロジェクトが思い通りに進まない」を減らす—10の観点からの実践チェック

プロジェクトの進行に悩んだら立ち返るべき10の視点
プロジェクトは計画通りに進まないことがよくあります。その原因の多くは、重要な観点が抜け落ちたり見過ごされたりすることにあります。ここでは、プロジェクトを推進するうえでチェックすると良い10の観点をご紹介します。
- 範囲:やるべきこと・やらないことが明確か(例:要件リストやWBSで整理)
- スケジュール:納期や各工程の期限が無理なく設定されているか(例:ガントチャートの作成)
- コスト:必要なお金を事前に見積もり、定期的に確認しているか(例:コスト見積もり表)
- 品質:成果物やサービスに対する品質目標が決まり、確認方法も決まっているか(例:品質管理表)
- 資源:人やモノなど必要な資源が足りており、アサイン漏れがないか(例:担当者リスト)
- コミュニケーション:誰が誰に何を伝えるか整理できているか(例:連絡体制図や報告書フォーマット)
- リスク:想定できる問題点を洗い出して対策を準備しているか(例:リスク登録簿)
- 調達:外注や調達が必要なものを明確にし、契約や納期を管理しているか(例:調達台帳)
- ステークホルダー:関係者全員の立場や要望、影響度を整理して対応しているか(例:ステークホルダー一覧)
- 統合:上記すべての項目をまとめ、バラバラにならないよう統制できているか(例:プロジェクト憲章)
テンプレート活用と共通言語化が導入のコツ
上記10の観点は、どのプロジェクトにも共通して必要なものです。しかし、実際には各チームや担当者ごとに言い方ややり方が異なり、混乱が起こることも少なくありません。
このような混乱を防ぐには、用語や成果物のテンプレートを用意して共通言語にすることが有効です。たとえば「WBS(作業分解図)」や「リスク登録簿」などのひな型を使い回し、みんなが同じ意味で使えるようにします。
結果として、誰が見てもどのタイミングで何を確認すれば良いかが明確になり、プロジェクト運営の安定につながります。
次の章に記載するタイトル:入門者向けの最短ルート—まずはここから着手
入門者向けの最短ルート—まずはここから着手
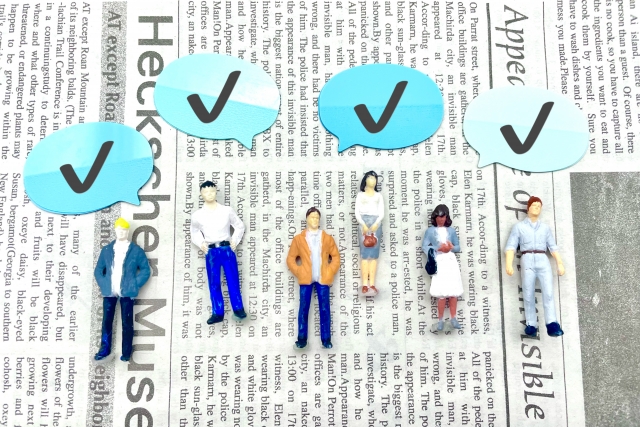
1. 基本用語をざっくり覚える
まずはPMBOKの「5つのプロセス群」と「10の知識エリア」という骨組みだけでも理解しましょう。たとえば「立ち上げ」「計画」などプロジェクトの流れと、「品質管理」「コミュニケーション」など管理ポイントの意味をざっくり押さえます。
2. 小さいプロジェクトでテンプレートを活用
学んだ用語や流れに基づいて、いきなり大きな仕事に使うのではなく、まずは社内の小さなプロジェクトやチームの仕事に、PMBOK風の計画書・進捗表などのテンプレート(ひな型)を試してみましょう。段階的に慣れるのがコツです。
3. 第7版で「柔軟な考え方」を追加
最初は「手順」中心でも、次は第7版の「原則」や「テーラリング」(状況に合わせて工夫する)に目を向けてみてください。決まった型から、だんだん自分の現場に合うやり方を増やしていきます。
4. 数値管理にも挑戦
PMBOKではEVM(アーンド・バリュー・マネジメント)のような進捗やコストを数字で管理する方法も紹介されています。簡単な指標で構いませんので、表やグラフで「予定通り進んでいるか」をチェックする習慣をつけてみてください。
5. 共通フレームで振り返りも積極的に
社内研修やガイドラインなど、複数人でプロジェクトを進める共通の考え方・用語があると、仕事の属人化も防げます。最後に、振り返りやプロジェクトレビューで「どこがうまくいき、どこを直せばいいか」を定期的に話し合うことで、継続的にスキルを高められます。
次の章に記載するタイトル: 追加の補足情報(実務Tips)
追加の補足情報(実務Tips)
代表的な成果物テンプレートのご紹介
プロジェクト管理の現場では、一定のフォーマットに沿って成果物を作成することが役立ちます。代表的なテンプレート例を挙げます。
- プロジェクト憲章:プロジェクトの目的や目標、主な関係者を明記した文書です。冒頭で「このプロジェクトはなぜ必要か?」を短くまとめると、他のメンバーにも伝わりやすくなります。
- WBS辞書:作業分解図(WBS)で細分化した各作業の内容や責任者、成果基準を一覧でまとめます。作業内容が曖昧なまま進む事態を防げます。
- スケジュールネットワーク図:作業の順序や依存関係を図にしたものです。Excelやホワイトボードで矢印を書くだけでも充分役立ちます。
- リスク登録簿:起こりうるトラブルと、その対応策を一覧化します。「何がリスクか」「誰が対処するか」を明確にするのがポイントです。
- 変更要求フォーム:要件や計画に修正が必要な場合、記録・管理するための用紙です。内容・理由・影響範囲を記入する欄を用意します。
- コミュニケーション計画:誰が誰に、どのタイミングで、どんな手段で情報を伝えるのかをまとめた材料です。メール、週次ミーティング、チャットなども具体的に記載しましょう。
- 品質計画書:成果物の品質基準や検証手順を整理します。一度作ると、レビューやテスト時の基準が明確になり便利です。
- 調達計画書:外部資源の購入や委託の方針をまとめたものです。必要な場合は、見積先や発注プロセス、納期条件などを明記してください。
よく使われるプロジェクトメトリクス(指標)
進捗管理やコスト予測には、数字を使った客観的な指標も活用します。代表的な例をいくつかご紹介します。
- SPI/CPI(スケジュール・コスト指標):本来の予定と実際を比べて「進み具合」や「コスト効率」を測る指標です。数値が1より高ければ計画より順調、低ければ要注意のサインとなります。
- 予測完了日/予測コスト:現状の進み具合から、プロジェクトがいつ終わりそうか・最終的にいくらかかりそうかを予測します。
- バーンダウン・バーンアップチャート:アジャイル開発と組み合わせる際に使うグラフ形式の指標です。残作業量や達成度を視覚的に確認できます。
実務でよくある「失敗パターン」と注意
プロジェクトがうまくいかない背景には、いくつか典型的な要因があります。
- スコープ(成果の範囲)が不明確なまま開始してしまう:何をゴールとするか決めないまま走り出すと、手戻りや納期遅延につながります。事前に「やること・やらないこと」の線引きを。
- 利害関係者(お客様や関係部門)の期待値をそろえない:「お互い分かっているつもり」がすれ違いのもとです。初期段階での合意形成や、こまめな確認が肝心です。
- 変更管理(計画変更時の記録・合意)が形骸化する:つい口頭だけで済ませがちですが、後で「言った・言わない」で混乱します。簡単でもフォームや記録に残す習慣を。
- 状況の可視化が弱い:進捗や課題が隠れていると、問題が深刻化しやすいです。毎週、簡単なレポートやグラフで現状を共有するとトラブルを早期に発見できます。
これらの実務Tipsを押さえれば、PMBOKを活用したプロジェクト管理がより実践的に、現場に根付きやすくなります。プロジェクト運営を円滑に進めるヒントとして、ぜひご活用ください。