目次
- はじめに:なぜ手法選定が重要か
- この記事でわかること
- 第1章 PMBOK:国際標準の知識体系
- 第2章 ガントチャート:タイムラインと依存関係の可視化
- 第3章 CCPM(クリティカルチェーン):所要バッファで遅延を制御
- 第4章 PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)
- 第5章 P2M(Project & Program Management)
- 第6章 スクラム:アジャイルの代表的フレーム
- 第7章 ウォーターフォール:段階的に完了させる計画駆動
- 第8章 カンバン:フロー最適化の可視化ボード
- 第9章 手法の選び方:タイプ別マッピング
- 第10章 すぐに使える実務テンプレの流れ
- 第11章 ツール活用のヒント
- 第12章 代表手法の比較早見表
- 補足:よくある誤解と注意点
はじめに:なぜ手法選定が重要か
プロジェクト管理と一口に言っても、実はさまざまな手法や考え方があります。例えば、アジャイルやウォーターフォール、スクラム、リーン、カンバンなどの言葉を耳にしたことはありませんか?それぞれの手法には特徴があり、すべてのプロジェクトに同じ方法が向いているわけではありません。プロジェクトの内容や目的、規模、関わる人々によって、最適な方法を選ぶことがプロジェクト成功の重要なポイントです。
また、「プロジェクト管理」と一言で言っても、その中身はさまざまなレイヤー(層)に分かれています。知識体系、計画を立てる技法、実際の開発の進め方、複数プロジェクトをまとめる考え方など、役割ごとに使うべき手段があります。例えば、PMBOKやP2Mは、プロジェクト全体の知識や大枠を整理したフレームワークです。それに対して、WBSやPERT、ガントチャート、CCPMといった方法は、計画や進捗の管理に役立つ技法です。そして、アジャイルやウォーターフォール、スクラムは、日々どのように開発や作業を進めるかを示す方法です。さらに、複数のプロジェクトを同時に扱うなら、ポートフォリオ管理(PPM)のような考え方も必要になります。
これらを一度にすべて理解するのは大変ですが、まずは「自分たちの課題がどの層にあるのか」を知り、そこに合う考え方や技法を選ぶのが近道です。このブログでは、主なプロジェクト管理の手法や考え方を、一つずつわかりやすく紹介していきます。まずは全体像を押さえて、迷わず選べるようになりましょう。
この記事でわかること
- プロジェクト管理手法の全体像
PMBOKやアジャイル、ウォーターフォールなど、手法ごとの役割や違いがわかる。 - 主要な技法とツールの使い方
WBS・ガントチャート・PERT・CCPMなど、計画や進捗を「見える化」する方法を学べる。 - 組織全体を見渡す考え方
PPMやP2Mを使い、複数プロジェクトをまとめて最適化する方法を理解できる。 - タイプ別に合う手法の選び方
プロジェクトの規模や特徴に応じて、どの手法が適しているか判断できる。 - 現場で使える実践ステップと注意点
すぐに取り入れられるテンプレやツール活用のヒント、誤解しやすいポイントを把握できる。
次の章に記載するタイトル:PMBOK:国際標準の知識体系
第1章 PMBOK:国際標準の知識体系

プロジェクトマネジメントの分野で幅広く使われている手法のひとつが「PMBOK(ピンボック)」です。これはアメリカのPMI(プロジェクトマネジメント協会)がまとめた国際的な知識体系であり、プロジェクト遂行に関わる基本的な考え方や流れを教えてくれます。
PMBOKの特徴
PMBOKは「プロジェクトを失敗なく進めるために大切なことは何か」を分かりやすくまとめたガイドラインです。特に第6版では、プロジェクト実行の流れを「立ち上げ・計画・実行・監視・終結」という5つのプロセス群で示しています。また、「範囲」「コスト」「品質」「リスク」など10の重要な知識エリアごとに注意点が整理されています。これにより、プロジェクトのどの部分に何を意識すべきか、一目で分かるようになります。
どんな人・現場に役立つか
PMBOKの強みは、業界やプロジェクトの規模に関係なく使える点です。たとえば、建設工事のような大きな現場だけでなく、ITシステム開発、さらには小規模なイベント運営にも応用が効きます。特にたくさんの関係者が関わる複雑なプロジェクトや、仕事を「標準化」して全員が同じやり方を共有することが重視される現場で役立ちます。
活用時のポイント
ただし、PMBOKはあくまで知識体系の「教科書」です。そのまま現場に当てはめようとすると堅苦しくなったり、現状に合わない部分が出てくることも少なくありません。導入する際は、現場ごとに良い方法を見つけてカスタマイズするのが成功のカギです。
次の章では、作業分解による「見える化」と「責任の明確化」が可能なWBSについて詳しくご紹介します。
第2章 ガントチャート:タイムラインと依存関係の可視化
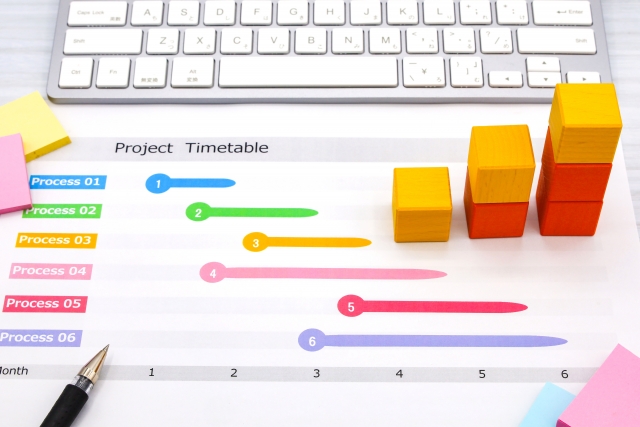
ガントチャートとは?
ガントチャートは、プロジェクト管理で広く使われるスケジュール管理手法で、横長の棒グラフの形でタスク(作業項目)の開始日と終了日を示します。これにより、全体のスケジュールや各タスクの進行状況を直感的に把握できます。Excelや専用ソフトでも簡単に作成でき、プロジェクトの全体像を共有するのに有効です。
基本的な使い方
- 時間軸でタスクを整理:作業の開始日・終了日を棒で表し、進行期間を可視化します。
- 依存関係の明示:矢印などでタスクをつなぎ、「Aが終わらないとBを始められない」といった順序関係を示せます。
- 具体例:家の建設なら「基礎工事→骨組み→屋根工事→内装→引き渡し」の流れを図示し、どの工程が遅れると全体に影響するかを把握できます。
メリットと活用ポイント
- 進捗管理:どこまで進んでいるか、どこに遅れがあるかを一目で確認でき、チームの連携がスムーズに。
- ボトルネックの把握:全体の遅れにつながる工程を早期に特定可能。
- マイルストーン管理:重要な節目を設定することで、納期遵守の確認が容易に。
- 柔軟なリスケジュール:タスクの棒をずらすだけで全体の影響を確認できるため、変更対応が簡単。
ベースラインの重要性
ガントチャートを運用する際には、プロジェクト開始時の**ベースライン(初期計画)**を記録しておきましょう。進捗や変更があったとき、当初計画との差分を確認でき、関係者間での認識合わせや対応策検討が容易になります。
次の章では、不確実な状況での計画に役立つ 「PERT」 について解説します。
第3章 CCPM(クリティカルチェーン):所要バッファで遅延を制御

クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント(CCPM)は、プロジェクト全体の遅延リスクを効果的に管理する手法です。不確実性や遅れが発生しやすいプロジェクト環境で使われることが多く、PERTの次に知っておきたい重要な手法です。
CCPMの特徴と基本概念
CCPMでは、まず作業の順序を整理し、時間が「最もタイトにつながる」道筋(クリティカルチェーン)を特定します。その上で、納期遅れリスクに対処するため、計画内に「バッファ(余裕時間)」を組み込みます。バッファは主に3種類あり、
- プロジェクトバッファ(最終納期を守るための余裕)
- フィーダーバッファ(クリティカルチェーンに合流する側道のための余裕)
- リソースバッファ(人や設備が必要なタイミングを守るための余裕)
などが挙げられます。
CCPMのメリット
従来のスケジュール管理手法では、各作業担当者が「念のため余裕」を個別に見込むため、実は全体で大きな余裕となってしまいがちです。CCPMではこのムダをなくし、必要な場所にまとめて余裕を配置することで、プロジェクト全体の遅延リスクを最小限に抑えられます。
具体的な適用例
たとえば、複数部署が協力する新商品開発プロジェクトで、各部署の作業が複雑に入り組んでいる場合、CCPMを使えば、どの作業が全体納期に最も影響するかすぐにわかります。その上でバッファを設定しておけば、予期せぬトラブルが起きても他の工程への波及を防ぎやすくなります。
ポイント
- 遅延が起きても焦らず対処できる安心感があります
- 「どこに余裕(バッファ)を取るべきか」が明確
- 大規模化したプロジェクトや、予測できない事象が多い現場で特に効果を発揮します
次の章では、組織全体の複数プロジェクトをまとめて最適化するためのPPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)についてご紹介します。
第4章 PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)

PPMとは何か
PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、複数のプロジェクトをまとめて最適化し、組織全体の目標に沿って経営資源(人・予算・時間)を効果的に配分するためのマネジメント手法です。
金融分野の「ポートフォリオ(投資の束)」の考え方を応用し、個別最適ではなく全体最適を目指します。
活用場面
- IT部門や新規事業部門:並行する複数のプロジェクトに対して、どこにリソースを重点配分するかを判断。
- 製造業・サービス業:新商品開発、既存商品の改良、システム更新など異なる性質のプロジェクトを同時に管理。
- 経営判断が必要な場面:進行中のプロジェクトが遅延した場合や、新規案件を立ち上げる際に、全体への影響を評価し優先順位を決定。
進め方のイメージ
- プロジェクトの一覧を可視化(目的、規模、進捗、リソース配分を整理)
- 経営戦略との整合性を確認(利益貢献度、成長性、リスク評価などの観点で見直す)
- 優先順位付けと選択
- 最優先で推進するプロジェクト
- 後回しにするプロジェクト
- 延期や中止にするプロジェクト
- 定期的なレビューで状況をアップデートし、柔軟に資源配分を調整
PPM導入のメリット
- 経営資源の最適配分:人材や予算を無駄なく活用できる。
- リスクの分散:リスクの偏りを防ぎ、組織全体で安定した成果を確保。
- 全体最適の実現:部分最適から脱却し、経営戦略に基づく迅速な意思決定が可能。
- 現場と経営層の連携強化:定期的なレビューで、現場の実態と経営の視点を擦り合わせられる。
実践のポイント
- まずは「見える化」から:エクセルや簡易ツールでも良いので、全プロジェクトを一覧化する。
- 経営層と現場の対話:一方的な優先順位付けではなく、関係者で合意形成を図る。
- 継続的な見直し:状況変化に応じて、優先度や資源配分を柔軟に更新する。
次の章に記載するタイトル:P2M(Project & Program Management)
第5章 P2M(Project & Program Management)

P2Mとは何か?
P2M(Project & Program Management)は、日本で生まれたプロジェクトマネジメント手法のひとつです。経済産業省が中心となって開発しました。P2Mの最大の特徴は、「プロジェクト単体」ではなく「複数のプロジェクトを含んだ全体(=プログラム)」を見渡して管理する点にあります。1つ1つのプロジェクト最適だけでなく、全体を統合して大きな目標達成を目指します。
どんな場面で使うの?
P2Mは、普通の案件管理よりダイナミックな変革や新しい事業など、大きな動きを束ねる時に活用されます。たとえば、新規事業立ち上げで開発・営業・マーケティング各チームが個別に動くだけではなく、全体を結び付けてシナリオ通りに成果を出さないといけない場合などです。分野が分かれていても、お互いに関連する活動を俯瞰し調整できるのがP2Mの強みです。
具体的な実践例
例えば、地方再生のプロジェクト群、企業のデジタル変革、複数の新製品開発を同時に進めるイノベーション戦略、などがP2Mの典型です。これらは、バラバラに進めると全体の目標達成が難しくなります。P2Mでは、各プロジェクトの進捗や状況を一元管理し、途中で優先順位の調整や再配置まで行い、全体目標から外れないようにコントロールします。
他の手法とのちがい
PMBOKやWBSが「個々のプロジェクトの管理」に強いのに対し、P2Mは「関連する複数プロジェクトの束ね役」となります。そのため、チーム間のコミュニケーション調整や、リソース(人やお金)のバランスを取る時にもよく使われます。
次の章に記載するタイトル:アジャイル:反復と顧客フィードバックで素早く価値提供
第6章 スクラム:アジャイルの代表的フレーム

アジャイル手法の中でも特に有名で広く使われているのが「スクラム」です。スクラムは、プロジェクトを小さな期間(通常は2週間から1ヶ月)の「スプリント」と呼ばれるサイクルで区切り、少しずつ成果物を積み上げていく進め方です。
スクラムの基本構成
スクラムには3つの役割があります。
- プロダクトオーナー:作るべきものの優先順位や内容を決めます。たとえば、お客様の「この機能がほしい」を整理して、チームに伝えます。
- スクラムマスター:チームがルール通りに進められるよう、障害を取り除きサポートします。まとめ役・潤滑油のような存在です。
- 開発チーム:実際に作業を進めるメンバーで、プログラマーやデザイナーなどが含まれます。
スプリントと会議
スクラムでは、次のような進め方を繰り返します。
- スプリント計画:次のスプリントで取り組む作業を決めます。たとえば「今週はA機能とB機能を作ろう」といった具体的な目標を立てます。
- デイリースクラム:毎日短い打合せをして、お互いの進捗や課題を共有します。困ったことがあれば早めに解消できます。
- スプリントレビュー:スプリントの終わりに成果物をお披露目し、フィードバックをもらいます。たとえば「このボタンの色をもっと見やすくしてほしい」など、直接声を聞けます。
- スプリントレトロスペクティブ:スクラムチーム自体の進め方を振り返り、「もっとこうしたらうまくいきそう」と話し合います。
スクラムのポイント
スクラムの最大の特徴は、計画と実行を短い期間で繰り返すことで、市場や顧客の声を早く取り入れられることです。新しいアイデアを試したり、やり方を見直したりしやすいので、変化の激しいプロジェクトに特に向いています。また、こまめにコミュニケーションをとることで、チーム内のズレや手戻りも減らせます。
次の章では、昔ながらの「ウォーターフォール」手法について解説します。
第7章 ウォーターフォール:段階的に完了させる計画駆動

ウォーターフォールモデルは、プロジェクトをいくつかの段階に分けて、上から下へ一つずつ順番に進めていく手法です。直訳すると「滝」のように、各工程を終えてから次の工程へと進むイメージが特徴です。この手法は、要件が最初から明確で、変更が少ないプロジェクトに向いています。
ウォーターフォールの代表的な流れ
- 要求定義:お客様や関係者と話し合い、何を作るかを決めます。
- 設計:どのように作るか、仕様や図面などに落とし込みます。
- 実装(開発):設計書に沿って実際に作業を進めます。
- テスト:完成したものが希望通り動くかを確かめます。
- 運用・保守:納品後も、問題があれば修正したり、必要な対応を続けます。
メリットとデメリット
ウォーターフォールのメリットは、全体像が分かりやすく、進捗も把握しやすい点です。各工程の区切りごとに成果物がはっきりするので、管理や品質チェックも行いやすくなります。しかし、一度決めた内容の変更がしづらいため、後から新しい要望が発生すると対応が困難です。
身近な例
家を建てるプロジェクトを思い浮かべてください。まず設計図を完成させてから建築を始め、途中で大きな変更が入ると、時間もコストも大幅に増えてしまいます。こうしたしっかりした計画が重要な場合にウォーターフォールは有効です。
次の章では、フローの最適化に効果的な「カンバン」についてお話しします。
第8章 カンバン:フロー最適化の可視化ボード

カンバンとは、日本発祥の「看板方式」にルーツを持つプロジェクト管理手法です。カンバンでは、作業の進捗や状況を一目で分かるように「ボード」に可視化します。これにより、チーム内で進行中の作業・次に着手すべき作業・完了した作業を明確に把握できます。
カンバンボードの使い方
カンバンボードでは、タスクを「To Do(これからやること)」「Doing(作業中)」「Done(完了)」などの列に分けて管理します。それぞれの作業がどこにあるかを、カードなどを使ってボード上で移動させるだけなので、誰が何を担当しているかも一目瞭然です。
たとえば飲食店の注文管理や、複数人で担当を分ける引っ越し作業など、さまざまな場面で応用できます。また、ITやソフトウェア開発現場では、付箋など物理的なボードだけでなく、オンラインツールを活用するケースも増えています。
フローの最適化とは
カンバンの最大の特長は「フローの最適化」です。これは、作業が途中で止まったり、どこかで滞留したりしないよう全体の流れを滑らかにする考え方です。たとえば、同時進行するタスクの数を制限することで、一つ一つの作業に集中し効率を高めることができます。その結果、納期遅延や作業ミスが減り、作業全体が円滑に回るようになります。
どんなプロジェクトに有効か
カンバンは、チームで進める日常的な業務や、次々と対応すべきリクエストが発生するような現場に特に有効です。業務の種類や規模を問わず、柔軟かつシンプルに運用できるため、効率化したい現場の「見える化」としておすすめできます。
次の章に記載するタイトル:手法の選び方:タイプ別マッピング
第9章 手法の選び方:タイプ別マッピング

プロジェクト管理手法はたくさんありますが、自分のプロジェクトにはどれが合うのか迷うことも多いと思います。ここでは、プロジェクトのタイプ別にどの手法が向いているかを分かりやすく整理します。
1. 目標・課題の明確さで選ぶ
- 目標や要件がはっきりしている場合は、ウォーターフォールやWBS、ガントチャートのような計画型手法が最適です。例としては、設計図にそって進める家の建設プロジェクトなどが当てはまります。
- 反対に、試行錯誤や調整が多い場合はアジャイルやスクラム、カンバンが向いています。新しいアプリ開発や、顧客の要望が頻繁に変わるプロジェクトなどが典型例です。
2. チーム規模と関係性で選ぶ
- 大きな組織や複数部署をまたぐ場合は、PMBOKやP2M、PPMのような体系的な知識体系の利用が効果的です。多くの人が共通認識で動く必要があるためです。
- 小規模チームやスタートアップでは、アジャイルやカンバンのような軽量なフレームワークが進めやすいでしょう。
3. プロジェクトの流れや仕事量の特徴で選ぶ
- 継続的で同じような作業が続く場合(運用・保守や定型的なタスク管理)には、カンバンが特に向いています。
- 作業や段階がはっきりしていて一つずつ進めるなら、ウォーターフォールやガントチャートが安心です。
- 変化が多く工程が繰り返される場合は、アジャイルやスクラムが活躍します。
4. 複数プロジェクトや全体最適を見たいとき
- いくつかのプロジェクトを同時管理したいときは、PPMやP2Mが適しています。経営視点でバランスを取りたいときに役立ちます。
プロジェクトごとに状況や目的が違うため、手法を柔軟に組み合わせることも有効です。必要に応じて部分的にアジャイルを取り入れたり、計画型手法にカンバンの見える化を足したりするのもおすすめです。
次の章:すぐに使える実務テンプレの流れ
第10章 すぐに使える実務テンプレの流れ

業務でプロジェクト管理手法を導入するとき、「何から始めれば良いのか分からない」と迷う方は多いです。ここでは、すぐに現場で使える基本的な進め方をステップごとに紹介します。
1. プロジェクトの目的やゴールを明確にする
最初に、プロジェクトの目的やゴールを簡潔にまとめましょう。たとえば「新しいシステムの導入」「製品の新バージョンをリリースする」などです。全員が同じ方向を目指すため、この一歩がとても重要です。
2. 主要な作業を大まかに洗い出す
大きな流れが分かったら、実現に向けて必要な作業をリストアップします。例:設計、開発、テスト、リリース準備、レビューなど。付箋やホワイトボード、エクセルなど、手軽なツールで書き出すと良いでしょう。
3. 作業を細かく分解して担当や順番を決める
各作業をより具体的に細分化し、各担当者や実行の順番を決めます。これがWBS(作業分解)の基本です。担当者が決まれば、各自のやるべきことも明確になります。
4. スケジュールを可視化する
ガントチャートやカンバンボードを使い、どの作業がいつ行われるか、どう進んでいるかを見える形にしましょう。無料のエクセルテンプレートやWebツールでも簡単に作成可能です。
5. 定期的な進捗確認と調整
進み具合や課題があれば、朝会や週次ミーティングで状況を共有します。計画に遅れが出た場合は、順序や担当の見直しも大切です。
このような流れを意識して取り入れることで、手法の違いに関わらず実践しやすくなります。自分の職場やチームに合わせて、柔軟にカスタマイズしましょう。
次の章に記載するタイトル:ツール活用のヒント
第11章 ツール活用のヒント

プロジェクト管理手法を効果的に運用するためには、適切なツールの活用が欠かせません。ここでは、実務の現場でよく見られるプロジェクト管理ツールの使い方のポイントについてご紹介します。
1. ガントチャートツールの活用
ガントチャート形式でスケジュールと進捗を把握できるツールは、多くの現場で役立っています。たとえば、Microsoft ProjectやBacklogなどがあります。これらを活用すれば、担当者ごとにタスクを割り当てたり、締め切りを可視化できます。また、ドラッグ&ドロップ操作で計画の見直しも簡単にできます。
2. タスク管理・チーム協働ツール
アジャイルやカンバンに便利な、TrelloやJira、Asanaといったツールが人気です。各タスクの状況をボード上で一目で管理できるため、誰が何を担当しているかをすぐに把握できます。日々の進捗確認や、課題の洗い出しにも最適です。
3. WBS作成ツール
WBSの作成にはExcelなどの表計算ソフトや、専用のWBS作成ツール(MindManagerなど)も有効です。階層的に分解されたタスクを一覧で整理し、担当者と締め切りも記入できる点がメリットです。
4. レポート・進捗共有の自動化
Googleスプレッドシートなどを使えば、進捗データの自動集計やグラフ化も可能です。手間を減らし、リアルタイムで状況把握できるので、定例会議の資料作成もスムーズになります。
5. ツール選びのポイント
導入コストや使い勝手、チーム規模に合うかどうかを必ず確認しましょう。最初はシンプルなものから始めて徐々に発展させるのもおすすめです。
次の章に記載するタイトル:代表手法の比較早見表
第12章 代表手法の比較早見表
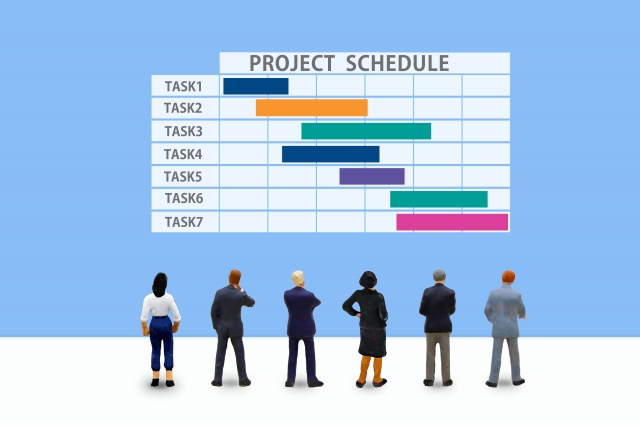
ここまでで、さまざまなプロジェクト管理手法について一つずつご紹介してきました。実際に選択する際、「どの手法が何に強いのか」「どんな場面で使えるのか」を分かりやすく比較したい方も多いのではないでしょうか。そこでこの章では、主要なプロジェクト管理手法の特徴や向いているケースを一覧でご紹介します。
比較早見表のポイント
以下の表では、目的、適用しやすいプロジェクトの特徴、メリット・デメリットに注目しています。たとえば、WBSは大きな仕事を細かく整理したいときに有効で、アジャイルやスクラムは変化が多く素早い反応が求められるプロジェクトに向いています。
| 手法 | 向いている場面 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| PMBOK | 標準化・大規模案件 | 国際的な信頼性、一通りの管理手順が習得できる | 学習コストが高い |
| WBS | 作業を細かく分けたい、責任分担を明確にしたい | 役割分担が明確、見通しが良くなる | 細分化しすぎに注意 |
| ガントチャート | スケジュールの流れを把握したい | 一目で進捗や関係性が分かる | 手作業だと変更が面倒 |
| PERT | 不確実性の高い計画に | ざっくりした見積もりが可能 | 条件の設定が難しい場合がある |
| CCPM | 遅延リスクの高いプロジェクト | バッファ設定で全体の遅れを抑えやすい | 調整に慣れが必要 |
| アジャイル | 変化への素早い対応が必要な場合 | 柔軟性が高い、ユーザーフィードバック反映が早い | チームワークの良さが不可欠 |
| スクラム | 小さな単位で成果を出し続けたい時 | 継続的な成果、改善の意識が高まる | 役割の理解が必要 |
| カンバン | 作業フローを最適化したい、進行状況を見たい場合 | 現場の「今」を重視できる | ともすると運用が雑になりやすい |
| ウォーターフォール | 最初に全体を決め切る必要がある大規模案件 | 計画的に進めやすい、段階ごとに整理できる | 途中変更に弱い |
この一覧を参考に、ご自身のプロジェクトや業務の特性と照らし合わせながら手法を選択してみてください。
次の章では「よくある誤解と注意点」について解説します。
補足:よくある誤解と注意点
プロジェクト管理の手法やツールを学ぶ際には、現場で誤解されやすいポイントがあります。ここでは代表的な誤解と注意点をまとめます。
「万能な手法」は存在しない
どの手法も完璧ではなく、プロジェクトの性質やチームの状況によって適性は異なります。
- アジャイル:変化に柔軟だが、すべての現場に適するわけではない。
- ウォーターフォール:計画重視だが、要件変更が多い現場には不向き。
現実的には「ハイブリッド型」(要件定義や設計はウォーターフォール、実装はアジャイルなど)が有効なケースも多いです。
PMBOKは手順書ではない
PMBOKはプロジェクトマネジメントの知識体系をまとめたガイドラインであり、マニュアルではありません。建築とIT開発では重視点が異なるように、現場ごとにカスタマイズして応用することが重要です。
ツールや技法への過信に注意
WBSやガントチャートは「計画立案と可視化」のための道具にすぎません。
「私たちの手法はガントチャートです」と言うのは誤りで、これらは管理手法そのものではなく、他の手法(アジャイルなど)とも組み合わせて活用すべきものです。
名前だけで選ばない
有名な手法であっても、そのまま導入すれば成功するわけではありません。小規模に試し、本当に必要な要素だけを取り入れることがスムーズな運用につながります。
知識体系と現場運用のバランス
PMBOKやP2Mなどの体系は全体理解に不可欠ですが、現場の工夫や独自ルールも大切です。両者を組み合わせることで実効性が高まります。
部分最適だけでは解決できない
複数プロジェクトを抱える組織では、各チームが個別に調整しても全体最適にはなりません。PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)やP2M(プロジェクト&プログラムマネジメント)といった上位レベルの手法を活用し、優先順位やリソース配分を全体視点で調整することが必要です。
プロジェクト管理に「必ずうまくいく方法」は存在しません。重要なのは、現場の状況や目的に応じて柔軟に組み合わせ、現実的に運用する姿勢です。