この記事でわかること
- 山口周氏の思想から学ぶ、VUCA時代のプロジェクトマネジメントの新しい視点
- 「プロジェクトは始める前に半分決まる」— 目的設計と期待値調整の重要性
- 成功確率を高める「勝てるプロジェクト」の見極め方と判断基準
- 成果を左右する「誰とやるか」— 人選とチーム設計の実践ポイント
- 炎上を防ぐための実践知:期待値管理・SOS発信・事前チェックリストの活用法
目次
山口周とプロジェクトマネジメントの接点

山口周氏は、外資系コンサルティング会社などで活躍してきた豊富な実績を持つ実務家であり、同時に現代の働き方や組織について鋭い視点を持つ思想家としても知られています。氏は、実際に数多くのプロジェクトに関わる中で、人や組織が持つ「不確実さ」や「複雑さ」にどう対処すべきか、深く考察してきました。
近年よく耳にする「VUCA」(ブーカ:変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)という言葉が示すように、現代のビジネス環境はかつてない速さと複雑さで変化しています。山口周氏は、そうした環境下でプロジェクトを遂行するには、従来の「管理中心型」だけのやり方では限界があると述べています。そのため、プロジェクトの立ち上げ段階、特に「開始前」の戦略設計や人選が非常に大きな意味を持つと指摘しています。
例えば、JBpressでの講演や、noteでの連載記事では「プロジェクトの成否の半分は始める前に決まっている」と繰り返し述べています。これはつまり、プロジェクトを本格的にスタートする前の準備や計画、目的の明確化、適切な人材配置こそが、後々のトラブルや失敗を回避する最大のポイントだというわけです。
また、山口氏の著書『【新装版】外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』は、現場の実務者が実際に使える考え方や行動をわかりやすくまとめた一冊として、多くのビジネスパーソンやリーダーに支持されています。リーダーの役割や、人を動かすためのコミュニケーション、プロジェクトそのものの始め方など、具体的な事例とともに解説されているのが特徴です。
この連載では、山口周氏の知見をベースに、「プロジェクトを炎上させないコツ」や「勝てるプロジェクトと人選のポイント」など、誰でも実務で活かせるヒントを紹介していきます。
次の章に記載するタイトル:開始前で勝負が半分決まる—“舞台設定”と目的設計
開始前で勝負が半分決まる—“舞台設定”と目的設計
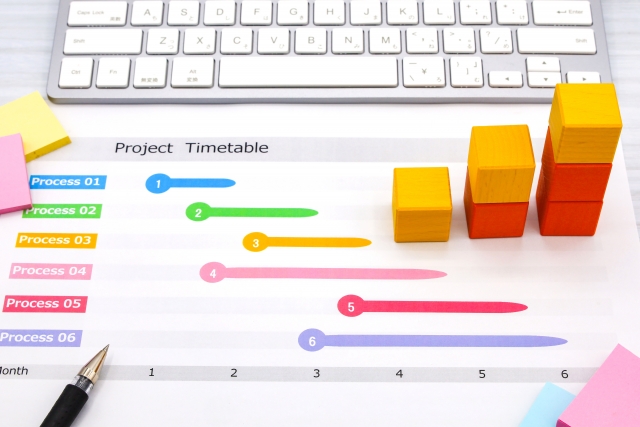
プロジェクトを進める際、多くの人が「始まってから頑張ればうまく行くだろう」と考えがちです。しかし、山口周さんが強調するのは、実はスタートを切る前の準備こそが成功へのカギであるということです。ステージを整え、どの方向に進むのかを明確にしなければ、どれだけ努力しても的外れになる危険が高まります。
背景・狙い「なぜやるのか」を合わせる
プロジェクトの最初に欠かせないのは、その「目的」を全員でしっかり認識することです。たとえば、イベントを企画する場合、「単に開催する」のではなく「参加者全員が新しい発見を持ち帰れる場にする」など、意味のある目標を定めましょう。これにより、関係者全員が自分の役割を理解しやすくなり、目的を見失いにくくなります。
“舞台設定”がもたらす安定感
また、「舞台設定」とは、協力するメンバーや関係者、ルール、進め方の枠組みづくりを指します。たとえば、誰が最終的に決めるのかを初めに決めておくことで、不必要な話し合いや混乱を防げます。また、プロジェクトの成功や失敗をどのように判断するのか、評価のポイントを共有することも重要です。
期待値マネジメントでトラブル回避
プロジェクトに参加する人たちは、時に理想が高すぎる目標を持ってしまいます。そのため最初から“できる範囲”“目標とするレベル”を明確にしておくと、後で「こんなはずではなかった…」といったトラブルを避けやすくなります。これは「期待値マネジメント」と呼ばれ、無理のない成功を目指すためには不可欠な考え方です。
次の章では、プロジェクト自体が“そもそも勝てるかどうか”をどう見極めるかをご紹介します。
勝てるプロジェクトを見極める—炎上を避ける最初の関門

プロジェクトで失敗を防ぐための最初の大きなポイントは、「そもそも勝てるプロジェクトかどうか」を見極めることです。山口周氏は、リーダーの力量は実際のマネジメント手法よりも、“案件そのものを正しく選ぶ目”に大きく影響を受けると指摘します。
多くの人が「プロジェクトは開始した後の進め方次第」と考えがちですが、実際には着手前の段階で成否がほぼ決まっています。ここでは、選ぶべき案件と避けるべき案件の違いをより具体的に見ていきましょう。
何が“勝てる”プロジェクトをつくるのか
勝てるプロジェクトとは、無理なく成功につなげやすい条件がそろっている案件のことです。ただし、「必ず楽な案件を選べ」という話ではありません。重要なのは、目的が明確で納得できるか、関係者間で目標や役割が揃っているか、限られた時間や予算で現実的に達成できる内容かどうかを、事前に冷静に見極めることです。
例えば、関係者が多すぎて意見が割れている案件や、求められる成果に対して納期や予算が明らかに足りない場合、最初から“負け戦”になるリスクが高くなります。一方で、「この内容なら自分たちで十分にやり切れる」と自信を持てるプロジェクトは、着実に成果を出しやすいでしょう。
「案件の目利き」はリーダーの責務
プロジェクトリーダーや責任者には、無理な案件・勝率の低い案件を安易に引き受けない勇気も求められます。「断る」という選択肢を持つこと自体が、健全な組織運営への第一歩です。また、成功して当たり前と思われる案件でも、その一つひとつを確実に成果につなげていくことで、組織の信頼や自分自身の評価は着実に高まります。
案件を選ぶ際には、スケジュールやリソース、利害関係者の顔ぶれなど、開始前の診断ポイントを一つずつ丁寧に確認してください。それが、炎上を未然に防ぎ、楽しく充実したプロジェクト経験へとつながります。
次の章では、「人が先、計画は後—人選で成否の50%が決まる」について解説します。
人が先、計画は後—人選で成否の50%が決まる
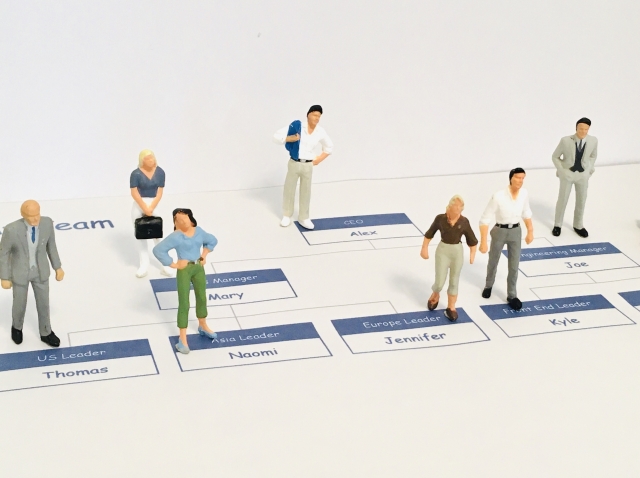
プロジェクトマネジメントにおいて「人を集めること」の重要性は、しばしば軽視されがちです。しかし、山口周さんの考え方では真っ先に取り組むべきポイントと言えます。例えば、経営書で知られるジム・コリンズも「まず優秀な人をバスに乗せる」という比喩を使い、最初に何よりも『誰と一緒にバスに乗るか』=『誰をチームに加えるか』が大切だと指摘しています。
現場では、与えられたメンバーで計画だけを練りがちな状況が多く見られます。ですが、受け身でチームの構成を受け入れるのではなく、リーダー自らが「この人となら成果が出せる」と感じるメンバーに声をかけていく姿勢が成否を大きく左右します。
例えば、新規サービスの立ち上げでは、経験やスキル以上に“やる気”や“信頼できるか”が大切になることもあります。「○○さんなら急な変更にも柔軟に対応してくれる」「××さんはアイディアが豊富で議論をリードしてくれる」など、役割や期待値を明らかにすることも欠かせません。山口さんの講演でも、「最初のうちにケンカが起こるのはむしろ良い兆候。早期に摩擦を表に出し、役割や責任をすり合わせることで、のちの大きなトラブルを防げる」と述べられています。
つまり、人選は単に能力だけではなく、その人の個性や価値観、行動スタイルもよく観察し、それぞれが持つ強みや弱みを早めにチーム内で共有しておくことが肝心です。その上で、目標や期待を明確化し、合意形成を目指すことが、質の高いプロジェクトへとつながります。
次の章では、初期ダッシュの設計—コミュニケーション、合意、期待値 について詳しくご紹介します。
初期ダッシュの設計—コミュニケーション、合意、期待値

プロジェクトの初動が肝心
プロジェクトがスタートした直後の「初期ダッシュ」は、後々の進行を大きく左右します。この段階で躓くと、後からの立て直しが難しくなりがちです。そのため、最初にどれだけ地固めができるかが成否の重要なカギとなります。
メンバー同士の細かなコミュニケーション
まず心がけたいのは、メンバー同士の密なコミュニケーションです。例えば、どんな些細な内容でも「これは誰が担当するのか」「いつまでにやるのか」といった点を、初回の集まりで明確にしましょう。曖昧なまま進めると、「あれは誰がやるはずだったの?」といった混乱が生まれ、信頼関係にも影響します。
役割と意思決定の仕組みをはっきり示す
それぞれの役割分担だけでなく、「何か問題が起きたら誰に相談するか」「最終的に誰が判断するのか」といった意思決定の流れも、初期に示しておくことが重要です。例えば、チームリーダーが最終責任者となる場合は、決断の方法を全員に共有しておくことで、進行時に空中分解を防げます。
課題範囲と優先順位の合意
プロジェクトの範囲や目的、何を優先するかなどの重要事項は、後回しにせず、最初の段階で合意を取りましょう。例えば「今回は新商品の初期モデルまで開発し、量産化は次の段階で議論する」と明確に線を引いておくと、「まだやるべきことが残っている」という誤解を防げます。
期待値コントロールの工夫
スタート時点で「やや低め」の期待値を設定し、必ずクリアできる目標から始めましょう。たとえば「今月中にプロトタイプの骨組みを完成させる」と明言し、着実に達成することで、チーム内外の信頼を高めることができます。できること・できないことの線引きを明確にし、余計なプレッシャーがかからないよう設計することも大切です。
次の章に記載するタイトル:無理難題への対処—いったん断る、SOSを早めに出す
無理難題への対処—いったん断る、SOSを早めに出す

まずは“無理です”と伝える勇気
プロジェクトマネジメントでよくある悩みの一つが、「この条件ではうまくいかない」と思えるような無理難題な依頼です。多くの場合、クライアントや上司の期待に応えたい気持ちが働き、つい安易に「何とかします」と引き受けてしまいがちです。しかし、山口周さんは「いったん断る」ことを鉄則として勧めています。
いったん断るというのは、単にNOと言うのではありません。「現状では実現が難しい理由」や「必要な条件」などをきちんと説明した上で、相手との対話を始めるサインでもあります。無理な要求をそのまま受け入れると、後になって問題が大きくなり、チーム全体や関係者の苦労が増えてしまうことが多いです。
断ることで見えてくる“本当の目的”
一度立ち止まって依頼主と議論をすると、相手が本当に求めているものや、妥協できる部分がより明確になります。たとえば「急いで欲しい」という要求の裏側には、「最低限ここまでできていればいい」という本音が隠れている場合があります。こうした本質的な目的を正しく掘り出すためにも、疑問点はきっぱりと伝えていきましょう。
SOSは恥ではない—早く共有するほど効果的
また、計画が思うように進まなかったり、途中で不安や異変を感じた時、「助けてほしい」「状況が厳しい」とSOSを出すのは決して弱さではありません。むしろ早い段階で周りと情報を共有しておくことで、対応の選択肢や支援の手が増え、被害を最小限に抑えることができます。
例えば、進捗が遅れている場合にも「このペースでは危ない」と率直に伝えることで、実際にどう調整できるか、誰に応援を頼むべきかなど、新しい打ち手を早めに探れます。問題が小さいうちや前兆の段階で“可視化”することが、プロジェクトの炎上を防ぐ最良の方法と言えるでしょう。
不安の“見える化”がチームを救う
「一人で抱え込まず、不安を共有することでむしろ安心を与える」というのも山口さんの提案です。リーダーが正直に現状や難しさを打ち明ければ、他のメンバーも課題感を共有でき、建設的な意見や協力が生まれやすくなります。この透明性の高いコミュニケーションこそが、チームワークと成果の質を高める秘訣です。
次の章に記載するタイトル:実務で使えるチェックリスト(要点の実装)
実務で使えるチェックリスト

はじめに
前章では、プロジェクトマネジメントの各段階で重要となる心構えや具体的アクションについてご説明しました。この章では、それらを実務で活用するため「チェックリスト」にまとめ、現場で迷わない判断ポイントを提案します。実際の仕事にすぐ活かせる形でポイントごとに簡潔にまとめました。
1. 事前診断のチェックポイント
- 目的を明確に説明できるか(「何のためにやるか」が一文で話せるか)
- 最終的な意思決定者は誰かを特定しているか
- 関わる人たち(ステークホルダー)が、誰でどういう立場か整理できているか
- 制約条件(スコープ・予算・納期)を洗い出し、表にできているか
- 成功か失敗かを判断する基準が具体的に書かれているか
2. 勝てるかどうかの目利き判断
- 成功の条件を満たすための手段やルートが現実的か検証したか
- 信頼できる支援者や協力者が明らかか
- 想定される障害(ボトルネック)が明確で、それを取り除ける見込みがあるか
- 条件が揃わない場合、受け方・やり方を再設計したか
3. 人選と役割分担
- 必要なスキルや知識を書き出し、担当者が手配できているか
- それぞれの役割・責任・権限が曖昧になっていないか
- チームの関係を早い段階からこまめに気にかけ、働きやすさを意識しているか
4. 期待値設計
- 過剰な約束を避け、無理のないゴール設定を意図しているか
- 期待より少し低めのコミットをして、それを上回る実績を心がけているか
- 成果物の納品を何段階かに分け、中間で確認を重ねているか
- 小さな合意形成を積み重ねているか
5. 危機対応・リスクマネジメント
- 難しそうな話には一旦「すぐ回答しない」選択肢も想定したか
- 要件や条件が苦しい場合、妥協点や交渉ポイントを自分で考えられているか
- 早い段階で「助けてほしい」とSOSを出せる雰囲気作りを進めているか
- 不安やリスクを率直に共有し、全員の協力で染み出しを防止できているか
まとめてコツコツチェック
このリストを使うことで、ギリギリの場面や「本当に大丈夫?」と不安になった時、自分やチームの状態を客観的に振り返ることができます。一つずつ項目に印をつけながら、着実に進めることが成功への近道です。
次の章では、山口周さんの代表的な著書や、さらに学びを深めるために役立つ情報をご紹介します。
代表的著書と入手情報

山口周さんが執筆した「【新装版】外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント」(大和書房、2023/6/15刊)は、実際の現場で活用できるプロジェクトリーダーのノウハウが詰まった一冊です。この書籍は、多くのビジネス書紹介ガイドや書籍紹介メディアで高く評価されており、2025年時点の「おすすめ本」としてもたびたび取り上げられています。
具体的には、「プロジェクトとは何か」から、「どう人を巻き込むか」「どのようにリスクに備えるか」まで、幅広い内容を分かりやすく解説しています。現場目線で実例も多いので、これからプロジェクトマネジメントを学ぶ方や、実務で悩みがちな方にとって実用性が高い内容になっています。
書籍は書店や大手ネット書店(Amazon、楽天ブックスなど)で入手可能で、中古書店や電子書籍の取り扱いもあります。タイトルやISBN(国際標準図書番号)、著者・出版社情報をもとに購入ページが容易に検索できます。たとえば、中古書販売サイトやECサイトでは、商品説明欄で「ISBN」や「著者」「出版社」など明記されているため、間違いなく目的の一冊にたどりつけます。
また、最新の学び直しリストやブックガイドにも頻繁に登場しており、独学や研修の参考図書としても選ばれています。身近な書店やネット書店で手に入りやすい点も魅力です。
次の章に記載するタイトル:山口周式PMのエッセンス(キーメッセージ)
まとめ—山口周式PMのエッセンス

山口周氏の考え方をベースにしたプロジェクトマネジメントのポイントをまとめます。これまでの章でお伝えしてきたとおり、プロジェクトの成功は、始まる前から半分以上決まっています。まずは「なぜこのプロジェクトをやるのか」「どこを目指すのか」といった目的設計が重要です。曖昧なままでスタートを切ると、途中で迷走したり、チームのモチベーションが続かなくなったりするからです。
実際の進行では、計画そのものよりも「集まった人」が成果を左右します。どれだけ素晴らしい計画でも、それを実行できる”人”がいなければ形にはなりません。したがって、リーダーは段取りよりもまず適材適所の人選に力を注ぐことが肝心です。そして、初期の段階でしっかりと期待値を合わせ、合意を作ることで、後々のトラブルを大きく減らせます。
もしも「そもそも無理な条件」や「無理な納期」が見えた時には、勇気を持って立ち止まる、もしくは早い段階でSOSを出すことで、大きな炎上を未然に防ぐことも大切です。言いづらいからと我慢して進めてしまうと、問題が大きくなりやすいというのが現場のあるあるでもあります。
また、意思決定の透明性やコミュニケーションの質も見逃せません。隠し事や曖昧な説明をせず、本音で話すことで、メンバー同士の信頼が生まれます。こうした空気の中では、問題や課題も早期に発見しやすくなります。
山口周式プロジェクトマネジメントの真髄とは、「勝てる条件に全力を注ぎ、そうでなければ無理をしない」「人を軸にプロジェクトを設計する」「本音で向き合う」——この3つに集約できます。これらのエッセンスを踏まえ、皆さんの日々の仕事にもぜひ役立ててみてください。