目次
この記事で分かること
- WBSの基本と必要性
WBSとは何か、なぜプロジェクトに欠かせないのかが理解できます。 - WBSの型と使い分け
成果物軸とプロセス軸の違い、それぞれの特徴と実務での活用方法がわかります。 - WBS作成の手順
実際にWBSをどう作るか、ステップごとの流れと具体例を学べます。 - 品質を高めるコツと落とし穴回避
粒度の決め方、依存関係の整理、責任者設定など、実践的な注意点が理解できます。 - WBSの効果と活用シーン
ビジネス上のメリット、アジャイル開発での活用、ツール・テンプレートとの連携がわかります。
はじめに:WBSとは何か、なぜ必要か

プロジェクトを成功させるうえで大切なのは、全体像をしっかりと把握し、計画的に作業を進めていくことです。そこで活躍するのが「WBS(Work Breakdown Structure/作業分解構成図)」という手法です。WBSは、プロジェクト全体を階層的に、どんどん細かい作業単位に分けていく図になります。たとえば、大きな家具を組み立てるときに、箱を開ける、パーツを確認する、ネジを締めるといったステップに分けるイメージです。
このように細かく分解することで、「どんな作業が必要なのか」「進捗はどこまで進んでいるのか」を一目で確認できるようになります。また、WBSは計画書にもなり、作業ごとのコストや期間の見積り、担当者を決めるといった具体的な管理もスムーズにできます。さらに、関係者どうしで必要な作業内容を共有したり、作業の抜けや重複を防いだりするのにも役立ちます。
WBSには階層構造があり、一番上がプロジェクト全体や大きな目標、その下に主要な成果物や大きめの作業、その下に小さなタスクが続きます。一般的には、3層程度でまとめると分かりやすく扱いやすいとされています。
次の章では、WBSの型についてわかりやすく解説します。
WBSの2つの型:成果物軸とプロセス軸

WBS(作業分解構成図)には、大きく分けて2つの型があります。それが「成果物軸」と「プロセス軸」です。どちらの方法にも特徴があり、案件やプロジェクトの性質によって使い分けると、より抜け漏れが少なく進行しやすくなります。
成果物軸(成果物ベースのWBS)
「成果物軸」とは、プロジェクトで生み出す具体的な成果物を中心に、作業を分解していくやり方です。たとえば、Webサイト構築プロジェクトの場合なら、「トップページ」「会社概要ページ」「お問い合わせフォーム」などの成果物ごとに作業項目を整理します。この方法は、短期間で終わるプロジェクトや、完成形が最初からはっきりしている場合に特に向いています。
プロセス軸(プロセスベースのWBS)
一方で「プロセス軸」は、成果物ではなく、作業の流れや活動自体に着目して分解・整理していきます。たとえば、同じWebサイト構築でも「企画」「設計」「開発」「テスト」などのプロセス単位で作業を分類するイメージです。この方式は、中長期で進む大規模プロジェクトや、最終的な成果が最初ははっきりしないような場合にも適しています。
実務では両者の組み合わせも有効
現場では「成果物軸」と「プロセス軸」のどちらか一方と決めつけず、両方を組み合わせて使うことも多いです。たとえば、まず成果物ごとに分けてから、その中の作業をプロセス単位に細分化する、といった形です。この2つをバランスよく使い分けると、抜け漏れを防ぎやすくなり、より実践的なWBSになります。
次の章では、WBSを実際に作成する手順についてご説明します。
WBSの作成手順(実務フロー)

WBS(Work Breakdown Structure)の作成は、プロジェクト管理の中でも特に重要なプロセスです。ここでは、実務で利用できるWBS作成のステップをわかりやすくご紹介します。
1. 上位から大枠を切る
最初に、プロジェクト全体を大まかなフェーズや区切りで分割します。例えば、「企画」「要件定義」「設計」「実装」「テスト」「移行」など、各工程ごとに分けましょう。これにより、プロジェクトの全体像を把握しやすくなります。
具体例
新しいウェブサイトを作る場合は、「企画 → デザイン → 開発 → テスト → 公開」というように分割します。
2. フェーズ内を段階的に分解
各フェーズをさらに細かく割り、実際に作業する単位まで分けます。ここでは、作業が「数時間~数日」程度で終わるくらいの大きさになるまで分解します。これを「作業パッケージ」と呼ぶこともあります。
具体例
「テスト」フェーズでは、「動作確認」「バグ修正」など細分化し、それぞれの担当や作業内容を明確にします。
3. 依存関係を明確化
各作業や工程が、どの順番で進める必要があるか、同時にできることは何かを整理します。PMBOKの考え方を参考に、前後関係や並行可能な作業がわかるようにします。
具体例
「設計」は「要件定義」が終わってから、「実装」は「設計」が終わってから始める、といった順序です。
4. 抜け漏れ・重複チェック
細分化した作業をツリー構造で見渡し、やり忘れや同じ作業の重複がないか確認します。この段階で、作業ごとのリソース(人員や時間)も把握しましょう。
具体例
リスト化したタスクをチームメンバーに確認してもらい、「漏れている作業がないか」や「似たようなタスクが重なっていないか」をダブルチェックします。
5. スケジュール・リソース割当・リスク計画への接続
できあがったWBSを、実際のスケジュールや担当割当、リスク管理につなげて活用します。ガントチャートを作って進行管理したり、各作業に必要な人や日数を割り振ったりします。
具体例
WBSをもとに「Aさんは設計を担当、Bさんは実装を担当」「この作業は6月末までに終える」など、具体的に管理します。
次の章では、「作成・運用のコツ(品質を上げる要点)」について解説します。
作成・運用のコツ
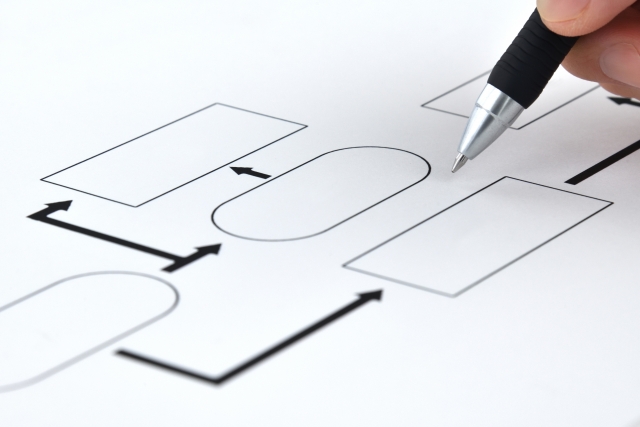
WBS(作業分解構成図)の品質を高めるためには、作成と運用のいくつかのポイントを意識することが大切です。ここでは、誰にでも取り入れやすい実践的なコツをご紹介します。
適切な粒度に分解する
WBSを作成するとき、一つひとつの作業(タスク)をどこまで細かく分けるかが重要です。細かくしすぎると、管理項目が増え、かえって管理が大変になります。逆に大ざっぱすぎると、進捗把握や問題発見が遅れることも。手間と効果を天秤にかけて、「管理しやすい」レベルまで細分化するのがコツです。たとえば、「資料作成」を「資料構成決定」「原稿作成」「レビュー・修正」「印刷準備」くらいまでに分け、さらに日々の業務で把握しやすい単位を意識してください。
実施順序や依存関係を明確に
タスク同士の順番や、何が終われば次に進めるかなど、作業のつながりを意識しましょう。これにより、後から作業を追加・変更するときも見通しがつきやすくなります。例えば、「サーバ設置」が終わらなければ「ソフトウェアインストール」は始められません。このように、前後関係や依存関係を意識して構成することで、計画の精度が上がります。
責任者と進捗管理を明確に
各作業パッケージごとに担当者を決めておくと、進捗が分かりやすくなります。誰がどの作業を進めているか明示することで、遅れや問題の早期把握につながります。医院内のプロジェクトであれば、「受付担当」「看護師責任者」など、実際の担当者名を入れると効果的です。
コスト・期間の見積もりに直結させる
作業パッケージごとの作業量・期間・必要な人員をイメージしておくと、トータルのコストやスケジュール見積もりが立てやすくなります。例えば、「広告宣伝」パッケージならいつまでに、どれくらいの費用で行うか、をあらかじめ想定しておくと変更にも強くなります。
コミュニケーションツールとして使う
WBSは内部メンバーだけでなく、ステークホルダー(関係者)との共有ツールにもなります。全体像を見せることで、誰が・いつ・何をするのかが分かりやすくなり、合意形成や進捗のすり合わせもスムーズになります。
次の章に記載するタイトル:依存関係の基本(PMBOKの考え方を踏まえて)
依存関係の基本(PMBOKの考え方を踏まえて)

プロジェクトを計画したり実行したりする際に、各作業の並び順や関係性を明確にすることはとても大切です。特に「Aの作業が終わらないとBが始められない」といった依存関係を見落としてしまうと、予定通りにプロジェクトを進めることが難しくなります。この点については、国際的なプロジェクト管理の基準であるPMBOK(Project Management Body of Knowledge)でも、依存関係の整理と明確化が強く推奨されています。
依存関係の4つの種類
依存関係には主に次の4種類があります。
- 完了-開始(FS)型:Aが終わってからしかBを始められない例。例えば「設計図が完成してから製作を開始する」ようなケースです。
- 開始-開始(SS)型:Aが始まったら、Bもスタートできる場合。「基礎工事が始まったら、同時に資材発注も始められる」といった例です。
- 完了-完了(FF)型:Aが終わるときに、Bも終わらせる必要がある場合。「テスト作業が完了した時点で、報告書作成も終える」などが当てはまります。
- 開始-完了(SF)型:やや特殊ですが、Bの完了がAの開始に依存する場合です。日常業務ではあまり見かけませんが、順番をコントロールする必要がある特殊な業務で使います。
強制依存と任意依存
依存関係には「強制的なもの」と「任意的なもの」があります。強制依存は法律や物理的な制約からどうしても変えられないもの(たとえばコンクリートが固まるまで次の作業に進めない、など)です。一方で任意依存は、段取りや方針の都合で決めているもの(資料作成を先にやる、など)です。WBSを作成する時は、特に強制依存をしっかり洗い出しておくことが重要です。
順序決定とクリティカルパス
依存関係が整理できたら、どの作業がいつ始まって、どの作業がどれに遅れられないかがはっきりします。全作業の“最短完了ルート”は「クリティカルパス」と呼ばれ、プロジェクトの遅れに直結します。WBSを役立てて依存関係を可視化することで、どこに重点を置いて進捗管理をすればよいか分かりやすくなります。
次の章に記載するタイトル:WBSとプロジェクト管理プロセスのつながり
WBSとプロジェクト管理プロセスのつながり
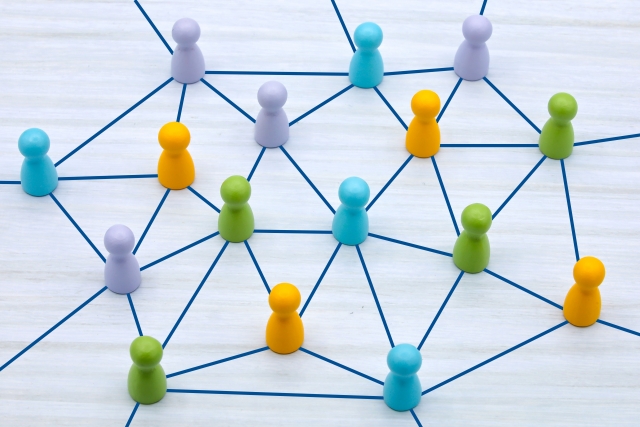
どのようなプロジェクトでも、「何を」「いつまでに」「どこまでやるか」「どれだけコストをかけられるか」を最初に決めて進めます。これらを明確にした後、WBS(作業分解構成図)を用いて、プロジェクトを実際の作業単位に細かく分解していきます。こうすることで、一人ひとりが何をすべきかが見えやすくなり、全体像も把握しやすくなります。
WBSの作成は、プロジェクト管理の中心的なプロセスと密接につながっています。たとえば、目標設定で決まった「ゴール」から逆算して必要な作業をWBSで細かく抽出します。その作業をもとに、リソース(人や時間、予算)を割り当てたり、スケジュールを作成したりする流れになります。
また、WBSがあることで、スケジュールの遅れや予算のオーバーといったリスクも事前に見つけやすくなります。個々の作業がどのようにつながっているか、どこに手間がかかりそうかを可視化できるため、管理者だけでなくチーム全体の意識も統一されやすいのが特徴です。
さらに、実際にプロジェクトを進めていく途中で変更が発生した場合も、WBSを見直すことで柔軟に対応できます。たとえば、新しい作業が追加になった場合や、優先順位が変わった場合は、WBSを修正し、それに基づいてスケジュールやリソース計画も調整します。
こうして、WBSはプロジェクトの計画・実行・監視などさまざまな管理プロセスの基盤となり、プロジェクト全体を円滑に進める役割を担っています。
次の章に記載するタイトル:WBSのメリット(ビジネス効果)
WBSのメリット(ビジネス効果)

WBS(作業分解構成図)を導入することで、プロジェクトには様々なビジネス上の効果が期待できます。
タスクの可視化と追跡性の向上
WBSを作成すると、プロジェクトの作業やタスクが一覧で見える化されます。これにより、どの作業がどこまで進んでいるのかが明確になり、作業遅延や抜け漏れに気付きやすくなります。例えば、プロジェクトの進捗状況をチームで共有したい場合、WBSを使えば誰でも全体像や各作業の状況を把握できます。
リソース・進捗管理の容易化
それぞれの作業に必要な人員や時間を割り当てやすくなります。WBSを見ながら「この作業にはどのくらいの人手が必要か」を具体的に考えやすくなり、適切なリソース計画が立てられます。また、進捗管理もしやすくなるため、リーダーやマネージャーの負担も軽減されます。
期間・費用見積りの精度向上
プロジェクトを細かい作業単位に分解することで、各タスクの期間や費用を具体的に見積もれます。例えば「全体で何週間かかりそうか」「どのタスクにどのくらいの費用が必要か」といった点もブレが少なくなり、予算オーバーや納期遅延のリスクが下がります。
抜け漏れ・重複の回避
WBSでは作業を項目ごとに洗い出して整理します。これにより、作業の抜け漏れや重複を発見しやすくなります。事前に気づいて対策を立てやすくなりますので、トラブルの未然防止にもつながります。
全体像の共有と関係者間の合意形成
WBSは見た目にもわかりやすいため、プロジェクト関係者の共通認識を作りやすいというメリットもあります。「何を」「誰が」「いつまでに」するのかをチーム全体で共有しやすく、各メンバーや関係部署とスムーズに合意形成できるのも強みです。
次は「アジャイル開発におけるWBS活用のポイント」について説明します。
アジャイル開発におけるWBS活用のポイント

アジャイル開発では、変化が激しく計画の見直しも頻繁に発生します。そのため、WBS(作業分解構成図)は「一度作って終わり」ではなく、プロジェクトの進行に合わせて柔軟に更新し続けることが大切です。WBSを活用することで、タスクの見落としや重複を防ぎ、チーム全員に作業全体のイメージを共有できます。
特にスプリント計画やバックログ精緻化において、WBSは頼りになるツールです。たとえば、今後の2週間で対応する作業をWBSの中から抽出し、それを具体的なタスクとしてバックログに反映させます。これにより、チーム全員が「どんな作業が残っているか」「誰がどこまで担当しているか」を把握しやすくなります。
加えて、定期的なミーティング時にWBSを見直すことで、新たな課題や優先度の変更にもすぐ対応できます。アジャイル開発の特徴である「柔軟な対応力」を生かすためには、WBSの運用も固く考えずシンプルかつ見やすくしておくとよいでしょう。
次の章に記載するタイトル:WBSの階層イメージ(一般例)
WBSの階層イメージ(一般例)

WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクト全体を階層的に分解し、構造的に管理しやすくする手法です。ここでは、具体的な階層イメージとして、Webサイト刷新プロジェクトを例にご説明します。イメージしやすいよう、各レベルとその内容を分かりやすく示します。
レベル1:プロジェクト主要成果物
最も大きな枠として、プロジェクト全体がレベル1にあたります。例えば、「新Webサイトの刷新」がこのレベルです。このレベルはプロジェクトの目標やゴールに近い部分で、最終的に何を達成するのかを明確にします。
例:
- 新Webサイトの刷新
レベル2:主要成果物を構成する要素(サブ成果物や主要タスク群)
レベル1の下に、プロジェクトを構成する主要な要素を分けます。たとえば、サイト刷新の中には「ロゴ刷新」や「ガイドラインの見直し」など、最終成果物を作り上げるための大きな作業のかたまりが含まれます。
例:
- ロゴ刷新
- ガイドライン見直し
- 新ページ構成案作成
- テスト・検証
レベル3:詳細サブタスク
レベル2の各項目をさらに細かく分解したものがレベル3です。実際に誰が何をするのか、具体的な作業内容や担当者が明らかになります。たとえば、「ロゴ刷新」なら「ブランドカラー選定」や「UXデザイナー割当」など、実作業レベルの項目が並びます。
例:
- ブランドカラー選定
- UXデザイナー割当
- ターゲット分析
- 社内レビュー実施
このように階層を分けて整理することで、作業の抜けや重なりを防げますし、誰が何を担当するのかも把握しやすくなります。
次の章では、WBS作成時によくある落とし穴とその回避策についてご説明します。
作成時によくある落とし穴と回避策

WBS(作業分解構成図)を作成する際には、誰もが遭遇しやすい落とし穴があります。その代表例として、タスクの粒度(細かさや大きさ)が適切でないことが挙げられます。粒度が細かすぎる場合、タスク管理が極めて煩雑になってしまい、関係者の負担やミスの温床になりがちです。逆に粒度が粗すぎると、タスク単位での正確な進捗把握が難しくなり、プロジェクト全体の状況を見失う恐れがあります。
もう一つの落とし穴は、タスク同士の依存関係がきちんと整理されていない場合です。この状態ではスケジュール上に無理や重複、論理的な矛盾が生じ、プロジェクト進行が止まったり手戻りが発生したりします。また、成果物視点が弱いと、スコープ(目的と範囲)が曖昧になり、重要なタスク抜けや過剰対応が発生しやすくなります。
上記の落とし穴を避けるためには、いくつかの方法があります。まず、タスクの粒度の基準を揃えることです。目安としては「1タスクが数時間から数日で完了する大きさ」に設定し、それぞれが全体の中でバランス良く並んでいるかをレビューしましょう。
また、WBSを作る際は成果物軸(完成するものごと)とプロセス軸(作業工程ごと)を併用して使い分けることで、必要な工程と成果物の両面から抜けや漏れをチェックしやすくなります。タスク間の依存関係については、明確に書き出し、ネットワーク図やガントチャートなどのスケジューリングツールと連携することで、論理的な矛盾や重複を未然に防げます。
次の章に記載するタイトル:ツール・テンプレートの活用
ツール・テンプレートの活用
WBSを効率よく作成・運用するためには、専用のツールやテンプレートの活用がおすすめです。最近では、ExcelやGoogleスプレッドシートといった身近な表計算ソフトだけでなく、専用のプロジェクト管理ツールも多く登場しています。これらのツールは、タスクの分解や依存関係の整理、ガントチャートとの連携まで一元的に管理できる機能が備わっています。また、あらかじめ用意されているWBSテンプレートを使えば、ゼロからシートを作る手間なくすぐに作成を始められるのも大きなメリットです。
例えば、Excelのテンプレートでは行ごとにタスクやサブタスクを記入し、階層ごとにインデントや色分けをすることで視覚的に整理できます。インターネット上には無料でダウンロードできるテンプレートも多く公開されています。
また、TrelloやAsana、Backlogなどのコラボレーション型ツールでは、タスクごとの担当者割り当てや進捗管理がしやすくなります。さらに、ガントチャートを自動表示してくれるツールなら、WBSの内容とスケジュールをそのまま見える化できます。
このようなツールやテンプレートを活用することで、WBSの作成と運用のハードルが大きく下がります。パソコン操作が得意でない方でも、手順や入力例がガイドされているため、迷わず導入できます。自分やチームに合ったツールを選び、プロジェクトの規模やメンバー構成に応じてカスタマイズしてみてください。
次の章では、WBSをうまく運用するためのチェックリストについて説明します。
WBSをうまく運用するためのチェックリスト

WBS(Work Breakdown Structure)をうまく活用するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、運用時に確認しておくべきチェックリストをご紹介します。
1. 目的・スコープ・成果物定義の確認
はじめに、プロジェクトの目的と範囲(スコープ)が明確になっているか確認しましょう。また、このプロジェクトで達成すべき成果物が具体的に定義されているかも大切なポイントです。
2. 成果物軸/プロセス軸の適切な決定
WBSを成果物中心で分解するか、プロセス中心で分解するか決めましょう。プロジェクトによっては両方を組み合わせて使うことも効果的です。その場合、区分けが明確になるよう意識しましょう。
3. 作業の粒度を統一する
タスクや作業項目の大きさ(粒度)をそろえることが管理しやすさのコツです。目安として、ひとつの作業は数時間から数日以内に完了する規模に分割しましょう。
4. 依存関係をはっきりさせる
各作業の「あとの順番」「まえに終わらせる必要がある作業」など、依存関係を明確にしておきましょう。これにより、スケジュールの調整やリスク管理がしやすくなります。
5. リソース・責任者・期限・所要時間を紐付ける
それぞれのタスクについて「誰が担当か」「いつまでに完了するか」「どれくらい時間がかかるか」をはっきりさせましょう。責任者が明確だと、進捗管理もスムーズです。
6. コストや期間見積もりの構造が整っているか
WBSをもとにコストや期間の見積もりができる状態か確認します。これにより、現実的なプロジェクト計画が立てられます。
7. ガントチャートやリスク計画と連携
WBSの情報がガントチャート(スケジュール表)やリスク管理計画と連動しているかもチェックしましょう。各工程の進捗やリスクが把握しやすくなります。
8. 関係者によるレビューの実施
関係者全員でWBSをレビューし、漏れや重複がないか確認しましょう。現場の意見を取り入れることで、より実行可能な計画に仕上がります。
次の章に記載するタイトル:参考にした主なポイント(出典の要旨)
参考にした主なポイント

この章では、記事執筆にあたって参考とした主な出典、それぞれの要点についてご紹介します。皆さまがWBSについて学ぶ際にも役立つ情報が詰まっていますので、ご参考になれば幸いです。
Asana(アサナ)
Asanaでは、WBSの基本的な考え方や、どのようにタスクを適切な粒度で分解するかを、実例を使って解説しています。特に、依存関係についてはPMBOK(プロジェクト管理知識体系ガイド)の定義を取り入れつつ、実際の現場でどのように指針を活かせるかが具体的です。
マネーフォワード
マネーフォワードの解説では、WBSの定義、導入することで得られるメリット、プロセス軸と成果物軸という2つの視点からのWBSの違いとその適用場面について、図解付きで分かりやすくまとめられています。
パーソル
パーソルは、WBSがプロジェクト管理の全体プロセスの中でどのように位置付けられるのかについて、実際の業務フローを踏まえた説明が特徴です。
Jooto
Jootoでは、WBSのツリー構造を作る手順や、順番付けのルール、階層ごとの管理の仕方、抜け漏れ防止の効果などに重点を置いています。誰でも取り組みやすい工夫やコツが紹介されています。
Sun*(サンアスタリスク)
Sun*のサイトでは、アジャイル開発にWBSをどう活用するかが詳しいです。WBSの本来の目的を再確認しつつ、継続的に変化するアジャイルプロジェクトの進め方にどのように取り込めるかを解説しています。
KDDI
KDDIのWBS資料は、基礎用語や作業パッケージの定義、コストやスケジュール見積りへの活用方法、WBSを使うことで増すチーム内外のコミュニケーション価値について説明しています。
Adobe
Adobeが公開しているガイドでは、3層構造でのWBSの具体例や、それぞれの階層における特徴について、明確な事例を通じて紹介されています。