この記事でわかること
- プロジェクトマネジメントで起こる主なトラブルの種類と実例
- トラブルが発生する根本原因とその見極め方
- 効果的なトラブルシューティングの手順と対応プロセス
- 再発防止に役立つマネジメント戦略とチーム運営のコツ
- プロジェクトマネージャー・PMOに求められる資質とスキル
目次
1. プロジェクトマネジメントのトラブルとは何か?

プロジェクトマネジメントの現場では、さまざまなトラブルが発生します。トラブルとは、プロジェクトの進行が止まったり、遅れたり、うまくいかなくなる事象のことを指します。その内容は多岐にわたり、例えば計画していたスケジュールが守れない、完成した成果物の品質が基準に達しない、チーム内の意見が合わずコミュニケーションが円滑に進まない、といったことが挙げられます。
トラブルの代表例としては、次のようなものがあります。
- 作業の遅れや納期の遅延
- 製品やサービスの品質低下
- 要望や仕様がはっきりしない、曖昧な指示
- メンバー同士、または顧客との意思疎通の不足
- チームのモチベーションや人間関係の悪化
- パワハラや過度なプレッシャー、健康問題
プロジェクトマネージャーは、進捗や品質の管理、予算の調整だけにとどまらず、チームメンバーの調整や顧客対応、時には突発的な問題解決まで担います。そのため、トラブル対応の責任も重大で、プレッシャーが大きくなることがよくあります。
このように、プロジェクト現場で起きるトラブルは非常に幅広いです。そして、どんなに準備や計画をしても、全ての問題を未然に防ぐことは難しいのが現実です。重要なのは、トラブルが起きた時に慌てず、冷静に対処する方法を知っていることです。
次の章では、こうしたプロジェクトマネジメントのトラブルがなぜ発生するのか、その主な原因について解説します。
2. トラブルが発生する主な原因

要件・計画の不明確さ
プロジェクトの出発点として重要なのが、要件や計画の明確化です。しかし、プロジェクトの目的ややるべきことが曖昧なままだと、担当者ごとに認識がズレてしまいます。例えば、「新しいホームページを作成する」という目標だけだと、デザイン重視か機能重視かが分からず、出来上がりが意図と異なることもあります。この結果、完成後に修正が多発したり、納期が遅れてしまったりします。
作業量把握の不十分
必要な作業量やかかる時間の見積もりが十分でない場合、途中でスケジュールが大きく狂うことがあります。たとえばイベント準備で「準備は1週間で十分」と見込んだものの、細かい作業を洗い出していなかったために予想外の業務が発生し、スタッフの負担が増えるケースがあります。このように、見積もりの甘さが全体の遅れや失敗につながるのです。
コミュニケーション不足
チームメンバーや外部との連携がうまくできないと、情報共有に漏れが生じます。例えば「誰が何を担当するか」の認識にズレがあり、AさんもBさんも同じ資料を作成していた、といった無駄が生まれやすくなります。また、伝えたはずの情報が別メンバーに届いておらず、仕事が止まってしまうなど、認識違いによるトラブルも頻発しがちです。
リスク管理の不備
プロジェクトには必ず何らかのリスクがありますが、「どんなリスクがあるか」「起きた時どう対処するか」をあらかじめ洗い出しておくことが大切です。しかし、この点をおろそかにすると、同じ問題が何度も繰り返されたり、対応が後手になり事態が悪化したりします。たとえば「予算オーバー」の対策が考えられていないと、気付いたときには取り返しがつかない状況になりかねません。
人間関係・組織課題
プロジェクトは“人”が動かします。パワハラやアンフェアな評価、メンバー同士の不満など、人的な問題が生じると士気が下がり、スピードや品質にも悪影響を及ぼします。「AさんとBさんが口をきかないために、本来は協力が必要な業務が停滞する」といったこともよく見られます。
次は、「トラブルシューティングの鉄則とプロセス」について解説します。
3. トラブルシューティングの鉄則とプロセス

トラブル対応の基本的なステップ
プロジェクトでトラブルが発生したとき、感情的な判断や急ぎ足の対応では、かえって問題が悪化する恐れがあります。そこで、一定の手順に沿って冷静に対応することが重要です。この章では、実際のプロジェクト現場でも使えるトラブルシューティングの基本的な流れについて解説します。
1. 現象の把握
まず、何がどのように問題になっているのかを、具体的に洗い出しましょう。例えば、「納期までに作業が終わらない」という場合も、“どの作業”が、“どれくらい遅れているのか”、“なぜそうなったのか”など、できるだけ多くの事実を集めます。関係者から情報を集めたり、現場の状況を確認したりして、客観的データを残すことがポイントです。
2. 影響範囲の特定
次に、そのトラブルが及ぼす影響範囲を確認します。遅延している作業が全体の流れにどう影響するのか、他のメンバーやお客様にどんな影響を与えるのかを調べます。優先順位が高い部分や、リスクの大きい箇所が見つかれば、そこに注力して対応することが大切です。
3. 原因の特定・切り分け
問題の本質に迫るため、考えられる原因をリストアップします。例えば、“作業が遅れる”原因として「人手不足」「誤った見積」「手順のミス」などが考えられます。それぞれの可能性を一つずつ検証し、真の原因を突き止めます。
4. 解決策の実行
原因が分かったら、まず急場をしのぐ応急対応を行い、プロジェクトの進行を止めないようにします。その後、根本的な改善策を設計し、実施していきます。場当たり的な修正は、思わぬ副作用を生むことがあるため、しっかりと根拠を持って実施することが大切です。
5. 再発防止策の策定
問題が解決した後は、同じトラブルが繰り返されないように、仕組み自体を見直します。マニュアルの整備や業務フローの改善、自動化ツールの導入など、再発を防ぐ取り組みを行います。
次の章では、実際のトラブル対応のポイントや具体的な実例について説明します。
4. トラブル対応のポイント・実例

リスク共有と文書化の重要性
トラブルが発生したとき、まず大切になるのがリスクをチーム全体で共有し、対応の過程や判断をしっかり文書化することです。たとえば、進捗遅延などの問題が発生した際、誰が対応し、どのように判断したのか記録しておきます。こうした記録は、後から同じような問題が起きたときに参考になり、原因や対応策を全員で共有できるため、将来的なトラブルの予防にもつながります。
PMOによる支援の実例
プロジェクトを取りまとめる役割(PMO:プロジェクト・マネジメント・オフィス)は、炎上につながりかねない小さなトラブルを早期に発見し、プロジェクトマネージャー(PM)をサポートします。たとえば、要件が曖昧だと感じた場合、PMOはすぐに関係者に確認や追加ヒアリングを促します。加えて、進捗管理ツール(PPMツールなど)を活用して、タスク管理やリスクの見える化を支援することで、無理な計画の早期発見や情報の整理に役立てています。
人の問題に対する対応事例
プロジェクトでは、パワハラやメンバー同士の衝突など、計画変更だけでは解決できない人に関する問題も起きることがあります。たとえば、プロジェクト内でメンバー間の信頼関係が崩れてしまった状況では、PMが個別にヒアリングを行い、それぞれの立場や悩みを整理します。その上で、必要に応じて外部の専門家に相談したり、メンバー配置を工夫するなど、現場ごとに最適な方法を模索しています。
トラブルシューティングに必要な考え方
トラブルが起きたときに大切なのは、その本質がどこにあるのかを見極めることです。例えば、納期遅延の原因が単純な人員不足なのか、根本的な計画ミスなのかを調査します。そのうえで、誰が・いつまでに・どのように対応するのか具体的な行動を決め、積極的に解決へと動く姿勢が求められます。PMが自ら現場に出て状況を確かめるなど、能動的な対応が成功へのカギです。
次の章では、トラブル予防および再発防止のためのマネジメント戦略についてご紹介します。
5. トラブル予防・再発防止のためのマネジメント戦略
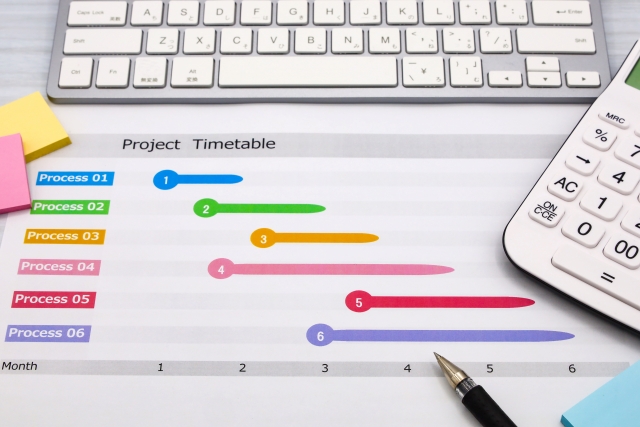
要件定義・計画の徹底
トラブルを防ぐ最初の一歩は、プロジェクトの目的や範囲、必要な要件をしっかり決めておくことです。何を作りたいのか、どんな成果を目指すのかを初めに明確にして、関わる人全員で理解をそろえることが重要です。例えば、新しいシステムを導入するときは、使う機能や予算、納期などを具体的に話し合いましょう。この段階で認識のズレがあると、後になって「思っていたのと違う」といった問題が起きやすくなります。
進捗・報告体制の整備
役割分担を明確にしておくことも欠かせません。プロジェクトリーダーや担当者が「誰が何をいつまでにやるのか」をはっきり決めておくことで、仕事の押し付け合いや抜け漏れを防げます。たとえば、毎週1回チームで進捗を共有しあう場を作れば、問題を早めに見つけやすくなります。また、PM(プロジェクトマネージャー)やPMO(プロジェクト管理部門)の間でも、役割が重ならないよう工夫しましょう。
運用プロセスの改善・自動化
作業を人の手で行う場合、どうしてもミスは起こります。ヒューマンエラーを減らすには、「この手順でやれば間違いにくい」という業務フローの見直しが大切です。さらに、定型的な作業は自動化するのも効果的です。例えば、情報の入力ミスを防ぐために、自動で値をチェックするシステムを入れるなどの工夫が挙げられます。
心理的安全性の確保
チーム全体が本音で話せる雰囲気を作ることで、問題の芽を早く見つけられます。「こんなこと相談してもいいのかな」とためらわずに話せることが、トラブル予防につながります。普段から意見交換の場を設けたり、ミスや失敗を責めるのではなく改善に向けて話し合う姿勢が大切です。心の安全性が高いと、みんなが協力しやすい風土になり、結果として大きな問題を防げます。
次の章に記載するタイトル:プロジェクトマネージャー・PMOに求められる資質とスキル
6. プロジェクトマネージャー・PMOに求められる資質とスキル

プロジェクトを円滑に進めるためには、プロジェクトマネージャーやPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)に特有の資質やスキルが求められます。ここでは、特に重要なポイントについて分かりやすく解説します。
1. 推進力・調整力
プロジェクトの目的やゴールを明確に関係者に伝える力が重要です。例えば、開発プロジェクトの場合、納期や品質に対する意識をチーム全体で共有しやすくするために、定期的なミーティングを設けて進捗状況を確認することが効果的です。また、関係者同士の意見調整や、納品物のチェック(成果物レビュー)、スケジュール管理も率先してリードします。難しい場面でも、前向きに物事を進める姿勢が信頼につながります。
2. トラブル対応力
トラブルが発生した際は、本質を見極める冷静さを持つことが大切です。例えば、納期遅延が発生した場合、単に叱責するのではなく「なぜ遅れたのか」「今後どう対処するか」を具体的に整理し、担当者や解決策、対応期限を明確にします。能動的に行動し、都度状況を確認する姿勢が、チームを落ち着かせる効果もあります。
3. 文書化・情報共有力
プロジェクトリーダーは、リスクや課題、対応策を記録し、適切にチームと共有する力が欠かせません。例えばプロジェクト管理ツールや共有フォルダを活用し、誰でも最新の状況や課題を確認できる仕組みを用意しましょう。これにより情報の漏れや、トラブルの見逃しを防ぎやすくなります。
4. コミュニケーション力・心理的ケア
クライアントやチームメンバーとの信頼関係を築くには、日々の丁寧なコミュニケーションが大切です。たとえば、困っているメンバーに声をかけたり、成功を素直にねぎらう姿勢も効果的です。また、メンバーの心理的な負担にも配慮しましょう。悩みや小さな不満も早い段階で受け止めることで、大きな問題に発展するのを防げます。
プロジェクトマネージャーやPMOは、単なる指示役ではなく、全体を支える「まとめ役」としての資質が求められます。どれか一つだけでなく、これらをバランスよく身につけていくことが、安定したプロジェクト運営には不可欠です。