プロジェクト管理の現場では、数字は存在しているのに “本当の状態がわからない” という状況が頻繁に起こります。
・進捗は進んでいると言う
・予算もなんとか使っている
・でも、納期とコストの未来は誰も説明できない
このギャップを埋める仕組みが EVM(Earned Value Management/アーンドバリューマネジメント) です。
EVMは、スケジュール・費用・成果を 「価値」という共通の物差し に変えることで、感覚や主観ではなく、データに基づいてプロジェクトの健康状態を判断できるようにします。
この記事でわかること
- EVMの意味と役割が理解できる
進捗・コスト・成果を “価値” という共通軸で管理できる手法だと分かります。 - PV・EV・AC などの基本概念が分かる
EVMが難しそうに見えても、実は3つの数字の関係で理解できることが見えるようになります。 - EVMが実務で強い理由が分かる
意思決定がしやすくなり、問題の早期検知につながる点が理解できます。 - EVMの導入ステップが具体的に分かる
価値の設定、コスト収集、評価方法、レポート活用までの流れがつかめます。 - テンプレ例や成功/失敗事例で実務のイメージが持てる
単なる知識ではなく「どう使うか」「なぜ失敗するか」まで見えるので現場で使える理解になります。
目次
■ EVMとは?プロジェクトの進捗とコストを一体化して管理する手法

EVMは、プロジェクトの進捗を金額換算することで、計画と現実の差を見つけるための技術です。
従来の管理では、
- 進捗率は進んで見えても価値が伴っていない
- 予算が消えていく理由が見えない
- 納期のずれが後からしかわからない
こうした “見えるようで見えていない構造” が問題でした。
EVMは「価値という一つの尺度」を導入することで、進捗 × コスト × 時間を同時に監視し、
・どこで遅れているか
・どれだけ無駄が出ているか
・このまま行くとどこへ着地するか
を明確にできます。
▪ なぜ従来の進捗管理では不十分なのか?
WBS や進捗率管理は役に立ちますが、限界があります。
たとえば1000万円のプロジェクトで「今70%です」と言われても、
それが 700万円分の価値を生んだ状態なのか、それとも400万円しか価値がないのに800万円使っているのか、数字だけでは判断できません。
従来管理の弱点は次の3つです
- 進捗とコストが別管理になっていること
- 進捗率に主観が乗りやすいこと
- 価値=成果として換算されないこと
だからこそ、出来高を価値として扱う EVM の登場意義が生まれます。
▪ EVMが解決する3つの課題(納期・コスト・早期異常検知)
EVMが強い理由は、「現状の問題」だけでなく “今のまま進むとどうなるか?” を数値で見せられることです。
EVMが解決できる主な課題は次の3つです
- 納期の読み違い
- コスト問題の曖昧な感覚依存
- 問題が顕在化する前の異常検知
つまり EVM は、プロジェクトの未来を “予測可能な事象” に変えるための装置だと言えます。
■ まず押さえるべきEVMの基本概念
EVMは専門用語が多くて難しそうに見えますが、
実は たった3つの数字の関係を見るだけの仕組みです。
その3つが
- PV(Planned Value):本来生じているはずの価値
- EV(Earned Value):実際に生み出した価値
- AC(Actual Cost):実際に使った費用
これだけです。あとの指標はすべて、この3つの組み合わせで説明できます。
例として「1000万円・10ヶ月のシステム開発」を追いかけながら理解してみましょう。
▪ PV(計画価値)
PVとは “この時点までにどれだけ価値が積み上がっているべきか” を表します。
もし最初の2ヶ月で設計フェーズを終える予定で、そこに500万円分の価値が割り当てられているなら、
2ヶ月目の時点のPVは 500万円 です。
▪ EV(出来高価値)
EVは “実際に完了した価値” です。
たとえば、計画では500万円の価値がある設計フェーズが、半分しか終わっていなければ EVは250万円です。
EVはコストではなく価値なので、
「たくさん働いたか」ではなく “何を達成したか” で評価する点が特徴です。
▪ AC(実コスト)
ACは 「その時点までに実際に使った費用」 のことです。
設計に600万円使ってしまっていたら、ACは600万円です。
ここで3つを比べてみます
- 本来は500万円の価値があるべきだった(PV)
- 実際は250万円しか価値を作れていない(EV)
- でも600万円使ってしまっている(AC)
この 3行 だけで、
進捗は遅れ、しかもお金を食いすぎているというプロジェクトの現実が浮かび上がります。
文章で背景を理解したうえで、
箇条書きで整理・比較を補強すると 読み手の理解負荷が大幅に下がる のが分かると思います。
▪ EVMの本質は「出来高に価値を持たせること」
進捗率は、多くのプロジェクトで“なんとなく”測られます。
でも EVM は、「何%進んだか」ではなく
それがいくらの成果につながったのか?
という問いに変換します。
この発想は、「努力が目的ではなく成果が目的である」というプロジェクトの本質的な考え方を数字で強制するものです。
■ EVMが強いと言われる理由(実務価値)
EVMの価値は、単に進捗を測ることではありません。
それは “プロジェクトという曖昧な生き物に、骨格を与えること” にあります。
普通の管理では、進捗報告はこうなりがちです:
「少し遅れてますが、今週巻き返します」
「今のところ大丈夫です」
「予算は少し厳しいかもです」
これらの言葉は、聞く側が解釈しなければ意味を持ちません。
EVMはこの曖昧さを排除し、現場・管理者・経営層の言葉を数字で統一する 効果があるのです。
▪ 進捗とコストを一本の尺度で語れる
EVMが浸透した組織では、プロジェクトレビューでこんな会話が生まれます:
「現時点のEVは1,200万円、PVは1,500万円です。SPIは0.8なので、
スケジュールは20%遅れています。」
これだけで 誰でも事態が理解できる ことに気づいてください。
- “頑張っています” ではなく どれだけ遅れているか
- “予算が厳しいかも” ではなく どれだけ赤字方向か
EVMは、プロジェクトを 数字が語る世界 に変えます。
▪ 管理者・経営層・現場が同じ数字で意思決定できる
現場は “今困っている” と言います。経営層は “本当に問題なのか?” と疑います。
この乖離が調整コストを生み、対応が遅れます。
しかし、
- EVは600万円しかない
- ACは900万円使っている
- このままいくと赤字△400万円が見込まれる
という話になれば、議論は抽象論から離れ、意思決定ができるテーブル に移ります。
▪ 異常検知が早い=修正余地を確保できる
プロジェクトの怖いところは、問題が顕在化したときには「既に取り返しがつかない状態になっていること」です。
EVMで「偏差が積み上がる初期段階」を検知できれば、
- 人員配置の変更
- 外注調整
- スコープの見直し
- 予算承認の前倒し
など、まだ手の打てる位置 で評価できるようになります。
EVMは、単なるレポートではなく「損害を未然に防ぐための時間を買う技術」 と言えます。
■ EVMはどうやって導入する?(やり方と手順)
EVMの概念が理解できても、「じゃあ結局どう導入するのか?」が落とし穴です。
導入は “教科書の理論” ではなく、実務の設計です。
ここで重要なのは 5つのステップ です。
▪ ステップ1:WBSの出来高定義(価値評価の設定)
EVMは、WBSに価値配分するところから始まります。
例えば「要件定義 250万円」「基本設計 250万円」といった具合です。
ポイントは以下です:
- 「タスクの重さ」ではなく 成果の重さで配分する
- メンバーの認識差が出ないよう 値札を明文化する
- あいまいになりやすいフェーズは 指標を複数持つ
文章で流れを理解した上で、こうした箇条書きが精度の担保ポイント を補強します。
▪ ステップ2:PV(計画)設定
価値を割り振ったら、それが時間軸でどう積み上がるかを設定します。
これが PV の曲線になります。
- フロントロードか
- バックロードか
- 均等配分か
計画が違えば PV の形は変わり、結果として 「ズレの読み方」も変わります。
▪ ステップ3:AC(実績)収集
現場では、“正確なコストがすぐに取れない” という問題があります。
だからこそ EVM 導入の初期段階では
- 人件費の見積単価を統一する
- 工数記録の粒度ルールを作る
- 外注・内部を区別して集計する
といった 収集ルールの運用設計 が鍵になります。
EVMは理論より “地面に近い作業設計の方が難しい” のが実際です。
▪ ステップ4:EVの評価方法
ここが EVM 最大の失敗ポイントです。
「進捗率=出来高」と誤解してしまうとEVMの価値は崩壊します。
そのため EV では、
- 完了の定義(DoD)を明確にする
- 進捗の主観評価を排除する
- 成果物レビューを伴う
などの 品質基準とセット で価値を測ります。
▪ ステップ5:レポート・評価・是正
最後は計算した指標をどう使うかです。
EVMの価値は、レポートではなく 意思決定につながるか で決まります。
レポートを出しただけで終わる組織は100%失敗します。
「誰が、その数字を基に、何を判断するのか」を合意させて初めて EVM が“使える管理”になります。
■ Excelで使えるEVMテンプレート(無料DL)
EVMは Excel で十分導入できます。
テンプレートは、理解を深める “実務装置” でもあります。
テンプレートで最低限必要な構造は:
- PV/EV/ACの入力シート
- 主要指標(CPI/SPI/SV/CV)の自動計算
- 推移グラフとレポート化の画面
これらが揃っていることで、EVMが“学習対象”ではなく 使われる道具 になります。
無料テンプレはこちら:EVM管理Excel(DL)
この記事で解説した内容を、クリックひとつで実務に使えるExcelテンプレにまとめました。
PV/EV/ACの入力欄
主要指標の自動計算
推移グラフの自動生成
が入っているので、今日からEVMが実務で使えます👇
■ EVMの“限界”と誤用されがちなポイント
EVMは強いですが、万能ではありません。
むしろ、誤用されやすい手法 No.1 でもあります。
文章で理解した上で、誤用ポイントを整理すると以下です:
- 出来高評価が主観に戻ると、EVが崩れる
- 評価頻度が低いと、偏差検知が遅れる
- EVMを導入しても、意思決定文化がないと死ぬ
特に最後が重要で、EVMは “数字が意思決定に使われる組織” でなければ効きません。
単に計算しただけでは意味がない――
ここを理解しているかどうかで、導入成功確率は大きく変わります。
■ EVMを補完する他手法との比較
最近はアジャイルや EDM(Earned Duration Management)など、
EVMを補完する手法が登場しています。
それぞれの強みを整理すると:
EVMは価値の視点で強い
EDMは時間遅延の把握が得意
アジャイルのバーンダウンは量の把握が得意
この比較から見えるのは、1つの手法ではプロジェクトを捉え切れない という現実です。
EVMは強力ですが、それを盲信せず、他手法と組み合わせてこそ本領を発揮します。
■ 現場でのEVM活用例と成功・失敗ストーリー
実務では、EVMが機能するチームとしないチームに分かれます。
成功例では、
- CPI が下がり始めた段階で早期に対策を打ち、
- 外注調整とフェーズ削減によって黒字化した
という話がよくあります。
逆に失敗例では、
- EVが主観評価になっており
- 指標は動いているが意思決定に使われず
- 結果、数字と現場の実態が乖離した
というケースが典型です。
両者を分けたのは、
指標が意思決定に結びつく文化があるかどうか
という一点でした。
■ プロジェクト管理ツールとEVMの連携
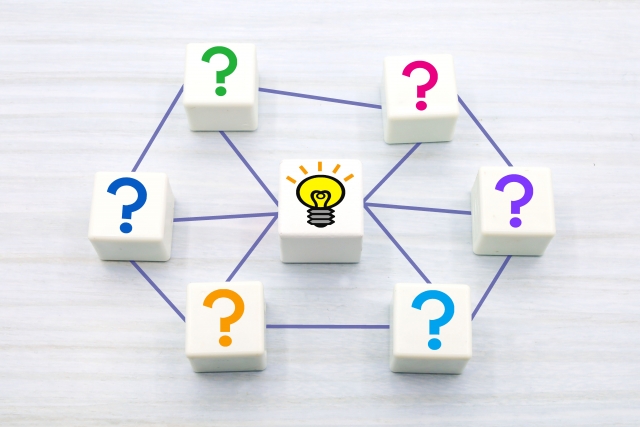
Excelで始められると言いましたが、
一定規模を超えるとツール連携のほうが安定します。
- Redmine
- Jira
- MS Project
- Wrike
- Backlog
などは、
- 進捗記録
- 工数集計
- レポート生成
を自動化でき、EVMの集計誤差や更新漏れを防ぐ役割 を果たします。
また今後は AI による
- 偏差の早期推定
- EV推定の自動化
- 異常検知アラート
などが進むため、EVMは“測る手法”から“アシストされる手法”に進化していきます。
■ まとめ|EVMは「数字でプロジェクトを見る力」を育てる武器
EVMの本当の価値は、「進捗を金額換算できる」ことではなく、
“プロジェクトを成果価値で捉える思考” を組織に根づかせること にあります。
✔ 価値を視点とした管理
✔ 予測を前提とした判断
✔ 数字を意思決定に使う文化
これらが揃ったとき、EVMは単なる管理手法ではなくプロジェクトが失敗する前に修正できる武器 へ変わります。
ぜひこの記事を入口に、まず小さなプロジェクトでも EVM を試し、価値基準でプロジェクトを見つめる習慣を育ててみてください。