目次
この記事でわかること
- PMIとは何かとその役割
世界的な非営利団体としてのPMIの活動内容や、日本での展開について理解できます。 - PMIが提供する資格の種類と基本情報
PMPやCAPM、ACPなど、キャリア段階や専門分野に応じた主要資格と受験の流れが分かります。 - PMBOKの位置づけと最新の特徴
プロジェクトマネジメントの国際標準ガイドであるPMBOKの意義や改訂のポイントを押さえられます。 - 日本国内の関連団体やP2Mとの違い
PMIとあわせて、日本独自の団体や知識体系の特徴や使い分けを理解できます。 - 資格学習・キャリアへの活かし方
学習ステップや用語整理、資格取得後のキャリアメリットや継続学習の重要性を把握できます。
プロジェクトマネジメント協会(PMI)とは
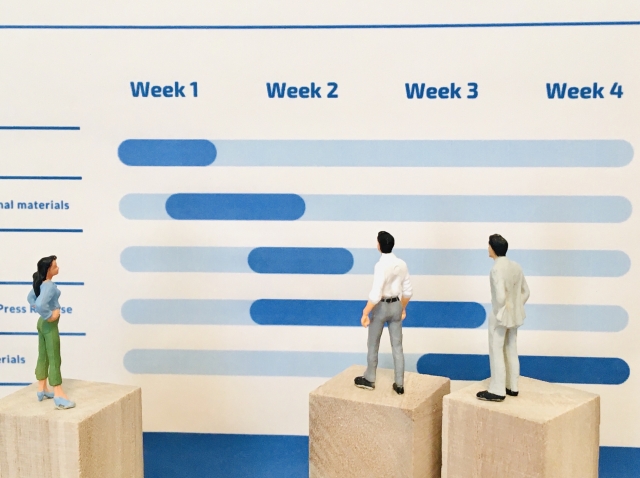
プロジェクトマネジメント協会(PMI)は、アメリカに本部を置く世界的な非営利団体です。この協会はプロジェクトの計画や実行に関わる専門職の人々を支援し、知識やスキルの向上を目指しています。
PMIは世界中に会員がいるため、その活動は国や業界を問わず幅広く認知されています。また、グローバルなネットワークを持ち、プロジェクトに携わる人なら誰でも参加できるコミュニティを提供しています。たとえば、多様な業界から参加者が集まり、情報交換や学びの場が用意されています。
日本では「プロジェクトマネジメント協会=PMI」という呼び名が定着しており、PMI日本支部も1998年から活動しています。日本支部は、セミナーや学習イベント、認定資格に関する案内など、多くの機会を設けており、日本国内でも広く認知されています。
PMIの主な役割は次の通りです。
- 専門知識の共有と能力開発
- マネジメントの国際標準や資格認定の提供
- キャリアや組織の成功に役立つ研究や出版物の発行
- 世界規模のネットワーキングやコミュニティ形成
このような活動を通じて、PMIは、個人がプロジェクトを確実に進める力を高め、また、組織が安定して成果を上げられる環境づくりに貢献しています。
次の章に記載するタイトル:PMIが提供する主な資格と受験の基本
PMIが提供する主な資格と受験の基本

PMIの主要な資格一覧
PMI(プロジェクトマネジメント協会)は、プロジェクトマネジメントに関するさまざまな資格を提供しています。代表的なものには「PMP(プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル)」があります。こちらは、実際のプロジェクト運営を指導した経験や知識が求められるため、世界的にも知名度や信頼度が高い資格です。また、これからプロジェクトマネジメントを学ぶ方向けの「CAPM(認定アソシエイト・イン・プロジェクトマネジメント)」も人気です。
加えて、複数プロジェクトの統括に特化した「PgMP(プログラム・マネジメント・プロフェッショナル)」や、組織全体のポートフォリオ管理を重視する「PfMP(ポートフォリオ・マネジメント・プロフェッショナル)」、さらには「PMI-ACP(アジャイル認定プロフェッショナル)」など、業務の内容やレベルに合わせてさまざまな資格が設けられています。
日本における受験の流れ
日本国内での資格試験は、主にピアソンVUEという試験センターで実施しています。試験はコンピューターを使用し、会場での受験が基本です。特にPMPについては、世界で利用されている在宅監督型(OnVUE)が日本では利用できず、指定された会場へ足を運ぶ必要があります。
PMP資格の特徴と維持方法
PMP資格は、ただ取得するだけでは終わりません。取得後も定期的な更新が必要で、その条件として「PDU(継続専門能力開発単位)」という単位の取得が求められます。このシステムにより、知識のアップデートや専門性の維持ができる仕組みになっています。PMPをはじめとするPMI資格は資格そのものの認知度や実務での活用範囲が広いため、多くの企業で高く評価されています。
次の章に記載するタイトル:PMBOK(ピンボック)と標準の位置づけ
PMBOK(ピンボック)と標準の位置づけ

PMBOKとは?
PMBOK(ピンボック)は、「A Guide to the Project Management Body of Knowledge」の略称です。これは、プロジェクトマネジメントに欠かせない知識や考え方を体系的にまとめたガイドラインです。PMIが作成しており、世界中で幅広く活用されています。
PMBOKの改訂と特徴
初版が出版されて以来、おおよそ4年ごとに内容を見直し、現代のビジネス環境に合うよう改訂が続けられています。2021年に発行された第7版では、従来の手順重視から一歩進み、「価値の提供」や「基本原則」にフォーカスを当てるアプローチにシフトしました。このことで、より柔軟に各プロジェクトの特徴や環境に対応しやすくなっています。
業界横断のスタンダード
PMBOKはITや建設、製造などさまざまな分野で活用される知識体系です。特定の業種だけでなく、多種多様なプロジェクトにも適用できます。例えば、製品開発の進め方を整理したいときや、大きなイベント運営の流れを明確にしたいときにも参考にできます。
実務との関係
PMBOKは決してマニュアルではなく、必ずこうするという指示書でもありません。むしろ、プロジェクトを進めるうえでの「基礎」や「考え方」を提供しています。実際の現場では、自分たちの状況に合わせてこの知識体系を柔軟に使うことが大切です。
次の章に記載するタイトル:日本国内の関連団体と活動
日本国内の関連団体と活動

日本国内には、プロジェクトマネジメントの普及と発展を支えるさまざまな関連団体が活動しています。ここでは、代表的な団体とその主な取り組みについてご紹介します。
PMI日本支部(PMI Japan Chapter)
PMI日本支部は、プロジェクトマネジメントを学びたい方や、これから始めたい方を対象に、初心者向け講座や勉強会、コミュニティイベントを積極的に開催しています。例えば、「頑張る私のPM道場」というプログラムでは、PM(プロジェクトマネジメント)の基本を基礎から分かりやすく学ぶことができます。参加者同士で学び合いながら、ネットワークを広げられるのも特長です。
日本PMO協会(NPMO)
日本PMO協会は、プロジェクトマネジメントやPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)の知識と技能を広めるために設立された一般社団法人です。資格制度の運営、セミナーや研究会、コンサルティング、出版、会員組織の運営など、幅広い活動を行っています。特にPMO分野の認定資格や、実践的な研修・セミナーが特徴です。これにより、PM・PMO・ビジネススキルの向上を図りたい方にとって、非常に役立つ場となっています。
プロジェクトマネジメント学会・シンポジウム
国内には、プロジェクトマネジメント学会も存在します。毎年、シンポジウムを開催しており、例えば「次世代の日本を共に描く ~今、必要とされるプログラム&プロジェクトマネジメント~」というテーマで業界の最新動向や実践事例が紹介されています。こうしたイベントは、知識のアップデートや、同じ関心を持つ人同士の交流の場として好評です。
次の章に記載するタイトル:日本発の知識体系:P2Mの存在
日本発の知識体系:P2Mの存在

P2Mとは何か?
P2M(Project & Program Management)は、日本で生まれたプロジェクトマネジメント手法です。この考え方では、個々のプロジェクトだけでなく、複数のプロジェクトをまとめて進める「プログラム」の管理も大事にしています。たとえば、ビル建設・IT導入・教育活動など、複雑に絡み合う複数のプロジェクトが一つの大きな目標に向かう場合、全体をまとめてうまく進行させるためにP2Mが力を発揮します。
PMIやPMBOKとの違い
PMIやその標準ガイドであるPMBOKが、主に一つ一つのプロジェクト運営に強いのに対し、P2Mは「大きな枠組み」で全体をどう進めるかに重きを置いています。言い換えれば、P2Mでは組織や社会全体の目標を達成するため、連携する複数プロジェクトの調整や資源配分など上の視点から考えることができるのです。
日本での活用例
日本では特に官公庁の大規模開発や、交通・インフラ整備など複合的な事業でP2Mの知識体系が活用されることがあります。また、P2Mの内容に基づく資格や研修も提供されており、PMBOKと合わせて学ぶことで管理の幅が広がります。
併せて学ぶメリット
P2MとPMBOKの両方を知ると、実際の仕事で使える引き出しが増えます。個人のプロジェクト進行方法に加え、組織全体を俯瞰して動かす力を養える点が特徴です。
次の章に記載するタイトル:資格学習で押さえるべきキーワードと用語
資格学習で押さえるべきキーワードと用語

プロジェクトと運営管理の違い
まず「プロジェクト」と「運営管理」の違いを押さえましょう。プロジェクトは「明確な始まり」と「終わり」がある一時的な活動です。例えば、新しいアプリの開発やイベントの開催など、目的が達成されたら完了します。
一方、運営管理は日常的・継続的な業務(ルーティンワーク)の管理です。たとえば会社の経理や店舗運営のような、終わりのない仕事を指します。
プロジェクトライフサイクル
プロジェクト学習で頻出するキーワードに「プロジェクトライフサイクル」があります。これはプロジェクトの始まりから終わりまでの流れを段階ごとに区切ったものです。それぞれの段階を「フェーズ」と呼び、計画→実施→完了という流れをたどります。フェーズごとに進め方や必要な成果物が異なります。
プロセスグループ
プロジェクトを管理する際には「プロセスグループ」という考え方を使います。これは主に5つのグループ(立上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結)に分かれています。
- 立上げ:プロジェクトを正式に始める準備(ゴールや責任者の決定など)
- 計画:やるべきことや期限などを具体的に決めていきます
- 実行:チームで計画に沿って作業を進めます
- 監視・コントロール:進捗や課題をチェックし、必要があれば調整します
- 終結:成果を確認し、関係者に報告した上で、正式にプロジェクトを終えます
学習への活用と効率的なアプローチ
初学者の方は、PMI日本支部が開催している入門イベントや初級講座を活用するのが効果的です。基礎用語や流れを実際の事例と合わせて学べるため、実務にも役立てやすくなります。
次の章に記載するタイトル:キャリアとメリット(PMP・PMIの価値)
キャリアとメリット(PMP・PMIの価値)
PMI資格がキャリアに与える影響
PMIの資格、特にPMP(Project Management Professional)は、プロジェクトマネジメントの世界で広く認知されています。IT、建設、製造、金融など、さまざまな業界で通用する“共通言語”の役割を果たします。資格を持っていると、プロジェクトを効率的に進めるための知識や実務力を備えている証拠として企業に評価されやすくなります。
PMP資格のメリット
PMP資格を取得すると、転職や昇進の場面で有利になるケースが多いです。求人情報に「PMP保有者歓迎」といった記載が見られることも増えつつあります。また、プロジェクトを成功に導いた経験やスキルを第三者が認める仕組みのため、自信をもって自らの価値をアピールできます。年収アップを目指す方や、担当プロジェクトの規模拡大を目指す方にも強みになります。
継続学習と専門性の維持
PMPなどのPMI資格は、取得しただけで終わりではありません。資格を維持するためには「PDU(Professional Development Units)」と呼ばれる継続学習が必要です。例えば、セミナーへの参加、書籍での学習、現場での実践活動などがPDUに該当します。この仕組みにより、常に新しい知識が身に付き、実践的なスキルを磨き続けることが可能です。長いキャリア形成を見据えた場合にもメリットが大きいのが特徴です。
次の章に記載するタイトル:参加・受験・学びの実践ステップ(例)
参加・受験・学びの実践ステップ(例)
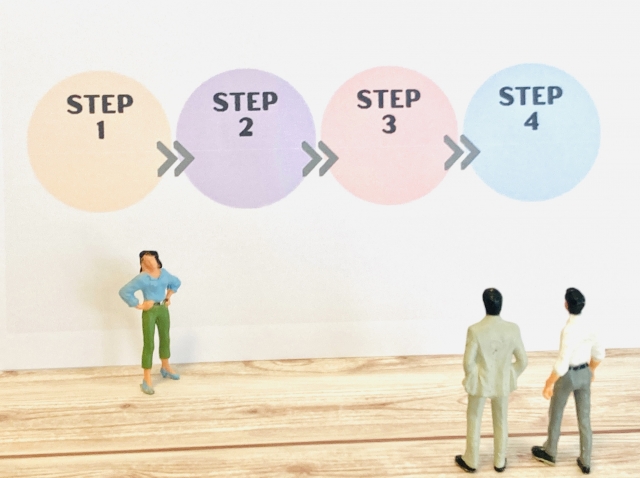
1. 目的を明確にする
資格取得を目指す際には、なぜPMIの資格を取るのかをはっきりさせましょう。例えば、PMP資格を取得して自分のプロジェクトマネジメント(PM)力を証明したい、あるいはPMO(プロジェクト管理組織)の専門知識を深めたい――という具体的な目標が大切です。明確な目的があれば、学習のモチベーションもぐっと高まります。
2. 学習計画の立て方
次に必要なのは学習計画の作成です。PMBOK(ピンボック)第7版をしっかり理解することから始め、模擬試験を用いて実践力をチェックしましょう。分かりにくい用語は自分なりに整理してノートにまとめたり、1日●ページや1週●章といった具体的な学習スケジュールを組んだりすると習慣化しやすいです。
3. コミュニティの活用
一人で学習を続けるのは難しいものです。PMI日本支部などが主催している入門講座や勉強会は、同じ目標を持った仲間と出会う良い機会です。国内シンポジウムなどで最新の実例や知見交換もでき、自分の理解が深まり、また励ましにもなります。
4. 試験本番に向けて
実際に受験申請を行う際は、指定のピアソンVUEテストセンターから試験予約をします。日本国内のPMP資格試験は会場受験が原則です(自宅受験ではないので注意)。また、資格取得後は定期的な更新が必要です。更新のためにはCPD(継続的専門能力開発)活動の計画を立てておきましょう。
5. PMO志向の場合の工夫
もしPMOや組織全体のPM能力向上を目指すなら、日本PMO協会が提供している資格やセミナーの情報も活用しましょう。PMP資格と組み合わせれば、より幅広い知識と実践経験を得ることができます。
次の章に記載するタイトル:よくある疑問への要点回答
よくある疑問への要点回答

PMIとPMPの違いについて
PMIとは「プロジェクトマネジメント協会」という団体を指します。一方、PMPは「プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル」という、PMIが主催し認定する資格の名称です。団体と資格を混同しやすいですが、PMPはPMIが提供する代表的な資格であると覚えておくと分かりやすいでしょう。
PMBOKとPMPの学び方について
PMBOKとは、PMIがまとめたプロジェクトマネジメントの知識体系ガイドです。PMPの取得を目指す際、多くの人がPMBOKに沿って学習します。第7版では原則志向が強化され、従来の方法論だけでなく、アジャイル(柔軟で変化に強い進め方)やハイブリッド(複数手法の混合)も対象となっています。
日本独自の知識体系「P2M」とは?
P2Mは、プログラムマネジメントに特化した日本発の知識体系です。複数のプロジェクトをまとめて管理し、より大きな成果や価値を生み出すためのフレームワークとして作られました。企業の成長戦略や社会インフラなど大規模プロジェクトの運用に特に強みがあります。
PMO向けの資格や協会
プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)向けの公式な協会や認定資格は、日本PMO協会が提供しています。組織横断でプロジェクトを支援する役割に就く方は、この協会や資格を検討すると良いでしょう。
次は「主要情報源の信頼性メモ」についてご案内します。
主要情報源の信頼性メモ
信頼できる情報源を押さえておくことは、プロジェクトマネジメントの学習や資格取得においてとても重要です。ここでは、代表的な信頼性の高い情報源と、それぞれの特徴についてご紹介します。
公式情報源について
まず、最も信頼性が高いとされるのは公式系の情報源です。たとえば、PMI認定試験を運営する「ピアソンVUE」のサイトは正確な試験情報や受験手続きが常に最新の内容で提供されています。また、「PMI日本支部」の公式サイトやイベント情報も、資格の内容や活動情報を確実に把握できる場です。さらに、「NPMO協会」の公式サイトも、国内のプロジェクトマネジメント動向の一次情報として活用できます。
これらは一次情報源と呼ばれ、間に誰かの解釈や要約が入らず、公式に発表されているという安心感があります。重要な変更点や発表は、まず公式サイトで確認するクセをつけると良いでしょう。
解説・補助情報について
一方、学習サイトや書籍、資格スクールの「PMP」「PMBOK」解説記事も多く出回っています。これらは分かりやすくまとめられているため、基礎知識の整理や用語の理解には役立ちます。ただし、参考として使う場合は情報が最新版(PMBOK第7版など)に沿っているか、ページの更新日や筆者の専門性も合わせてチェックしましょう。
特にネット上の記事やブログは、古いバージョンの内容がそのまま残っている場合もあります。必ず一次情報を優先し、分からない点は公式サイトで再確認することをおすすめします。
次の章に記載するタイトル:補足(用語のクイック定義)
補足(用語のクイック定義)
この章では、プロジェクトマネジメントに関してよく使われる主要な用語を、初めての方にもわかりやすく簡潔にまとめました。資格取得や学習を進めるうえで役立つはずです。
PMI(プロジェクトマネジメント協会)
アメリカに本部を置く非営利団体です。世界中でプロジェクトマネジメントの知識や資格、交流の場を提供しています。
PMBOK(ピンボック)
PMIが作成したプロジェクトマネジメントの知識体系ガイドです。標準的な手法と考え方がまとめられています。
PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)
実務経験を持つ方向けの、PMIの代表的な国際資格です。プロジェクトを管理・運営する力を証明できるものです。
CAPM(認定アソシエイト・プロジェクトマネジメント)
プロジェクトマネジメントの知識が基礎からあることを示す入門者レベルの資格です。
P2M
日本で開発されたプロジェクト&プログラムマネジメントの体系です。日本のビジネスの現場に即して作られています。
PMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)
複数のプロジェクトを横断的に管理・サポートする専門部署のことをいいます。
日本PMO協会
日本においてPMOの普及や知識体系づくり、資格認定を行っている団体です。
これらの用語は、どれもプロジェクトマネジメントの学習・実践で頻繁に出てきます。用語の意味を押さえておくと、資格勉強や現場での会話もスムーズです。