この記事でわかること
- プロジェクトチャーター(憲章)の定義と目的
- 主な構成要素(目的・範囲・リスク・関係者など)の理解
- 他文書(計画書・チームチャーター)との違いと使い分け方
- 実務での作成手順とテンプレート活用のコツ
- 実際の活用例と成功に導く運用ポイント
目次
プロジェクトチャーターとは何か

プロジェクトチャーター(プロジェクト憲章)は、プロジェクトをスタートさせる際に正式に作成される、とても重要な書類です。
この文書が作成されることで、そのプロジェクトが会社や組織から正式に認められたことになります。
同時に、この書類によってプロジェクトマネージャーやメンバーは、プロジェクトを進めるために必要な権限や役割を与えられます。
プロジェクトチャーターには主に、取り組むプロジェクトの目的(なぜ実施するのか)、範囲(どこまでを対象とするのか)、目指す目標(何を達成したいのか)、関係する人たち(誰が関わるのか)といった基本情報が記載されます。
例えば、新しい商品を開発するプロジェクトの場合、「何のための商品か」「開発のゴール」「関わる部署やメンバー」などが明記されます。そのため、プロジェクトに携わる全員が「このプロジェクトはこういうものだ」と同じ理解を持てるようになるのです。
また、PMBOKガイドという国際的な基準書でも「プロジェクトチャーターはプロジェクトの存在を正式に認可する文書であり、プロジェクトマネージャーに資源を使う権限を与える」と定義されています。
つまり、プロジェクトチャーターはプロジェクトを始める上での“許可証”ともいえる存在です。
プロジェクトチャーターの主な構成要素
■ プロジェクト定義まとめ表
| 項目 | 内容のポイント |
|---|---|
| 1. プロジェクトの目的と背景 | なぜ実施するのか、ビジネス上の理由や課題を明記する |
| 2. 目標・成果物 | 達成したい具体的な結果や、完成するアウトプットを示す |
| 3. スコープ(範囲)と制約事項 | 対応範囲・対象外の内容、期間・予算・リソースなどの制約を整理する |
| 4. 前提条件とリスク | 想定している条件や、発生しうるリスクと影響を記載する |
| 5. 主要ステークホルダー | 関係者・担当範囲・役割を明確にする |
| 6. PMの権限と責任範囲 | どんな判断をできるか、どこまで責任を持つかを定義する |
| 7. タイムライン・マイルストーン | 主要スケジュールと重要な節目を整理する |
| 8. 予算とリソース概要 | 必要な費用・人員・外部リソースの見積りを示す |
| 9. 成功基準 | プロジェクトが成功したと言える状態を定義する |
プロジェクトチャーターは、プロジェクトの計画を明確にするために必要な情報がまとめられた文書です。
ここでは、一般的に含まれる主な構成要素について詳しくご説明します。
1. プロジェクトの目的と背景
まず、なぜこのプロジェクトを行うのか、その理由や必要性を明記します。たとえば、「新しい顧客管理システムを導入し、業務効率を上げること」など、ビジネス上の動機や背景を書くことで、関係者全員が共通の理解を持てるようにします。
2. プロジェクトの目標・成果物
プロジェクトを通じて達成したい具体的な目標と、得られる成果物を記載します。たとえば、「3か月以内にWebサイトを公開する」「新商品を開発する」など、成果が分かりやすい形で記載します。
3. スコープ(範囲)と制約事項
プロジェクトで対応する作業の範囲や、逆に含まれない内容を明記します。また、期間や予算、利用できる人や道具といった制約も合わせて書きます。こうすることで、後から想定外の作業が増えるのを防ぐ効果があります。
4. 前提条件とリスク
プロジェクト開始時点で想定している前提条件や、起こりうるリスクも記載します。例えば「必要な人員が1か月後に確保できることを前提とする」や、「外部業者が遅延する可能性がある」などです。
5. 主要なステークホルダー
プロジェクトの関係者や、その中で誰が何の役割を担当するかをはっきりさせます。これにより、協力体制を明確にし、情報伝達のミスを防ぎます。
6. プロジェクトマネージャーの権限・責任
プロジェクトマネージャーがどんな決定を下せるのか、どこまで責任を持つのかを明記します。たとえば「予算の範囲内で購入を決定できる」など、実務に即した内容が求められます。
7. タイムライン・マイルストーン
プロジェクトの主要なスケジュールや、重要な節目(マイルストーン)を示します。例えば「4月末までに設計を完了」「6月に試作品を完成」などです。
8. 予算やリソースの概要
プロジェクトに必要な予算や人員などの資源をざっくりと見積もります。こうした情報があると、無理のない計画が立てやすくなります。
9. 成功基準
プロジェクトが成功したと言える状態がどんなものか、明確に基準を設けます。たとえば「予定通り納品できたか」「目標の利用者数を達成したか」などです。
以上が、プロジェクトチャーターに含まれる主な要素です。ひとつひとつを丁寧に書くことで、計画の抜けや漏れを防ぎます。
プロジェクトチャーターの重要性と役割

プロジェクトチャーターは、プロジェクトのスタートを公式に認める大事な書類です。
これが発行されることで「このプロジェクトは正式に始まっています」と関係者全員が認識しやすくなります。
そのため、曖昧なまま作業が始まってしまうことを防ぎ、後々のトラブルを避ける役割を果たします。
また、プロジェクトチャーターは目的や目標、関わるメンバーの役割を文書に明確にします。
たとえば「なぜこのプロジェクトをするのか」「どんな成果を目指すのか」「誰が何を担当するのか」などを書き出しておくことで、意見の食い違いを減らし、みんなが同じ方向を向きやすくなります。
組織内で意見の衝突が起きがちな場面でも、プロジェクトチャーターがあることで冷静に話し合う土台となります。
さらに、プロジェクトを進めるリーダー(プロジェクトマネージャー)には、プロジェクトチャーターによって必要な権限やリソースが与えられます。
たとえば、予算や人員をどのように使うか、どのような判断を下せるかがここで明確になるのです。
これは実際にプロジェクトをしっかり動かすための「お墨付き」とも言えます。
そして、プロジェクトチャーターはこれから進む計画や作業の道しるべにもなります。
計画段階や実行時に「最初に決めたことからずれていないか?」「目的に沿った進み方をしているか?」を確認しやすくなるため、プロジェクトのブレを防ぎやすくなります。
プロジェクトチャーターの作成手順・テンプレート活用
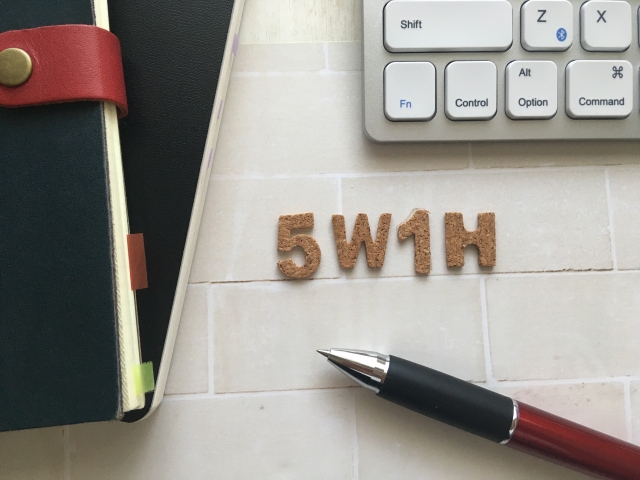
1. 情報収集から始めましょう
プロジェクトチャーターを作る際、まずやるべきことは情報集めです。
プロジェクトの目的や背景、達成すべきこと、関係者など、必要な情報をしっかり集めましょう。
例えば、「新製品の開発」であれば、市場のニーズや競合の情報、チームの体制なども参考になります。
2. 構成要素を整理する
集めた情報は、そのまま書き出すのではなく、「何を・なぜ・どうやって」行うのかという観点で整理します。
プロジェクトの目的(なぜやるのか)、目標(何を達成するのか)、スコープ(どこまでを対象とするのか)、関係者(誰がかかわるのか)などの要素ごとに分かりやすくまとめましょう。
3. 視覚的に、簡潔に表現
説明を文章だけでなく、表や図、チャートを使ってまとめることで、内容がすぐに伝わります。
たとえば進行スケジュールをガントチャートにしたり、関係者の担当範囲を図で示すと、関係者全員が理解しやすくなります。
長い説明よりも、ポイントを絞った短い文章と図が効果的です。
4. テンプレートを活用する
一から書くのは大変なので、既存のテンプレートを使うのがおすすめです。
インターネット上でWordやExcel、Googleドキュメント形式の雛形が多く見つかります。
1ページにまとめたシンプルなものから、スライド形式で発表にすぐ使えるものまで、用途に合わせて選べます。
5. ステークホルダーのレビューと修正
作成したチャーターは、プロジェクトに関わるメンバーや上司、依頼主などに確認をとりましょう。
意見をもらったら必要に応じて修正し、全員が納得できる内容に仕上げることが肝心です。
このプロセスによって、後々のトラブルも防げます。
テンプレート活用のポイント
- シンプルな構成のものから始める
- 不要な情報は省いてA4一枚や1スライドで作成
- 例:Googleで「プロジェクトチャーター テンプレート」と検索すると多数ヒットします
プロジェクトチャーターと他文書の違い
プロジェクトチャーターと他文書の違い・使い分け表
| 項目 | プロジェクトチャーター | プロジェクト計画書 | チームチャーター |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | プロジェクト開始の承認と権限付与 | プロジェクトの進め方・管理方法を具体化 | チーム内の役割・ルール・行動方針を明確化 |
| いつ作るか | 立ち上げ時(開始前) | 承認後、計画段階で作成 | チーム形成時・計画作成と並行して作成 |
| 誰に向けた文書か | 経営層・依頼者・主要関係者 | チーム内外の実務担当者 | チームメンバー中心 |
| 主な内容 | 目的、背景、成果物、責任者の権限、成功基準など | スケジュール、役割分担、リスク、予算、管理方法など | 会議ルール、意思決定方法、コミュニケーション方針など |
| 役割の違い | プロジェクトの存在を公式化する | 実行のための行動指針や進め方を定める | チーム内の働き方・協力体制を整える |
| 関係性 | プロジェクトの出発点となる土台 | その上に積み上げる行動の地図 | 地図を基に動くチームの動作ルール |
| 注意点 | 抽象的になりすぎないこと | 実行可能性と現実性を持たせること | 守られるルールとして合意形成すること |
| 活用ポイント | 権限、目的、期待値をクリアに共有すると手戻りが減る | 計画は見直しを前提に更新する | チームで合意し、振り返りの材料として使う |
プロジェクトの運営では、さまざまな文書が使われます。
その中でも「プロジェクトチャーター」と混同しやすい文書に、プロジェクト計画書やチームチャーターがあります。
それぞれの違いをしっかり理解することが、円滑なプロジェクト運営に役立ちます。
プロジェクトチャーターとは何か
プロジェクトチャーターは「このプロジェクトを正式に始めてよい」という承認を得るための文書です。
例えば、新しい商品を開発すると決めたとき、このプロジェクトが会社から正式に認められて動き出すためには、プロジェクトチャーターが必要です。
これにより、リーダーやメンバーはプロジェクト遂行のための権限を得ます。
プロジェクト計画書との違い
プロジェクト計画書は、プロジェクトチャーターが承認された後で作成されることが多い文書です。
主に「誰が、いつ、どのように進めるか」など、プロジェクトを詳細に管理する計画をまとめます。
たとえば、開発スケジュールや担当メンバーの割り当て、リスクへの対応策などが具体的に記載されます。
プロジェクトチャーターが“スタートの許可証”だとすれば、計画書は“行動の地図”のようなものです。
チームチャーターとの違い
チームチャーターは、プロジェクトのチーム内での役割やルールを決めるための文書です。
たとえば「会議は毎週○曜日に実施する」「意思決定は全員で合意を取る」など、チーム内の行動規範が中心となります。
一方でプロジェクトチャーターは、プロジェクト全体の目的やゴール、プロジェクトリーダーの権限といった大枠を記載します。
そのため、チームの内側の話に限定せず、経営層や関係者全体に向けて示すという役割があります。
使い分けのポイント
プロジェクトチャーターは「プロジェクトを始めてよい」という土台となる文書、計画書はその上に積み上げる具体的な進め方を示すもの、チームチャーターはさらにその中でのチーム運営規則となります。
これらを使い分けることで、役割の混乱や無駄な手戻りを防げます。
活用時のポイントと注意事項

プロジェクトチャーターを最大限に活用するためには、いくつかの大切なポイントと注意事項があります。
ここでは、初めての方でも迷わずプロジェクトチャーターを運用できるコツを解説します。
1. 全体像を分かりやすくまとめる
プロジェクトチャーターは、関係者が「このプロジェクトは何を目指すのか」をぱっと見て分かる資料です。
目的、目標、スコープ(範囲)など、主要な要素を簡潔かつ具体的にまとめましょう。
文章が長くなりすぎたり、専門用語が多すぎると、関係者が理解しにくくなります。
たとえば「新商品開発プロジェクト」であれば、「新しいスナック菓子の発売を目標とし、2024年中に全国展開を目指す」など、誰でもイメージできる形で書くことが大切です。
2. テンプレートで内容を確認
チャーターには入れるべき要素(目的、成果物、主なスケジュール、担当者など)が決まっています。
なにか抜けている部分がないか、テンプレートに沿ってチェックしましょう。
団体や業界によっては推奨フォーマットが公開されています。
3. 合意形成と定期的な振り返り
一度作ったら終わりではありません。作成後は必ず関係者に配布し、内容に同意できているか確認しましょう。
プロジェクトの進行中にも定期的に見直すことで、目標や状況のズレに気づけます。
そして合意済みのチャーターを軸に話し合えば、トラブル防止にも役立ちます。
例えば、「途中で納期や品質に関する意見が対立したとき、最初に合意したチャーターをもとに再調整する」といった活用法です。
4. 大規模プロジェクトでは補足資料も用意
参加人数や範囲が大きい場合、チャーター単体では詳細が不足しがちです。
その場合は、詳細な業務分担表やリスク一覧など、追加資料を別途作ると良いでしょう。
チャーターはあくまで全体像の共有が目的なので、細かい内容は補足資料でサポートします。
プロジェクトチャーターの実務活用例

新規システム導入プロジェクトでの活用例
例えば、ある企業が新しい勤怠管理システムを導入する際、プロジェクトチャーターはとても役立ちます。
まずチャーターで、目的(勤怠管理の効率化)、対象範囲(全社員の勤怠記録)、スケジュール(1年以内の導入)などを明確にしました。
これによって、関係者全員がプロジェクトに期待する成果や進め方を同じように理解でき、経営層の承認もスムーズに得られました。
また、途中で「なぜこのシステムが必要なのか」といった疑問が生じても、チャーターを見返すことで根拠や方針を確認でき、軌道修正もしやすくなります。
業務改善プロジェクトの場合
部署間の業務フローを見直すような改善プロジェクトを始めるときにも、プロジェクトチャーターが重宝されます。
たとえば、営業部と経理部の連携を強化するプロジェクトで、現状の課題や目標、関係者、想定されるリスクなどをチャーターに整理しました。これにより、異なる部門同士での認識ずれがなくなり、開始前からゴールや手順が明確になるなど、円滑なプロジェクト運営が実現しました。
アジャイル開発での組み合わせ活用
最近注目されているアジャイル開発の手法でもプロジェクトチャーターは有効です。
例えば「インセプションデッキ」と呼ばれるワークショップ形式のツールと合わせて使われます。
プロジェクトの意義や優先順位を話し合い、チャーターで決めた内容を参照しながら作業を進めることで、開発メンバー全員が同じ方向に進みやすくなるのです。
まとめ

本記事では、プロジェクトチャーターの基本から実務での活用例まで、幅広く解説しました。プロジェクトチャーターは、プロジェクトの方向性や目的、主要な関係者、範囲などを明確にする公式な文書です。
この一枚の文書を用意することで、関係者同士の認識を合わせ、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
実際の作成では、定型のテンプレートやチェックリストを活用しながらも、実際のプロジェクト内容に合わせて適切にカスタマイズすることが重要です。また、他のプロジェクト関連文書と混同しないよう、役割や特徴を理解し、図や事例を盛り込むことで具体性を高めると良いでしょう。
プロジェクトチャーターの理解と運用力は、プロジェクト成功の土台となります。ぜひ本記事を参考に、ご自身のプロジェクトにも導入してみてください。