この記事でわかること
- 「プロジェクトマネジメント義務」とは何か、その基本的な考え方
- 善管注意義務との違いと、法的な根拠の有無
- IT業界などで問題になりやすい実務上の事例と責任範囲
- 契約形態(請負・準委任)による義務の違いと適用ポイント
- 紛争を防ぐための契約書・プロジェクト管理上の注意点
目次
プロジェクトマネジメント義務とは
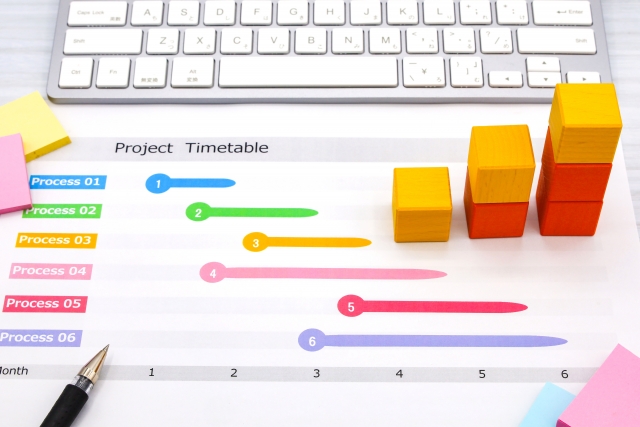
プロジェクトマネジメント義務の概要
プロジェクトマネジメント義務とは、特にIT業界などで受託者がシステム開発やプロジェクト全体をしっかり管理し、納期や品質、リスクなどを適切にコントロールする責任のことを指します。たとえば、ITベンダーがソフトウェアを開発する場合、計画を立て、進捗状況を常に把握し、問題が生じそうな時にはすぐに対応策を講じることが求められます。
法律には書かれていないが重要
この義務は、民法などの法律に具体的な条文があるわけではありません。しかし、多くの裁判例で「受託者はプロジェクト全体を見渡して適切に管理する責任がある」と判断されています。つまり、実務の中で少しずつ認識され、今では当たり前のように考えられています。
具体的に求められる内容
プロジェクトマネジメント義務の内容としては、次のようなものがあります。
- 進捗のチェック:計画通りに作業が進んでいるかを定期的に確認します
- リスク対策:何か問題が起きそうなら早めに察知し、解決策を検討します
- 納期の管理:完成期限を守るために、必要な調整や追加作業を行います
- ユーザーサポート:システムの発注者が専門知識に詳しくない場合は、分かりやすく状況説明したり、決断をサポートしたりします
例えば、開発の途中で想定していなかったトラブルが起こった時、単に発注者の指示を待つのではなく、受託者自身が問題の原因を調べ、どう対応するか提案する姿勢が必要です。東京地裁の判例でも、「進捗の遅れや問題が発生した場合、積極的に管理、対応すること」がプロジェクトマネジメント義務に含まれるとされています。
次の章では、善管注意義務について解説します。
善管注意義務とは

善管注意義務の概要
善管注意義務とは、民法第644条で定められている法律上の義務です。正式には「善良な管理者の注意義務」と呼ばれ、契約によって何らかの業務を任された場合に、その業務を担当する人が普通の人よりも少し高いレベルの注意を払って仕事をしなければならない、という決まりです。
善管注意義務の対象となるケース
この義務は、特に「準委任契約」や「委任契約」と呼ばれる契約形態で適用されます。たとえば、ITエンジニアにシステムの保守管理を依頼したり、コンサルタントに経営のアドバイスをお願いする場合が該当します。
実際の内容と特徴
善管注意義務では、「契約で約束した内容に従い、一般的な人や同じ業務をする人なら当然気をつけるべきレベルの注意」を持って業務を進めることを求めます。たとえば、エンジニアなら、通常行われるセキュリティ更新を忘れず実施する、コンサルタントなら業界の最新情報を踏まえて提言を行う、といったことです。
特徴的なのは、「必ず結果を出さなければならない」という義務(完成義務)は負わない点です。つまり、最善を尽くしても、期待通りの成果が得られなかった場合でも、義務違反にはなりません。ただし、明らかに注意が足りなかった場合や、基本的なミスがあった場合は、問題になることもあります。
次の章では、「プロジェクトマネジメント義務」と善管注意義務の違いについて詳しく解説します。
両者の違い

法的根拠の違い
プロジェクトマネジメント義務と善管注意義務には、そもそも根拠となる部分が異なります。プロジェクトマネジメント義務は、主に契約書や裁判例で具体的に定められます。たとえば、ITシステムの開発契約に「進捗状況の報告を定期的に行う」「リスクの予測や対策を実施する」といった条項が入ることで、義務内容がはっきりします。一方、善管注意義務は民法第644条という法律そのものに根拠があり、幅広い業務委託契約に適用される原則です。
担当者・対象となる範囲の違い
プロジェクトマネジメント義務の主な対象は、ITベンダーなど受託者側です。たとえばシステム開発会社が契約先企業の要望通りにプロジェクトを進める責任を負います。善管注意義務の場合は、委任・準委任契約を結んだ受任者全般が対象です。身近なところでは、会計士や弁護士が顧客の依頼を受けて業務を遂行する際にも、この義務が発生します。
業務内容・責任範囲の違い
プロジェクトマネジメント義務は、プロジェクト全体を適切に計画し、進捗やリスクまで細かく管理することが求められます。そして、その具体的な範囲や基準は、契約や個別の裁判例で詳細に定義されます。たとえば「どこまでリスク管理を徹底しなければいけないのか」「何を報告する義務があるのか」が明文化されています。
これに対し善管注意義務は、「一般的に期待される注意レベルで業務を行うこと」が求められます。たとえば「普通の弁護士ならここまで調査するだろう」「会計士ならこの程度確認するだろう」という基準で業務遂行が判断されます。
契約形態と実務での使い分け
成果物の完成責任が強く求められる契約(例:システム開発の請負契約)では、プロジェクトマネジメント義務が重視されます。一方で、仕事の過程を重視する契約(例:コンサルティングなどの準委任契約)では、善管注意義務が特に重要となります。
次の章では、「実務で生じる影響と紛争事例」について解説します。
実務で生じる影響と紛争事例

実務における影響
システム開発やITプロジェクトの現場では、プロジェクトマネジメント義務と善管注意義務がどのように働いているかによって、トラブルの発生しやすさやその後の対応が大きく変わります。
例えば、プロジェクトマネジメント義務のある契約であれば、ベンダー(開発会社)は進捗管理表を用いて定期的に報告し、リスクが大きくなる前に積極的にユーザー側と調整を重ねます。もしこの管理が不十分だった場合、「進捗遅延が発生したが事前連絡がなく、納期に間に合わなかった」といったトラブルに発展しやすいです。
一方、善管注意義務が重視されるケースでは、たとえばシステムの保守業務や、専門知識をもってアドバイスをする場面が該当します。この場合、受任者(専門家や技術者)は、通常期待される注意や配慮をしっかり行えば、仮に成果物が完成しなくても法的責任を問われないことがあります。実際、想定外の技術的困難が発生した場合でも、注意深く対応した記録があれば、紛争に発展しにくくなります。
代表的な紛争事例
実際にあったトラブルの例としては、「契約のどちらが適用されるか分かりにくく、責任の所在が曖昧だった」ことから、裁判になったケースがあります。たとえば、大規模なシステム導入プロジェクトでユーザーとベンダーが話し合いを十分に行っていなかったため、納品後に大幅な修正や追加費用が発生し、どちらが責任を負うのかで訴訟が起こることがありました。
また、善管注意義務に基づく契約では、「必要な調査や助言を全力で行ってきたか」が裁判の争点となりやすいです。システムの障害が発生したが、業界標準の対策や十分な報告がなされていれば、ベンダー側の責任は認められない判断も多いです。
トラブルを防ぐには
どちらの義務が契約に該当するかは、現実的には契約書の内容、契約形態(請負か準委任か)、過去の裁判例がカギとなります。実務では、契約書で「どこまで責任を負うのか」「何を期待するのか」を明確に定め、お互いに認識のずれがないようにすることがトラブル防止につながります。
次の章に記載するタイトル:まとめ
まとめ

本記事では、「プロジェクトマネジメント義務」と「善管注意義務」の違いを具体的に解説し、実務でどのような影響が生じるか、また実際の紛争事例を交えてご紹介しました。
プロジェクトマネジメント義務は、主にシステム開発や業務委託契約など現代的なビジネス現場で重視される義務です。これは単に与えられた業務を行うだけでなく、計画の策定や進捗管理、納品に至るまでの全体の流れをしっかりと管理する役割を持っています。一方、善管注意義務は、受託者として一般的・常識的に注意すべきことを守る義務であり、民法でも定められています。
両者の違いを正しく押さえ、契約段階でそれぞれの義務内容や責任範囲を具体的に記載することは、後のトラブルを未然に防ぐために欠かせません。実際、契約書で曖昧な点が残ると、後になって「どこまでやるべきだったのか」という争いになりやすいのが現状です。
日々の契約書作成や運用、万が一のトラブル対応に際しては、この記事でまとめたポイントを参考に、実務に活かしていただければと思います。