目次
- この記事でわかること
- 実践講座を選ぶ基準:短期で“できる”に到達する設計か
- 1日で基礎~実務の型まで掴む:E-PROJECT「プロジェクトマネジメント実践研修」
- 幅広いラインナップとオンライン運営力:インソース「プロジェクトマネジメント研修」
- PMO協会による“決定版”の実践型:日本PMO協会「【法人向け】実践型 プロジェクトマネジメント研修」
- 比較・選び方のポイント(タイプ別)
- 無料で試す・広く学ぶ:体験セミナーとeラーニングの活用
- 実務で即使うスキルの具体例(演習で作る成果物)
- オンライン開催の品質チェックリスト
- 価格感と導入の目安
- 比較リスト(用途別の向き不向き)
- よくある導入目的と期待成果
- 失敗しない選定ステップ
この記事でわかること
- 実践講座を選ぶ基準
短期集中・成果重視の設計になっているかを見極めるポイントが理解できる。 - 学び方の工夫
座学・グループワーク・成果物作成を組み合わせ、知識を「知っている」から「できる」に変える方法がわかる。 - 主要研修の特徴
E-PROJECT、インソース、日本PMO協会など代表的な研修プログラムの特徴と違いが整理できる。 - タイプ別の選び方
短期実践型、資格重視型、PMO戦略型、ソフトスキル特化型など、自分に合った研修タイプを見極められる。 - 導入と活用のポイント
オンライン開催の品質チェック、費用感、期待できる成果、選定ステップまでが理解でき、失敗しない選び方ができる。
実践講座を選ぶ基準:短期で“できる”に到達する設計か

プロジェクトマネジメント(PM)の研修や講座を選ぶ際、多くの方が「短期間で実務に活かせるスキルを身につけたい」とお考えかと思います。いわゆる“実践講座”の中でも、短期集中かつ成果重視の設計かどうかが非常に大切なポイントです。
座学×グループワーク×成果物作成の組み合わせ
実務直結型の講座は、知識習得(座学)だけでなく、グループでのディスカッションや、実際に手を動かして成果物を作る演習をセットにしているものが多くあります。この成果物には、作業分担を整理する「WBS(作業分解構成図)」や、進捗管理に欠かせない「ガントチャート」、責任範囲を明確にする「RACI表」や、さまざまなリスクをまとめた「リスク管理表」などが含まれます。これらを作る過程で、「知っている」だけでなく「実際にできる」状態へとスキルが進化します。
演習とフィードバックの反復
「知識を得る→すぐ演習する→現場でどう活かすかを振り返る」というサイクルを短い時間で何度も回すことが、即戦力としての定着につながります。間違った点や良かった点について講師やグループ内からフィードバックが得られる仕組みがある講座は、とくに実践力が身につきやすいです。
短期間で要点を圧縮学習
多くの実践講座は、1日~3日程度の短期集中型に設計されています。最重要ポイントであるPMBOK(国際標準のプロジェクト管理知識体系)の要点を絞り込み、現場で“明日からどう動くか”に役立つ内容を、効率よく詰め込んで提供しています。特に、急にプロジェクトマネージャーの役割を任された方や、実装の現場で壁にぶつかっている方には、この短期集中型がマッチしやすいです。
オンライン開催の運営品質も要チェック
昨今ではオンライン研修が主流となりつつありますが、グループワークをどう運営できるかが講座選びの大きなポイントです。たとえば、数人ずつグループに分かれる「ブレイクアウトセッション」や、全員で同時に作業できる「ライブボード」、講師との質疑応答がしやすい「双方向性」のある設計かどうか。こうした運営品質に注目することで、対面型に近い学びを実現できます。
次の章では、1日の研修で基礎から実務の型まで身につく具体例として、「E-PROJECT『プロジェクトマネジメント実践研修』」をご紹介します。
1日で基礎~実務の型まで掴む:E-PROJECT「プロジェクトマネジメント実践研修」

E-PROJECT「プロジェクトマネジメント実践研修」は、1日でプロジェクトマネジメントの全体像をしっかりと身につけられることが大きな特徴です。目的は、計画や立案だけでなく、実行・管理・終了までの各段階ごとに“どこが重要なのか”を理解し、実際の現場で役立つスキルを磨くことにあります。
本研修は、理論を学ぶ座学と、グループワークを行う実践演習が組み合わさっています。参加者同士で話し合い、協力して進めるため「覚えるだけ」で終わらず、「どう使えばよいか」が感覚として身につきます。特に、リスク管理やスコープ(プロジェクトの範囲)管理、タイムマネジメントといった基礎的な内容から、最近注目されるアジャイル方式のセッションまでをカバーしています。数名のグループで話し合いながらケーススタディや演習に取り組み、現場で役立つ実践力を高めます。
特徴的なのは、具体的なツールやテンプレートを使って演習できる点です。「リスク分析表」や「タスクリスト」といった、実務現場でそのまま応用できる資料を用いるため、研修後すぐに自分の業務で活かせます。「まずこれをやってみよう」と一歩を踏み出すきっかけとなります。
実際に研修を受けた方の声として、基礎から応用まで幅広く学べたことや、アジャイルの雰囲気を体験できたことが評価されています。また、グループワークによる「チームで進める経験」から、コミュニケーション力や協働力が高まったとの声も多いです。新入社員はもちろん、実務経験が浅い方にも価値があり、様々な層の参加者から支持されています。
料金は、1日研修の場合おおよそ「30,000円(税込)/6名以上」が目安です。人数や内容に合わせて柔軟なカスタマイズも相談できます。
次の章に記載するタイトル:幅広いラインナップとオンライン運営力:インソース「プロジェクトマネジメント研修」
幅広いラインナップとオンライン運営力:インソース「プロジェクトマネジメント研修」

インソースの「プロジェクトマネジメント研修」は、幅広い受講者層に対応したラインナップと、充実したオンライン運営力が大きな特長です。若手社員から管理職まで、それぞれのレベルや役職ごとに3つの系統に分かれたコース設計を採用しています。それぞれの研修では、プロジェクトの進め方全体像や「どの場面で何をすべきか」を、ワーク(実践的な課題やディスカッション)を中心に学びます。このワークは、スケジュール管理・コスト管理・関係者とのコミュニケーションといった、実際目の前で起こるプロジェクトの場面で役立つ内容です。
オンライン研修においても、講師がライブで進行し、グループワークを積極的に取り入れることで、従来の集合研修に近い学びの体験を提供しています。自宅や職場からでも臨場感を持ち、同期の受講者と交流しながら進められるため、参加へのハードルも低くなっています。
また、インソースでは動画教材やeラーニング、冊子教材、基礎知識・リスク管理・課題設定などに対応したテスト付き教材など、多層的なコンテンツも用意しています。これにより、忙しいビジネスパーソンでも自分に合った学習方法を選べます。
Q&Aによるサポートもわかりやすく、研修内容の具体的な実施可否や、現場での導入イメージについて質問できるため、安心してスタートできる点が魅力です。
次の章に記載するタイトル:PMO協会による“決定版”の実践型:日本PMO協会「【法人向け】実践型 プロジェクトマネジメント研修」
PMO協会による“決定版”の実践型:日本PMO協会「【法人向け】実践型 プロジェクトマネジメント研修」

日本PMO協会が提供する「【法人向け】実践型 プロジェクトマネジメント研修」は、プロジェクトマネジメントの根本から実務での応用までを網羅する決定版の研修です。ほかの研修と大きく異なるのは、知識を「聞いて終わり」にせず、すぐにチームや現場で役立つ“実装力”として身につける設計です。
参加型の学習スタイル
この研修は講師による一方通行の解説スタイルではなく、対話型の講義やゲーム、グループワーク中心で進みます。たとえば、架空のプロジェクトシナリオを基にグループごとに分かれて目標設定や計画立案を行い、途中で発生するトラブルにも対応しながら、受講者全員で学びを深めます。このような体験型の進行によって、知識と実践が結びつきやすくなります。
厳選された講師陣
講師には、PMに必要な資格を持った人や、実際に大規模なプロジェクトの現場を経験した専門家がそろっています。単にテキストで学ぶのではなく、「現実の現場でこう活かせる」という具体例を多数提示してくれるので、実務未経験者でも腹落ちしやすい内容です。
重要スキルの身につき方
研修では、プロジェクトやPM(プロジェクトマネージャー)の本質を重視します。目の前の作業に追われるだけでなく、「未来をどう描くか」「その未来実現のためにどう計画し、実行途中でどう見直すか」など、コンピテンシー(能力要素)として重要な思考法も学べます。具体的には、
- ヴィジョンシートを使った目標設定
- 実行計画の作成
- マヌーバリング(計画軌道の修正と実行)の練習
などを、研修の中で実際に体験します。
成果物テンプレートも充実
実務ですぐ使える「プロジェクト宣言書」「WBS(作業分解図)」「ガントチャート」「RACI(責任分担表)」「コスト・リスク管理表」「終了宣言書」など、多様な成果物テンプレートも研修内で一通り扱います。したがって、終了後はすぐに社内プロジェクトにそのまま活用できる実践力が身につきます。
次の章に記載するタイトル:比較・選び方のポイント(タイプ別)
比較・選び方のポイント(タイプ別)

短期集中・実践特化型を選ぶ場合
短期間で成果を求める現場向きです。このタイプの研修は、数日間で必須スキルを集中的に学び、演習を通じて知識を実践に落とし込めます。たとえば「急にPM(プロジェクトマネージャー)に任命された」「すぐに使える力が欲しい」という方にピッタリです。内容は課題解決型のワークショップが多く、終わった直後から現場での行動に活かしやすいのが特徴です。
資格・理論体系重視型を選ぶ場合
資格取得や理論体系の理解を重視する方は、PMBOK(プロジェクトマネジメントの標準ガイド)などを学ぶカリキュラムが合います。こうした研修では「PDU」「CPU」などの資格更新ポイントを取得できます。理論の裏付けが職場での説得力にもつながるため、実践型と並行して受講することで理解と定着が深まります。
戦略・PMO構築型を選ぶ場合
大規模プロジェクトや全社的な標準化、ガバナンス強化を目指す場合は、このタイプの研修が適しています。具体的には「プロジェクト横断で仕組みを整えたい」「意志決定の流れを明確にしたい」などのニーズに応えます。実際のプロジェクト事例に基づく演習が含まれることも多いです。
ソフトスキル特化型を選ぶ場合
プロジェクトを成功させるには技術的な知識だけでなく、チームビルディングやコミュニケーション力も欠かせません。ソフトスキル特化型研修では、「複数部署との調整」「説明や交渉」「チームのモチベーション維持」など、人間関係や働きかけに強くなれる内容が中心です。現場マネジメント力を伸ばしたい方におすすめです。
次の章に記載するタイトル:無料で試す・広く学ぶ:体験セミナーとeラーニングの活用
無料で試す・広く学ぶ:体験セミナーとeラーニングの活用

プロジェクトマネジメントを学ぶ際、まずは気軽に体験したい、コストを抑えて幅広く知りたいという方も多いのではないでしょうか。実は、無料で参加できる体験セミナーや、家庭・職場で活用できるeラーニング教材は非常に有効です。
体験セミナーで「やってみる」
具体例として、JPSビジネスカレッジが提供する「実践型プロジェクトマネジメント研修無料セミナー」があります。こういった体験セミナーは、講師の話を聞くだけでなく、参加者同士でグループワークやケーススタディを実際に行えるのが特徴です。これにより、プロジェクトの進め方を実感として掴みやすくなります。理論だけでなく「どうやって計画を立てるのか」「トラブルのとき、どんな行動が必要か」など、実際の現場に近い形で体験できるのでおすすめです。さらに、講師や他の受講者との交流から、最新の手法や話題も得られやすいというメリットがあります。
eラーニングの便利な使い方
また、受講スタイルに柔軟性を求める場合はeラーニングも有効です。たとえばインソースでは、動画や冊子教材を組み合わせた学習コンテンツと、それに連動したテストも利用できます。自分の都合に合わせて学習を進めることができ、復習や繰り返し学習にも役立ちます。加えて、自社内で教育を完結したい場合(内製育成)や、社員全体に均一な知識を手軽に配布したい場合にも向いています。忙しい方や、地方にいる方にとっても参加のハードルが低い点は魅力的です。
次の章では、実務で即使うスキルの具体例と、演習を通じて得られる成果物についてご紹介します。
実務で即使うスキルの具体例(演習で作る成果物)

研修で学ぶ内容が現場でどのように役立つのか、具体的な演習成果物を使ってご紹介します。実際のプロジェクト現場ですぐに活用できるスキルや資料が身につきます。
計画・分解:WBSやスコープの明確化
プロジェクトの第一歩は計画です。演習では最初に「WBS(作業分解構成図)」を作成します。たとえば、イベント開催なら「会場準備」「集客」「当日運営」といった大きな流れを細かい作業に分けて一覧にまとめます。同時に「スコープ明確化シート」や「成果物定義書」を使い、作業範囲や作るべきモノが何かを全員で確認します。
スケジュール作成:ガントチャートやマイルストーン
次に、「ガントチャート」を使ってスケジュールを可視化します。いつ、誰が、何をするかを横軸で表現し、一目で進捗が分かります。重要な節目は「マイルストーン」として明確に設定。「クリティカル経路」という、遅れると全体が遅延するポイントにも注目し、計画の見直し力も鍛えます。
役割・責任分担:RACIチャートと承認経路
「RACIチャート」で誰が何を担当し、誰が最終的な判断をするかを整理します。例えば『作業担当(Responsible)』『最終決定者(Accountable)』『支援者(Consulted)』『報告先(Informed)』に分け、迷いのない担当分担を目指します。承認フロー図も併用し、書類や成果物の回覧ルートを明確化します。
コスト・リスク管理:管理表やリスク登録簿
予算やリスク管理も重要です。「コスト管理表」には予算、支出、予測残高を記入し、管理の手間を減らします。「リスク登録簿」では、想定されるリスクの内容、危険度、どんな対応策を取るか、いつ警戒サインが出るか(トリガー)までまとめます。
プロジェクト基盤:ヴィジョンシートや宣言書
プロジェクトそのものの目的やゴールも演習で言語化します。「ヴィジョンシート」で何を目指すのかを整理。「プロジェクト宣言書」は開始時点での立ち上げ理由や目標をまとめた資料です。終わった時には「終了宣言書」で完了条件や学んだことを明記します。
運営・アジャイル:タイムマネジメントやアジャイル体験
日々のプロジェクト運営には「タイムマネジメント表」で作業の時間配分を見直します。アジャイル手法の演習も行い、短い周期で実際に成果を振り返り、必要に応じて目標や方法を調整することも体験できます。
次の章:オンライン開催の品質チェックリスト
オンライン開催の品質チェックリスト
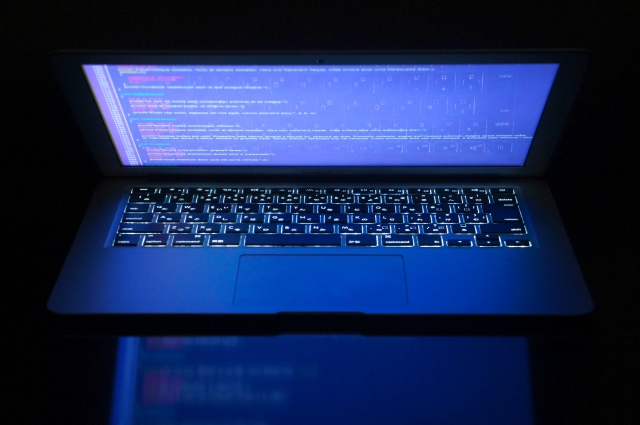
1. 双方向性の仕組みが整っているか
オンライン研修では、講師が一方向に話すだけでは理解が深まりにくいです。たとえば、ZoomやTeamsの画面共有だけでなく、講師がリアルタイムで進行をコントロールし、受講生の発言や質問に積極的に答える仕掛けが必要です。また、オンライン上のホワイトボード機能を活用して、その場で図や意見を可視化できると、理解がさらに深まります。ほかにも、途中で投票機能を使ったり、チャットを用いて意見交換を行う方法も効果的です。
2. グループワークや小演習の存在
実践的なスキルを身につけるには、受講生同士の交流や協働が欠かせません。ブレイクアウトルーム(小部屋機能)を使って少人数のグループでの演習やディスカッションを設けているかどうかは重要なチェックポイントです。これにより、受講生は実際の現場でのやり取りに近い体験を積むことができます。
3. 成果物の共同編集がしやすい環境
プロジェクト管理では、WBS(作業分解構成図)やガントチャート、RACI表(役割分担表)などの成果物が欠かせません。研修内でこれらを作る際、専用テンプレートの事前提供やGoogleドキュメントなどの共同編集ツールの活用があるかどうかを確認しましょう。受講生全員で同じファイルを同時に編集することで、実践力が自然と身につきます。
4. 受講後のアフターフォロー
学びを職場で活かすためには、受講後のサポートが大切です。研修の資料や録画の提供があるか、学びを定着させる小テストや職場への持ち帰り課題が用意されているかを確認しましょう。さらに、講師や事務局からのフィードバックがあると、自分の成長を客観的に振り返ることができます。
次の章に記載するタイトル:価格感と導入の目安
価格感と導入の目安
1日で完結する法人向けプロジェクトマネジメント実践研修の費用について、多くの研修会社では、参加者1人あたりの単価や1回(1クラス)ごとの一式料金で提示するケースが一般的です。例えば、E-PROJECTの「1日研修」は、参加者6名以上という制限付きで1名あたりおよそ30,000円(税込)が目安となっています。人数や実施内容によっては、カスタマイズ見積もりの相談も可能です。
また、研修会社によってはオンライン形式で実施することにより「オンライン割引」が用意されていたり、eラーニングと組み合わせて申し込むことでボリュームディスカウントが適用される場合もあります。特に多人数・継続的な導入を検討している企業にとっては、このような割引制度の有無を事前に確認しておくと安心です。
加えて、プロジェクトマネジメント資格更新に必要な「PDU(プロフェッショナル開発単位)」の付与対象かどうかも、選定時のチェックポイントとなります。PDU付与の有無によって受講者や企業のメリットが変わるため、ニーズに合わせて比較するとよいでしょう。
次の章に記載するタイトル:比較リスト(用途別の向き不向き)
比較リスト(用途別の向き不向き)

主要研修ごとの特徴一覧
プロジェクトマネジメント研修には多彩な種類があり、用途や受講者の目的によって最適な選択が変わります。ここでは代表的な研修を用途ごとに分け、その向き不向きを整理しました。
1. E-PROJECT:明日から現場で使える力を重視
「現場で明日から使える実践的な方法を知りたい」という目的には、E-PROJECTの実践研修が適しています。フェーズ横断型のカリキュラムで、プロジェクト計画から実装、振り返りまでを1日で体験。ワークシートやツール演習も充実しているので、短期間で現場力を養いたい方に向いています。しかし、幅広い理論や体系的知識の網羅にはやや物足りないかもしれません。
2. インソース:体系的な学び×オンライン活用
「会社全体で研修を内製化したい」「幅広く基礎から網羅的に学びたい」方はインソースの研修がおすすめです。1日で全体像を学べるうえ、オンライン運営やeラーニング、確認テスト、冊子教材まで幅広いサポートが特徴。自社の研修制度やフォロー体制と組み合わせると効果的です。反面、実務演習や個別具体の課題解決には追加フォローが必要な場合があります。
3. 日本PMO協会:全体設計×勝ち筋モデル重視
「PMO視点を採り入れ、プロジェクト成功パターンを知りたい」方には日本PMO協会の実践型研修が最適です。プロジェクトのヴィジョン策定から終了宣言まで、一貫してマネジメントツールを用いた成果物作りに取り組みます。個々のスキルアップだけでなく、プロジェクト横断での“勝ち筋”設計を学びたい方向き。PMO未経験者や理論ベースの学習が目的の方にはハードルが高いこともあります。
4. まとめ記事:比較軸で全体を俯瞰
「限られた予算や期間、資格取得やソフトスキルも視野に入れたい」なら、研修比較まとめ記事が参考になります。短期集中タイプ・資格対応型・PMO支援型・ソフトスキル重視など、自分の課題や目的に合わせて選択可能です。
次の章では、「よくある導入目的と期待成果」をご紹介します。
よくある導入目的と期待成果
プロジェクトマネジメント研修は、さまざまな状況や課題に合わせて導入されることが多いです。ここでは、よくある導入目的と、それによって得られる期待成果について分かりやすく解説します。
急遽PMに任命された方の立ち上げ支援
突然プロジェクトリーダーに指名された中堅社員の方が、短期間で現場で必要なマネジメントの型やツールを身につけるため、1~3日で集中して学べる実践型研修の需要があります。たとえば、WBS(作業分解図)の作成や進捗・課題管理の手法、関係者への報告書作成など、すぐに現場で活かせる内容が中心となります。このような導入目的の場合、研修後すぐに「実務で役立つ手順」や「成果物のサンプル」を自分のものにできる成果が期待されています。
部署横断プロジェクトの失敗防止
営業・開発・バックオフィスなど複数部署が関わるプロジェクトでは、スコープ管理(=範囲の明確化)、リスク管理、コミュニケーションのズレがよく問題になります。こうした失敗要因を減らし、プロジェクトを円滑に進めるために研修を導入するケースが多く見られます。具体的には、関係者全員で合意できるルール作りや、リスクを洗い出して共有するワークショップなどを通じて、「チーム連携の強化」や「トラブル予防」が成果として狙われます。
PMO設置・標準化推進
プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の設置や、社内基準の標準化を目指す企業でも、研修が重宝されています。宣言書(プロジェクト憲章)の策定、役割分担表(RACIチャート)、マイルストーンレビューや終了宣言の作成方法など、組織全体に共通言語や共通手順を根付かせるための内容が求められています。期待される成果は、「全社的なプロジェクト運営レベルの底上げ」や「共通フォーマットの浸透」となります。
次の章では、失敗しない選定ステップについて解説します。
失敗しない選定ステップ

プロジェクトマネジメント研修の選定で失敗しないためには、具体的なステップに沿って検討を進めることが大切です。
1. 現場の課題・ボトルネックを把握する
まず、自社の現場で何が問題なのか見極めましょう。進捗管理がうまくいかない、コスト計算が煩雑、途中で要件がしょっちゅう変わる、関係者の意見がまとまらない、品質担保が難しい、リスクの予測や対策が課題…といった「どこで詰まって」いるかを具体的に書き出します。
2. 学びの成果物を明確にする
次に、研修を受けた後、現場に何を持ち帰りたいかイメージしておきます。例えば「自社オリジナルのWBSテンプレート(工程表)を作る」「RACI(役割分担表)でプロジェクトの見える化」「リスク対策表で未然防止を強化」など、実務現場ですぐ使える“形のある成果”を用意できるかをチェックしましょう。
3. 受講後の実装計画を立てる
学んだ内容を現場で定着させるため、受講後3週間ですぐに運用化する計画を立てます。
- 週に1回、研修の振り返りや進捗チェック(週次レビュー)
- 作った成果物(テンプレート等)は必ず本番で使ってみる
- 成果物や進め方について、簡単なふり返り(軽量レトロスペクティブ)を実施
この3段階で選定し、計画的に運用すれば、研修の効果を最大限に引き出すことができます。