この記事でわかること(主要5点)
- VUCA時代におけるプロジェクトの前提
「開始前に成否の半分が決まる」という考え方と、その理由(目的・意思決定・準備の重要性)を理解できます。 - プロジェクト成功のための設計ポイント
意味のある目的設定、期待値コントロール、最終意思決定者の明確化など、具体的な成功条件を学べます。 - 準備と初期フェーズの実務的工夫
役割分担・意思決定フロー・情報共有・初期ダッシュといった「開始時の整地」の実践方法がわかります。 - リスク回避と心理的安全性のつくり方
無理な案件の見極め方、断る勇気、早期SOSの仕組み化など、炎上を防ぐための具体策を知ることができます。 - 若手・初リーダーへの実践アドバイスと学習リソース
プロジェクトロジックの設計、転換点での心得、新装版『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』など参考リソースを活用した学び方を掴めます。
目次
VUCA時代の前提:プロジェクトは開始前に成否の半分が決まる

現代は「VUCA(ブーカ)」と呼ばれ、不確実性や複雑さが高まる時代と言われています。ビジネスの世界でも、何が起こるかわからない状況が日常となり、単純なルールや過去の経験だけでは通用しなくなっています。こうした中で、プロジェクト型の働き方が広まりつつありますが、従来のマニュアル通りの進め方はもはや十分ではありません。
山口氏は「プロジェクトの成否の50%は開始前に決まっている」と述べています。これは、目的や期待値のすり合わせ、誰が最終的な決定を下すのかといった意思決定の仕組み、プロジェクトメンバーや時間、情報の整え方――こうした前準備が、プロジェクトの成功に大きく影響するからです。
例えば、「何のためにこのプロジェクトをやるのか?」という意義が曖昧なまま進めると、途中でメンバーの足並みが揃わなくなりがちです。また、意思決定者が曖昧だと、ちょっとしたトラブルや判断の遅れが、大きな遅延や失敗につながります。
これからの時代に求められるのは、プロジェクトを単なる作業の連続ではなく、一つの「作品」として設計し、開始の段階からゴールまでの道筋をしっかり考えることです。準備段階の質が、その後の展開や成果に直結します。
次の章では、プロジェクト成功のカギを握る「意味のある目的」と「期待値の設計」について掘り下げます。
意味のある目的と「期待値」の設計
意味のある目的がプロジェクトを動かす
プロジェクトを開始する際、重要なのは「なぜこれをやるのか」という意味を明確にすることです。ただ与えられた目標を追いかけるのではなく、その目的が組織や社会にとってどのような価値を生むのかを整理し、誰もが納得できる形で言語化します。たとえば新しいサービスを作る場合でも「上司に指示されたから」では人は動きません。「顧客の困りごとを解決し、会社の成長に貢献する」と全員が納得できる目的があれば、チームの結束が高まります。
関係する人の「納得感」がカギ
プロジェクトでは、関わる人-上司や同僚、外部パートナーまで含めて-がその目的に納得していることがとても大切です。これを「腹落ち」と表現することもあります。もし、関係者が納得していないまま進むと、途中で異論や抵抗が生まれ、進行が滞ることがよくあります。そのため、関係者全員に目的をしっかり説明し、共感してもらうプロセスを怠らないようにしましょう。
「期待値」をコントロールする視点
また、プロジェクト成功の確率を高めるには「期待値」の設計がポイントです。期待値とは、プロジェクトの成果に対して周囲が自然にもつ「どの程度うまくいくか」「何を成し遂げるか」といった予測や希望を指します。最初から高いハードルを掲げてしまうと、チームの心理的な負担が大きくなったり、スタート直後に失望感を生むことがあります。そのため、計画の段階で「現実的な達成ライン」を設定し、「まずここまでクリアできれば十分」という段階的な目標が効果的です。
期待値は“やや低め”が実は有利
具体的には、成果やスケジュールなどを「少し余裕をもって」組み立てることが有効です。最初の目標を過度に高くすると、ちょっとした遅れやミスがすぐに「失敗」と認識されてしまいます。一方、控えめな目標設定なら、小さな成功の積み重ねで自信も育ちます。そして、徐々に期待値を上げて成果を広げていくことで、最後は大きな期待にも応えられるようになります。
次章では、「最終意思決定者は一人に:合議制の遅延リスクを断つ」について解説します。
最終意思決定者は一人に:合議制の遅延リスクを断つ

多数決ではなぜ遅れるのか
プロジェクトを進める上で「みんなで決めよう」というやり方は、一見フェアで納得感があるように見えます。しかし、多くの人が最終判断に関わると、どうしても意見のすりあわせや調整が発生し、ひとつの結論にたどり着くまでに時間がかかります。「全員一致でなければ先に進まない」といった状況になれば、些細な意見の違いでもプロジェクトはなかなか進みません。
責任の所在が曖昧になるリスク
決定が多数でなされる場合、後で問題が起きた際に「自分は反対だった」「みんなで決めたから自分だけの責任じゃない」という意識が生まれやすくなります。誰が本当に責任を持っていたのかが曖昧になれば、リーダーシップも弱くなり、重要なタイミングで判断が遅れるリスクが高まります。
最終意思決定者を一人に絞るメリット
プロジェクトの最終的な決断は、最終責任者が一人で担う体制を明確にしましょう。これにより、意思決定が格段に速くなり、何かトラブルが起きても「誰がどう判断し、次にどう動くか」が一目瞭然になります。
たとえば、指示を出す人が明確なプロジェクトでは、迷いなく方針転換や作業の優先順位づけができます。一方、合議制のままだと「誰かが決めてくれるだろう」「自分の意見は通らなかったし……」と当事者意識が薄れがちです。
現場でありがちな誤解と対策
「みんなの意見を聞かずに決めるのは独裁的では?」という声もよく聞かれます。しかし、最終決定者を一人に絞ることと、多様な意見を拾うことは両立できます。たとえば、最終的な意思決定の場では責任者を一人に定めつつも、途中段階では広く現場の声やアイデアを集める仕組みを併用することが有効です。
すぐに真似できるポイント
・会議の冒頭で、「今回の決断は誰が最終的に責任を持つか」を明確化する
・議論の途中で合意形成が難航していたら、「最終判断は○○さん」と整理する
・事後の評価も、最終責任者を中心に振り返る
プロジェクトをスムーズに進めるためには、「最終意思決定者を明確に一人にすること」が何より大切です。
次の章に記載するタイトル:舞台設定と初期ダッシュ:人・時間・情報の整地
舞台設定と初期ダッシュ:人・時間・情報の整地
役割と責任を明確にする
プロジェクトが始まる前に、まず「誰が何を担当するのか」をしっかり整理します。たとえば、資料作りはAさん、進捗管理はBさん、最終確認はCさん、のように担当者を決めることで、後に“あれ、これ誰がやる?”と迷う時間が減ります。
また、責任の範囲を具体的に伝えるとトラブルを未然に防げます。単に「この仕事を頼む」と伝えるだけでなく、「あなたがやってくれることで、全体がどう前に進むか」という目的も共有すると、みんなの納得感が上がります。
意思決定フローをはっきりさせる
どんなプロジェクトも途中で「判断が必要」な場面が何度もやってきます。この時に、「誰が最終判断するのか」「誰が意見を出すのか」「どうやって記録に残すか」など意思決定の流れを最初に整えておくことが大切です。
たとえば、週1回の定例ミーティングで主要な決断事項を洗い出し、記録してから実行しましょう。これにより、途中での曖昧さや責任のなすりつけを防ぐことができます。
コミュニケーション回路を作る
話し合いがきちんとできる“道”を最初に作ることで、プロジェクトはスムーズに進みます。グループチャット、共有ファイル、リマインダーなど、必要に応じてツールを揃えましょう。
また、「情報の出し惜しみ」は大敵です。関係者に必要な情報を“全員にはやく”届ける仕組み(例えば、朝会や簡単な週次メール)を作ることで、共通認識が生まれます。共通認識ができれば、手戻りや思わぬ誤解を減らせます。
初期ダッシュを意識する
プロジェクト開始直後の動きは、その後の進み具合に大きく関わります。序盤で小さな“できた”を早めに作り、それをみんなで共有すると、「うまくいきそう」という手応えと安心感が広がります。たとえば、1週目で「資料のたたき台を作る」「初回ミーティングで論点を洗い出す」など、全員が成果を体感できるゴールを置くのがポイントです。
論点や不安は後回しにせず、「問題の種」を出し切ることも重要です。スタートダッシュで摩擦があれば、早めに“ぶつかる”方が後からの修正が楽になります。いわば“喧嘩は早いうちに”。本音でぶつかることで、プロジェクトが進むうちに起きるすれ違いを防げます。
次の章に記載するタイトル:無理難題は「いったん断る」のが鉄則
無理難題は「いったん断る」のが鉄則

要求の目利きが、プロジェクトの未来を決める
プロジェクトを受ける際、最初に重要なのは「この案件は本当に成功できるかどうか」を見極める目利き力です。たとえば納期が極端に短い、予算が明らかに不足している、関係者がバラバラで意見がまとまっていない――こうした案件は、始まる前から危険信号が出ています。
こうした厳しい条件のプロジェクトを安易に引き受けると、後から状況が悪化しやすくなります。無理な案件ほど、炎上や失敗リスクが格段に高まります。したがって、「難しそうだ」と感じた際は、勇気を持っていったん断ることが、自分自身とチームを守る最善策です。
「まず断る」が基本の動き
断るのは、相手や上司に悪い印象を与えそうで抵抗を感じる方も多いかもしれません。しかし、「いったんお断りします」と丁寧に説明すれば、信頼を損なうことは意外とありません。むしろ無理を通して失敗するより、プロとしての判断力を評価されることも多いです。
たとえば「この期限内では品質を担保できません」や、「現状の体制では目標達成が難しいです」と具体的な理由を伝えましょう。どうしても引き受ける必要がある場合も、必ず条件やリスクを明示し、「見直しができる場合は再検討します」と伝える癖をつけることが大切です。
勝てる場所、自分が活躍できる案件を選ぶ
著者は「勝てるプロジェクトを選ぶ」ことが炎上を避ける最短ルートだと強調しています。プロジェクト管理の上手い下手は、実はもっと後の話。そもそも無謀な案件を避けることが、何よりも重要なのです。
例えば、チームの強みが活かせそうなテーマ、過去の経験が生かせる分野、関係者と信頼関係を築きやすい案件など、自分とチームに「勝ち筋」が見える仕事を選びましょう。それが自信につながり、結果的には周囲と良好な関係を築く近道でもあります。
次の章では、心理的安全性を運用に組み込むポイントについて解説します。
不安の共有と早期SOS:心理的安全性を運用に組み込む
プロジェクトが進む中で、メンバーや関係者が不安や懸念を抱えるのはごく自然なことです。ですが、これを「気のせい」「そのうち解消する」と放置してしまうと、小さな火種が大きなトラブルに発展します。そのため、不安や疑問は小さいうちにオープンに話し、「今のままで大丈夫?」と率直に共有する文化を作ることが重要です。
不安を共有できる場をつくる
プロジェクトリーダーやマネージャーは、定期的なミーティングや1on1面談などを活用し、メンバーが素直な気持ちを言いやすい空気づくりを心がけましょう。例えば「どんな些細なことでも気になったら教えてください」と繰り返し伝えるだけでも心理的ハードルを下げられます。
迷ったらすぐSOS、がルール
自分一人で抱え込まず「迷ったらすぐ助けを求める」をプロジェクト運用の明確なルールとして浸透させることも効果的です。初期の段階で問題をオープンにすれば、被害が広がる前に対応策を考えられるからです。たとえば「納期が厳しい」「技術的に難所がある」「連絡がうまく伝わっていない」など、小さな問題も報告・相談しやすい雰囲気を意識しましょう。
具体例:早期SOSが功を奏した現場
ある営業支援プロジェクトでは、メンバーの一人が新しいツールの使い方に不安を感じていました。早い段階で「自信が持てない」と共同リーダーに相談したことで、追加トレーニングを即時実施。結果、その後のみんなの作業効率が飛躍的に向上しました。このように、早期にSOSを出すことで、問題の潜伏期間を短縮し、プロジェクト全体の品質とスピードの両方が向上します。
小さな火種を消すことが大事故を防ぐ
心理的安全性をただのスローガンではなく、「実際の運用ルール」として根付かせることで、誰もが安心して「困った」「助けてほしい」と言える場になります。それが結果的に大きなピボット(方向転換)やトラブル対応もスムーズに行える強いチームにつながります。
次の章に記載するタイトル:プロジェクトロジックの設計:詰将棋のように「必ず出るアウトプット」を組む
プロジェクトロジックの設計:詰将棋のように「必ず出るアウトプット」を組む
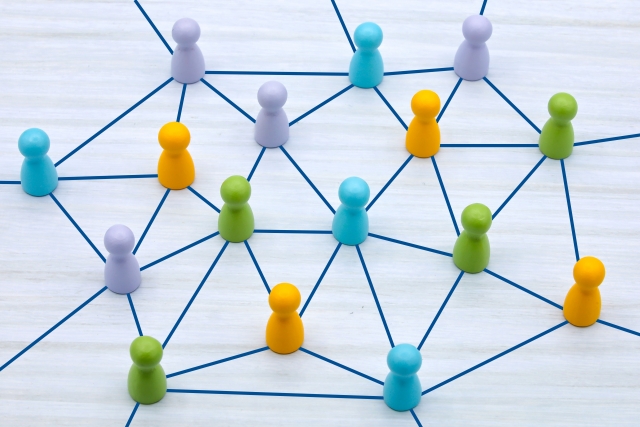
プロジェクトが成功する背景には、関係者の納得感やリスクへの備えだけでなく、「必ず狙った成果が出る筋道=プロジェクトロジック」の存在があります。これは山口氏が提唱する“詰将棋的”な設計思想に基づくものです。どの手順を取っても、最終的なアウトプットに辿り着けるよう、論理を組み立てておくことが必要なのです。
プロジェクトロジックとは?
プロジェクトロジックとは、ゴールに至るまでのプロセスが論理的につながっている状態を指します。たとえば、お料理レシピでいうなら「材料を切る」「炒める」「味付けする」のように、順を追って進めば必ず目的の料理が完成する状態と似ています。どこで誰が何をしても、本来の結果にブレが出ないように道筋を備える──これが“詰将棋”の考え方です。
具体例でイメージする
たとえば、社内イベントの準備プロジェクトを考えてみましょう。イベントの開催がゴールなら、
- 会場手配
- 参加者リストアップ
- 当日の進行表作成
など、順番に進めるべき工程があります。
ここで大切なのは、「どの工程も必ず次の成果物(アウトプット)につながる」ように設計することです。たとえば会場が確保できなければ代替案を用意する、参加者リストと進行表が連携される仕組みを作る、といった工夫が“詰将棋”の一手となります。
炎上を防ぐロジックチェックのすすめ
山口氏は過去著書でも「論理設計に無理やほころびがないかを点検することが、リスク低減に有効」と述べています。プロジェクト開始前に、各工程が本当に正しい順序に並び、抜け漏れや論理の飛躍がないか、一度図や表に洗い出してみることを強くおすすめします。作業が一つ抜けるだけでゴールに到達できなくなるような構造では、炎上のリスクが大きくなってしまうのです。
関係者が「腹落ち」できるシナリオ作り
また、プロジェクトの筋を明快に見せることで、関係者が「このやり方なら確かにうまくいきそうだ」と納得できます。各自がやるべきことや、もし問題が起きた場合の対応策をあらかじめ共有しておけば、不安や疑問も減り、現場の迷いや焦りも起きにくくなります。
次の章では、若手や初めてリーダーを担う方が押さえておきたいプロジェクト上の「転換点」について解説します。
若手・初リーダーが押さえるべき転換点
手続き処理型からプロジェクトマネジメント型へ
社会人のキャリアが進むにつれて、仕事の内容も変化します。最初は、決められた手順を丁寧にこなす「手続き処理型」の働き方が中心です。しかしプロジェクトを任されるようになると、指示待ちから、自分で方針を考え、成果物を生み出す「プロジェクトマネジメント型」にシフトします。この段階では、成果物がまさしく自分の作品となり、やりがいが格段に増します。多少の苦労があっても、プロジェクトが無事に完了した時の達成感は、何物にも代えがたい喜びです。
多様なチームでは一辺倒な管理は通用しない
プロジェクトリーダーが直面する現実の一つに、「チームの多様性」があります。年齢、専門分野、価値観が異なるメンバーが集まると、従来どおりの管理方法がうまくいきません。全員が一様に動いてくれるわけではなく、それぞれ異なる強みと弱みを持っています。ですので、メンバーの個性や特性を見極め、それぞれに合わせたコミュニケーションや役割分担が不可欠です。
初リーダーが優先すべき4つの行動
特に初めてリーダーを務める場合、何から手をつければよいか迷うものです。ここでは、押さえておきたい4つのポイントをご紹介します。
意思決定を一元化する
プロジェクトにおいて最も重要なのは、決定事項がどこで下されるのかを明確にすることです。曖昧な合議制を避け、最終的な決定者を一人に定めることで、進行の遅延や責任の分散を防げます。早期に論点を出す
気になることや揉めそうな点は、早めにテーブルに載せるのが鉄則です。問題点を先延ばしにすると、後から大きな障害になります。小さな違和感も初期段階で共有しましょう。期待値をコントロールする
チームや関係者ごとに「どこまでを、どのくらいの質や速度で求めているか」が異なります。期待値をすり合わせずに進めると、完成後に「思っていたものと違った」とトラブルになりがちです。適宜確認・調整しましょう。案件の目利き力をつける
すべてのプロジェクトを成功させるのは現実的ではありません。自分やチームの強みを生かせる案件は何か、勝算の高いプロジェクトを見極めて選べる力も重要です。
次の章に記載するタイトル:参考リソースと著書(新装版)
参考リソースと著書(新装版)

新装版『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』のご紹介
プロジェクトマネジメントについて深く学びたい方には、新装版『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』(大和書房、2023年6月15日発行)をおすすめします。本書は、多くの現場で高い評価を受けており、プロジェクトの始め方から実行、そして振り返りまでをわかりやすく解説しています。専門用語に偏りすぎず、誰にでも理解しやすい内容が特徴です。このため、初学者だけでなく、経験者の振り返りにも役立つと支持されています。
入手方法について
この書籍は、全国の書店やオンラインショップで新刊として購入できます。また、中古書籍市場でも流通しているため、状態や価格に合わせて多様な入手手段が利用できます。電子書籍版もあるため、タブレットやスマートフォンで手軽に読むことも可能です。
その他の学習リソース
書籍以外にも、プロジェクトマネジメントに関するさまざまな学習リソースが存在します。たとえば、公式のウェブサイトや、企業が発信するコラム、動画配信サービスなどです。これらを組み合わせることで、理論と実践の両面から学びを深められます。
本書の活用法
本書の各章には、具体的な事例や実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれています。単に読むだけでなく、自分のプロジェクト現場に照らしてアウトプットしたり、チーム内で章ごとにディスカッションするのも効果的です。また、不明点や疑問が出た場合は、関連するリソースや専門コミュニティを活用し、さらに理解を深めましょう。