この記事でわかること
- PM(IPA)とPMPの違いと特徴
- 合格率・試験形式・評価方法の比較
- 各試験の範囲と難所のポイント
- 用途別のおすすめ資格選び(国内・海外・初心者)
- 学習時間・勉強法・合格率の正しい見方
目次
まず押さえるべきは「PM(IPA)」と「PMP」

プロジェクトマネジメントに関心を持ったとき、多くの方が最初に目にするのが「PM(IPA)」と「PMP」という二つの資格です。ここでは、それぞれの特徴について分かりやすく整理します。
PM(IPA:情報処理推進機構 国家資格)とは?
日本で最も有名なプロジェクトマネージャ資格の一つが、IPA(情報処理推進機構)が実施するプロジェクトマネージャ試験、通称「PM」です。この資格は、国家資格に位置づけられており、ITやシステム開発の現場でプロジェクト責任者として活躍したい方に適しています。
合格率は例年13〜15%ほどとかなり低めで、受講者の中でも上位を占める難関の資格です。合格するには、特に午後IIの論文試験でA評価(高評価)を取る必要があり、ここが最大の壁となっています。論述式のため、知識だけでなく実際の経験や、現場で起こる課題を分かりやすく伝える力、論理的に説明する力が求められます。
PMP(Project Management Professional:国際資格)とは?
一方で「PMP」は、アメリカのPMI(プロジェクトマネジメント協会)が主催する、世界的に認知度の高い資格です。ITに限らず、建設や製造業など多種多様な業界で評価されており、日本国内はもちろん海外でも通用します。
PMP試験の合格率は公式には公表されていませんが、受験者の体験談や統計から、約50〜60%と推察されています。合格には、広い範囲の実務知識とプロジェクトマネジメント経験が必要です。受験要件に一定期間以上のプロジェクトマネジャー経験が含まれているため、完全な初心者には少しハードルが高いかもしれません。
PMPの試験は主に選択式問題(マークシート形式)で出題されます。難易度は中〜上級程度とされ、やや専門的な内容にも及びます。なお、入門編のCAPM(Certified Associate in Project Management)よりは難易度が高く設定されています。
次の章では、両資格の合格率や評価方式を実際のデータで比較していきます。
合格率・評価方式の実データ比較

PM(IPA)とPMPは、どちらもプロジェクトマネジメントに関連する代表的な資格ですが、合格率や評価の仕組みに違いがあります。
PM(IPA)の実データと評価方法
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施するプロジェクトマネージャ(PM)試験の直近データによると、令和5年度秋期の合格率は13.5%でした。受験者数は7,888人、合格者は1,066人で、平均年齢は38.1歳です。合格率の推移を見るとここ数年は13〜15%の間で安定しています。
PM試験の合否は、主に午後IIの論文で決まるのが特徴です。ここではA〜Dの4段階評価が用いられ、A判定が必須となります。午後IIでは、実務経験に基づいた具体的なプロジェクト事例やマネジメント手法について、自分の考えや対応策を書きます。そのため、受験者の経験と論述力が問われます。
PMPの合格率と難易度
一方、PMP試験の公式な合格率は公表されていません。しかし、受験者の体験談や各種調査から、目安としておおむね50〜60%が合格しているとされます。また、試験問題の正答率は60〜70%が目安となる場合が多いです。合格の可否はCBT(コンピュータベーステスト)上で出され、選択式の問題が中心です。
PMPは受験資格にプロジェクトマネジメント経験や教育要件が含まれるため、入門資格(例:CAPM)より高いレベルと位置づけられています。経験の有無も試験を通す上での重要なポイントとなります。
次の章では、試験範囲・出題形式と難所について詳しく解説します。
試験範囲・出題形式と難所
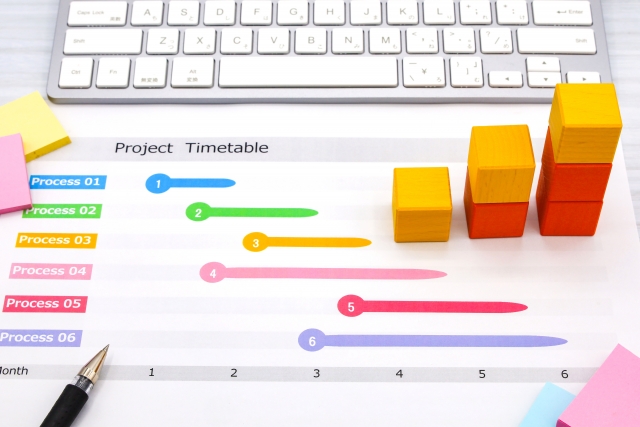
PM(IPA)の試験内容と特徴
PM(IPA)試験は、午前I・午前II・午後I・午後IIの4つのパートに分かれています。午前Iと午前IIでは主にマークシート方式や選択式の一般知識問題が出題され、幅広いITやプロジェクトマネジメントの知識が問われます。
午後Iでは記述問題が中心です。ここでは単なる知識だけでなく、実際にどう対応するかなど応用力が求められます。午後IIに進むと、論述(いわゆる論文)形式になります。自分のこれまでの経験や知識をもとに、論理的に説明する力が必要です。「実際にプロジェクトマネージャーを経験したことがある人」のリアルなエピソードや考え方の深さが評価されます。
具体例として、「トラブル発生時にどんな対応策を取るか」や「チームメンバーとのコミュニケーションで工夫したこと」など、自分なりの体験を論理立てて述べることが合格のカギです。こうした設問に対し、合格者は緻密な構成と実践的な視点で論述をまとめています。
PM(IPA)の難所
最も難しい点は午後IIの論述問題です。知識があるだけでは不十分で、計画的に論文対策を行う必要があります。特にITプロジェクト管理の実体験や自分の役割を振り返った上で、納得感のあるストーリーを作り上げる力が求められます。未経験からの独学ではこの部分が最大の壁となります。
PMP試験の内容と特徴
PMP試験は全部で180問の選択式問題から構成されています。このうち175問が採点対象で、残りの5問は統計上の調整用(プレテスト)として使われます。問題は広範なプロジェクトマネジメント知識を網羅しているうえ、実際のビジネスの場面を想定した状況対応問題も多く含まれています。
たとえば「予定外のリスクが発生した時、どのような判断を下すべきか」といった具体的なケーススタディが問われるため、単なる暗記で乗り切るのは難しいです。理論や知識だけでなく、実際の現場で活用するイメージを持って対策することが重要です。
PMP試験の難所
PMPは出題範囲が広いため、「どこまで学べばよいか」が分かりにくいと感じやすいです。また、知識の暗記だけでなく背景や理由を理解し、現場で応用できる力が問われる点もこたえます。問題文自体がやや長めな傾向があり、素早く内容を理解する読解力も不可欠です。
次の章に記載するタイトル:他の関連資格との位置づけ
他の関連資格との位置づけ

PM(IPA)やPMPに加えて、プロジェクトマネジメントにはいくつかの関連資格が存在します。それぞれの資格の特徴や位置づけを分かりやすく見ていきます。
CAPM(PMI)の特徴
CAPMはPMPと同じくPMIが認定する資格ですが、主にこれからプロジェクトマネジメントを学ぶ初級者向けです。PMPを本格的に目指す前のステップとして位置づけられています。試験の難易度もPMPより低く、基礎的な知識の確認が主な内容となります。
PRINCE2とITILの違い
PRINCE2はイギリス発祥のプロジェクトマネジメント資格で、厳密なプロセスや手順を重視するアプローチが特長です。ITILも同様にプロセス主導ですが、ITサービスマネジメント分野で知られています。合格率はPRINCE2が70〜75%、ITILは約90%とされ、難易度は相対的に低めです。
国内民間資格との比較
国内にも民間資格として、PMS(プロジェクトマネジメント・スペシャリスト)、PMC(プロジェクトマネジメント・コーディネーター)、PMR(プロジェクトマネジメント・レジスタード)などがあります。これらは合格率が約45〜78%と幅広く、受験者層や内容によって難易度も異なります。
まとめ
このように、プロジェクトマネジメント資格には段階や国ごとの違いがあります。どれを選ぶかは自分のキャリアプランや必要な知識レベルによって異なります。
次の章に記載するタイトル:どちらを選ぶべきか(用途別の目安)
どちらを選ぶべきか(用途別の目安)
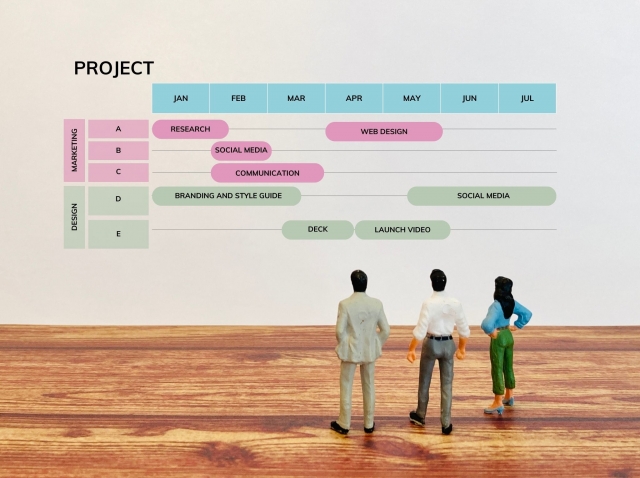
試験を選ぶ上でよくある悩みに、「PM(IPA)とPMP、どちらが自分に合っているのか?」というものがあります。この章では、目的やキャリアプランごとにどちらを選ぶべきか、目安としてご紹介します。
1. 国内IT業界・国家資格重視の場合
日本国内のIT業界や官公庁、SIer(システムインテグレーター)などでは、PM(IPA)の評価が非常に高いです。PM(IPA)は、実務経験や知識だけでなく、論述による高度な言語化力が問われるのが特徴です。特に「論文でどれだけ自分の実力・経験を説明できるか」という点が重視されます。国内でプロジェクトマネージャーとして長く活躍したい方、またはキャリアアップで説得力を持たせたい方におすすめです。
2. グローバル案件・外資志望ならPMP
PMPは世界的な評価を受けており、外資系企業や海外のプロジェクトに関わる際に特に役立ちます。プロジェクトマネジメントの標準的なフレームワークや用語を証明できる資格なので、社内外で共通認識を持って話ができます。転職やグローバルな業務を意識している方に最適です。
3. PMをこれから目指す・実務経験が短い人へ
PMPは一定の実務経験が前提となるため、まだ経験が浅い方にはハードルが高い場合があります。そのような場合、まずCAPMという入門資格で基礎知識を固め、その後実務経験を積んでPMPへ進むのが良い流れです。CAPMでも国際的な基本知識の証明となります。
用途や目指すキャリアに合わせて、資格選びを工夫しましょう。
次の章に記載するタイトル:想定学習時間・対策のコア
想定学習時間・対策のコア

PM(IPA)の学習時間と対策のポイント
PM(IPA)の試験に向けて必要な学習時間は、受験者の知識や経験により異なります。一般的には少なくとも200~300時間の勉強が必要とされます。特に注目したいのは午後試験の対策です。
午後Iでは応用的な問題に答えるため、過去問を繰り返し解くことが有効です。一度解いたら終わりではなく、解答例の記述や論理展開を自分の言葉で説明し直す練習も効果的です。
午後IIは記述量が多く、解答構成力や論理の一貫性が大切になります。合格者の多くは「設問の指示に真っすぐ答える」「必要なキーワードや事例を盛り込む」「字数制限を守る」ことを意識しています。例えば、模擬論述を繰り返し、3,000字の原稿を時間内に書き終える訓練を積みましょう。一度書いた論述は読み返し、無駄な説明や漏れをチェックすることが上達のカギです。
PMPの学習時間と対策のコア
PMPは出題範囲が広く、覚えるだけでなく運用力も要求されます。一般的な学習時間は150~200時間程度が目安ですが、「知らなかった」「経験がない」分野に出会うと、追加で時間をかけてカバーする必要があります。
対策としては、公式テキストや推奨書籍を分野ごとにチェックし、知識がどの場面で活用できるかをイメージしながら進めると効果的です。シナリオベースの問題では、実際の職場やプロジェクトで遭遇しそうな事例に置き換えて、どう対応するか考える習慣をつけましょう。
また、模擬試験をこまめに受けて、自分の弱い領域を確認し、重点的に復習することが合格の近道です。「本当に理解できているか?」を常に自分に問いかけながら進めてください。
次の章に記載するタイトル:合格率の見方と注意点
合格率の見方と注意点

資格試験を目指す上で、合格率はやはり気になるポイントですよね。しかし合格率の数字だけで難易度や自分との相性を測ろうとすると、思わぬ落とし穴があります。
PMPの合格率は“目安”として受け止める
PMP試験に関しては、合格率や合格基準となる点数を公式に発表していません。そのため「PMPの合格率は〇%」という声は、あくまで受験者の体験や外部調査会社がまとめたデータに基づいた目安となります。受験者によって試験内容や難易度が微妙に異なることもあり、正確な数字をもとにした比較は難しいです。ネットや書籍で紹介されているレンジ(例:60〜70%前後)を参考情報として捉えてください。
PM(IPA)の合格率は公的な実績
一方、PM(IPA)の合格率はIPAが公式に年次公表しています。たとえば直近数年では合格率が15%前後で推移しており、受験者のおよそ7人に1人が合格する計算です。数字としては低い部類に入り、対策の徹底や長期的な学習が不可欠と言えるでしょう。
合格率で「簡単さ」を判断しない
合格率が高い試験=簡単、低い=難しい、とは一概に言えません。受験者層や前提条件も異なれば、各試験団体の合格基準の考え方、問題傾向も違います。特にPMPのように国際資格の場合、合格ラインが受験者ごとに調整されることもある点に注意しましょう。
情報の出どころと“最新性”に注意
公表されていないPMPのデータや、複数年分の平均値だけで判断せず、具体的な体験談や最新の傾向も複数集めて参考にしてください。PM(IPA)の場合でも、年度ごとに難易度が若干変化するため、直近の合格率推移を確認するとよいでしょう。
次の章に記載するタイトル:具体的な勉強ステップ(タイプ別)
具体的な勉強ステップ(タイプ別)

IPA「PM」受験者向けの勉強法
IPAのプロジェクトマネージャ試験(PM)を目指す方は、午前試験から順を追って対策していくことがおすすめです。
午前対策
- まずは過去問を繰り返し解き、出題されやすいテーマに集中して知識を固めていきます。
- 暗記よりも、なぜその選択になるのか理由を考えることで応用力が身につきます。
午後I対策
- 設問がどんな意図で出されているのかを読み解く練習が効果的です。
- 問われている要点を短くまとめる記述のトレーニングも重要です。
- 実際に自分で記述し、解説と見比べて何が不足しているか確認しましょう。
午後II(論文)対策
- 論文問題は型(テンプレート)を用意しておき、毎回それに当てはめる練習をします。
- 問題の意図に合うこと、具体例を添えること、失敗体験や学び、再発防止策まで一貫した流れにすると読みやすくなります。
- 本番を想定した時間配分リハーサルも欠かせません。模擬論文を書いて、制限時間内にまとめられるようにしましょう。
PMP受験者向けの勉強法
PMP資格は受験前の準備や計画も重要です。
受験要件の確認・計画立て
- まず、自身が受験要件(学歴・経験年数・研修修了)を満たしているかをチェックします。
- 試験日を決め、逆算してスケジュールを立てましょう。
公式ガイドとドメイン整理
- 出題範囲となる"People"(人)、"Process"(工程)、"Business"(ビジネス)の3ドメインを体系的に整理します。
- アジャイルやハイブリッド型のマネジメントにも対応できるよう、関連事項を整理していきます。
模擬試験の活用・得点力アップ
- 模擬試験で実践的な問題に慣れることが得点力アップの近道です。
- 特に状況に応じた最適な判断を問う問題(シチュエーション問題)に慣れることが肝心です。
- 毎回の模試で60〜70%以上得点できるか確認し、理解が不十分な部分は振り返りましょう。
次の章に記載するタイトル:よくある質問(FAQ)
よくある質問(FAQ)

Q1. PM(IPA)とPMP、どちらに合格しやすいですか?
合格しやすさは単純に比較できませんが、公開されている合格率だけを見ると、PM(IPA)は毎年合格率が1割台、PMPは公式な発表ではありませんが約5〜6割とされます。この数字から見ると、一般的にはPMPの方が合格しやすいと感じる人が多いでしょう。ただし、PMPは受験資格として一定のプロジェクト経験や専用研修修了が必須ですし、試験自体も英語で受けるケースが多いため、単純な難易度比較はできません。
Q2. IT業界未経験者でもPM(IPA)やPMPは取れますか?
PM(IPA)は未経験でも合格の例がありますが、問題には実務的な内容や論述があるため難易度は高いです。特に午後II試験は想定プロジェクトの状況設定や判断根拠を文章でしっかり説明しなければならず、これが大きなハードルになります。PMPはそもそもプロジェクト経験が受験条件なので、未経験者では受験できません。
Q3. 合格後の評価はどの程度期待できますか?
PM(IPA)合格は、高度なIT人材としての証明になります。ITスキル標準(レベル4)に相当し、大企業や専門職でのキャリアアップ、応募条件や昇進要件で有利に働くことが多いです。
PMPは海外プロジェクトや外資系企業でグローバルスタンダードとして認知されています。国際標準のプロセス理解と実施能力を証明するため、国内外の多様な業界で評価されます。
Q4. どちらも取得した方が良いですか?
キャリアの進み方や職種によります。国内メインでIT分野の上流職種を目指すならPM(IPA)、外資系や海外と関わるならPMPが有利になる傾向です。どちらも取得すればベストですが、学習負荷は高くなります。
次の章に記載するタイトル:関連資格の俯瞰とロードマップ例
関連資格の俯瞰とロードマップ例
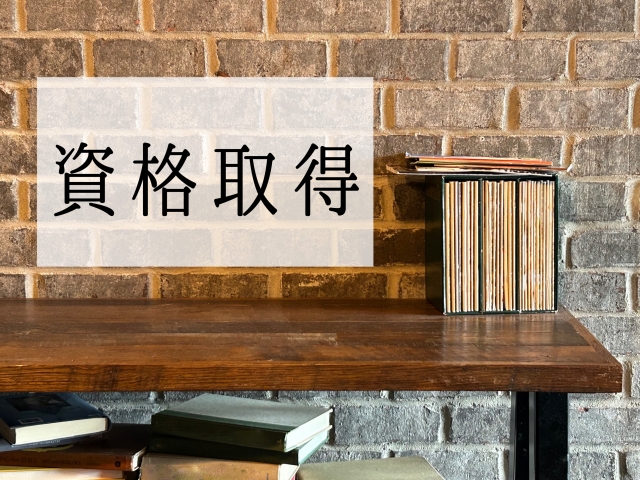
資格の全体像と選択のポイント
プロジェクトマネジメントの資格には、さまざまな種類があります。それぞれ目的やキャリアステージに応じて活用できる道筋があります。
初級〜中級:基礎固めと選択の分岐
初めてプロジェクト管理を学ぶ方には、国際資格のCAPM(Certified Associate in Project Management)が入門に適しています。ここで、プロジェクト管理の基礎知識や用語を身につけられます。一定の実務経験を重ねた後、より広範な知識と実践力を証明したい場合は、PMP(Project Management Professional)を目指すのが一般的です。
国内派の強化方法
国内業務を中心にスキルアップを考えている方には、IPAが主催するPM(プロジェクトマネージャ)試験が有力です。この試験では論述試験が用意されており、計画立案や課題解決の具体的な表現力も評価されます。国内企業での認知度も高いため、キャリアパスの中では重要な選択肢の一つです。
ITサービス寄り資格と発展方向
ITサービス運用やマネジメントを志す場合は、ITIL資格が役立ちます。ITILはサービスマネジメントのプロセス標準に強く、体系的な業務改善に応用できます。得られた基礎をもとに、プロジェクトマネジメント力の横展開を図りたい場合はPMP資格を追加することで、プロジェクトをまたぐ管理能力が高まります。
欧州案件やグローバル志向なら
欧州企業やグローバル案件を意識したい方には、PRINCE2資格もおすすめです。プロセス重視のアプローチで、分かりやすい手順設計が身につきます。PMPなどと組み合わせることで、多様なプロジェクト文化への対応力が広がります。
国内民間資格の選び方
民間のプロジェクトマネジメント関連資格(PMS、PMC、PMRなど)は、資格ごとに合格率や求められるスキルに幅があります(合格率45〜78%)。職務内容や担当領域に見合ったものを選ぶことが大切です。例えば、短期間で基礎を押さえたい場合は合格率の高い資格、専門性を深めたい場合は実践的な試験内容の資格を選ぶのが良いでしょう。
このように、自分自身のキャリアや担当業務に合わせて最適な資格ロードマップを描いていくことが、長期的な成長につながります。