目次
はじめに
本記事は、プロジェクトマネジメント業務を業務委託で行う際に発生しやすい「源泉徴収」について、実務で押さえるべき基礎知識と対応をわかりやすく解説します。
目的
プロジェクトマネージャー側(受託者)と発注側の双方が、支払・申告で戸惑わないことを目指します。契約前後に確認すべきポイントや、実務フローの基本手順を示します。
対象読者
フリーランスや個人事業主でPM業務を請け負う方、発注側の管理者、経理担当者など、実務で判断や手続きが必要な方を想定します。会計や税務の専門家でなくても理解できる表現で書いています。
この記事で学べること
- 源泉徴収の仕組みの概要
- 業務委託と源泉徴収の関係性
- 必要になるケースと不要なケースの見分け方
- 実務での計算・処理の流れと注意点
読み方と注意点
各章で具体例を交えて説明します。まずは全体像をつかみ、必要な章を先に読むと実務ですぐ使えます。税務の解釈は状況により異なるため、判断に迷う場合は税理士へ相談してください。
この記事でわかること
- プロジェクトマネジメント業務における「源泉徴収」の仕組みと基本ルール
- 業務委託契約で源泉徴収が「必要なケース」と「不要なケース」の違い
- 源泉徴収が必要な場合の税率計算と実務フロー(仕訳・納付手順付き)
- フリーランス・個人事業主側の管理・確定申告での注意点
- 契約書・クラウドソーシングなど実務での判断ポイントとトラブル防止策
源泉徴収とは何か

定義
源泉徴収とは、企業や支払者が給与や報酬を支払うときに、あらかじめ所得税などを差し引き(預かり)、国に納める仕組みです。受け取る側は差し引かれた後の金額を受け取ります。
適用される場面と具体例
主に次のような場面で使われます。
- 給与:会社が従業員に給料を支払うとき
- 報酬:講演料、原稿料、弁護士など一部の専門家への支払い
例:原稿料10万円に源泉税1万円が差し引かれると、受け取るのは9万円です(税率はケースにより異なります)。
目的
税金の納付漏れを防ぎ、公的な税収を確保するための前払いです。税務処理を集中的に行えるため、国や納税者の負担を軽減します。
受け取る側の扱い
差し引かれた税は最終的な税額の一部として扱います。年末調整や確定申告で精算し、過不足があれば還付や追加納付が発生します。
実務上のポイント
支払者は正しく差し引き、納付期限までに国に納める義務があります。受け取る側は源泉徴収票などの書類を保管し、確定申告時に使えるようにしてください。
業務委託と源泉徴収の関係

概要
プロジェクトマネジメント業務を外部の個人事業主や法人に委託する場合、原則として源泉徴収は不要です。所得税法204条に該当する「特定の報酬・料金」だけが源泉徴収の対象になります。日常的な事務や進行管理など、一般的なPM業務は多くの場合対象外です。
対象外の例(よくあるケース)
- 進捗管理、スケジュール調整、会議ファシリテーション
- 資料作成やプロジェクト計画の補助業務
- 一般的なコンサルティング(士業的助言を伴わないもの)
対象となる例(源泉徴収が必要なケース)
- 弁護士・税理士などの士業による報酬
- 芸能関係の出演料や原稿料、講演料で204条に該当するもの
- 業務内容が明らかに士業の独占業務や報酬規定に当たる場合
実務上のチェックポイント
- 契約書や請求書で相手が個人か法人かを確認します。法人への支払いは通常、源泉徴収不要です。個人事業主でも多くは不要ですが、業務内容で判断します。
- 業務範囲を明確に記載し、士業的な助言や法務・税務行為が含まれるかを確認します。
- 不明な場合は税務署や税理士に照会してください。源泉徴収が必要なら、所定の方法で税額を差し引き納付します。
源泉徴収が必要なケースと対象外ケース

源泉徴収が必要なケース
- 士業など専門職への報酬:弁護士、会計士、税理士など。専門的な知識や資格に対する報酬は多くの場合対象です。例:法律相談料、会計顧問料。
- クリエイティブ系の報酬:原稿料、デザイン料、翻訳料など。作品や原稿の対価が該当します。
- 講演料・出演料:講演やイベント出演、芸能人・プロスポーツ選手への報酬。
対象外となる主なケース
- 一般的な事務代行や管理業務:データ入力、経理代行、施設管理、プロジェクトマネジメント(単なる進行管理や調整)などは原則不要です。例:事務の外注、現場の進行管理。
- 法人へ支払う報酬:相手が法人の場合、原則として源泉徴収は不要の場合が多いです。
判定のポイントと注意点
契約書の内容と実際の業務内容で判断が変わります。業務が“成果物”や“個人の専門性”に依拠するなら源泉徴収の可能性が高くなります。したがって、契約時に業務範囲を明確に記載してください。税務署や税理士に確認することをおすすめします。しかし、実態と契約が異なると後で指摘を受けることがあるため、業務の実態を記録しておくと安心です。
源泉徴収が必要な場合の計算方法と実務フロー

計算方法
報酬を支払う際は原則として報酬額の10.21%(所得税+復興特別所得税)を差し引きます。1回の支払額が100万円を超えると、超過分には20.42%の税率を適用します。
例1:報酬20万円の場合
- 源泉税=200,000×10.21%=20,420円
- 支払う金額=200,000−20,420=179,580円
例2:報酬120万円の場合
- 最初の100万円分=1,000,000×10.21%=102,100円
- 超過分200,000×20.42%=40,840円
- 源泉税合計=142,940円、受取人へ支払う額=1,200,000−142,940=1,057,060円
実務フロー(簡潔な手順)
- 支払発生:請求書や契約で報酬額を確認します。
- 源泉税の計算:上の税率に従って差し引き額を計算します。
- 会計処理:
- (例)報酬20万円の場合の仕訳例
- (借方)外注費200,000 / (貸方)未払金179,580
- (借方)未払金20,420 / (貸方)預り金(源泉所得税)20,420
- 納付時に預り金を減らし、現金または普通預金で納付します。
- 支払と納付:受取人へは源泉差引後の金額を支払い、源泉徴収した税額は翌月10日までに税務署へ納付します。
- 年末・年度末対応:該当者には支払調書などの提出・交付義務があるため確認します。
注意点(実務上のポイント)
- 税率の判定は「1回の支払額」を基準にします。継続支払いの扱いや源泉徴収の有無は契約内容や報酬の性質で変わるため、迷う場合は税理士に相談してください。
フリーランス・個人事業主側の注意点

概要
プロジェクトマネジメント業務などで報酬から源泉徴収された場合は、受け取った金額だけを見ずに「支払われた総額(請求した金額)=収入」と「差し引かれた源泉徴収額」を分けて管理します。確定申告で差し引かれた税額を精算し、過不足があれば還付や追加納付になります。
受領額と源泉徴収額を分けて管理する
- 例:請求額100,000円で源泉徴収10,000円、振込は90,000円の場合、帳簿には100,000円を売上、10,000円を源泉所得税として記録します。
- 振込明細や支払通知に源泉額が明記されているか確認してください。明細がなければ支払者に依頼しましょう。
帳簿と証憑の保存
- 請求書、領収書、振込明細、支払調書や源泉額が分かる書類を保存します。税務署や税理士から問われたときにすぐ提示できるようにします。
確定申告での扱い
- 確定申告では総収入から必要経費を差し引いて税額を計算し、源泉徴収された額を税額から控除します。控除後に税額がマイナスなら還付、プラスなら不足分を納付します。
実務上のチェックリスト
- 支払明細に源泉額があるか確認
- 帳簿に総額と源泉額を分けて記録
- 必要書類を保存(請求書、振込履歴、支払通知等)
- 不明点は税務署や税理士に相談
以上を習慣化すると、確定申告時のトラブルを減らせます。
ケースバイケースの取り扱いと留意点

業務実態で判断する
プロジェクトマネジメント(以下PM)の仕事は幅広く、単にスケジュール管理や進行確認をするだけのケースと、仕様決定や成果物の最終決裁に深く関与するケースがあります。源泉徴収の要否は『業務の実態』で判断します。たとえば「指示は発注者が出して、報告だけ受ける」なら外注扱いになりやすいです。一方で「発注者に代わって指示・決定を行う」なら給与に近い取り扱いとなる可能性があります。具体的な業務内容を文書で残してください。
契約書のチェックポイント
契約書では業務範囲、報酬の支払方法、税務処理(源泉徴収の有無)を明確にします。例:月額で顧問的に関与する場合は源泉対象になりやすいので、業務の独立性や成果物ベースであることを明記すると良いです。請求書や業務指示の記録も保存してください。
クラウドソーシング等のプラットフォーム案件
プラットフォームは発注側の設定で源泉徴収を行う場合があります。登録画面や案件ページに「源泉あり/なし」の表示があることが多いので、受注前に必ず確認してください。例:プラットフォームで「源泉徴収あり」にチェックが入っていると、支払額から差し引かれて受け取ることになります。差額を想定して報酬交渉することをおすすめします。
実務上の対応例と留意点
・不明点は書面で確認し、メールで合意を残す。
・請求書は契約条件に合わせて作る(源泉を差し引かれる前の金額を明記)。
・継続的な顧問料のような契約は税務上の扱いが厳しく見られるため、業務の独立性や成果基準を具体化する。
・支払側から源泉が差し引かれた場合は、支払通知や明細を保存する。
以上を踏まえ、契約・業務実態・プラットフォーム設定を総合的に確認して対応してください。
まとめ・実務上のポイント
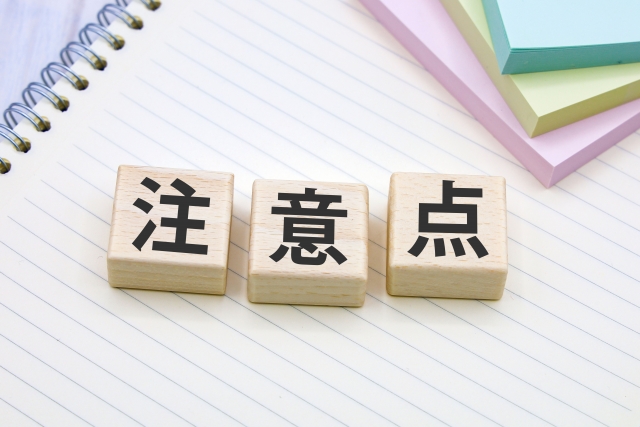
要点まとめ
プロジェクトマネジメントを業務委託で行う場合、原則として源泉徴収は不要です。ただし、業務の実態や契約の書き方によっては源泉徴収の対象になることがあります。個別の業務内容を確認してください。
実務チェックリスト(発注者側・受注者側共通)
- 契約書に業務範囲と成果物を明確に記載する(指揮命令の有無を明示)。
- 請求書に作業内容を具体的に記載する(作業日数や成果物名を明記)。
- 源泉が必要か迷ったら、支払側で税務担当に確認するか、受け手に相談を促す。
- 源泉が発生した場合は、所定の税率・納付期限・会計処理を遵守する。
実務上のポイント(具体例)
- 例:PMが成果物の納品と報告を行うのみなら業務委託扱いになりやすい。逆に指揮命令下で長期的に働く場合は給与性となるリスクがある。
- 例:外注先が複数の小規模作業を請け負うときは、個々の契約ごとに源泉の要否を判断する。
注意点と相談先
税務判断は事案ごとに異なります。重要な契約や金額が大きい取引は、税理士や社内税務担当、国税庁の案内で最終確認してください。適切に対応することで後からの修正や追徴を防げます。
安全に進めるため、契約段階での確認と記録を習慣化してください。