この記事でわかること
- PMBOKとは何か
- 第6版と第7版の違い
- 5つのプロセス群と10の知識エリア
- 第7版の新しい考え方
- 学び方とキャリア活用
目次
PMBOKとは何か — 国際標準の知識体系

PMBOK(Project Management Body of Knowledge)は、プロジェクトを円滑に進めるための知識や手法をまとめたガイドラインです。世界中で活躍するプロジェクトマネージャーの多くが、このPMBOKを基準としてプロジェクト運営を行っています。PMBOKを策定したのは、アメリカに本部を置くPMI(Project Management Institute)という団体です。
PMBOKの目的
PMBOKは、「プロジェクトをどう計画し、どう実行し、どう完了へ導くか」という道筋を示します。例えば、新しい商品を開発する場合や、イベントを開催する時など、様々なプロジェクトで役立ちます。そのため、IT業界だけでなく、建設、製造、サービス業など幅広い分野で活用できます。
共通言語としてのPMBOK
PMBOKが広く使われている理由の1つが「共通言語」を提供できることです。プロジェクトには多くの関係者が関わります。たとえば、発注者、現場の担当者、経営陣など、それぞれ立場や考え方が異なります。PMBOKには、作業の進め方や管理方法が整理されているため、各関係者が同じ認識を持って協力しやすくなります。
フレームワークとしての役割
PMBOKでは、プロジェクトを「計画」「実行」「監視・制御」「完了」など、いくつかの大きな流れに分けて整理しています。これにより、プロジェクトの状況を段階ごとに把握しやすく、課題が発生しても落ち着いて対応できます。
次の章では、PMBOKの第6版と第7版の違いについてご紹介します。
第6版と第7版の違い — 枠組みから原則へ

プロセス重視から原則重視への変化
PMBOKガイドの第6版は、プロジェクト管理を「枠組み」として学ぶスタイルが特徴でした。これは、プロジェクトを始めてから終わるまでを5つのプロセス群(立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結)で捉え、「何をどの順番で進めるか」を詳しく説明したものです。また、知識エリアと呼ばれる10の管理分野が整理されており、実務で迷いにくい道案内のような役割を果たしていました。
一方、最新の第7版は「原則」や「価値」という考え方に大きくシフトしました。世界や働き方が急速に変化する中、厳密な手順に縛られるよりも、状況に合わせて柔軟に判断できる“どんなときも大切にしたい考え方”を軸としています。これにより、プロジェクトごとに合った最適な進め方を選べるようになりました。
何がどう変わったのか?
第6版では、例えば「計画段階ではどんな資料が必要か」「進捗確認はどのように行うか」など、具体的な手順が明確に記載されていました。作業リストをなぞる感覚で、はじめての人でも流れを追いやすい内容です。
しかし第7版は、細かい手順ではなく、「目的」や「価値」にフォーカスしています。たとえば、「関係者と信頼関係を築くことが大切」「本当に価値のある成果を目指す」といった原則が示されています。それぞれの職場や業界に合った方法で、この原則をどのように実現するかが重要です。
どちらの学び方が役立つ?
初心者の方は、まず第6版の枠組みを押さえることで、プロジェクト管理の全体像や流れを掴みやすくなります。そのうえで、第7版の「原則」や「価値志向」のアプローチで、応用力や実践力を身につけるのが効果的です。
次の章では、「5つのプロセス群 — 流れで押さえるプロジェクト運営」について詳しくご紹介します。
5つのプロセス群 — 流れで押さえるプロジェクト運営

プロジェクト運営の「流れ」をつかもう
PMBOKでは、プロジェクトを進めるうえで現場で役立つ「5つのプロセス群」という流れがあります。たとえば、家づくりを想像してみてください。最初に理想の家について話し合い、次に設計や予算を決めます。そのあと大工さんたちが現場で家を建て、進捗を確認しながら問題があれば対応し、最後に完成した家を引き渡します。この一連の流れが、PMBOKのプロセス群にそっくりです。
1. 立ち上げ(Initiating)
最初に「何を、なぜ、いつまでにやるのか」を決める部分です。プロジェクトの目的や目指す成果をはっきりさせ、関係者と認識を共有します。たとえば、社内システムの導入プロジェクトなら「業務効率を上げるために新しいシステムを半年以内に導入する」など、具体的な方針とゴールをはっきりさせます。
2. 計画(Planning)
次は「どうやって進めるか」を決める段階です。スケジュールや予算だけでなく、「誰がどの仕事を担当するか」や「どんなリスクがあるか」といったことも考えます。まるで旅行の計画を立てるとき、行き先や行程・予算・持ち物を決めるのと同じです。
3. 実行(Executing)
計画で決めたことを実際に動かすステップです。メンバーに役割を伝えたり、必要な資材を準備したりと、手を動かすフェーズです。計画通りに進まないことも多いので、柔軟な対応も欠かせません。
4. 監視・コントロール(Monitoring and Controlling)
ここでは「進んでいるか」「問題はないか」を定期的にチェックします。たとえばダイエットで体重の記録をつけるのと同じように、進捗やコスト・品質を見守り、問題があれば早いうちに軌道修正します。
5. 終結(Closing)
最後は「終わらせる」作業です。成果物を正式に受け取ったり、プロジェクトに関わった人たちへ感謝を伝えたり、記録や反省点をまとめて次回に活かせるよう整理します。イベントの後片付けやアルバム作りに近い作業です。
こうして5つの流れをつかんでおけば、プロジェクトの進め方もグッと分かりやすくなります。
次の章に記載するタイトル:10の知識エリア — 何を管理するのか
10の知識エリア — 何を管理するのか

プロジェクト運営を理解するうえで、「何を管理するべきか」が具体的になるのがPMBOK第6版で定義された「10の知識エリア」です。各分野は、いわばプロジェクト成功の“要素”ともいえるもので、一つひとつが無視できません。ここでは、それぞれの知識エリアについて、日常的なイメージに置き換えてご説明します。
1. 統合マネジメント(全体をまとめる)
プロジェクトをひとつの流れとして見ながら、各種計画や対応策を調整し、全体として目標達成へと導きます。いわば指揮者のような役割です。
2. スコープマネジメント(やること・やらないことを決める)
プロジェクトで「どこまでやるのか」「なにをやらないのか」を明確に管理します。例えば、引越しの準備で何を運ぶかリストアップするイメージです。
3. スケジュールマネジメント(計画通りに進める)
作業の順番やスケジュールを決め、進行が遅れていないか管理します。学校の時間割を考えるようなものです。
4. コストマネジメント(予算を守る)
決められた予算内でプロジェクトを終えるために、お金の流れや使い方を管理します。
5. 品質マネジメント(成果物の質を保つ)
納品するものやサービスの質が落ちないように検討・管理します。料理で例えれば、決まった味や見た目に仕上げるためのチェックに似ています。
6. リソースマネジメント(人と物の調達や配置)
必要な人員や設備、材料などを集めて、適した場所・タイミングで使えるように調整します。
7. コミュニケーションマネジメント(情報共有)
関係者に情報がきちんと伝わるよう工夫します。例えば、家族みんなでグループチャットを使うようなものです。
8. リスクマネジメント(不測の事態に備える)
問題が起きた場合を想定して、対策や対応を事前に準備します。旅行前に予備の傘を用意する感覚です。
9. 調達マネジメント(外部とのやりとり)
必要なものを業者などから購入・依頼し、約束通りに納品されるよう管理します。
10. ステークホルダーマネジメント(関係者との関わり)
プロジェクトに関わる全ての人たちの期待や意見を把握し、信頼関係を築く努力をします。
この10の分野を意識することで、プロジェクトを「どこで何が起こるか」を把握しやすくなります。
次の章では、第7版の学びどころ — 原則・価値・アプローチの多様性について解説します。
第7版の学びどころ — 原則・価値・アプローチの多様性

原則ベースで考えるプロジェクト管理
PMBOK第7版は、従来の細かな手順やルールではなく、「原則」に基づいてプロジェクトを進める点が特徴です。原則とは「どの現場にも通じる大事な考え方」のことを指します。たとえば「チームワークを大切にする」「関係者に価値を届ける」などは、業界や規模を問わず大切なポイントです。このように、単なる手順書ではなく、何が本当に大切かを考えて行動できるのが第7版の特徴です。
価値の提供に注目
第7版では、プロジェクトの成果が「どれだけ価値を生み出したか」にフォーカスします。たとえば新しいアプリを作る場合、「計画どおり完成したか」だけでなく、「ユーザーが便利に使えるか」「会社の売上や評判につながったか」までを考えます。こうした“価値志向”の考え方を持つことで、プロジェクトが本当に役立つものになるか常に意識できます。
多様なアプローチへの対応
やり方についても、第7版では「ウォーターフォール型」だけでなく「アジャイル型」やその組み合わせといった柔軟な方法を認めています。ウォーターフォールは計画を重視し、順に進めます。一方アジャイルは、要望や状況に合わせて柔軟に進める手法です。チームやプロジェクト内容に応じて、どちらか、または両方を組み合わせて使えるのが今の時代の特徴です。
状況適合と成果重視とは
プロジェクトごとに、求められるやり方や判断が違うのは珍しくありません。第7版では「この状況にはこのアプローチが合う」と現場で考えてカスタマイズする「状況適合」を推奨しています。また「成果」にしっかり目を向けて進めることが強調されており、ただ“やるべきことをやる”のではなく“結果が出ること”を意識して運営するのがポイントです。
次の章に記載するタイトル:学び方のロードマップ — 最短理解から実務適用へ
学び方のロードマップ — 最短理解から実務適用へ
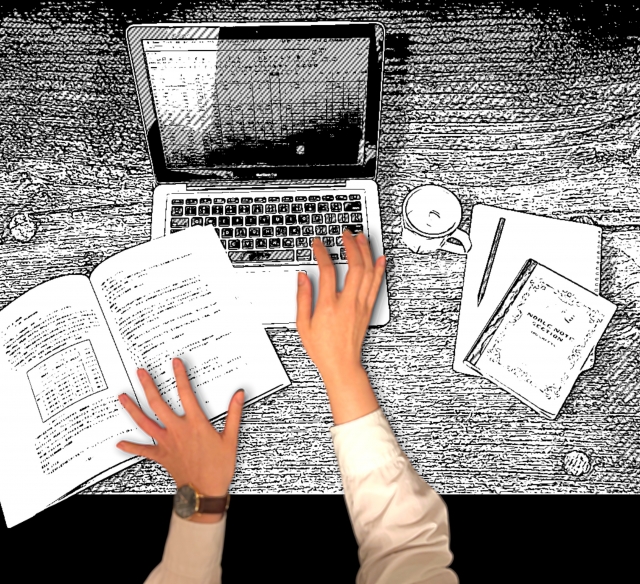
全体像のインプット:共通言語の獲得
プロジェクトマネジメントを学ぶ最初のステップは、第6版でまとめられた5つのプロセス群(立ち上げ・計画・実行・監視コントロール・終結)と、10の知識エリア(スコープ・スケジュール・コストなど)をざっと眺めることです。これにより、業界で使われる「共通言語」を早い段階で身につけやすくなります。知らない用語が出てきたときにも、全体の枠組みが分かっていれば、後から理解に繋がりやすいです。
第7版の原則的アプローチへのステップアップ
基礎用語と流れが分かったら、第7版の特徴である「価値を重視」「さまざまな手法に対応」といった考え方も学びます。具体例として、「計画」は状況により細かく作り込む場合もあれば、ざっくりまとめて頻繁に見直す方が合うこともあります。自身が担当するプロジェクトに応じて、柔軟な管理が必要であるという意識を持つことが重要です。
ミニプロジェクトで実際に回す
学んだ知識を定着させるには、実際に「小さなプロジェクト」を一巡する体験が効果的です。例えば、社内の簡単なイベントやチームの改善活動などで、プロジェクト憲章を書き、タスク分解(WBS)、スケジュール案、リスク洗い出しと登録を一通り行ってみます。手を動かすことで、座学では見えなかった気づきや用語の使い方が身につきます。
書籍+講座を併用して強化
基本の入門書を1冊読むと全体の感覚が掴めますが、より理解を深めるには演習やケーススタディも役立ちます。最近は1日で概要を学べる講座や、オンラインで繰り返し学べる教材も充実しています。インプット→演習→振り返り、のサイクルを意識しましょう。
実務用テンプレートを整備する
「計画書」「リスク・課題・変更管理ログ」「コミュニケーション計画」など、汎用テンプレートをチームや自分用に準備しておくと、実際のプロジェクトで迷いにくくなります。テンプレートを使って必要事項を漏れなく管理できるので、実務へのブリッジとして強い味方になります。
次の章に記載するタイトル:初学者におすすめの入門書・情報源
初学者におすすめの入門書・情報源

PMBOKについて学び始めたい方にとって、最初に手に取る書籍や情報源はとても重要です。ここでは、「全体像をつかみたい」「何から始めればよいかわからない」という初学者の相談によく応える代表的な入門書やネット情報を紹介します。
プロジェクトマネジメント標準 PMBOK入門(第7版対応)
この書籍は、PMBOKの全体構成を迷わず理解できると評判です。最新の第7版にも対応しており、専門用語はできるだけ平易な表現で解説しています。「プロジェクトの計画から終結まで、どのような流れか?」という基礎に焦点を当てているので、初めて読む一冊におすすめです。
PMBOKはじめの一歩(入門解説・事例・アジャイル概説まで)
この本は、従来のPMBOK知識体系だけでなく、アジャイル式プロジェクト管理にも触れています。理解のポイントごとに簡潔な図や比較を交えていて、難しく感じがちな部分もスッと頭に入ります。また「身近な事例」を交えて解説されており、実際の現場でどのように役立つか想像しやすい内容です。
やさしい入門・ストーリーベースの解説書
このタイプの書籍は、「ダイエットを成功させるプロジェクト」など誰でもイメージしやすいテーマをもとに、PMBOKの考え方を紹介します。難しい言葉を避けているため、「プロジェクトマネジメントって何?」という最初の一歩を踏み出す方にぴったりです。「計画を立てる→進捗を管理→ふりかえり」という日常の中で起きる流れと結び付けて解説するので、親しみやすさが特長です。
Webの基礎解説記事
最近では、企業の公式サイトや専門の学習サイトで、PMBOKを簡単に解説した記事も多く見つかります。たとえば「PMBOKの役割」「10知識エリアと5プロセス群」、また「導入メリット」などの要素を図表入りで整理したガイドは、短時間で全体像をつかむのに便利です。スマートフォンやパソコンから手軽に情報収集できるのも、忙しい社会人にはうれしいポイントです。
体系理解の入門講座(1日)
さらに、「1日完結」の短期講座も注目されています。企画・計画・実施・評価の段階を、事例を交えて学ぶ形式です。実際の演習も盛り込まれているため、理解が深まるうえ、「これなら実務に活かせそう」と感じる方も多いです。書籍やWeb記事で基本を押さえた後、講座で知識を実感としてつなげていく、という順序もおすすめできます。
次の章に記載するタイトル:実務で効く運用ポイント(現場でのつまずき回避)
実務で効く運用ポイント(現場でのつまずき回避)

現場でプロジェクトマネジメントを実践する際、理論だけでなく具体的な運用が重要です。ここでは実際によくあるつまずきポイントと、それを回避するコツをご紹介します。
スコープの明確化と変更管理
まずは「何をやるか・どこまでやるか」をはっきりさせることが大切です。作業の一覧(WBS:作業分解構成図)を作り、それをもとに“計画の基準”であるベースラインを決めます。運用中に追加作業が発生しそうなときは、変更管理ログ(記録表)に記入し、関係者で変更の要否や影響を確認します。これにより、いつの間にか仕事が増えていく「スコープの膨張」を防ぎやすくなります。
リスクと課題の違いを意識して記録
プロジェクトを進めるとき、「起こりそうな心配事」と「実際に発生した困りごと」は区別して記録します。前者はリスク登録簿にまとめ、定期的に発生確率や影響度を見直します。後者は課題ログに残し、誰が・いつまでに対応するかを明記し、対応状況を追います。これにより、対策漏れや責任の曖昧さを防げます。
ステークホルダーとのコミュニケーション計画
関係者との連絡では、「どのくらいの頻度で」「どのチャネル(メール・会議など)で」「どの程度の詳しさで」情報共有するかを事前に合意することが大切です。担当者が偏って情報を抱え込むことを防ぎ、チーム全体の透明性を高められます。
ベロシティや進捗の“見える化”
進み具合は、ただ「進んでいる」と口頭で伝えるのではなく、定量的な指標を使いましょう。例えば、バーンダウンチャートを使った作業残量の可視化、EVM(出来高管理)による進捗とコストの分析などが有効です。プロジェクトに合った指標で進行をチェックし、問題があれば早めに手を打てます。
ウォーターフォールとアジャイルのハイブリッド運用
プロジェクトの特性によっては、一部は最初にしっかり決めごとをして(ウォーターフォール方式)、一部は柔軟に作業内容を調整しながら進める(アジャイル方式)など、ハイブリッドの運用が効果的です。例えば、要件が変わりやすい部分だけアジャイルで回すなど、状況に応じた設計を意識しましょう。
次の章に記載するタイトル:第7版対応のポイント — 原則と価値に紐づく設計
第7版対応のポイント — 原則と価値に紐づく設計

成果重視から価値重視への考え方の切り替え
PMBOK第7版では、プロジェクトの成果物そのものではなく、「そのプロジェクトがどのような価値を生み出すか」に目を向けることが大きな特徴です。たとえば、イベント運営のプロジェクトであれば、単にイベントを実施すること自体ではなく、参加者や主催者、スポンサーが得る体験や満足度といった価値が大切です。そのため、評価指標(メトリクス)も「何人が参加したか」だけでなく、「どれだけ参加者が満足しているか」など、価値に沿ったものを選びましょう。
チームの自律性と適応性を考慮した設計
また、プロジェクトの進め方についても、第7版では状況に合わせて選ぶ柔軟性が求められています。たとえば、「作業を細かく計画してから進める(予測型)」方式が合う場合もあれば、「都度状況を見ながら進める(適応型)」や、両方を組み合わせるハイブリッド型が効果的な場合もあります。重要なのは、チーム自身が状況を見極めて判断し、自律的に動けるような体制や仕組みを設計段階から組み込むことです。
振り返りと継続的な成長の仕組みづくり
プロジェクトをより良くするためには、「終わったら振り返る」のではなく、日常の運営の中に「定期的に振り返る(レトロスペクティブ)」時間を設けることがポイントです。これにより、小さな気づきを早期に活かし、失敗や課題もすぐに修正できます。たとえば、「週に一度、業務のうまくいった点・改善したい点を共有する」など、チーム全体が率直に学び合える環境をつくることが大切です。
次の章に記載するタイトル:PMP学習・キャリア観点
PMP学習・キャリア観点

PMP資格とは何か
PMBOKの知識体系は、プロジェクトマネジメントの国際資格「PMP(Project Management Professional)」と直結しています。PMP資格は、PMBOKで整理された知識や考え方をベースにした試験です。そのため、PMBOKの基礎を理解することは、PMP取得を目指す方にとって欠かせません。
資格取得のメリット
PMP資格は、国内外の多くの企業が高く評価しています。資格を持つことで、プロジェクトリーダーや管理職などへのキャリアアップの道が広がります。また、採用選考や社内昇進の要件にPMP取得が含まれている場合もあり、自身の価値を分かりやすくアピールできる材料になります。
学習の進め方
PMBOKに関する知識は、独学でも学ぶことができますが、参考書や外部セミナー、研修などを活用する人が多いです。また、身近なプロジェクトや業務改善の場で学んだ知識を積極的に試すことも有効です。模擬試験や過去問を繰り返し解くことで、実践力や理解度が高まります。
キャリア形成とPMBOK
PMPをはじめとするプロジェクト管理の知識体系は、プロジェクト型の働き方が増える現代においてますます重要になっています。エンジニア職、営業職、企画職など職種を問わず、多様な業界で活用できる普遍的なスキルです。経験や資格を積み重ねることで、より大きなプロジェクトへの参画や管理職へのステップアップがしやすくなります。