目次
はじめに
この記事でお伝えしたいこと
この記事では、WBS(作業分解構造図)の「要素をどう分けて考えるか」を、初めての方でも理解できるように整理してご紹介します。
WBSの基本から、作り方、階層の考え方、実務での注意ポイントまで、順を追って学べるつくりです。
こんな方に読んでほしい内容です
プロジェクトマネージャーに限らず、チームのまとめ役やメンバー、発注側の担当者などにも役立つ内容です。
社内の小さな施策から、大規模な開発や建設プロジェクトまで、幅広い場面で使える考え方として整理しています。
今後の流れについて
このあとの章では、
・WBSの基本
・要素をどう分けて考えるか
・階層構造の見かた
・分解の進め方
・実務でのコツと注意点
・メリットや活用例
といった内容を、実例も交えながら解説します。
「今すぐ使える実務の知識」を届けることを意識して進めていきます。
この記事でわかること
- WBS(作業分解構造図)の定義と目的
- 要素分解の手順と階層構造の基本
- 成果物型・プロセス型WBSの違いと使い分け方
- 実務での作成ポイントと注意点
- WBS導入によるメリットと活用効果
WBS(作業分解構造図)とは何か
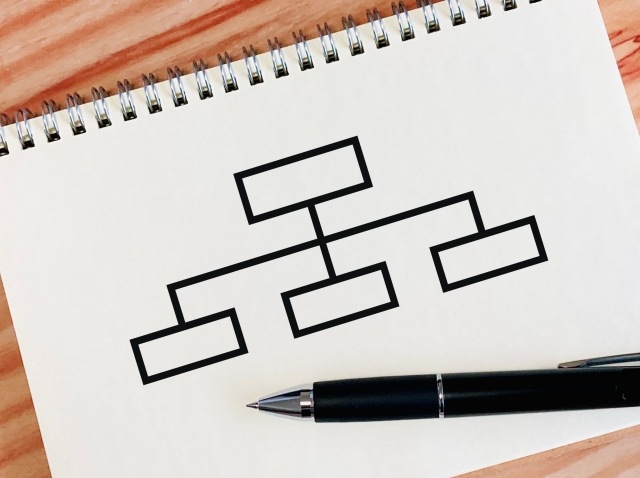
WBSの基本的な考え方
WBS(Work Breakdown Structure/作業分解構造図)は、プロジェクトの目的や成果物から逆算し、「必要な作業をどのように分けるか」を整理するための図です。
全体像が見えるようになり、作業の漏れや重複を防ぐことができます。
なぜWBSが必要なのか
WBSを作ると
「何を」「いつまでに」「誰が行うのか」
がはっきりします。
その結果、スケジュール作成やリソースの配分、リスク管理がしやすくなり、関係者の認識も揃いやすくなります。
WBSの作り方の流れ(シンプルに)
WBSは次のような手順で整理していきます。
- 最終的な成果物(目的)を明確にする
- 成果物を主要な要素に分ける
- さらに具体的な作業単位まで細かくする
- 各作業に責任者や工数を割り当てる
具体例でイメージする
WBSは、多くのプロジェクトで同じ考え方が使えます。
- 建築なら:設計→基礎工事→躯体→内装…というように工程ごとに分けていく
- イベントなら:企画→会場手配→集客→運営…と整理し、担当者を決める
- ソフトウェア開発なら:要件定義→設計→実装→テスト…に分け、機能ごとにタスク化する
作成するときの注意点
細かくしすぎると管理が大変になり、逆に粗すぎると抜け漏れが発生します。
チームで「どの粒度が適切か」を話し合い、バランスを取ることが大切です。
WBSの要素分解の基本手順

まず押さえておきたいこと
WBSは、4つのステップで作ると理解しやすくなります。
ここでは、例として「社内研修の実施」をテーマに、誰でも取り組める形で説明します。
ステップ1:成果物やプロセスから作業を洗い出す
まずは、最終的な成果物(=研修の実施)を明確にします。
そこから逆算して必要な作業を挙げていきます。
例)講師の手配、会場準備、資料作成、参加者案内 など
ステップ2:作業の大きさと順番を整理する
挙げた作業を、実際にこなせるサイズに分けていきます。
例えば「資料作成」であれば、
・目次を作る
・内容を執筆する
・校正する
といった流れに分けられます。
1つの作業が2〜5日で終わるくらいの単位が目安です。
ステップ3:作業を構造化し、期日を決める
洗い出した作業を成果物ごとにグループ化し、階層として整理します。
さらに、開始日や終了日、重要な節目(マイルストーン)を設定することで、全体の流れが見えるようになります。
ステップ4:担当者を割り当てる
最後に、各作業の担当者を決めます。
責任範囲や完了の基準(成果物や合格条件)を共有し、定期的に進捗を確認して調整します。
作成するときの注意点
粒度が細かすぎると管理が大変になり、粗すぎると進捗が見えなくなります。
関係者と話し合いながら、「実務で扱いやすい分解レベル」を見つけることが大切です。
WBSの階層構造と分解レベル

WBSはどんな階層で構成されるのか
WBSは大きく4つの階層で整理すると理解しやすくなります。
上から順に
- プロジェクトレベル
- フェーズレベル
- タスクレベル
- ワークパッケージレベル
という形です。
階層に分けることで、役割分担や進捗確認がしやすくなります。
各階層の役割とイメージ
それぞれの階層には、担当範囲や目的が異なります。
プロジェクトレベル
プロジェクト全体の目標や最終成果物を示します。
例:新製品の開発
フェーズレベル
プロジェクトを大きな工程に分けたものです。
例:設計、試作、検証、量産準備
タスクレベル
具体的な作業単位を表します。
例:回路設計、材料選定
ワークパッケージレベル
1人または1つのチームが担当して完結できる最小の作業単位です。
例:回路図を作る、部品を発注する
分解レベルの目安(どこまで細かくするか)
・ワークパッケージは担当者が明確で、数日〜数週間で終わるサイズが目安です。
・タスクは作業の性質に基づき、実行しやすく管理しやすい大きさで設定します。
管理しやすくするための工夫
WBSを使いやすくするためには、次の工夫が有効です。
・それぞれの要素に番号や短い説明を付け、識別しやすくする
・成果物に基づいて分解すると、関係者と合意しやすい
・定期的に見直し、粒度が大きすぎる場合はさらに分割する
こうした階層を意識することで、進捗の見える化や責任範囲の明確化が進みます。
WBSの分解方法(成果物型・プロセス型)

成果物型WBSとは
成果物(納品物)を起点として、それを構成する要素に分けていく方法です。
例えばWebサイト制作なら
・サイト本体
・コンテンツ
・運用マニュアル
などを上位に置き、そこからページやファイル単位へ細かくしていきます。
責任範囲や検収の基準が明確になりやすいので、成果物がはっきりしている短期〜中期のプロジェクトに向いています。
プロセス型WBSとは
プロジェクトの進め方(プロセスやフェーズ)を基準に分解する方法です。
例えば
要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → リリース
といった流れを上位に置き、各フェーズの作業や成果物を洗い出します。
成果物がまだ定まっていない初期段階や、長期プロジェクトで使いやすい形です。
どちらを選ぶかの考え方(具体例)
・短期間で製品を納品するような案件
→ 成果物型が向いています。納品物ごとに担当や検収基準が整理しやすいためです。
・段階的に作り込んでいく長期案件
→ プロセス型が有効です。フェーズごとのレビューや承認が管理しやすくなるためです。
実際の分解ステップ(シンプルに)
- 最上位にプロジェクト全体を置く
2a) 成成果物型なら、主要な納品物を挙げ、さらに部品やドキュメントへ細かくする
2b) プロセス型なら、主要フェーズを挙げ、各フェーズ内の作業や成果物を細分化する - 最小単位(ワークパッケージ)に担当者・期限・検収基準を設定する
ハイブリッド型の使い方と注意点
実務では、両方を組み合わせるケースも多くあります。
たとえば上位はフェーズ(プロセス型)で整理し、その中を成果物ごとに分けるなど、状況に合わせて柔軟に使い分けることが大切です。
WBS作成の実践ポイント・注意点

タスクの粒度をどう決めるか
タスクは「1週間〜数週間で終わる」程度が扱いやすい大きさです。
例えばWeb制作の場合、「デザイン」という単位では大きすぎるので、
・ワイヤーフレーム作成(1週)
・ビジュアル作成(2週)
・レビュー実施(1週)
といった形に分けると進捗が見えやすくなります。
細かすぎると管理負荷が増え、粗すぎると状況がわからなくなるため、適切な粒度が大切です。
抜け漏れや重複を防ぐ進め方
上位レベルから論理的に分解していくことがポイントです。
成果物ベースの場合
成果物が完成するために必要な要素を洗い出す
プロセスベースの場合
工程ごとの成果物や作業内容を確認する
また、チェックリストや短時間のレビュー会で第三者に確認してもらうと、見逃しや重複の防止につながります。
担当者と期日を明確にする
各作業には担当者と期限を必ず設定します。
責任範囲が明確になると、意思決定が早まり進捗管理もしやすくなります。期日は余裕を持たせ、依存関係も明記しておきましょう。
プロジェクト特性に合わせた分解をする
成果物型とプロセス型は、プロジェクトの特性に応じて使い分けます。
・研究開発のように成果がまだ見えにくい場合はプロセス型
・反復や外注が多い場合は成果物型でスコープ管理
必要に応じて両方を組み合わせても問題ありません。
実務で役立つチェックポイント
実際にWBSを使う際は、次の点を確認すると精度が上がります。
・タスクの完了基準が明確か
・同じ階層に成果物と活動が混ざっていないか
・タスク数が多すぎたり少なすぎたりしていないか
・定期的にWBSを更新できているか
短時間のレビューと責任の明確化を繰り返すことで、WBSは現実的で使える設計図になっていきます。
WBSのメリットと活用効果

WBSを使うことで得られる主なメリット
プロジェクト全体の見える化
WBSは作業を構成要素に分けるため、「誰が何をするのか」が一目でわかります。
例えばソフトウェア開発なら、画面設計・実装・テストなどの作業が整理されます。
進捗管理とリスクの早期把握
作業を小さな単位で管理できるため、遅れや問題を早く発見できます。
たとえばテスト工程の遅れも原因特定がしやすくなり、対策が早く打てます。
リソース配分の最適化
作業ごとに必要な人員や時間を見積もれるため、適切な人材配置や外部委託の判断がしやすくなります。
その結果、コスト管理にも役立ちます。
関係者間の認識が揃う
作業範囲と責任者を明確にすることで、認識のズレが減りコミュニケーションもスムーズになります。
活用効果をイメージしやすい具体例
建築プロジェクト
工程ごとに資材発注や人員配置を行えるため、遅延の防止につながります。
イベント運営
準備・当日運営・撤収を分けて担当を決めることで、当日の混乱を減らせます。
製品開発
リスクの高い機能を先に分解し、早い段階で検証することでトラブルの回避につながります。
成功させるためのポイント
・タスクの粒度は管理しやすいレベルにする(数日〜2週間が目安)
・WBSは固定せず、状況に応じて更新していく
・関係者と共有し、責任範囲を明確にする
・依存関係と必要工数を明示して優先順位をつける
WBSはプロジェクト成功の基盤になります。
適切に作成し、運用していくことで現場が動きやすくなります。
WBSの形(フォーマット例)とサンプル
WBSはどんな形で作るのか
WBSは、表形式やツリー図など、いくつかの表現方法があります。
実務ではExcelやスプレッドシートで管理されることが多く、次のような構造で作られます。
よく使われる項目例
・番号
・タスク名(または成果物名)
・担当者
・開始日/終了日
・必要工数
・完了基準(納品物や合格条件)
簡単なサンプルでイメージする
例として「イベント運営」のWBSは、次のように整理できます。
企画
- 目的整理
- 日程決定
会場準備
- 会場手配
- レイアウト調整
集客
- 告知文作成
- SNS・広告掲載
当日運営
- 受付
- 進行管理
このように、上位の要素から分解していくと、構造が分かりやすくなります。
WBSでよくある失敗と防止策
粒度がバラバラになる
失敗例
あるタスクは1日、別のタスクは3ヶ月など、粒度が揃わず管理が難しくなる。
防止策
数日〜数週間で管理できるサイズに揃えることを目安にします。
責任者が曖昧なまま進む
失敗例
複数人で共有され、結果的に誰も責任を持たない状態になる。
防止策
各タスクには担当者を必ず設定し、完了基準まで共有します。
成果物と作業が混ざる
失敗例
「仕様書」という成果物と、「会議をする」という作業が同じレベルに混在し、構造が崩れる。
防止策
同じ階層には性質の近い要素(成果物か作業か)を揃えることを意識します。
WBSを作って終わりになる
失敗例
計画時に作り込んだものの、更新されず誰も見なくなる。
防止策
WBSは固定せず“生きた設計図”として更新することが大切です。
定期的なレビューを入れ、運用しながら改善していきましょう。
WBSを活かすには「更新」と「粒度」が鍵
WBSは作って終わりの資料ではなく、プロジェクトを進めながら更新していく設計図です。
粒度を揃え、責任範囲を明確にし、使いながら改善することで、プロジェクトの成功に直結します。
まとめ
WBS(作業分解構造図)は、プロジェクトを進めるうえで欠かせない「設計図」の役割を果たします。
全体像を整理し、作業を分けて見える化することで、進捗管理や責任分担がしやすくなります。
この記事では、WBSの基本から作り方、階層の考え方、分解方法、実践のポイント、そして活用のメリットまで順に紹介してきました。
特に大切なポイントは次の通りです。
・成果物や工程から作業を分解する
・数日〜数週間で扱える粒度に整える
・担当者と期限、完了基準を明確にする
・プロジェクト特性に合わせて成果物型とプロセス型を使い分ける
・WBSは作って終わりではなく、状況に応じて更新していく
WBSの考え方は、大小さまざまなプロジェクトで活用できます。
まずは小さな取り組みでも、作業を整理してみるところから始めてみてください。
使うほど精度が高まり、チームの動きがスムーズになっていくはずです。