はじめに
プロジェクトマネジメント計画書は、計画したプロジェクトを成功に導くための地図のような役割を果たします。たとえば、新しいシステムをつくる場合、計画書には「誰が」「どんな作業を」「いつ」「どのように行うか」といった情報がわかりやすくまとめられています。
この計画書は、プロジェクトの規模によって10ページほどのものから100ページ以上におよぶものまでさまざまです。プロジェクトを進めていくうちに状況が変わることもあるため、計画書の内容も柔軟に見直しや更新を行います。最初に作成して終わりではなく、途中で「本当にこの進め方でよかったか?」と立ち止まって確認できるようにするのが目的です。
また、計画書をつくるプロセスは「計画担当者だけの作業」ではありません。関係者全員の認識をすり合わせたり、同じ情報を共有したりする大事なタイミングです。「こんなリスクがあるのでは?」「実はやり方に違和感がある」といった現場の声も反映できます。そのため、計画の内容だけではなく、計画づくり自体がプロジェクトの質を高めるポイントにもなっています。
次の章では、計画書にどんな内容を盛り込むべきか、その必須セクションをご紹介します。
この記事でわかること
- プロジェクトマネジメント計画書の基本構成と役割
- PMBOKとPEP(Project Execution Plan)の関係と活用法
- 成功率を高める計画書作成の実務ポイント
- チーム全体での合意形成・柔軟な計画運用のコツ
- 抜け漏れを防ぐ実践的チェックリスト(全8項目)
計画書の基本構成—押さえるべき必須セクション

1. 目的・ゴールの明確化
計画書の冒頭部分では、プロジェクトの目的やゴールを具体的に記載します。このとき「QCD」(品質・コスト・納期)に基づき、たとえば「3カ月以内にシステムを稼働させる」「予算1,000万円以内で完了する」など、数値で測れるKPIも示します。これにより、関係者全員の認識合わせができ、進行中に方向性がブレにくくなります。
2. スコープ(範囲)設定
スコープでは「どこまでやるのか」をはっきりさせます。たとえば「顧客管理システムの開発」なら、対象機能や対象外機能をリスト化します。また必要な作業・成果物・受け入れ基準などもセットで挙げ、後々の認識ズレを防ぐのが重要です。
3. 体制・役割分担の明示
プロジェクトを進める体制や、それぞれの役割分担も記載します。組織図としてビジュアル化したり、「○○さんはリーダー」「○○さんは設計担当」と名前とともに責任範囲を明記したりします。これは、万一問題があった場合の連絡や責任の所在の明確化にも役立ちます。
4. スケジュールと進捗管理
スケジュールは、大まかなタスク分解(WBS)や見積もりをもとに作ります。各作業の期間や依存関係、主要な「マイルストーン」を示し、さらに「ここまで出来ていれば進捗50%」など進捗率の定義も合わせて明記します。
5. コスト・リソース計画
費用の内訳や人員・ツールなどのリソースも盛り込みます。たとえば「Aさんが100時間、Bさんが80時間」「外部ツール購入費30万円」など、何にどのくらいお金や人手がかかるのかを具体的に書き出しておきます。
6. リスク管理
予測されるトラブルや障害をリストアップし、「発生した場合の対応」も考えておきます。たとえば「開発遅延が起きたときはリーダーへ連絡」「追加予算申請フロー」などを簡単に決めておくと、万一の事態にも慌てず対応できます。
7. 品質・コミュニケーションの方針
納品物や作業内容の品質基準を決めておきます。さらに、定例ミーティングの頻度、進捗報告の方法(メール、チャット など)、問い合わせ受付担当など、連絡体制・コミュニケーションのルールも明確にします。
次の章では、計画書を実際に作成するための標準的な手順について解説します。
PMBOK整合とPEP(Project Execution Plan)の位置づけ

PMBOKとは何か?
PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)は、世界的に広く使われているプロジェクト管理のガイドラインです。計画・実行・監視・コントロール・完了という流れに基づき、スコープ(作業範囲)、スケジュール、コスト、品質、リスクといった要素を管理します。
例えば住宅建設やITシステム開発などの場面で、「間取りを決める」「資材を発注する」「予算内に収める」といった工程を明確に定め、それをどのように進めるかを整理するのがPMBOKの考え方です。計画書をしっかり作成すれば、自然とPMBOKに沿った進め方を実践できるようになります。
PEP(Project Execution Plan)の特徴と役割
PEPは「プロジェクト実行計画書」を意味し、プロジェクトの全体設計図となる文書です。概要・目的・体制・スケジュール・リスク対応などを具体的にまとめ、各担当者が「誰が、何を、いつまでに、どのように進めるのか」を明確に共有できます。
また、計画通りに進んでいるかを定期的にチェックし、必要に応じて修正や対策を打てるのも特徴です。これにより、抜け漏れの防止やトラブル発生時の迅速な対応に役立ちます。
PMBOKとPEPの関係性
PMBOKが示す「管理計画書の枠組み」を、現場で具体的に実行可能な形に落とし込んだものがPEPと考えるとわかりやすいです。
- PMBOK:知識体系としての「ガイドライン」
- PEP:そのガイドラインを実務に適用するための「実行計画書」
両者は補完関係にあり、PMBOKをベースにPEPを作ることで、ルールや手順を実際のプロジェクト現場に即した形で共有できます。
実務での活用例
- ITシステム開発:PEPで「要件定義~テスト」までの詳細な進め方を文書化し、ベンダー・ユーザー間の共通理解を確保する。
- 建設・インフラ:PMBOKで基本ルールを押さえつつ、PEPで現場向けに具体的なフローや役割を示す。契約遵守や認識の齟齬防止に有効。
まとめ
計画書作成においては、PMBOKを土台として体系的に管理しつつ、PEPで現場に即した実行計画に落とし込むことが理想的です。特に複数部門や外部ベンダーを巻き込むプロジェクトでは、この二つを組み合わせることで合意形成と進行管理をスムーズに行えます。
成功率を高める実務Tips

プロジェクト計画書を実際に活用する上で、成功率を高めるためのコツをご紹介します。経験豊富なプロジェクトマネージャーも、ちょっとした工夫や注意点を押さえることで、計画倒れやトラブルの回避につながります。
1. 規模に応じたドキュメント簡略化
計画書は「全部しっかり書かなければ」と思いがちですが、重要点を絞ることも大切です。たとえば、小規模なグループ作業ではA4用紙1枚程度でまとめる、という柔軟さで十分です。余分な手間を減らしながらポイントだけを全員が把握できるよう意識しましょう。
2. チーム全体での合意形成
プロジェクト計画書は一人で作って終わり、ではありません。リーダーがメンバー全員と内容を確認し、「分からないところ」や「不安な点」を率直に話し合う場を必ず設けましょう。こうすることで後々の食い違いを防げます。たとえば、朝会や週次ミーティングなど、その場に合わせて柔軟に進めてみてください。
3. 柔軟に見直す習慣
システム開発の現場ではイレギュラーがつきものです。一度作った計画書も“たたき台”と捉え、必要に応じて見直しましょう。進捗や課題が出たら、計画書を最新状態に更新することが、軌道修正と成功への近道になります。
4. 簡単な進捗管理ツールの活用
エクセルやGoogleスプレッドシートなど、身近なツールでタスクとスケジュールの見える化を行うと、関係者全員で状況を把握しやすくなります。進捗が一目で分かるガントチャート形式などがおすすめです。
5. 成功・失敗事例を残す
プロジェクトが終わったら「何がうまくいったか」「次に気をつけることは何か」を簡単なメモとして残しておきましょう。次のプロジェクト計画書作成の際に、大いに参考になります。
次の章では、いますぐ使えるチェックリストについて解説します。
いますぐ使えるチェックリスト
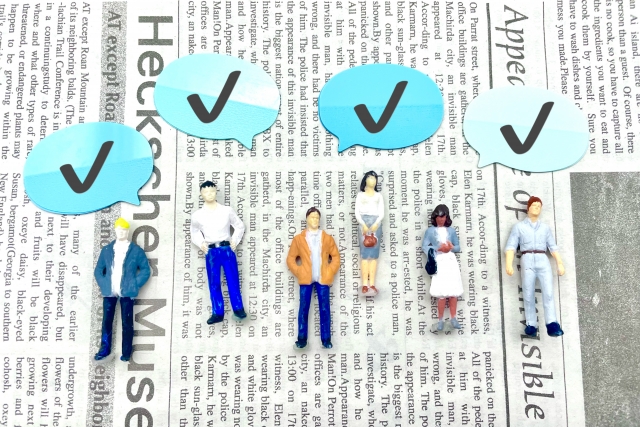
プロジェクト計画書チェックリスト
計画書の完成度や実効性を高めるには、網羅的なチェックが不可欠です。以下のリストを活用することで、抜け漏れを防ぎ、実行性の高い計画書を作成できます。
1. 基本情報・目的の明確化
- プロジェクト名、目的、背景、期間、範囲(スコープ)が明記されているか
- ゴールがQCD(品質・コスト・納期)など測定可能な指標で定義されているか
- 対象と非対象が明確化され、受入基準が設定されているか
2. 体制・役割分担
- プロジェクト組織図やメンバーリストがあるか
- 役割・責任(RACIマトリクス等)が明示されているか
- 承認フローや責任の所在が不明瞭になっていないか
3. スケジュール・進捗管理
- 主なタスク、担当者、マイルストーンが明記されているか
- WBS(作業分解構成図)、クリティカルパスが設定されているか
- スケジュールがガントチャート等で視覚化されているか
- 進捗率の定義や管理方法が明確になっているか
4. 成果物と品質管理
- 成果物の提出基準や品質基準が定義されているか
- チェックポイントやレビュー体制が整備されているか
5. コスト管理
- コストの見積もり方法や根拠が明記されているか
- 予備費や全体収支計画が含まれているか
6. リスクと変更管理
- 想定リスクの一覧(リスク登録簿)があるか
- リスクごとの対応策が記載されているか
- 仕様変更や契約変更時の手順・合意形成の方法が明記されているか
7. コミュニケーションと情報共有
- 定期的な報告ルールや連絡体制(頻度・チャネル・エスカレーション方法)が明記されているか
- 関係者全員が計画内容をいつでも確認できる環境があるか
8. 契約・PEP反映事項
- 契約条件やプロジェクト実行計画(PEP)で定められた要素が反映されているか
- 実務に直結する内容がPEPに落とし込まれているか
このチェックリストを使えば、計画書の品質を高め、プロジェクト推進の実効性を確保できます。