この記事でわかること
- プロジェクトマネージャー資格の種類と難易度の全体像
- IPA PM試験・PMPの特徴と合格率の違い
- PMO・P2Mなど関連資格の難易度比較
- キャリア別に最適な資格の選び方
- 合格に向けた学習戦略と勉強期間の目安
目次
プロマネ資格「難易度」の全体像

プロジェクトマネージャー(プロマネ)資格には、さまざまな種類があります。大きく分けて、国家試験、国際資格、民間資格の3つのカテゴリーが存在します。それぞれの資格は、出題の方法や評価ポイントが異なるため、実際の「難易度」の感じ方も人によって大きく変わります。
国家試験の代表例は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施しているプロジェクトマネージャ(PM)試験です。この試験は“高度”と呼ばれる枠に分類されていて、合格率はおよそ10%台前半。試験の内容は選択問題だけでなく、記述式や論述式も含まれており、問題の難しさがはっきりしています。
一方、国際資格の代表は「PMP(Project Management Professional)」です。PMPは、受験のために学歴・実務経験・35時間研修受講といった厳しい受験条件が設定されています。試験自体の合格率は公式に発表されていませんが、一般的には約60%程度と言われています。
このように、プロマネ資格ごとに求められる知識や試験対策、難易度の感じ方が異なっているのです。次の章では「IPAプロジェクトマネージャ(PM)試験の難易度と合格率」について詳しく解説します。
IPAプロジェクトマネージャ(PM)試験の難易度と合格率
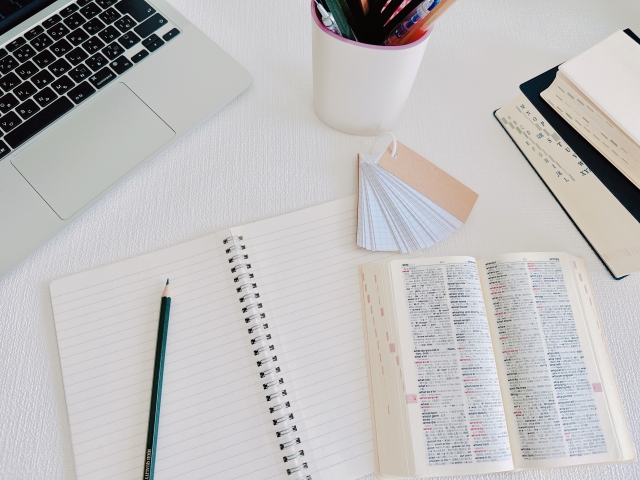
PM試験の合格率と位置づけ
IPA(情報処理推進機構)が実施するプロジェクトマネージャ(PM)試験は、IT系国家資格の中でも特に難関とされています。直近5年間の合格率はおよそ13〜15%で、受験者の約6〜7人に1人しか合格できません。この数字からも、PM試験がどれだけハードルの高い試験かが分かります。
試験の最大の難関:午後I・II
PM試験は「午前Ⅰ」「午前Ⅱ」「午後Ⅰ」「午後Ⅱ」という4つのセクションから構成されています。このうち多くの受験者にとって特につまずきやすいのが、記述問題の午後Iと論文問題の午後IIです。午後IIでは与えられたテーマについて自分の実務経験や知見をもとに論理的かつ具体的な文章を構成し、A評価(高評価)を得る必要があります。ここで「論理的な流れ」「説得力」「具体例に基づく説明」が求められるため、単なる理論知識では太刀打ちできません。
必要とされる能力:経験の抽象化
午後IIの論文では、実際のプロジェクト管理経験をもとに、その課題や対応策を自分なりに抽象化(まとめ直し)、分かりやすく整理して説明する力も問われます。たとえば、「納期遅延を回避するためにどんな工夫をしたか」など、具体的なエピソードと自分の行動を筋道立てて伝える必要があります。
ITSSレベル4とは
PM試験はITスキル標準(ITSS)で「レベル4」に該当します。これは企業が求めるIT分野の高度な専門人材に位置づけられるレベルです。プロジェクト全体の指揮をとり、組織をリードする能力が求められます。
未経験・独学での合格は難しい
IT分野未経験者が独学で合格を目指すのは非常に困難です。合格には「実務経験に基づく論述力」と「過去問での徹底したトレーニング」が不可欠です。実際のプロジェクトマネージメント経験を活かしつつ、学習計画を立てて目的意識を持ちながらの対策が重要となります。
次の章に記載するタイトル:PMP(Project Management Professional)の難易度と受験要件
PMP(Project Management Professional)の難易度と受験要件

PMP(Project Management Professional)は、世界的に認知度が高いプロジェクトマネジメント資格です。PMPの資格取得は、決して簡単ではありませんが、しっかり対策すれば十分に合格を目指せます。ここでは、PMPの難易度や受験のための具体的な要件、学習の流れについてご紹介します。
PMP受験の主な要件
PMPを受験するには、次の条件を満たす必要があります。
- 学歴に応じた実務経験
・大学卒業以上:過去8年以内にプロジェクトマネジメントの実務経験が36カ月
・短大または高卒:過去8年以内に実務経験が60カ月 - 35時間の公式プロジェクトマネジメント研修を受講
大学を卒業している方は3年分のプロジェクト経験が求められ、短大・高卒の方は5年分が必要です。さらに公式の研修受講も条件なので、受験までにある程度の準備時間が必要です。
取得までの流れ
PMP取得のプロセスは、以下のようになります。
- PMI(Project Management Institute)のアカウントを作成
- 受験要件に沿って申請書を作成(実務内容を英語でまとめる必要あり)
- 35時間の研修受講修了を証明する書類の提出
- 受験申込・受験料支払い
- 試験(約4時間、選択式問題)
- 合格後は3年ごとに資格を更新(60PDU=継続学習ポイントが必要)
PMPは1回取得して終わりではなく、合格後も知識のアップデートが求められます。この更新作業もPMPの難易度の一部といえます。
合格率の目安と学習負荷
PMP試験の合格率は公表されていませんが、概ね60%前後と推測されています。PMIが試験内容や採点基準を公開していないため、対策本やオンライン講座を使った入念な準備が欠かせません。
合格者の声では、「集中して4カ月学習し合格」という例もあります。実務経験と英語力があれば、コツコツと計画的に学習することで合格を目指しやすい資格です。
次の章では、IPAプロジェクトマネージャ試験とPMPの比較(目的・出題・負荷)について詳しく解説します。
PM試験とPMPの比較(目的・出題・負荷)

目的の違いを分かりやすく
PM試験とPMP資格は、どちらもプロジェクトマネジメント能力を問う資格ですが、求められる背景や目的が異なります。
PM試験(IPAプロジェクトマネージャ試験)は、日本国内におけるIT領域での高度なマネジメント力を評価する国家試験です。ITプロジェクトに特化し、現場経験に基づいた考察や論理的思考力も重視されます。
一方、PMP(プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル)は、国際プロジェクト標準であるPMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)に準拠した、多様な業界・国際的な標準力の証明です。業界や業種を問わず、グローバルな仕事に役立ちます。
出題形式と内容の違い
PM試験の難しさは、実務力と論述力をどちらも試される点にあります。午前は選択問題ですが、午後Iでは記述式、午後IIでは自分の経験や考えをまとめる論文式問題が出題されます。現場経験を言語化する力も重要です。
PMPは四択中心の筆記試験で、PMBOKやアジャイルなど幅広い知識範囲から出題されます。状況問題も多く、知識だけでなく現場対応力もみられますが、論述や記述の負担はありません。
負荷(難易度・学習量)の違い
PM試験は論文対策や記述練習が必要となり、対策にまとまった時間がかかります。合格率も約13〜15%と難関といえます。
PMPは受験要件(実務経験や講習受講)が必要ですが、試験自体は選択問題が主。合格率は非公表ですが、およそ60%程度とも言われます。知識の範囲が広いため、計画的な学習が重要です。
まとめ
PM試験は日本のIT領域に特化した国家資格、PMPは国際標準で幅広く通用する民間資格です。実務での深い経験や論述力を問うか、グローバルな基準で知識と実践力を問うかが大きな違いとなります。
次の章に記載するタイトル: PMOや関連資格の難易度の目安
PMOや関連資格の難易度の目安

PMO関連資格とは?
プロジェクトマネジメント分野には、PM(プロジェクトマネージャ)やPMP以外にも、PMOやそれに連なる専門資格が複数あります。PMOは「プロジェクト・マネジメント・オフィス」の略で、複数プロジェクトの管理や支援を担う役割です。大企業や組織でプロジェクト推進の司令塔となることが多く、その専門性を証明する資格があります。
P2M(プロジェクト&プログラムマネジメント)
P2Mは「日本版プロジェクト&プログラムマネジメント資格」と呼ばれるもので、合格率は60〜75%となっています。これは、受検者の6〜7割が合格できる水準です。難易度は「やや高い」とされますが、しっかりテキスト学習とポイントを抑えておけば合格を目指せます。主にプロジェクト全体像の理解やマネジメントに関する体系的な知識を問われます。
PMOスペシャリスト(NPMO認定PMO-S)
PMOスペシャリスト資格も人気があり、合格率は約55%です。半数以上が合格するものの、やや高めの難易度となっています。出題範囲は「PMOの役割」「実務の進め方」などの知識確認が中心で、実務の現場でどう適用するかも問われることが多いです。とはいえ、PM試験やPMPほどの長文問題や論述は比較的少なく、学習負担はやや軽い点が特長です。
難易度のまとめと学習のコツ
どちらの資格も共通するのは、マネジメントの理論と言葉を覚えるだけでなく、どうやって実際の業務に当てはめるかまでイメージできるかが鍵となります。実務経験がなくても、事例集や模擬問題を通じて具体的なイメージを掴むことが、合格への近道です。
次の章に記載するタイトル:あなたはどれを選ぶべきか(キャリア別の指針)
あなたはどれを選ぶべきか(キャリア別の指針)

キャリア設計を進める際、どのプロジェクトマネジメント系資格が自分に合っているのか悩む方は多いと思います。ここでは、主要資格それぞれに適した人物像やキャリア志向についてわかりやすく解説します。
IPAプロジェクトマネージャ試験が向いている方
たとえば、国内のIT企業でシステム開発や運用のプロジェクトに携わり、高度なマネジメント能力を客観的に証明したい場合、IPAプロジェクトマネージャ試験が適しています。とくに日本国内の老舗企業や大手SIerで評価が高く、論述力や事例分析力が重要視されます。昇進や社内評価にも直結しやすいのが特徴です。
PMPが向いている方
グローバルな働き方や、多様な業界(IT以外も含む)のプロジェクトマネジメントに挑戦したいなら、PMPがおすすめです。世界共通で認知されており、外資系企業や海外案件へのアプローチ時にアピールできます。また、資格の維持に継続的な学習が必要になるため、最新の知見習得や自己成長に積極的な方に向いています。
P2MやPMO系資格が向いている方
企画からプロジェクト全体の統制、さらにはPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)としての横断的なサポートや管理業務を目標とする場合にはP2MやPMO系資格が選択肢となります。複数のプロジェクトを束ねる立場を目指す方、あるいは経営層に近い視座で調整・管理をする方におすすめです。
具体的な選択の目安
- 日本国内でITエンジニアやプロジェクトリーダーとして高みを目指す → IPA PM
- グローバルキャリア志向・業界を問わず幅広いプロジェクトで力を発揮したい → PMP
- 組織横断のポートフォリオ管理やPMO専門職を志向 → P2MやPMO資格
ご自身の現在地と将来像を照らし合わせて、最も納得できる資格を選ぶことが大切です。
次の章に記載するタイトル:「合格に向けた学習戦略(難易度を超えるための実践策)」
合格に向けた学習戦略(難易度を超えるための実践策)
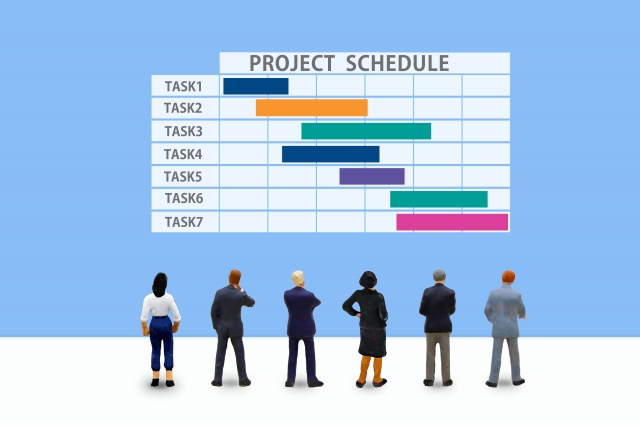
実践型の勉強法で壁を乗り越える
プロジェクトマネージャ(PM)試験やPMP(Project Management Professional)資格の合格を目指すには、戦略的な学習が不可欠です。それぞれの試験に特化した学習のポイントを押さえて、効率よく合格を目指しましょう。
PM試験:午後II(論文)が最大の山場
PM試験の場合、最も対策が難しいのは午後IIの論文問題です。合格のためには、次のステップが効果的です。
- 自分の実務経験を見直す: 失敗の原因、その対策、得られた成果や再現性に着目し、具体的な体験談をまとめます。
- 型化して練習: 「失敗要因→対策→成果→再現性」の流れをテンプレートとして論文を書きます。
- 過去問で具体的に練習: 出題パターンに沿って、毎回違う事例も交えて文章を書くことで、応用力を高めます。
午後I(記述式)は過去問を通じて「問題をどのように分解するか」「根拠をどこから持ってくるか」を意識し、記述のコツを身につけます。午前問題は幅広い知識が必要なので、何度も繰り返すスパイラル学習を意識しましょう。
PMP:要件整理と効率的トレーニング
PMP試験は、まずご自身の実務経験や受験資格を「棚卸し」することから始めるのがおすすめです。申請に必要な要素を、早めに整理しておきましょう。
- 35時間の定められた研修: eラーニングや短期講習で、最新の試験範囲や用語をカバーしましょう。
- 模擬試験の徹底活用: 良質な模試を使い、安定して合格基準に達するまで繰り返します。
- 申請書準備の前倒し: 証明書や実務記録は後回しにせず、早め早めの準備が重要です。学習の弾みがついた状態で、受験予約まで進めることで途中で失速しにくくなります。
やる気の維持もカギ
どちらの資格も、長い学習期間が必要です。自分なりの目標やペースを決め、進捗を可視化することで、やる気を維持しましょう。勉強仲間と進捗を共有するのも良い方法です。
次の章では、「よくある疑問(難易度に関するQ&A)」について解説します。
よくある疑問(難易度に関するQ&A)

Q1. PM試験とPMP、結局どちらの方が難しいのでしょうか?
PM試験とPMP、それぞれ難しさの特徴が違います。PM試験は論文や記述式問題が中心で、実際に文章を書いて説明する力が求められます。一方、PMPは選択肢から正解を選ぶ形が多く、考え方や知識の幅を問われます。たとえば、書くことや論理だてて説明するのが得意な方はPM試験を選びやすいです。知識を整理し、模擬テストを繰り返し学ぶスタイルが合う方はPMPの方が向いています。
Q2. IT業界未経験でも合格は可能ですか?
PM試験の場合、IT業界やプロジェクトマネジメントの経験が全くない状態での合格は難しいです。特に独学では実務のイメージが付きにくいため、社内のロールモデルや実際のプロジェクト経験を通じて理解を深めることが重要です。
PMPは受験要件に実務経験が含まれているため、未経験の方がすぐ挑戦することはできません。まずは実務の現場で経験を積み、知識と実務を結びつける準備が必要です。
Q3. 難易度を下げるコツはありますか?
PM試験では過去問分析と論文の練習がポイントです。論点ごとに整理された模範解答や合格者の論文など、具体例に触れて書く力を養いましょう。PMPは公式教材や資格予備校の演習問題を繰り返し解き、苦手分野をなくすことが合格への近道です。自分に合った学習計画で無理なく進めることが大切です。
Q4. 忙しい社会人でも合格できますか?
両資格とも働きながら合格した方がたくさんいます。コツコツと時間を積み重ねたり、短期間に集中して学ぶ人もいます。隙間時間で学習用アプリを使うなど、自分なりの工夫をすると、仕事と勉強の両立もしやすいです。
次の章では、「学習期間と負荷の目安」について分かりやすくご紹介します。
学習期間と負荷の目安
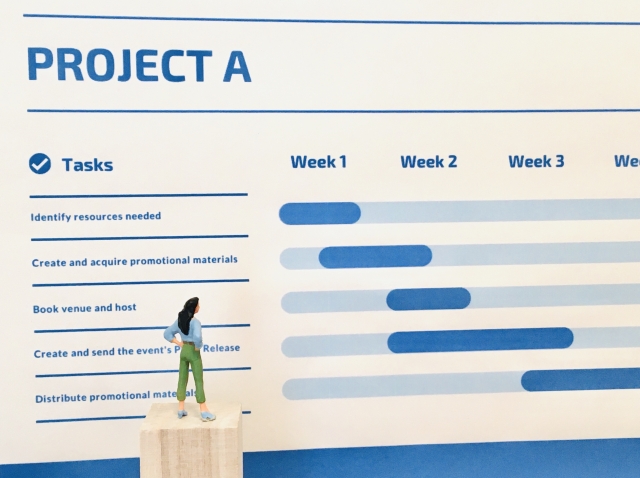
PM試験の学習期間と負荷
PM(プロジェクトマネージャ)試験は「合格率が1桁台」という難関試験です。このため、受験生の多くは半年以上の継続的な学習を前提としています。主要な対策は午後IIの論述試験で、次のようなステップが一般的です。
- 午後IIの過去問を複数年分解いて答案を作成する
- 模範解答や解説例と照らして自己評価する
- 回答パターンや論理展開を身につける
自分一人だけではなかなか答えの型やポイントを掴みづらいため、添削サービスや勉強会の活用も有効です。日々2時間前後の学習を続けて半年~1年程度費やす方が多く、社会人受験者はスケジュール管理が重要になります。
PMPの学習期間と負荷
一方、PMP(Project Management Professional)は、「通学講座+独学」「通信教材+模擬試験」といった形式で集中的に取り組むケースが多いです。学習期間の目安は4カ月前後が一般的ですが、効率よく知識をインプットし、問題形式に慣れることが大切です。
PMPでは、試験対策と並行して「受験申請」や「実務証明書類の準備」など、書類作成の工数も無視できません。社会人の場合は業務と並行作業になるため、土日や平日夜間の時間を有効活用しましょう。
やや異なる学習アプローチ
PM試験では「論述力」と「IT・業務知識のバランス」が問われますが、PMPでは「選択肢から解答を選ぶ」スタイルが中心です。したがって、PM試験では書く練習を多く、PMPでは模擬試験を繰り返す練習が重要です。
次の章に記載するタイトル:まとめの指針(次の一歩)
まとめ

プロジェクトマネジメントの資格取得を目指す上で、「何を重視したいか」によって最適な選択は異なります。ここまで解説した通り、難易度や合格率、目的ごとに特色がありますので、ご自身のキャリアや立場に合わせて次の一歩を考えてみましょう。
PM試験を中心に目指す場合
高度なIT知識を証明したい場合、IPAのPM試験を選ぶのが近道です。具体的には、まず過去問を集めて全体像をつかみ、自分なりの論文テーマも徐々にストックしておくことが大切です。この積み重ねが、合格への最短ルートとなります。
PMP資格へのチャレンジ
国際的な評価を得て、業界や国をまたいだPMとしての市場価値を高めたい方にはPMPに挑戦する価値があります。はじめに最新の受験要件を調べたうえで、必要となる35時間の公式研修の予約、PDU(継続学習単位)取得など、3年単位での運用を計画的に立てましょう。長期的視野で無理なくステップアップできます。
PMOや組織統制の領域に進みたい場合
PMOや組織全体のマネジメントに意欲がある方なら、P2MやPMO認定など関連資格の取得も検討しましょう。業務範囲が広がることで、さらなるキャリアアップのチャンスにつながります。
まず取るべき具体的なアクション
- 公式サイト等で最新の受験要件を確認する
- 過去問題や出題傾向の資料を集める
- 自分のキャリアプランを1~2年スパンで見直す
迷った際は、一度立ち止まって自己分析を行い、本当に目指したい方向性や働き方を再確認することが、資格選びを後悔しない大切なコツです。成長の道のりは一人ひとり違うからこそ、情報を得て、計画的に歩み始めてみてください。